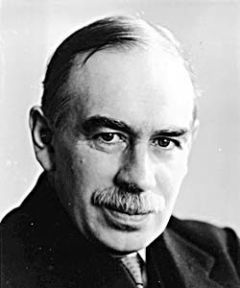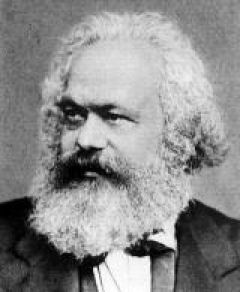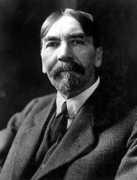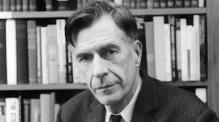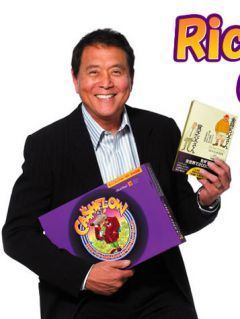以下のサイトは、あらゆる本、食品、飲料、美容製品、家電製品、パソコン、ソフト製品、乗用車、バイクとあらゆる日常で必要な製品が網羅されているサイトです。
買ったもの値段の3%が還元されて、それがこのサイトのモノを買えます。
また、エステなどの美容サイトや居酒屋、バー、レストランなどあらゆる飲食店が通常の半額で利用できて、それも最低2%以上の還元率でポイントとして貯まり、それがこのサイトのショッピングで使えます! 
例えば、あなたが会社の飲み会で、このサイトの飲食店を使い、2万円を飲食代で使い、そのうちの2%(=400円)が還元され、それがこのサイトのモノを買えるのです。
これほどの凄い還元率のサイトは知りません。
これほどの凄いサイトは前代未聞です。 このサイトを使わずに、これからの生活を送れますか?
使いたいなと思ったら、すぐに使いましょうね!
↓
![]()
この著者の飯田経夫氏は、常々アメリカの日本に対する態勢を批判してきた人です。
90年代の後半にこの人を知りましたが、その単純明快でわかりやすい筆致に引き込まれた私ですが、最近インターネットで詳細を調べると、このかたは亡くなってしまったのですね。

非常に惜しい人をなくしましたね。
そのアメリカ批判の内容は、その野放図な政策のつけを日本に肩代わりしてもらう、という姿勢を批判していたのですね。
アメリカの株式制度では、株の持ち合いという慣習がないのですね。
ですから、企業の業績が、素直に反映されやすいのです。
つまり、すぐに自分の株価が上がり、自分が儲けることを最優先に考えているのですね。
しかし、「株の持ち合い」は日本には厳然と存在しているのです。
それは系列関係をより確かにし、企業の買収といったを防ぐためにあるのです。
こういった自分の直接的な儲かりを最優先にするか、長期的な自分の会社の業績を優先するかの違いがあるのです。
こういう精神は、元のアメリカの精神にはあったのです。
鉄鋼王カーネギー、自動車王フォードなどですね。
こういった人たちの精神を、今のアメリカの企業家たちは忘れてしまったのでしょうか。
アメリカの企業は四半期主義にあるといいます。
アメリカの上場企業は、資金調達を主に株主に頼っているので、経営者は株主の利益を優先させているのです。
株主の利益を上げた経営者は有能で、下げた人間は無能と烙印をおされ首になるといいます。
こうなると、M&Aやリストラクチャリングで会社の売買だけで手っ取り早く収益を稼いだほうがいいということになります。
それが、そのまま国の経済のいきかたの違いになっていますね。
モノづくりは、手間ひまのかかる作業です。
トップからヒラまでのチームワークですから、労使関係にも気を配る必要があるのです。
しかし、金融で儲けることにおいては、男一匹の才覚と運のすべてをかけて一発当てることができるのです。
アメリカの経済の中心はこのようになってしまっているのですね。
しかし、経済の中心に据えるべきは、国が最優先で取り組まなければならないのは、やはり「モノづくり」ですね。
「海外の投資家が、その国の長期的な利益を考慮した真に重要な投資をする保証はない。それは、その国の経済をただ不安定にするだけだ。」 というケインズの言葉を引き合いに出すまでもなく、グローバル金融の昨今においては、資本の気まぐれな移動が起きてしまうのは、やはりその経済が順調にいっていない時ですね。
そうならないようにするためには、やはりモノづくりが健全とおこなわれていれば、そういう資本の気まぐれはそうそう起こらないでしょう。
もちろん景気の波はありますから、たとえその国の経済が不況に健全なモノづくりが行われていれば、持ち直すことは間違いないでしょう。
そういうモノづくりを怠ってきたのがアメリカの経済なのです。

いや最近の、研究で明らかになったことは、『闇の権力』によってアメリカの経済界は乗っ取られているということです。
モノづくりをしようと思えばできないことはなかったでしょう。
しかし『闇の権力』の乗っ取られたアメリカの経済界はそんなことはしないで、金融で自分たちの懐を肥やすことしか考えてなかった。
『闇の権力』とは、ハルマゲドン(最終戦争)を引き起こして、人類の大半を核戦争で抹殺し 、ウィルス兵器をつかって人類の大半を断種し、生殖能力を奪い家畜化するという計画をもっている人たちです。
アメリカの軍事部門は『闇の権力』の手先である「DARPA(国防高等研究計画局)」の傘下に入ってます。
アメリカの製造業は常に世界の先端を走ってきました。
自動車、家電、鉄鋼、造船、光学機器といった分野で驚異的な発展を遂げる事が出来たのですが、 その軍事機密に関しては、民間に流れることを法律で禁止しているのです。
その『闇の権力』に、現在のアメリカの為政者たちは乗っ取られてているので、この国の経済はモノづくりで世界での先端を走ってきたのに、すぐに後続に追い抜かれる、ということを続けてきたのです。 それで納得がいくでしょう。
なお、その『闇の権力』云々については、ベンジャミンフルフォード著の『闇の巻力に握りつぶされた人類を救う技術 現代編』に詳しいので読んでいただきたいです。
そこで自国ではモノづくりをしないで、日本に内需拡大を迫ったのです。
1985年の9月におこなわれたプラザ合意において、日本は円高になったのです。
そして86年の前川リポート(元日銀総裁の前川春雄による)において、5兆円規模の内需拡大を目標とさせられたのです。
その当時、私は幼少だったので全然記憶にはないですが、当時の総理大臣だった中曽根康弘がテレビCMに出演して、「アメリカの製品を買いましょう!」ということで、自らがアメリカのワイシャツを着るシーンを披露していたようですね。
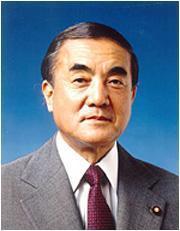
中曽根康弘
このことを知って、私は「科学的な知識を得ることは、知った人間がこういう具体的な行動をするためにあるんだなあ」と思った次第です。
その内需拡大においては、低金利政策と大規模財政出動をされたようです。
その際に、株と土地にお金が集中して、バブルが発生したことは周知の通りですね。
しかしこの日本の内需拡大でアメリカの経済がたてなおったかといえばそうではなく、この年の数年前のレーガノミクスで、財政が赤字になり、そのために金融を引き締めたため、金利が上昇し諸外国のお金がアメリカに集中したのです。

それで人件費が高騰し、生産拠点を海外へ移さざるを得なくなり、それでさらに輸入品が多くなり、さらにアメリカの赤字は増したのです。
ここに懸念が残ります。
国は、ひとたび豊かになるとモノを作らなくなるのでしょうか?
国が経済的に豊かになると、為替レートで換算した人件費が国際的に見て高くなるのです。
するとアメリカのように生産拠点を海外に移さざるを得なくなるのです。
そのことにこれからの日本も懸念を抱いていかなくてはならないでしょう。
「モノづくりは遅れた国がすべきもの」というような風潮ができてしまうこともなた懸念していかなくてはならないでしょう。
いかにも金融でお金を得ることが時代の最先端なんだみたいな風潮が広がってはならないですね。
また、飯田経夫氏は、低開発国の開発についても提言を呈しています。
高度工業化や産業化を達成できたのは、ヨーロッパ北西部プロテスタンティズム文化圏諸国や北アメリカ、日本、NIESという地球上のごく一部の国々だけであり、低開発国の離陸がいかに難しく困難な道のりであるかを説いています。
その開発援助は、「途上国の安定と発展が世界全体の平和と繁栄にとって不可欠である」とか、「日本がその国力に相応しい役割を果たすことが重要な使命である」という、ここだけ読むともっともらしい言説がまかり通っていたようですが、それにも苦言を呈していたのです。
やはり、こういうことは人類学や文化人類学のような学問を学ぶとわかりやすいのですが、経済発展のためには、毎日働かなくてはいけないわけですから気候が適切でなければなりません。
極端に暑かったり寒かったりしていては、働くことができません。
そしてモノが流通するわけですから、道が整備されていなくてはいけませんし、言語が統一されていなくてはいけません。 そのためには道路を国全体に整備し、言語を書けるように教育も普及されていなくてはいけません。

もとより、モノを自国で作らなくてはいけないわけですから、そのための教育も行わなくてはいけないのは言うまでもないでしょう。
そういう経済発展のための条件を整えるためには、ものすごいお金と時間がかかるのは言うまでもありません。
日本が明治維新から、急激な経済発展を遂げれたのは、こういう条件が運よく整っていたからにほかなりません。 しかし、こういう条件のない第三国は、かなり難しいのは他言を待ちません。
でもそれはそれらの国の人々を貶すわけではないです。
しかし、その開発援助のためのお金は、その国の政府高官の懐に入ったり、ニーズを調べずに実施しているから何の役にも立っていなかったし、雨ざらしになっていたのが現状だったようです。
しかし、もとよりこういう経済発展への離陸は非常に難しいことであるのは先に書いた通りです。
やはりこういった面でも同様に、新聞や雑誌等での言説だけでは、その物事委の本質はわからないものです。
こういう飯田経夫氏のように明快に、事の内面を明らかにしている評論を読まなくては。
10年以上も前に読んだ本ですが、今も学ぶことが多くあり、しかも明快な筆致で書いているので何回も読み直したくなる内容です。
学者として、知識人としてあるべき姿を体現していたのがこの飯田経夫氏にほかなりません。
その姿勢を経済学の面で学びたい方は、この本をおススメします。
●この本は以下からどうぞ!
↓
日本経済の目標―「豊かさ」の先に生まれるものは
モバイル
日本経済の目標―「豊かさ」の先に生まれるものは
★その他、おススメ図書
ベンジャミンフルフォード著 『闇の巻力に握りつぶされた人類を救う技術 現代編』
![]()