私はかねがね、大学入学とその前では、人生がいい意味でかわらなくてはならない、と思っていました。
何故なら、大学な学ぶ学問は、社会をよくするためのものであるし、それを学び行動に移すことで社会がよくなるからだ。
なのに、それを学んで生活が変わっていないのなら学ぶ意味はないというように思い、そして今でもその思いに違いはないです。
その趣旨と同じようなモラルで、この著者はいてくれたので安堵の思いになりました。
しかしちょっとニュアンスは異なりますが。
この増田四郎さんは歴史家ですが、「これまでの勉強から180°の転換が必要」と書かれています。
これまでの高校のとは違い、自分の脳みそで考えるということを強調しているのです。 これまでのばらばらの暗記であった学習から、事件を統一的に考えることを強調しているのです。
民法の問題と経済の問題はそれぞれ別個の問題のように見えますが、同じ意味合いを持っているということです。
これはニュアンスが違いますが、私の経験ですと、政治学で読んだ本から歴史学で学んでいることで参考になることを偶然見つけたことがありまして、その意義に凄く面白くなって、のめり込んで言ったのを覚えています。
う~んとうなっていて、打開が見えない時にふと違う分野の本を読んでみる。
するとヒントが見つけることが出来たりしたときの喜びは代えがたいものがありました。
そういったいろんな学問を修めるメリットを教授たちは知っているはずなのに、なぜ講義で教えてくれないんだろうと不思議でしたが、やはり大学の先生たちは、教師というよりも研究の方が大事なんですね(笑)
いや批判する資格はないかもしれません。
私も教授になったら、そうなってしまうかもしれないですから(笑)
現代の学問のシステム上、1つの専門を持ってなくてはならないですし、専門のない人は教授として認めてもらえません。
しかし、専門だけにこだわって、他のことについては何ら知らないというようなのでは更に良くないですね。
私が大学生の時に、民法の教授に「これは憲法との関連ではどうなのでしょう?」と質問したら、私の専門は民法だからわからないといわれてしまいました。
国の最高法規を修めながらの法律でしょう? 何故、わからないとはねつけるのかなあと不思議でした。
やはりこういうことがあってはならないのです。
専門家であると同時に一般的な見識を持つことが大事なのです。
東洋史の専門家であるからといって西洋史その他の歴史に無頓着であってはならないでしょう。
その分野についてつまびらかに知っていても自家撞着になるだけです。
これはここにだけ固有のものだ、と思っていても比較してみると、他にもいっぱい例はあったりするものですし、比較を通じて浮き彫りになることもしばしばなのです。
やはりこのようにいろんな学問を深く、そして広く学んでいる人の本は、やはり説得力に富み、いつまでも読み進めてしまう魅力を持っているものですね。
自分の専門の事しか知らないというのでは、修めているようで、実際は怠惰を証明しているようなものですね。
やはり机上だけの勉強になってはいけないということですね学問は。
この増田氏の専門は歴史学ですが、それを修めるには本だけ読んでいてはいけないということのようです。
歴史を学ぶということは、町、村、地域社会がだんだん広がっていく変化、そこに住む人間の意識、そういうものを丹念に具体的に調べる事の重要性を強調しています。
地域史の研究をしなくてはならないといいます。
単に年表を暗記して事件を学ぶだけではいけないようです。
また深く考えて、どのようにして資本主義が開花したかということを考えましょう、といわれても誰もいきなり答えることはできないでしょう。
それは問題意識をもって学んでいるとわかるようになるのでしょうか、どうなのでしょうか?
やはり偶然にそのふしが見つかるとやはり楽しいものがありますね。
それをセレンディピティというのだそうですが、それもまた高校までの勉強では味わえない魅力ですね。
マックス.ウェーバーが、プロテスタントの教義の中に資本主義の精神を見つけ、そのことを書いた本が世界中で読まれることになったのですが、その発見は資本主義の精神の原型を見つけようとしたのではないでしょう。
マックス.ウェーバー
どういうところにあるのかなという問題意識をもち続けて勉強していった時に偶発的に見つけたのではないでしょうか?
それは彼の自叙伝を丹念に読まない事にはわかりませんが、そういう偶発的な発見というのは、やはり問題意識の有無によって発見できるかできないかが決まるのだと思います。
優れた経営者は、「お客様がどのようなことをされたら嬉しいか」ということを考え続けていたら偶発的に見つけることができたという自叙伝を結構な数読んだことがあります。
そういった部分で共通点はありますね。
そういったセレンディピティの魅力を周りの人たちに喧伝して回ったのですが、反応はダメでした(苦笑)
資本主義の精神ではなく、それがはぐくみやすい土壌はどのようなものかということもやはり興味深いありますね。
三圃農法は代表的な密集村落ですが、このようなところでは資本主義は育たないようです。

逆に散村、小村地帯のように領主のあまり支配の強くないところ、生産物を農民が比較的自由に選べるところの方が資本主義は発生し発達していきやすいということですね。
これは目の覚める発見ですね。
これは増田氏の発見かどうかわかりませんが、非常に面白く興味深いことでした。
これは非常に普遍的な事実の発見ですから、産業化が全く発達しない国の村や町の状態を調査するのがいいでしょう。
そこが三圃農法でしているのなら、それを変えなくてはならないのでしょう。
やはりこういった細部にわたる研究がマルクスの史観には欠けているので、私にはある程度説得力があっても、この史観を全面的に支持はできなかったですね。
西洋史を修める人でも、東洋と西洋、現代と自分というものを絶えず考えながら、そこで社会科学的な問題となる代表的なものを調べていってヨーロッパ(西洋)に問題を呈示することが、それを修める人の役割だ、と書いているのです増田氏は。
やはりこのような問題意識があれば、どの学生もきちんと講義に出ると思うのですが…実際はなかなか難しいですね(笑)。
歴史を修めるにしても、他のどの学問を修めるにしても、本格的な勉強のためには他の国で書かれた本を読めなくてはだめですね。
ゆえに、大学教授たるもの英語のほかどこかの国の言語を義務付けられているのです。
それのみか、昔に書かれたものも読めなくてはならないのはいうまでもないです。
歴史学のような過去のことを学ぶ学問であればなおさらです。 その古典は客観的な史料を素材とした芸術なのです。
やはりそれも民衆の心を学ぶためにも必要でしょう。
その他、日本における哲学の不在、大学の必要性、友人の必要性等といったことについてつまびらかに論じてあります。
大学にきてどのようなアプローチが必要かわからない人、あるいはおぼろげながらわかっていても不十分さを感じている人はこの本を読んで理解すべきでしょう。
この本は1966年が初版なのにいまだ版を重ねて売れているのですからかなり良さが語り継がれてきたのでしょう。
●この本は以下よりどうぞ!
↓

★おススメのネット本スーパー 『honto』です!
書籍や電子書籍を買うごとに、100円につき1ポイントが貯まります!
そのポイントは、また書籍や電子書籍を買うときに使えます。
更に会員になると、毎月10%あるいは20%の割引きのクーポンが送られます。
電子書籍なら30%offの場合も!
こんなサービスのいい本屋さんのサイトは知りません!
↓











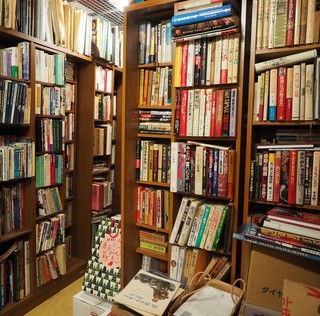













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます