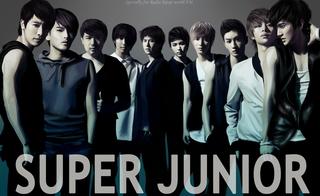この本を読んで、経済援助の困難さ、または私たち経済大国に生まれ育った人たちが普段目にし、触っている者の有難さについて痛感しました。
その内容は以下ですね。
普通に経済が運営される。
それは、モノと貨幣との交換ですね。
しかし、それをおこなう際にも、単純に計算が出来なくてはなりません。
しかしそれには当たり前ながら教育が必須です。
しかし、援助される側の国々の人たちは、そういう機会がほとんどないので、それすらもできかねています。
また病気にならないように接種を受ける、それも当たり前ながら、その大切さを知るためには、伝達が必要です。
人から教える、また紙や本、テレビなどを通じての伝達が必要です。
しかし、それもまた困難なことがわかっています。
援助される側の国の人たちは、その良さを知らないですから、その良さを知らせるためには、一番手っ取り早い方法は、紙ですね。
しかし、それがあまり少ないが故にそれもできかねているし、できても少数にしかできない。
また、投資や保険といったものに大切さまで教えるとなると、更に大変ということがわかりますね。
やはり我々、北の人たちというのは、そういった媒体を大いに受けているからこそ、そういうものがあり、その大切さがわかり、そして行動に移すことができる。
CMと同じように、何度も何度もその内容を知ることによって、行動に移すことができるのですね。
しかし、南の国の人たちは、そういう媒体が不足しているからこそ、そういった私たちにとって当たり前のことができないし、行動になかなか移せないでいることがわかります。
そういったうまれそだった環境によって、そういった違いが生まれてしまうのであって、自助努力にそういった経済状況の違いの原因を期することはできないということがわかります。
一番手っ取り早い紙の手段によって伝えることですら、なかなか一筋縄ではいかないのは明白です、これらの国では。 何故なら、いろんな言語が話されていますから意志の疎通が非常に難しいのです。
日本が、明治期に富国強兵政策を打ち出し、すぐに列強の仲間入りを果たせたのは、江戸時代に寺子屋などの教育施設が普及していて、教育がいきわたり、しかも言語も大した違いがなかったゆえに医師の疎通ができていた。 しかも、街道が整備されていたがゆえに、ものの流通もスムーズにいった。
そして働きやすい気候であったがゆえに朝から晩まで働くことができたのですね。
別のページで書きましたが、エジプトはあまりに暑いがゆえに昼の3時までみんなが寝ているようです。
フィリピンも同様のようです。
この気候的な云々についてはこの本では言及されていなかったですが、非常に重要なことですね。
また人々の心の習慣や文化といったものも考慮に入れないといけないでしょう。
私はいつかタイに旅行しにいきました。
バンコクではいろんな人が必死になって働いていましたが、山奥の方へ行くと働かずに一日中働く意志など微塵もなく、ほとんど寝ているような店員の人がいました。
そこらへんには、野菜や果物、その他穀物がいろいろ生えているので、無理やり売らなくても生活していけるのですね。
だから売る気が見えませんでした。
こういったいろんな条件が経済発展に有利であったがゆえに、日本はすぐに経済大国化が可能だったのですね。
決して南の国の人たちが自助努力を怠ったわけではないのですね。
モノを買うにしろ、勉強するにしろ、働くにしろ、私は日本が経済大国化に有利な国柄だったがゆえに可能なんだ、ということを日々実感しています。
そういった経済大国化への試みとして、いろんな施策をこの著者は10年以上にわたって南の国々において行動してきたのです。 それが、実ったという事例をたくさん挙げているのです、決して自慢ではなく。
それを喜ばしいことではあるとはいえるでしょう。
その出た結果を見れば、途上国でも経済発展は可能ということがわかります。
ただしいろんな要素が絡み合って、日本のようにスムーズにはいかないにしろ。
これは決して卑下しているわけではないことはお断りしたいですね。
やはりことを詳らかに分析していくと、やはり経済発展のためにはいろんな要素が必要ということがわかっているだけのことですね。
しかし、これから先、こういった国々の人たちが発展することは喜ばしいこととはわかりますが、でも経済発展には、環境問題、環境汚染という負の面が付きまとうのは事実です。
それを緩和する技術はあるのは事実ですが、全く無にすることはできないのです。
全世界が今の先進国のような発展をするためには地球があと3つ必要という研究もなされていることは頭に置いておいていいでしょうね。
そういう事も念頭においたうえで、やはりこれからの政策(国内国外問わず)の是非を考えないといけないでしょうね。
私は、これまでの実験で、クーラーと扇風機のどちらが最近のような暑い日にはいいかを試しました。
やはり扇風機では、それなりに涼しくはなりますが、完璧には涼しくならないです。
何度も試しましたが、やはりダメで、ちょっと寝て休もうと思って寝ると、いつの間にか3時間くらい寝てしまうのですね(苦笑)
エジプトの人たちの心境がわかりました。
それだと、自宅での仕事は全然はかどらないので、クーラーを使うことにしました。
それも、喫茶店もかねてですね。
喫茶店では当然クーラーはついていますから、そこでパソコンを持参して仕事をする。
そして閉店してしまったら仕方ないから、自宅に戻って仕事をする。
それの方が環境的にはいいでしょう。
おなじ時間帯に、自宅と喫茶店の両方がクーラーを使っていては二重の環境悪化=温暖化になりますからね。
やはり科学というものは、読んだ人や勉強した人に行動を促すものであるというのが一番大事な点と思いますね。
大学で学んだことで大いにいいと思ったのは、生ごみは捨てるのではなく土に埋めるのがいい、ということですね。
清掃工場に生ごみを回収してもらって燃焼させても水分が含んでいるがゆえに燃えにくい。
しかし土に埋めれば、それをバクテリアが分解してくれていい土になる。
ということを学んで、私は卒業後生ごみを一度も清掃工場の収集に出したことはなく、すべて土に埋めています。
それゆえに私の家の土の部分には冬であろうといつも青い草が生い茂っています。 最近の夏ごろはぼうぼうです。
こういう行動に移すべきことは移す、これが大事ですね。
しかし、途上国の援助には一筋縄でいかないことが多いですし、全部の国が発展するには、あと地球が3ついる、ということを考えれば、そうやすやすと答えを出すべきではないでしょう。
やはり研究に研究を重ねたうえで結論を出し、そのための行動をしていく、というスタンスが大事でしょう。
そういう事を考えてしまったのです、この本を読んで。
地球の上に住む以上、そういう事を日々考え、そして行動していくことは誰でも大事でしょう。
その行動が過ちであるとわかったら、それ以降はしないでいればいいだけです。
そのことに賛同してもらえる人にはこの本を読んでほしいと思いました。
●この本は以下よりどうぞ!
↓
★おススメのネット本スーパー 『honto』です!
書籍や電子書籍を買うごとに、100円につき1ポイントが貯まります!
そのポイントは、また書籍や電子書籍を買うときに使えます。
更に会員になると、毎月10%あるいは20%の割引きのクーポンが送られます。
電子書籍なら30%offの場合も!
こんなサービスのいい本屋さんのサイトは知りません!
↓