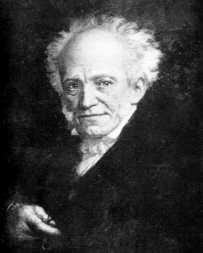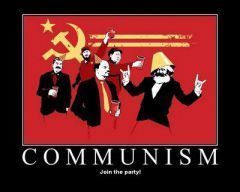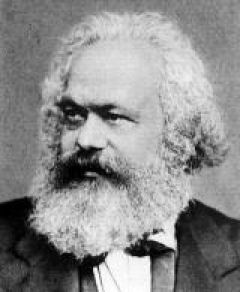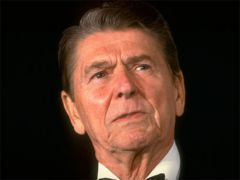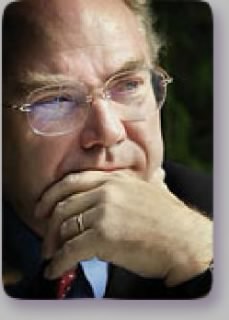★おススメのネット本スーパー 『honto』です!
書籍や電子書籍を買うごとに、100円につき1ポイントが貯まります!
そのポイントは、また書籍や電子書籍を買うときに使えます。
更に会員になると、毎月10%あるいは20%の割引きのクーポンが送られます。
電子書籍なら30%offの場合も!
こんなサービスのいい本屋さんのサイトは知りません!
↓
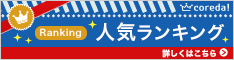

私は大学時代に、アメリカ社会について70年代に書かれた本をいろいろ読んで知識を蓄えました。
そこで読んで知ったのは、アメリカは世界で稀に見る平等社会ということです。

日本も同じように90年代は平等社会でした。
しかし、小泉構造改革によって、持てる者と待たざる者の格差は広がり、今や格差社会になっています。
歩んできた道は双方とも一緒なのです。
アメリカは超格差社会になってしまいました。
その契機となったのが、レーガン政権にほかなりません。
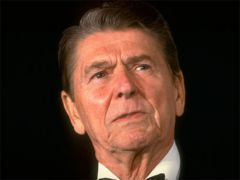
レーガン大統領
そのレーガン政権時代の社会の変移について詳しく知ることができるのが本書だと思います。
レーガン政権時代のアメリカは、爆発的な技術革新とかつてなかった繁栄を享受したといいます。
レーガンが政権についた81年時に、1900万人の雇用を生み出したといいます。
また、88年には失業率は5.3%にまで低くなり、インフレ率はカーター政権時代の3分の2にまで減少したといいます。
83年から始まった景気回復の足取りは、この年にまでに72カ月連続で好況になったといいます。
国が内外共にかつてないほど借金漬けになって派手に遊び暮らした時代、ぜいたく品が輸入され、成金が金を使いまくり、金持ちが減税の特権を受け、無思慮な逸楽がはびこるかたわらで、通りには乞食が溢れ、平均的な家族の可処分所得が将来ともに減っていきそうな暗雲立ちこめる時代だった、という表現がなされています。
トップ1%の所得がアメリカの全資産の11%を所有するまでになったということです。
債券、不動産、株式、ビジネス、不労所得が優遇され、かつてないほどの格差が拡大した時代、それがレーガン政権時代であったといいます。
しかし、平均的な家庭においては、73年に年間平均所得が3820ドルであたのが、89年には3853ドルと、ほとんど変わっていないのです。
要するに、金持ちを潤しただけで、平均的な家庭はレーガノミックスの恩恵を受けることなく終わったということですね。
この時代、雇用主は、新規雇用を抑え、仕事を細分化してコストを抑えたのです。
賃金は、パイロットからレジ係まで低く抑えられました。
これは、小泉構造改革の時と状況が一緒ですね。
88年には、5人に1人が年間5万ドル以上の世帯に属したようです。
83年の実に倍です。
経済的な二極化、中間層の「凋落」ですね。
政治においても、お金持ちたちに有利に事が運び、それが固定されてしまうことがわかります。
レーガンは共和党です。

その共和党の支持層は、アメリカでトップの20%の高所得層が占める割合が実に30%だといいます。
トップの40%の高所得層を含めれば50%にも及ぶという。
これではお金もちがお金持ちのままで固定されてしまうのがわかります。
そういった言動の様式は,富裕層の世代で継承されてしまうのです。
そんな状況をみて、マサチューセッツ工科大学のウォルター教授は、「アメリカで一番急増している党員は棄権党という名の党員である」という言葉を残しているそうです。
国民は政策に幻滅を感じれば感じるほど諦めてしまい、現在進行している富の再配分から恩恵を受けている人たちに投票を通じた意思決定をゆだねてしまうのです。
また、この時代は、企業家が英雄になった時代でもありました。
ホレーショアルジャー、ヘンリーフォード時代のように。
ベンチャー企業家が議会で歓迎され、ちやほやされ、『ヴェンチャー』『アントプレナー』『ミリオネア』『サクセス』『インク』などで取り上げられ、投資銀行家にすり寄られ俗世の聖者になりました。
現地ルポなどがないので、いまいち迫力に欠けますが、具体的な数値が明示されているので、興味深く読ませてもらいました。
日本とアメリカ、この2つの国は第二次世界大戦の直後は、為政者と一般国民の利害が一致していたがために、世界でも稀にみる平等国家であったのです。
しかし、それから時を経るにつれて、利害が不一致していき、為政者に有利な政策が決定されていったのは同じです。
第二次世界大戦後のアメリカにおいては、最高課税が91%というところも、日本と同じような状況だったのがわかるでしょう。
しかし両方とも今は、為政者やお金持ちたちに有利な政策が施されています。
このような時世においては、やはり「累進課税によって平等な社会が到来する」という言説が人々の頭に浮かぶのが普通ですが、歴史を垣間見るとそうではないようです。
普通の一般国民は、お金について勉強しない。
しかし、お金持ちたちはお金について勉強する。
そして、一般の国民は、お金を得る手段が「労働」しかない。
しかし、お金持ちたちの手段は、債券、不動産、株式その他いろいろと多岐にわたり、その方法も政治が変動しても自分に有利に働くように合法的に工夫をしている。
その結果、累進課税を施しても、お金持ちたちが貧乏になることはなく、格差はそのまま、というのがこれまでの資本主義の歴史のようです。
このように、「累進課税」において格差を是正することに期待はできないのですから、政府や企業に期待をかけるのではなく、「労働」だけでなく、他に自分がお金持ちになる方法を探し、実行していくのが望ましいと思います。
先に、レーガン時代に債券、不動産、株式、ビジネス、こういった不労所得の手段を持ってる人たちだけでなく、報酬の多い専門職の人も潤ったということです。

その報酬の多い専門職の人とは具体的に、メディア、学者、シンクタンク、コンサルタント、専門職ホワイトカラー、社会政策立案者そのほかのオピニオンリーダーといった人たちです。
では、報酬の多い専門職の人に自分もなればいいじゃないか、と反論されそうですが、ことはそう簡単ではなく、その時代の花形産業になるかどうかは、誰にも予見できないのです。
第2次大戦後、日本で一番お金が良かったのは、炭鉱労働者で、普通の労働者の3倍の給料をもらっていたといいます。
しかし、今炭鉱労働者で働こうにも働けませんね?
炭鉱自体が少ないですし、石炭の需要が異常に低いわけですから。
そうではなく、どんな時代にでも自分のポケットにお金を入れてくれる「資産」を築くことが重要ではないでしょうか?
その資産を築くための勉強をすることが大事なのではないでしょうか?
そんな気がしてならないのです。
もはや、 「為政者やお金持ち」と「一般国民」、この両方の利害を満たす政治は期待できないし不可能なのですから、お金について勉強しなくてはいけない。
この『富と貧困の政治学』を読んでそう感じざるを得ませんでした。
また、レーガン時代にいろんな規制が緩和されたことが書かれています。
そこで、緩和された領域に属していた職業についていた人も儲かったということが書かれています。
1960年に国の機関にある14479ページにわたる文書にあった規制が、80年には87012ページにまで膨れ上がっていたのです。
それを一気にレーガン時代に緩和したのです。
それでいい面は、航空においては年60億ドルの節約になり、電話においては長距離電話の料金が下がったことで、電話する人が増え、電話会社も潤ったことは間違いありません。
航空や電話会社以外にも、規制緩和によって利益にあずかれた会社は多くありました。
しかし、そのような恩恵に自分の職業があずかれるかどうかは、誰にも予見できませんね?
そのような意味でも、「労働」のみに期待することなく、それ以外に「資産」を築くことが重要と言えるのではないでしょうか?
どのようにすれば金持になれるか? それは会社に入って「労働」するだけでなく、やはり起業することもその1つであるとわかります。
そのことは、ロバートキヨサキの多数の本でわかりますし、この『富と貧困の政治学』の本でもわかります。

レーガン時代に、アイデアマンや野心家が多く金持になった、ということがわかります。
それをわかって、自分がそのようになりたいかどうか、を自分の心に訊いてイエスであれば、すぐに行動するべきでしょう。
その起業の仕方は残念ながら学校では教えてくれません。
自分で勉強するしかないようです。
巷を見渡せば、アイデアマンや野心家による起業のチャンスはいくらでも転がっているのがわかります。
そのようなチャンスが日本では足りないといって、アメリカに渡り、アメリカでレストランチェーンを起業して成功している人を知っています。

そしてお金について勉強するのです。
この本を読んで、また他の本や昨今の情報からわかるに、「労働」だけに頼るのではなく「資産」を築くことも非常に大切であることがわかります。
レーガン時代のイデオローグは、やはりお金持ちを優遇していたのです。
資産税や不労所得税を下げたのです。
そして、高金利でした。
債務者よりも債権者を優遇していたのです。
それが今でもアメリカで受け継がれています。
これは日本の小泉政権時代でも同じで、それがそのまま今も受け継がれているのは間違いありません。
これでは、税不足になるのは間違いありません。
それを一般国民からの税で賄い、足りない場合は国債発行と、他国から(主に日本)の借り入れで間に合わせ、問題を先送りにしていったのです。
景気が非常に良かったのが80年代のレーガン時代であったのは間違いないことです。
同時に日本もその恩恵に浴すことができたのは間違いありません。
しかし、先に書いたように、アメリカにおいては富裕層がより富裕になり、一般的な国民の所得はそのまま、ということがわかりました。
アメリカの製品全般は、劣悪とまではいかないまでも、品質が劣るものが多くあり、好景気に沸いたレーガンの時代に、国内産の製品よりも、輸入品が多く買われ、そのためさらに貿易赤字が拡大したのです。
レーガノミックスの結果、アメリカの財政赤字と貿易赤字は更に膨れ上がったのです。

その責任を日本に押し付けて、金利を大幅に上げて、輸入品の値段も下げた結果、日本でもバブルが発生し、それが弾けてこんにちの不況を招いてしまったことも間違いないのです。
そのことは、飯田経夫氏の本に多く書かれていますが、その氏の本もいつか紹介したいと思います。
もはや今のアメリカにおいて、日本も同様に、資産家と一般的な国民を平等に近づけることはできないようです。
先にも書いたように、資産家や金持ちに有利な政策や、法律がまかり通り、その政策をおこなう共和党は、資産家や金持ちの支持によって成り立っているからです。
であるならば、その政策や法律を一掃して、新たに作りかえるような政策は、たとえ政権が代わっても難しいでしょう。
あまりに多すぎるために、変えるにしても非常に時間がかかるものですから。
であるならば、自分が豊かになりたいのか、あるいは今のままでいいのかを自分に問いかけて、どちらに進みたいかを考えて、そのことについて勉強し、それを行動していくことが求められるでしょう。
今のままでいいとしても、とがめだてすることはしません。
何故なら、今のアメリカも日本も同様に、普通に働けば普通に暮らせる社会だからです。
今の社会を憂えて、社会を良くしたいという野心があるのなら、自分が金持になって、可処分所得を増やし、それで世のため人のために使う、という道もあるはずです。
大戦後の60年代~90年代初頭の日本のような平等社会を、為政者頼みにするのではなく、自分の中に眠っている野心家としての魂の勃興を期待しましょう。
しかし、アメリカの財政赤字と貿易赤字、これをどうにかしないといけないことは誰にでもわかるでしょう。
そのためにアメリカ国民が何をすべきか?
日本人も何をすべきか?
非常に悩み、考えさせる問題でもあります。
このレーガンの時期の歴史を見て、内奥を研究して、その道を模索するのに、この本も1つの指針になることは間違いないでしょう。
この本を参考までにお勧めします。
富と貧困の政治学―共和党政権はアメリカをどう変えたか
モバイル
富と貧困の政治学―共和党政権はアメリカをどう変えたか
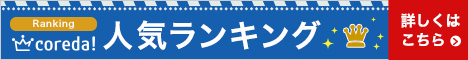

リンク