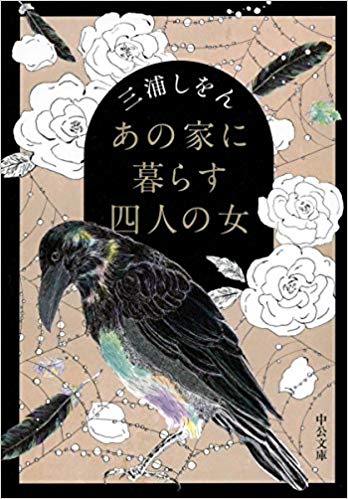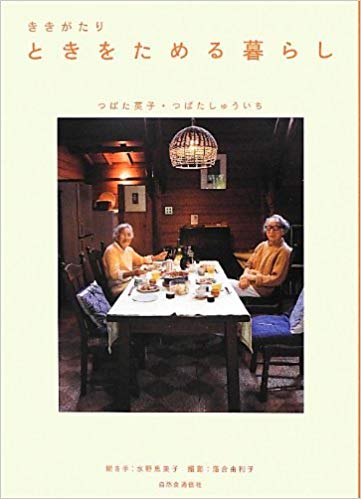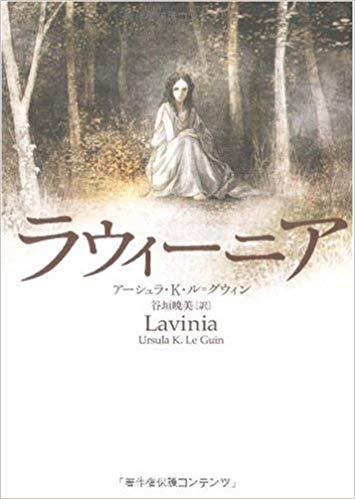最近、本を読む時間が減ったこともあって、なかなかレビューを書けずにいたのですが、
久しぶりにおもしろい作品に出会いました。
それが朝井まかてさんの『雲上雲下』。
朝井さんの作品はこれまで『恋歌』、『阿蘭陀西鶴』、『眩』など、江戸時代の人々を
描いた作品を読んだのですが、この作品はちょっと毛色が違いました。
まず、舞台が・・・物語の中?
語り手は草どん。
丈は二丈を超え、花を咲かせず、種を吐かず、実もつけず、枯れることのない草です。
聞き手は何やらわけありの子狐や山姥。
お話の登場人物は龍の子、田螺に乙姫などなど。
そう、私たちが小さいころからよく知っている昔ばなしの主人公たち。
もう長い間うらうらと眠ったり起きたりを繰り返し、自分が何者であるかも忘れた草どんが、
ひょっこり現れた子狐にお話をせがまれます。
「話なんぞ、わしは知らぬ」と言いながら、「とんと昔の、さる昔」と、するりと
口から言葉が出てくる草どん。
それを自分でも訝しく思いながら、草どんは次から次へと語り始めます・・・
とにかく、読み始めるとまず日本語がとても美しい。
民話なので会話はどこかの地方の方言なのですが、それがまた柔らかく、
懐かしく、できれば声に出して読み聞かせをしてほしいほど。
お話は誰もが知ってる昔ばなしですが、草どんの語りは昔ばなしでは
語られることのなかった出来事まで教えてくれます。
龍の子小太郎のせつない初恋や、恐ろしい山姥が若くて美しかったころ
恋人に裏切られた話・・・
そこにあるのは今の私たちと同じ感情をもった登場人物たち。
草どんの語る昔ばなしは勧善懲悪でも人生の教訓でもなく、ただ人々が喜んだり悲しんだり、
意地悪したり裏切ったりする姿が生き生きと描かれているのです。
小太郎の話、その母親と若い僧の悲恋を聞いた後、山姥は草どんに言います。
「言い伝えの元になった真実を物語ったのか」
・・・中略・・・
「小太郎とお花、犀龍と若僧の恋は、人の口から口へと伝えられる間に
削ぎ落されてしもうたのだろう。長い時をかけて、枝葉は伐られるものゆえ」
「その枝葉こそが、物語の命脈ぞよ」
山姥は続けます。
「お前さんは我知らず、蘇らせたのよ。物語の者らの心を。
酷さと弱さ、身勝手のほどを。いかんともしがたい、いたたまれぬほどの運命を」
「そして、希みを」
嫌われ者の山姥の言葉、なかなか深いです。
そしてこの後、子狐の正体がわかり、そしてまた草どんが何者であったのかを知り、
自らの物語を始めます。
そして・・・、終盤はちょっと映画の「ネバーエンディング・ストーリー」を
思い起こさせるような・・・

昔ばなしとは、所詮語られることがなければ消え失せてしまう世界。
小太郎は言います。
「おらたちの話を、もう誰も聞きたがらない、忘れられてゆくばかりなんだ」
私たちが子どもの頃は、確かに昔ばなしはもっと身近にあったような気がします。
今はありがたいことに、世界中の絵本や物語に触れる機会がふえました。
それはとてもうれしく幸せなことなのですが・・・
我が家の子どもたちが小さい時、ふと、思ったことがあります。
図書館でたくさんの絵本を借りて読んではいるものの、日本の古くから伝わる昔ばなしは
親が語らなければ子どもたちは知らないまま大きくなってしまうのではないだろうか、と。
それでも、あのころはまだテレビアニメで「まんが日本昔ばなし」があって
見たり聞いたりする機会はありました。
(それを本にしたものを義父母が買ってくれて、子どもたちもよく読んでいました)
でも、色鮮やかな絵本やわくわく刺激的な物語がたくさんある今、
わざわざ日本の昔ばなしを手に取る子どもたちがいるのでしょうか。
また、以前のように昔ばなしを語ってやれる親や、おじいちゃん、おばあちゃんが、
どれほどいるでしょう。
私自身もうおばあちゃんと呼ばれておかしくない年齢ですが、小さい時に聞いた昔ばなしを
そらで上手に語る自信はありません。
いつか、「おばあちゃん、お話して!」って言われるようなおばあさんに、なりたいものですねえ・・・
この作品を読んでいて、思い出したことがあります。
私の両親はともに忙しく働いていて、また姉たちとは年が離れていたので、
私はいつもひとりおとなしく遊んでいるような子どもでした。
休日に家族で出かけることもなく、小さいころの思い出といえば、怒られて
祖母にお灸をすえられたとか、姉妹喧嘩をしたことぐらいしかないのですが

そんな中で今でもよく覚えているのは、父が私を寝かしつけるのに
(ということはかなり小さかったのでしょうね)、自分で童話をアレンジしたお話を
してくれたことなのです。
それが、とてもうれしくて、面白くて。
今でも覚えているのは、ジャックと豆の木かなんかのアレンジで、
空に向かって豆の木を上っていたら途中から倒れてしまい、太平洋をまたいで
アメリカに着いてしまった、みたいな話(笑)
いや、豆の木ではなく梯子だったかな?
父が私を寝かしつけること自体珍しく(と思います)、またお話をせがんでも
してもらえるとは限らなかったので、実際聞いたのはほんの数回のことだと思うのですが、
半世紀以上過ぎた今でも覚えているものなんですねえ・・・
物語を語る時間は、語り手にとっても聞き手にとっても幸せな時間。
私にとって今は亡き父との幸せな思い出です。
今思うと、それが今の私の原点になったのかなあ・・・