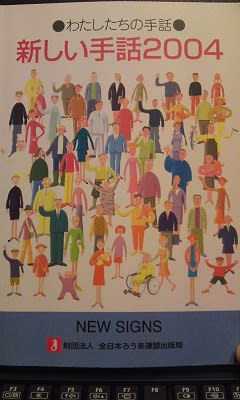| 米原万里の「愛の法則」 (集英社新書 406F)米原 万里集英社このアイテムの詳細を見る |
手話通訳者統一試験を目指した勉強会のメンバーから勧められて読みました。
第一章が「愛の法則」です。元は石川県の高校での講演会だったようですが、こんなタイトルの講演会を高校生に向かってやるって米原さんはやっぱ凄い人かも・・・。
第二章は「国際化とグローバリゼーションのあいだ」ということで、通常「グローバリゼーション」とはアメリカなどが自分たちのやり方を世界に広げることを意味するのに、日本の「国際化」というのは世界のスタンダードに近づける(迎合する)ことでしかなく正反対の意味だとばっさり。そして日本は島国故に能天気でいつも最強国一辺倒の「国際化」しかしてこなかったと。
米原さんは、英語を通じての国際化ではなく様々な国と直接の関係を築いてこその「国際化」だと説かれています。そのためには二つの外国語を身につけると良いと勧めておられます。私も英語がさっぱりできなくて嘆いてきましたが、これからはフランス語も併せて勉強して行くぞ!などと考えています。
さて第三章「理解と誤解のあいだ-通訳の限界と可能性」は、1998年に愛知県で開かれた文化講演会の記録です。一種の通訳論になっていてこの本を薦めてくださったOさんも「手話通訳者にも参考になります」とおっしゃってました。章タイトルの「理解と誤解のあいだ」が示すように言葉が違うということはすなわち文化が違うと言うことであって「同じ言葉でも思い浮かべるものは人それぞれ」であるということが中心テーマになっています。そして「ズレを最小限にするため」通訳が生まれたのだけれども、通訳の難しさは次のようなことであると図入りで説明されています。すなわち通常のコミュニケーションでは、(1)話し手の思い描く概念が(2)コード化され(3)表現され、その(4)メッセージが相手に認知され、(5)解読されて、ようやく(6)概念として伝わるのに「通訳を介したコミュニケーション」は(4)メッセージが通訳者に認知され、(5)解読された後に、(6)通訳者の思い描いた概念が、(7)別の言語にコード化され、(8)表現されて、やっと(9)相手にメッセージが認知され、(10)解読され、(11)相手の概念となるという経過をたどるため、(1)話者の概念と(11)相手が思い描いてくれた概念が等しくなることがよりいっそう難しくなるとのこと。従って通訳者の役割とは(1)と(11)が少しでも近づけるよう努力する必要があるのであって「話者の言葉を表面的に相手の言葉に言い換える(置き換える)」ことではないのだと説かれているのです。まさに通訳という行為の本質、一番大切なところをお話しされているのですね。
次には通訳者に求められる資質として「瞬時に言葉を選ぶ能力と努力」についてお話しされています。この「瞬時に」というのが同時通訳者のもっとも大切なところで「通訳でいちばん大変なのは時間の問題なんです。いい訳を選ぶために考えたり調べたりしている時間がない。ではいったいどうするのかというと、事前にできるだけ自分の頭の中の辞書を豊かにしておくしかないんです。」と「努力」の大切さを強調されています。
その上で現場の通訳テクニックとしては「字句どおり全部そのままに(通訳を)やっても、情報が多すぎて逆に伝わらないのだったら、省略できるところは省略して、ちゃんと伝わるようにしたほうがよいわけです。最終的に双方のイメージが一致することが大事ですから、途中の部分でいくら一生懸命になっても、肝心なところがだめになってしまったらなんにもなりません。通訳というのは、ある意味ではそういうふうに腹をくくって、初めて成り立つわけです。」と教えてくださっているのです。
もう一つのテクニックは、言葉の意味は文脈で決まるということです。そのため「その文脈とは何かということを考えていくと、それは文章の中の文脈だけではなく、その言葉を取り巻いている環境だったり、外の世界の歴史的文脈だったり、さまざまな要素が入ってきます。ですから、言葉を取り巻く状況そのものの理解を深めるように、できるだけ努めているわけです。」とここでも通訳者が通訳するに当たって準備(勉強)すべきことがらとは「環境や歴史」にまで深く立ち入って理解することであると教えてくれているのです。
第三章の終わりに米原さんが書かれた次の文章はこの本の中で私が一番気に入った一文であり、私が手話通訳者として座右の銘としたいくらいです。
「みんなが同時に笑えて、一緒に感動できる。いつもそれを目指しています。不完全だけれども、とにかくいつもそれを目指しつづけるというのが、通訳という職業ではないか思っています。」
最後の第四章は「通訳と翻訳の違い」というテーマで神奈川県の要約筆記協会での講演会です。
ここではいくつかトレーニング方法について参考になりました。
ひとつは「輪読会」。声を出して読み合わせるヤツですね。私も今度通研の勉強会で研究誌の読み合わせを試してみたいなと思いました。
二つ目は「立体的な読書」です。読んだ本や文章の内容を読み終わってすぐに要約して話すという方法です。「その本を読んだことがない人に、どんな内容か分かるように伝える」のだそうです。なるほど、これなど通訳者養成講座の基礎トレーニングに是非取り入れるべき方法ですね。
三つ目は「読書こそ最良の学習法」です。「通訳になるにはどれくらいの語学力が必要かと聞かれるたびに、読書を楽しめるくらいの語学力で、それは外国語だけではなく日本語もですよ、と強調するわけです。」と書かれています。
手話のDVDもいまはたくさん出ていますから、それらを何度も繰り返し見ることが大切ですね。そしてもう一つ「日本語」の読書も大切なわけです。
米原さんは「通訳には、分析的に物を聞き取って正確に把握する力と、それをもう一度統合してまとめて表現する能力、この両方が必要なんです。」として第四章の最後にこんなことを書かれています。私もこうしたスタンスを忘れず精進して行けたらいいなと感じました。
生きた言葉にするためのプロセス
通訳するときに、そのもやもやの結果として、つまり概念の結果として出てきた、コード化されて文字になったものや音になったものだけを拾って訳していたから、私は同時通訳できなかったのです。(中略)ですから通訳するときには、このもやもやをまた作り出さなければならない。つまり、先に言葉が生まれてきたプロセスを、もう一度たどらなくてはいけない。言葉が生まれてそれを聞き取って、あるいは読み取って、解読して何が言いたいかという概念を得て、その概念をもう一度言葉にしていく。つまりコード化して、音や文字にしていくプロセスを経ないと、生きた言葉にならないんですね。その結果だけをやるほうが早いと思われるかもしれませんが、実は今のプロセスを経た方が早いのです。
なぜかと言うと、言葉というのはその部品ではなくて一つのテキストだからです。小説だけではなくて、例えば、物理の好きな人は物理学でもいい、サッカーが好きな人はサッカーの記事でもいいけれども、言葉とはそういうテキストなのです。このテキストになったものを受け取って、そしてまたテキストにしていくプロセスです。だから単語ごとに拾って暗記したり、あるいは文法という骸骨の部分だけを頭に入れるということを、生きた言葉と無関係にいくらしても、ほとんど意味はないですね。魅力もありません。おそらく概念を捉えて訳すということをして、同時通訳は成り立つと思います。手話の場合はどうでしょうか、おそらく一語一句の訳は不可能ではないかと思うのですが、それができるという信仰を捨てない限り、通訳としての飛躍は不可能だと思います。