
ブッカー賞作家イアン・マキューアンのベストセラー小説を、『プライドと偏見』のジョー・ライト監督が映画化。幼く多感な少女のうそによって引き裂かれた男女が運命の波に翻弄(ほんろう)される姿と、うそをついた罪の重さを背負って生きる少女の姿が描かれる。運命に翻弄(ほんろう)される男女を演じるのはキーラ・ナイトレイと『ラストキング・オブ・スコットランド』のジェームズ・マカヴォイ。映像化は困難と言われた複雑な物語を緻密(ちみつ)な構成でスクリーンに焼きつけた監督の手腕に注目。[もっと詳しく]
「アラベラの試練」という作品が、最初でありまた最後であった。
2002年に出版され、イギリスで150万部のベストセラー、世界39カ国で出版されたイアン・マキューアンの「贖罪」という小説には、とても惹き付けられるものがある。
この小説での重要なヒロインは、上流階級のタリス姉妹だ。
姉のセシーリア・タリスは、キーラ・ナイトレイが演じているが、妹のブライオニー・タリスは、13歳の頃をシアーシャ・ローナン、18歳の頃をロモーラ・ガライ、そして77歳の頃をヴァネッサ・レッドグレープが、演じ分けている。
物語は、13歳の多感な少女であるブライオニーが、「嘘」をついたせいで、姉と身分の低い使役人の子どもであるロビー・ターナー(ジェームズ・アカヴォイ)の恋路が切り裂かれることになる。
小説家として名声を得たブライオニーが、晩年にずっと抱え込んできた「罪の意識」を、「贖罪」という小説で発表し、回想するという構成をとっている。
ともあれ、はじまりは、13歳の少女の「嘘」である。

少女は、なぜ「嘘」をつかなければならなかったのか。
冒頭、早熟な少女は、自分で書いた戯曲を、遊びに来ていたいとこたちを巻き込んで一幕の家庭劇のように演じようとしている。
主題は「アラベラの試練」。
この物語の巧みさは、実は少女が書いた「アラベラの試練」に、皮肉なことにその後の姉妹の運命が暗示されているところにある。
「アラベラの試練」はオペラ「アラベラ」から着想されているのだろう。
このオペラでは、ある青年士官に恋する妹であるが、その青年士官は姉に恋している。しかし、姉は、冷淡である。妹は、姉の名前で、青年士官に恋文を書く。この姉と妹の「恋文」を通じての二重性は、生涯の運命を決定付けていく・・・。
少女は、創作熱に浮かされて、夢中で「アラベラの試練」7頁を書き上げ、母にみせ、感心される。
少女は大好きな兄リーオンが帰ってくることが嬉しくて、この戯曲を書き上げたのだ。
「贖罪」の冒頭部分から引用すると、次のように描かれている。

ブライオニーには知るよしもなかったが、この瞬間こそは彼女の企てがもっとも実現に近づいたときだった。それに匹敵する満足はほかには得られず、以後のすべては夢と挫折に終わった。明かりを消したあとの夏のたそがれどき、天蓋つきベッドの心地よい暗がりにもぐりこんだ彼女は、しばしば輝かしくも憧れに満ちた夢想で胸をときめかせたものだが、それらの夢想はひとつひとつが小さな劇であり、主人公は決まってリーオンだった。たとえば、リーオンの人のよさそうな大きな顔が、孤独と絶望に沈むアラベラを見て悲しみに歪むところ。あるいは、ファッショナブルな街の社交場でカクテルグラスを手にしたリーオンが、友人たちに自慢しているところ――そう、ぼくの妹のブライオニー・タリス、有名な作家のね、もちろん聞いたことがあると思うけど。さらにまた、最終幕が下りたとき、興奮のあまり拳を突き上げるリーオン。もっとも、幕などここにはなかったし、幕のある舞台に彼女の芝居がかかる気づかいもなかった。この芝居の上演は、従姉弟たちのためではなく、兄の帰還を祝うため、兄の賞賛を勝ちえるためであり、そしてまた、取るに足らぬガールフレンドたちから兄を遠ざけ、正しい妻――田舎住まいに戻るよう兄を説得し、ブライオニーに新婦付き添い(ブライズメイド)になるよう優しく頼んでくれるような妻――へと導くためなのだった。
「贖罪」(新潮社より)

兄リーオンはなかなか故郷に戻ってこない。
少女の兄を慕う気持ちは、無意識にロビー・ターナーに転化することになる。
オペラ「アラベラ」と同じように、姉はロビーに冷淡なような仕種を見せている。
早熟な少女は、小説を創作するのと同じように、自分の側に、世界を再構成する鍵があると錯覚する。
ロビー・ターナーに思わせぶりな幼い媚態を仕掛けながら、本当の恋ではなく、恋の真似事のような感情を弄びながら、たぶん創作活動の「種」としようとしている。
姉セシーリアは、ブライオニーともかなり年が離れているが、ケンブリッジ大学出の才女であり、煙草をひっきりなしに吸いながら、「拒絶的でコケットで几帳面、自信家で世俗的であり過度なまでにドライな性格」のように描かれている。
空想家で、整頓好きで、人の感情を先回りしながら、自分の世界地図を丹念に色分けて秩序化しているようなブライオニーとは、ある意味対極の性格のようにも、描かれている。

昼下がりの噴水で、ささいなハプニングに乗じて、セシーリアがロビー・タナーに見せた挑発的ともみえるエロチックな振る舞いは、ロビー・ターナーのセシーリアへの思慕に火をつけることになる。
その光景を、偶然目にしてしまったブライオニーは、創作世界の物語の「序・破・急」の「破」を感知したかのように、想像力に火がつけられることになる。
その構成の展開には、必ず自分が関与する必要がある、と思いなすようになる。
ここではほんとうは、ブライオニーによって、ロビー・ターナーに向けての姉セシーリアを擬しての手紙が書かれなければならなかった。オペラ「アラベラ」の筋書きのように・・・。

けれど、展開はそうはならなかった。
ロビー・ターナーの側が、セシーリアに燠のようにくすぶったエロスの衝動を抑えることが出来ず、欲情的な手紙をタイプすることになる。もちろん、それは密室での自慰行為のようなものであり、セシーリアには別のスタンダードな一文をしたためる。
ブライオニーは、その「恋文」を姉に渡すよう頼まれ、それを覗き見ることになる。それは間違って渡されてしまった、欲情的な一文のほうであった。
この「性的な」表明は、ブライオニーを混乱させる。彼女の言語世界に、まだあまりにも「性」は、空想の領域である。しかも続いて、蔵書室でのロビー・ターナーとセシーリアの「行為」を目撃してしまうことになる。
早熟な少女ではあるが、生身の「性」は、彼女の言語の側に、世界秩序の側に、そして物語のリアルなモチーフの側に、位置づけられてはいない。
現実が彼女の虚構世界を、あっという間に、超えていくことになる。
その後、従妹のローラが兄リーオンとともにやってきた鼻持ちならない友人のマーシャルに襲われているところを目撃したブライオニーは、犯人を思わずロビー・ターナーだと証言してしまうことになる。
もう一度、物語の主導権を自分の側に取り戻さなければならないという、混乱した意識がそうさせたのかもしれない。
ここからブライオニーは、長い長い59年間にわたる「贖罪」の意識に、つきまとわれることになる。

「プライドと偏見」でオースティンの国民文学である長編小説を、まことに見事に映像作品に仕立てたジョー・ライト監督であるが、今回もまたイアン・マキューアンの複雑な時制が入り組んだ難解で高等的とも言える心理小説を、見事に映像化している。
とりわけ「プライドと偏見」で主役を演じたキーラ・ナイトレイの美しさを存分に引き出したのと同様に、「つぐない」でも、ある意味アプレゲール的な反抗的で自尊心の高いセシーリアが、ブライオニーの「嘘」のために、ロビー・ターナーを獄中に、そしてその後は苛酷な戦場に送り込むようになってから、旧家のお嬢様という位置を遠く離れて、献身的に愛情を注ぎ、ひたすら恋人の帰還を待っている悲劇の女性を貫き通す役柄の、キーラ・ナイトレイを情感深く描いている。
もちろん、本当の主役は、三人の役者で演じたブライオニーにあるとしても。
「感情の長くて興味深い旅路」の終着点の描き方も見事なものである。

「アラベラの試練」で物語ははじまり、そして贖罪劇の終焉も、「アラベラの試練」のかつて演じられなかった劇が、周到に関係者の前で、演じられるという劇的な構成を有している。
冒頭から、タイプライターの音が、もっとも重要なサウンドトラックかのように、映像に終始、重なっている。
僕たちは、そのタイプライターの音を、無意識に耳にしながら、ブライオニーという59年間にわたってこの「贖罪」という作品を紡ぎ出してきた作家の内面を推し量ることになる。
そしてもちろん、この作品を送り出した、イアン・マキューアンという優れた作家のことを・・・。
kimion20002000の関連レヴュー
「プライドと偏見」
「シルク」











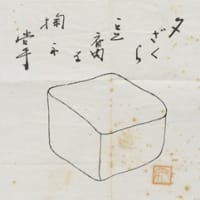


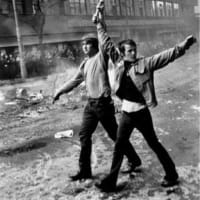



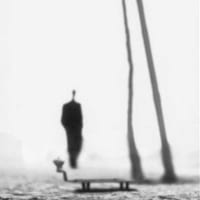

とても読み応えのある原作ですね。
他の彼女の作品は読んでいないので、がぜん興味がわきました。
何度も書き換えられていることに驚きました。
「アラベラの試練」は、最後に、演じられていて、本ならではのいいラストでした。
タイプライターがまことにうまく、サウンドとしても使われていましたね。
時代背景や、登場人物の心理の掘り下げ方もていねいで、とても説得力があったように思います。
原作は機会があれば、お読みください。
とても深いです。
最初の物語「アラベラの試練」にも、こんな意味があったのですね。
これを理解してもう一度見てみたいです。
原作もとても気になっています。
いやいや、勝手な思い込みかもしれないし・・・。
今後とも、よろしくお願いします。
TBがえしさせてくださいね。
翻訳もいいのでしょうが、なかなか読み応えがありますね。
この原作をもとにした脚本家の手腕も、感心させられました。
以前にもつけていただいたことがありましたよね?
TBの仕組みがよくわかっていなくて、
お礼申し上げないままですみません。
『アラベラの試練』にオペラの元ネタがあったとは知りませんでした!
そう思ってみると、どこまですごいんだ!
小説の着想がそもそもそこにあったんでしょうか?
今、原作も読んでいます(一部後半まできました)。
映画では存在感の薄いタリス夫妻や、
エミリーママの妹(ローラと双子の)の生き様も
重要な要素になってますね。
書き込みすぎるほど書いてあるのに、ムダがない。
小説と映画は、マキューアンとライトの間で交わされたラブレターのようです。
結構、難解な小説なんですけどね、これが海外ではベストセラーになっているということも、ちょっと吃驚させられますね。
他のブログでは余り読めない内容ですね。原作を読まれているからでしょうか。
映画においては客観と主観について特に関心を持って観ることが多いのですが、本作のショットにおける主観と客観、場面における主観と客観の使い分けと組合せという意味で、近年これほど感心させられた作品は他にないです。
原作を生かす最大限の努力をした結果生まれたアイデアなのでしょうね。
いやあ、この監督は凄いですよ。
細かいところまで計算していますね。
僕はとても感心しました。
13歳の少女の嫉妬と勘違いが嘘を生み、その嘘が致命的な悲劇を招くという物語。
キーラ・ナイトレイ主演のラブストーリーだとばかり思って見たら・・・。
嘘一つで皆の人生が大きく変わってしまう。
とくに注目すべきは、タイプライターの音と妹ブライオニーに扮するシーアシャ・ローナンの動きかも。
キーラ・ナイトレイのうっとりするような早口や、ダンケルクの海辺の5分半にわたる長回しにも眼を奪われました。
物語の構成も見事で、原作小説のエッセンスを抽出、整理して映画化した監督のジェフリー・ライトの手腕には、私は評価したいですね。
もっとシンプルでストレートな構成にしてもいいんじゃないか、という意見もありますね。
どちらにしても、力量のある監督さんだなあ、という印象は持ちますね。
かなり感心したものの、そうだったんだ~・・と
ちょっとがっかりしたところもあったりして
皆さんが絶賛なさってるほどには思えなかったんですが(^_^;)
キーラの美しさが存分に引き出されてたし、シアーシャ・ローナンのあの演技の上手さが際だっていて
とっても良かったです。
あのタイプライターの音と音楽もこの映画に合ってるなぁって思いました。
当方よりgoo様へのTBは通りにくい様子
ですが、記事は大切に反映させて頂きます。
>下心たっぷりで臨んだ私に、なにか言う権利もなさそうですが
いやいや、僕もほとんど下心があって(女優さんとかね)、見ているわけで・・・(笑)
映画としても見せ方は・・というと、もうちょっと素直な見せ方の方が良かったかなと。
妙に技巧に頼ってしまったあたりが残念で、もっと、ストレートに描いた方が、作品の芯のあたりを見せられたのでは、、、、と思った所でした。
まあ、マカヴォイ君目当てという、下心たっぷりで臨んだ私に、なにか言う権利もなさそうですが。
間違っているかもしれないし、公式サイトにもなにも解説はないんだけど、そう考えた方が、なんとなくブライオニーの気持ちがわかるような気がするんですね。
なるほど!
「アラベラの試練」には元ネタがあるのですね。
そう考えるとブライオニーの見方が少し変わってきます。
もちろん多感で夢見がちな少女ではあるのですが、
思っていたより頭でっかちではないのかもしれません。
聞いたことのある話を膨らませて小説を書く少女が、
兄を慕う気持ちをロビーに置き換えてしまう。
それも気がつきませんでした!
てっきり早熟な少女が恋に恋しているのだと思っていました。
奥が深い作品ですね~
もう一度見直してみようと思います!
とても高等的な作品です。
通常、この作品の映画化なんて、みんな尻込みしてしまいそうなものなのにねぇ。
まあ、「アラベラの試練」の戯曲についての意味づけは、僕の勝手な思い込みしかしれませんけどね。
ブライオニーを演じた3人の女優さんも見事でしたよね。
TBありがとうございます。
冒頭、劇の上演で騒いでいた彼女の戯曲「アラベラの試練」にそんな意味があったとは・・・。
たまたまブックオフで「贖罪」を見つけ購入。
原作、読んでみます。