「宝」といえば人々にとって貴重な品物のことであるが、丁寧に「お」を付けて「お宝」と言ってしまえば、品物を金銭に換算してしまう印象を抱く。「お」を付けると、逆に「宝」の持つ高貴さのイメージが損なわれるような感じがするのは私だけだろうか。テレビ番組の「なんでも鑑定団」でも、歴史的資料の価値を金銭で換算して、一喜一憂しているが、「家宝」だと思って代々大事にしていた品物が、低価格で判断されて出品者が落胆するシーンは、視聴する分には面白い。しかし「宝」は金銭的価値だけで判断されるものではない。
「タカラ」の語源を考えてみると、『大言海』という辞書によれば、タカは高貴の意味で、ラは接尾語という説を紹介し、また、江戸時代の辞書である『和訓栞』では、田力(タチカラ)つまり米の生産の意であることが説明されている。また、高崎正秀著『古典と民俗』によると、手に取り持った神がかりの依代の意で、タクラ(手座)の意味という説もある。これらは、「宝」が「高貴」・「田(米)」・「神」というキーワードで説明されている。必ずしも「お金」や「貨幣」には直接結びつくことはない。
「宝」に関する有名な万葉集の和歌がある。山上憶良が詠んだものであるが、「銀(しろがね)も金(こがね)も玉も何せむに勝れる宝子に及(し)かめやも」、つまり、金銀も玉も、どうして子どもというすぐれた宝に及ぼうかという意味である。「子宝」という言葉もあるが、この「子宝」を金銭的価値で判断されてはたまったものではない。子どもは「宝」ではあっても、決して金銭的価値で判断される「お宝」ではないはずである。金銭では測ることのできない「宝」の価値を考えることは、子どものみならず人間の尊厳をも顧みるヒントになるのではないだろうか。
さて、正月で宝といえば「宝船」を思い起こす。「宝船」は、宝物や米俵、七福神を船に乗せた一枚絵で、正月にこれを枕の下に敷いて寝ると吉夢を見ることができるという。この慣習は中世には既にあったとされ、江戸時代には、年末にこの宝船売りが町を売り歩いて、一般化したものである。様々な宝船の図像を見ても大判・小判(お金)がザックザック乗っているものは少なく、圧倒的に米俵が描かれている事例が多い。
そもそも、大判・小判も米俵を模した形をしているように、日本では、お金は米をシンボル化したものであり、しかも、その米は、一年の稲作労働から生まれてきた生産物であり、言ってみれば「生産力の象徴」であった。
これが、いつの頃からだろうか。お金のイメージから「生産力」の意味合いが薄れ、お金が「消費」を第一義としたものになってきている。これは高度経済成長期の出来事であろうか。いや、あえて時代を設定するならば、一九八〇年代ではないだろうか。高度経済成長期を生きてきた世代は、それ以前の自給自足とはいかないまでも、「生産」を基調とした日常生活(第一次産業中心の社会)を経験している。しかし高度経済成長期以降に生まれた世代は、日常生活の基調が「生産」ではなく「消費」へと変化した社会を生まれながらに過ごしてきた。この経験の有無による転換期こそが一九八〇年代であり、現在の高度消費社会、つまり日常生活では「生産」の感覚が薄れ、お金があれば何でもできると考えてしまうような「消費」第一の社会につながっているといえるのではないか。
最後に、とても「宝」とは思えない「お金」・「貨幣」についての思考を述べておきたい。お金は触ると汚いもの、触ると後で手を洗いたくなるという感覚は多くの人が持っている。この点は『お金の不思議―貨幣の歴史学―』(山川出版社)によると、貨幣にはケガレが宿るといい、神社でお賽銭を投げる行為も、よくよく考えるとお金を投げつける行為は神様に失礼にあたるが、なぜかそれが許されてしまう。これは、実はお金・貨幣に自分の災禍・罪穢を移し託して、お賽銭として神社に投げ入れることで祈願行為となるというのである。江戸時代の国学者本居宣長も『古事記伝』の中で「お金を払う」の「払う」と神社での「御祓い」の「祓う」は同じ意味だとし、「今俗に、物を買たる直(アタヒ)を出すを、払ふとも払をするとも云は、祓除の意にあたれり、又これを済(スマ)すと云も、令清(スマス)の意にて、祓の義に通へり」と述べ、「決済」の「済」と「清」も、ハラった後に、スム(清らかな)状態を指すという。お金のない状態が清らかとは、おかしな気もするが、貨幣を手放すことで、災禍・罪穢が清まるのであれば、それにも一理ありそうだ。
人、物、そして心も含めて、世の中のすべてのものを金銭的価値のみで判断していくことは、実は我々が自らが「宝」の持つ価値を放棄することにつながり、結局のところ、お金という単純な価値基準(拠り所)しか持てない脆い構造の社会になってしまうのではないかと、正月早々、要らない心配をしている。
(南海日日新聞2007年1月1日掲載原稿)
「タカラ」の語源を考えてみると、『大言海』という辞書によれば、タカは高貴の意味で、ラは接尾語という説を紹介し、また、江戸時代の辞書である『和訓栞』では、田力(タチカラ)つまり米の生産の意であることが説明されている。また、高崎正秀著『古典と民俗』によると、手に取り持った神がかりの依代の意で、タクラ(手座)の意味という説もある。これらは、「宝」が「高貴」・「田(米)」・「神」というキーワードで説明されている。必ずしも「お金」や「貨幣」には直接結びつくことはない。
「宝」に関する有名な万葉集の和歌がある。山上憶良が詠んだものであるが、「銀(しろがね)も金(こがね)も玉も何せむに勝れる宝子に及(し)かめやも」、つまり、金銀も玉も、どうして子どもというすぐれた宝に及ぼうかという意味である。「子宝」という言葉もあるが、この「子宝」を金銭的価値で判断されてはたまったものではない。子どもは「宝」ではあっても、決して金銭的価値で判断される「お宝」ではないはずである。金銭では測ることのできない「宝」の価値を考えることは、子どものみならず人間の尊厳をも顧みるヒントになるのではないだろうか。
さて、正月で宝といえば「宝船」を思い起こす。「宝船」は、宝物や米俵、七福神を船に乗せた一枚絵で、正月にこれを枕の下に敷いて寝ると吉夢を見ることができるという。この慣習は中世には既にあったとされ、江戸時代には、年末にこの宝船売りが町を売り歩いて、一般化したものである。様々な宝船の図像を見ても大判・小判(お金)がザックザック乗っているものは少なく、圧倒的に米俵が描かれている事例が多い。
そもそも、大判・小判も米俵を模した形をしているように、日本では、お金は米をシンボル化したものであり、しかも、その米は、一年の稲作労働から生まれてきた生産物であり、言ってみれば「生産力の象徴」であった。
これが、いつの頃からだろうか。お金のイメージから「生産力」の意味合いが薄れ、お金が「消費」を第一義としたものになってきている。これは高度経済成長期の出来事であろうか。いや、あえて時代を設定するならば、一九八〇年代ではないだろうか。高度経済成長期を生きてきた世代は、それ以前の自給自足とはいかないまでも、「生産」を基調とした日常生活(第一次産業中心の社会)を経験している。しかし高度経済成長期以降に生まれた世代は、日常生活の基調が「生産」ではなく「消費」へと変化した社会を生まれながらに過ごしてきた。この経験の有無による転換期こそが一九八〇年代であり、現在の高度消費社会、つまり日常生活では「生産」の感覚が薄れ、お金があれば何でもできると考えてしまうような「消費」第一の社会につながっているといえるのではないか。
最後に、とても「宝」とは思えない「お金」・「貨幣」についての思考を述べておきたい。お金は触ると汚いもの、触ると後で手を洗いたくなるという感覚は多くの人が持っている。この点は『お金の不思議―貨幣の歴史学―』(山川出版社)によると、貨幣にはケガレが宿るといい、神社でお賽銭を投げる行為も、よくよく考えるとお金を投げつける行為は神様に失礼にあたるが、なぜかそれが許されてしまう。これは、実はお金・貨幣に自分の災禍・罪穢を移し託して、お賽銭として神社に投げ入れることで祈願行為となるというのである。江戸時代の国学者本居宣長も『古事記伝』の中で「お金を払う」の「払う」と神社での「御祓い」の「祓う」は同じ意味だとし、「今俗に、物を買たる直(アタヒ)を出すを、払ふとも払をするとも云は、祓除の意にあたれり、又これを済(スマ)すと云も、令清(スマス)の意にて、祓の義に通へり」と述べ、「決済」の「済」と「清」も、ハラった後に、スム(清らかな)状態を指すという。お金のない状態が清らかとは、おかしな気もするが、貨幣を手放すことで、災禍・罪穢が清まるのであれば、それにも一理ありそうだ。
人、物、そして心も含めて、世の中のすべてのものを金銭的価値のみで判断していくことは、実は我々が自らが「宝」の持つ価値を放棄することにつながり、結局のところ、お金という単純な価値基準(拠り所)しか持てない脆い構造の社会になってしまうのではないかと、正月早々、要らない心配をしている。
(南海日日新聞2007年1月1日掲載原稿)












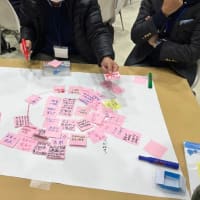







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます