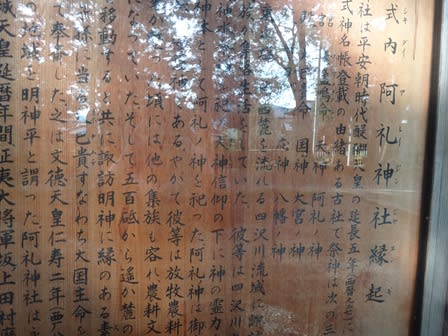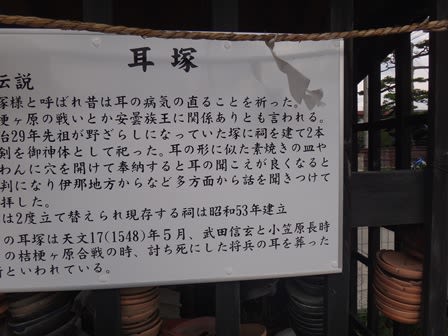10月12日(月) 晴れ時々曇り

歩いていていちばん辛いのは足でも心臓でも空腹でも雨でもなく暑さである。
東海道で熱中症を発症した経験から言って、盛夏とカンカン照りの日はなるべく歩行をしないように努めている。
その意味では今日は最高!この時季は元々肌寒いくらいのこの土地にあって、適当に曇ったり晴れたりの絶好のコンデイション。
朝食を済ませて7時40分に出発。(出発時間を早くするためには、こういう観光地化した街なかの宿は一泊2食付ではなく素泊まりでもいいかも知れない)
木曽福島駅の前の長距離バス亭。安い@!時間の制約がなければこれも手かもしれない。

宿場を出てしばらく行くと御嶽神社。本当はこの神社の中を通る道があったらしいが、気づかずに国道を行ってしまった。だがすぐに道は合流。

右にダムを見て、国道と線路を下に見て旧道は上って行く。

村の道にこんな立札があり、
津島様、って聞いたことあるようでまるきり思い出せなかったので検索してみたらありました。http://www.geocities.jp/gunmakaze/kodomonokoro/29tsusima.html
なるほど~☆歩いていると勉強になります(^^)
さらに進むと道の左側に廻り込む道があり、ガイドブックの地図を見るとトンネルをくぐれとの指示がある。
ところがトンネルの前はこんな幕。通行禁止になったのはつい最近らしい。(ガイドブックは2012年版)
ろくさんが偵察に行くもお先真っ暗でなにもみえない、との報告。

国道に廻り込む。
国道を歩いていても晴れているので気持ち良い。元橋の近くの交差点を過ぎて
ガードをくぐる。
ガードの下にこんな標識。
なるほどここから杉林に入ると小高い遥拝所があった。
鳥居峠では見られなかった御嶽山を拝観しようと西に目をやるが、あいにく白い雲がかかっていた。
御嶽山もいいけど、すぐそばを走る線路が好きだなあ。
木曽路は妻籠から馬籠間を除いては、ほとんど旧道に沿って鉄道が敷いてある。
昔の街道は今の鉄道にとって替わられたのだからたのだから当然と言えば当然だが、木曽川と鉄道と常に一緒に歩いているという感覚が好き。

一里塚の標識を過ぎて
いよいよ昔の木曽路歩きの難所中の難所、木曽の桟(かけはし)が見えてくる。
この両岸の奇岩がすごい。もちろん自然石。木曽福島側から見たところ。

木曽の桟とは、川の両岸をつなぐ橋ではなく、深い木曽川渓谷からほぼ垂直に切り立ちあがる岩場に取り付けられた丸太で組んだような繋ぎ棒のこと。
この赤い橋は向かい側から当時の桟の跡を見るために後世作られた橋である。
説明板↓
対岸からみた桟の跡。国道の下に川岸に垂直に立っているコンクリ柱の間を横に丸太や蔦葛を渡していたらしい。
こういうところを、参勤交代の行列、特に皇女和宮さんなどがどうやって通ったか昔の人に聞いてみたい。

本当は旧道はこの赤い橋を渡らずに桟側を渡る新しい旧道?があったのだがそれも今は危険個所のため、橋を渡って右岸道路、一番新しい旧道??を歩く。
これはけっこう遠回り@。
再び橋を渡る。鬼淵橋である。
と横に錆びた古い橋が横に横にかかっている。説明板を見ると何と、赤沢自然林へのトロッコ電車の軌道だったのだ。
赤沢自然林へは8年ほど前車で来たときに山の中を散策したものだ。


それで、上松宿のマンホールも森林鉄道の図柄。
9時40分頃。
国道の下を回り込んで上松宿に入る。
街道らしいいい曲がり方をしている。

そうか!今大相撲で活躍している御嶽海はここの出身らしい!
上松は木曽路でも相当高い位置にある。駅前の広小路を過ぎ歩道橋の横の道を上ると
上松の街が一望。
上松小学校の前、材木役所跡を過ぎ、ちょっと曲がり角を間違えて山に入りそうになったのを戻って見返り集落に入ると、なるほど振り返りたくなるような絶景。

買い物帰りか前を行くおばさんがゆっくりゆっくり歩いている。
途中の集会所の壁にこんな句が。思わずにんまり(^^)

もう寝覚め集落。当時のままの姿の立て場(お休み処)と向かいの蕎麦屋。
この2軒の間の坂を1㎞ほど下りてゆくと岩と水のおりなす景勝地「寝覚めの床」になるが8年前に一度言っているので今回はパス。
10時半頃。この蕎麦屋がやっていれば問題はないのだがどうやらもう営業はしていない様子。
道端の段差に腰かけてベビーあんドーナッツでおやつ。

上松と次の宿場、須原の間は中仙道にしては長い距離間で12㎞もある。どこかでお昼が食べられるか少々不安なので前もって甘いものでしのぐ。
さて、寝覚め郵便局で分かれている道を左に取り、
上松中学校の前を通り石畳の道を下って滑川を渡る。
上がったり下ったりの連続。
そしてガードをくぐると国道にぶつかる。
そこでなんと!左にバーンと流れ落ちるのが名勝「小野の滝」である。
こんな国道の沿いに、さらに滝の上には線路が通っているという珍しさ!@

昔の中仙道歩きの旅人がタイムマシンでやって来てこれを見たらびっくりして腰を抜かすだろうなあ。
しかし水は全然汚れていない。あくまで透明で美しい。
ここからはしばらく国道沿いに歩いていくが、小さな集落に入り込む旧道がところどころにあって飽きない(が、お腹が空いてきたし、アップダウンの激しい道が続くのでちょいと疲れてきた)
荻原一里塚の楓と榎の合体木。
木曽古道への入り口。
細い道の向こうは民家の庭のような空き地。おじさんが焚火していた。
この焔が火事誤認を呼び起こし、地元の消防署で火災発生警報を街中に鳴らしていた。
こんな道をしばらく進む。

立町を過ぎ、倉本の集落へ。小高い山の上の集落。

また少し国道に出て今度は右の池尻集落を過ぎる。
もう12時過ぎてきたのでお腹が空いてきた。ひとつだけ国道沿いにうどん屋さんがあったが、あくまで旧道を歩く~++;
この日は須原を15時04分の電車に乗らねばならないので(一本逃すと1時間待たなければならない)、うどん屋さんでゆっくり食べるのも時間が心配であった。
で、また午後の照り返しの強くなってきた国道を歩いているうちに疲れて来て、神明神社のあたりでは無言の喧嘩。
あそこでぜひにうどん屋に入っておくべきであった、いやそれでは落ち着かなかった、だいたい我慢が足りないとか、イニシアチブの取り方が云々・・・と境内の階段で
やりあう。(けっきょく、のれんに腕押しでだいたいわたしが自己嫌悪となって喧嘩は終結するけれど~~)
それでもようやく須原の文字が見えてきた。

左の道にひょいと入り込むともう須原の駅。
須原は「水舟の宿」といわれるだけあって清水が家々の前に設えた木船を伝って滴りこの宿場の暮らしを潤している。

木曽路に入ってたくさんの集落や宿場でこのような水場を見てきた。
水がきれいなのはこのあたりに住む人々にとってごくごく当たり前の事なのだろうなあ、としみじみ感じる。

14:00少し過ぎ。
駅のベンチにはよそのご夫婦のリュックあり。
どうやってお帰りになるのですか?、と聞くと「東京ですが中津川まで出て名古屋から新幹線です」と答えられた。
ここは東京と京都のほぼ中間なので交通アクセスがとても難しいですね、とお互い同じ感想。
わたしたちは来た道を戻り塩尻まで出てまた「あずさ」に乗る。名古屋周りも考えたが、来た道を振り返るためにも次回の往きも同じ予定である
駅前の雑貨屋さん(店と呼べるのはその1軒だけであった)でアイスクリームを買い、待合室で食べる。お昼を食べていないので超美味しい(^0^)!

今日の歩行は珍しく足に来た。駅の階段もちょっとロボット歩きのようになっていた(^^).
帰りの乗り継ぎ、塩尻の駅構内で立ち食いそばを食べる。美味しかった!!
17時07分の「あずさ」に乗り込む。次回はいよいよ木曽路最後です。

本日の歩行距離:迷い道、回り道含め約25㎞。
京都まで、あと約226㎞。