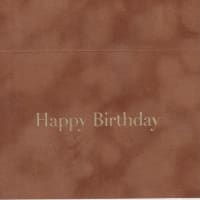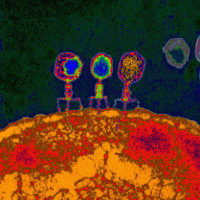コメントらんのご質問を参考に編集部内で少しまとめた情報です。
(必ずしも青木編集長の個人的意見ということではないですが)。
-------------------------------------------------------------
献血をするときに、「まさかHIV検査目的じゃないですよね」を確認する項目はあるのですが、「そうですよん」と答える人は通常いません。
「感染しているかもね~しらないよ~」とにっこり検査する人もいないでしょうから、あとで陽性をわかった場合は、「なんてこった!知らなかったヨ!」という状況になります。
日赤の血液センターがHIV陽性者に連絡をして教えてくれるかどうかは、センターの方針次第だそうです(全体の決まりごとではないらしい)。
拠点病院の学会発表を聞けばわかりますが、診断契機に「献血」という項目がありますし、実際に患者さんは血液センターの医師の紹介状をもって専門病院に来ます。
患者さんのブログにも「センターから連絡が来てさ・・」という体験記があります。
「教えていない」わけではありません。でも「全員に連絡している」というわけではないそうです。
微妙です。
教えてくれる親切なセンターは、おそらく「気づかないでエイズを発症したり、家族やパートナーに感染したらたいへんだろう」というお気遣いをしてくださっているのではないかとおもいます。
(杓子定規に「教えないよ」なんてことになったら困りますね)
「献血をした人(供血者)からの遡及調査」というものがあります。
平成14年4月から平成20年2月末までで、輸血でのHIV感染が疑われた事例は1例、B型肝炎事例は394、C型肝炎事例は4例。そのうちの1例、B型肝炎の事例が学会で報告されていました。
複数の人の血液を用いて製剤がつくられるので、特定のロットから、供血者を割り出し、さらにフォローをするというのは20人・30人だとたいへんなことですね。
---------------------------------------------------
平成19年3月に、輸血によるHBV感染が疑われた事例では、保管検体個別NATは陰性。
供血者の1人が平成19年1月にB型肝炎を発症していたとの情報が得られ、供血者のHBV-DNAと、発症をした患者のDNAで塩基配列が一致。
20プールNAT陰性、HBV保管検体個別NAT陰性だが、追跡調査により輸血用血液製剤からの感染が示唆された。
(第31回日本血液事業学会総会 2007年10月)
---------------------------------------------------
血液は低リスク層から提供してもらうべきだ、という話。
「HIV 感染献血者の高危険性行為に関する調査と血液の安全性確保対策」
Japanese Journal of Transfusion Medicine, Vol. 51. No. 3 51(3):333―340, 2005
http://www.yuketsu.gr.jp/gakkaishi/51-3/051030333.pdf
もうひとつ。2007年の台湾での献血→HIV感染3例、の話。別のMLに昔紹介した話題。
台湾の保健省担当者によると、3例のうち1例は12月はじめの外科手術後にすでに死亡。
残りの2例は加療中。政府は200万台湾ドルの補償を行う。
これ以前に、この23年間で台湾では輸血でHIVに感染した事例が16例ある。
2007年12月までに台湾で報告されているHIV/AIDS症例は14711例。
当局は献血ドナーに対して法的措置を検討中。
7月に改正された法律では、HIVに感染していることを知りながら献血を行った場合は5年から12年の懲役刑となっている。
台湾CDCの関係者が語るところによると、献血を行った男性は今年7月と11月に行った分を含めこ
れまでに6回の献血を行っている。記録によれば同一人物は2006年3月にも献血を行っているがこの時点ではHIV感染は把握されていない。
11月のスクリーニングでこの血液はHIV感染が判明し、すでに廃棄されている。
危険な性行為を行っている場合、複数の性的パートナーがいる場合、ホモセクシュアル/バイセクシュアルの場合、性感染症にかかったことがある、HIVに感染していると疑われるような場合は献血をしないようにと関係者はよびかけている。
消費者団体は政府に対し、新しいNATスクリーニングを採用するようにプレスカンファレンスで要求。これは感染が11日目からHIVを検出可能な検査。
消費者団体代表によると、すでに政府は医療関係者からHIV抗体検出まで22日かかるELISA検査から新しい検査に変更するように提言を受けていた。
これ以前に30代のゲイ男性が1998年から9年間献血を続けていた事例を示し、政府が人々の健康を守る義務を怠り続けていたを指摘。
政府の医療問題担当者は、HIV検出までの機関は22日から11日に短縮されており、輸血感染のリスクを下げることができると語る。
この11月医療問題担当部署は台湾輸血財団に対して、10万検体にこの新しい検査を行うこをと4000万台湾ドルで委託すしたばかりであった。
The China Post(2007年12月のニュース)
(必ずしも青木編集長の個人的意見ということではないですが)。
-------------------------------------------------------------
献血をするときに、「まさかHIV検査目的じゃないですよね」を確認する項目はあるのですが、「そうですよん」と答える人は通常いません。
「感染しているかもね~しらないよ~」とにっこり検査する人もいないでしょうから、あとで陽性をわかった場合は、「なんてこった!知らなかったヨ!」という状況になります。
日赤の血液センターがHIV陽性者に連絡をして教えてくれるかどうかは、センターの方針次第だそうです(全体の決まりごとではないらしい)。
拠点病院の学会発表を聞けばわかりますが、診断契機に「献血」という項目がありますし、実際に患者さんは血液センターの医師の紹介状をもって専門病院に来ます。
患者さんのブログにも「センターから連絡が来てさ・・」という体験記があります。
「教えていない」わけではありません。でも「全員に連絡している」というわけではないそうです。
微妙です。
教えてくれる親切なセンターは、おそらく「気づかないでエイズを発症したり、家族やパートナーに感染したらたいへんだろう」というお気遣いをしてくださっているのではないかとおもいます。
(杓子定規に「教えないよ」なんてことになったら困りますね)
「献血をした人(供血者)からの遡及調査」というものがあります。
平成14年4月から平成20年2月末までで、輸血でのHIV感染が疑われた事例は1例、B型肝炎事例は394、C型肝炎事例は4例。そのうちの1例、B型肝炎の事例が学会で報告されていました。
複数の人の血液を用いて製剤がつくられるので、特定のロットから、供血者を割り出し、さらにフォローをするというのは20人・30人だとたいへんなことですね。
---------------------------------------------------
平成19年3月に、輸血によるHBV感染が疑われた事例では、保管検体個別NATは陰性。
供血者の1人が平成19年1月にB型肝炎を発症していたとの情報が得られ、供血者のHBV-DNAと、発症をした患者のDNAで塩基配列が一致。
20プールNAT陰性、HBV保管検体個別NAT陰性だが、追跡調査により輸血用血液製剤からの感染が示唆された。
(第31回日本血液事業学会総会 2007年10月)
---------------------------------------------------
血液は低リスク層から提供してもらうべきだ、という話。
「HIV 感染献血者の高危険性行為に関する調査と血液の安全性確保対策」
Japanese Journal of Transfusion Medicine, Vol. 51. No. 3 51(3):333―340, 2005
http://www.yuketsu.gr.jp/gakkaishi/51-3/051030333.pdf
もうひとつ。2007年の台湾での献血→HIV感染3例、の話。別のMLに昔紹介した話題。
台湾の保健省担当者によると、3例のうち1例は12月はじめの外科手術後にすでに死亡。
残りの2例は加療中。政府は200万台湾ドルの補償を行う。
これ以前に、この23年間で台湾では輸血でHIVに感染した事例が16例ある。
2007年12月までに台湾で報告されているHIV/AIDS症例は14711例。
当局は献血ドナーに対して法的措置を検討中。
7月に改正された法律では、HIVに感染していることを知りながら献血を行った場合は5年から12年の懲役刑となっている。
台湾CDCの関係者が語るところによると、献血を行った男性は今年7月と11月に行った分を含めこ
れまでに6回の献血を行っている。記録によれば同一人物は2006年3月にも献血を行っているがこの時点ではHIV感染は把握されていない。
11月のスクリーニングでこの血液はHIV感染が判明し、すでに廃棄されている。
危険な性行為を行っている場合、複数の性的パートナーがいる場合、ホモセクシュアル/バイセクシュアルの場合、性感染症にかかったことがある、HIVに感染していると疑われるような場合は献血をしないようにと関係者はよびかけている。
消費者団体は政府に対し、新しいNATスクリーニングを採用するようにプレスカンファレンスで要求。これは感染が11日目からHIVを検出可能な検査。
消費者団体代表によると、すでに政府は医療関係者からHIV抗体検出まで22日かかるELISA検査から新しい検査に変更するように提言を受けていた。
これ以前に30代のゲイ男性が1998年から9年間献血を続けていた事例を示し、政府が人々の健康を守る義務を怠り続けていたを指摘。
政府の医療問題担当者は、HIV検出までの機関は22日から11日に短縮されており、輸血感染のリスクを下げることができると語る。
この11月医療問題担当部署は台湾輸血財団に対して、10万検体にこの新しい検査を行うこをと4000万台湾ドルで委託すしたばかりであった。
The China Post(2007年12月のニュース)