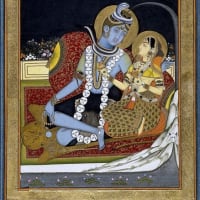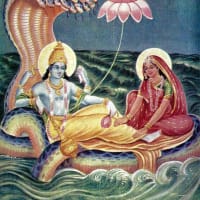第4章 システムとは何か
4-1 吉本の「共同幻想」論批判
① 上部構造の語の放棄:吉本
共同幻想は、上部構造、イデオロギー、あるいは『経済学批判』の「上層建築」、「社会的意識形態」と言い換えられる。
吉本は下部による上部決定論を連想させる上部構造の語を放棄。共同幻想の語を作り上げる。(柳田の共同幻覚が参考。)
『共同幻想論』は「子供たちが感受する異空間の世界」についての書とも言える。(吉本)
廣松の共同主観性と「よく似た」問題意識を持っている。
② 柄谷の吉本批判(その1):「対幻想」も「共同幻想」から逃れられない
田辺元の「種の論理」の類と個の間の中間項としての種。その種にあたるのが吉本の対幻想。
柄谷は言う。「個人幻想」や「対幻想」を立てても「共同幻想」から逃れられない。すべては「共同体」の「共同幻想」の所産。
柄谷は、共同体からおしだされた「外部」「他者」、単独者、単独者との非対称的な関係が、共同体に「場所」を持たないものとして必然的に創出されると言う。「場所」なき場所が「交通空間」。
③ 柄谷の吉本批判(その2):共同幻想論は他の国家・他者からの視点を欠く
共同幻想は国家(家族と背反しつつ拡大)を想定する。
ところが他の国家の問題が消える。例えば、日本人が「平和憲法を持っている」と思っても(※日本人の共同幻想)、外から見れば「アジア随一の軍隊を持った国家」。
共同幻想は物語とその伝承であり創世・創設神話を含む。吉本は、それについての他者の視点を語らない。
④ 柄谷の吉本批判(その3):生産様式を交換様式と捉える(199頁)
吉本は下部構造に対して相対的に自立した「幻想」を語る。(上部構造の、下部構造による決定論を拒否。)
ところがここには上部-下部の二元論がある。
柄谷はこの二元論を壊す。
下部構造における「生産」を、「交換」の1形式と捉える。
国家(ステート)、ネーション、経済はそれぞれ「交換」の固有の形式を持つ。
生産様式を交換様式と捉える(柄谷)。
ルイ・アルチュセールに依拠しつつ、原始的氏族的生産様式は「互酬」、アジア的生産様式、古典古代的奴隷制、ゲルマン的封建制は「略取-再分配」、資本主義的生産様式は「商品交換」:3つの交換様式。
3つの交換様式の接合、その接合の仕方と濃淡が、多様な社会構成体をもたらす。
吉本は、共同体の重層化はもとになる共同体を大きく壊さずに接合されるとする。彼は共同体の古層・基層を追い求めるだけで単線的すぎる。(合田)
4-2 「個人幻想」「対幻想」「共同幻想」:吉本
① 対幻想と共同幻想の「同致」etc.
吉本は複雑系の思想家。だから丸山の公私の峻別を批判。
「錯合」の平面化の阻止のため「個人幻想」「対幻想」「共同幻想」のレベルを区別。
個人幻想と共同幻想の「同致」。Ex. 「私は日本人である」
対幻想と共同幻想の「同致」。国家をエロス的に捉える。対幻想の次元で大切な人のために共同幻想である国家に身を捧げる。(石原慎太郎『国家なる幻影』)
①-2 対幻想
対幻想と共同幻想が競合するとき、前者を選ぶのが女性。(吉本)
フロイトは対幻想の領域を共同幻想の領域まで拡大しすぎた。
男女だけでなく、親子、姉妹、兄弟も性的である:対幻想。
② 「憑依」または「同調」
自己幻想が共同幻想に憑く。または自己幻想が共同幻想に侵食される。
その理由は、①共同幻想が自己幻想に先立つ先験性だから:「生誕」の問題。②「死」も先験性である(ハイデガー)。
「超越論的なもの」の二つのアスペクト:「生誕」と「死」。
ただし「死」の共同幻想にはないが、「生誕」の共同幻想にのみ見られるのは、対幻想と村落の共同幻想が相互に移行すること。
巫女は対幻想と共同幻想との「同調」or「同致」。
③ 「死」の先験性
「その死に向かって存在している」現存在の時間性を、村落共同体の共同幻想が、空間の方向に疎外(※=表出)したものが他界との境目、「危機的な分界地帯」、共同体と共同体の「間」。Ex. 『遠野物語』の「デンデラ野」
④ 「生誕」の先験性
自己幻想に先立つ先験性は「生誕」では「母体」である。
「まだ自分自身の中に自己を持つに至っていない胎児の心は子の他人(※母体)のなかに自分の自己を見出す。」(ヘーゲル『精神哲学』)
対幻想(とりわけ兄妹 Ex. 姉アマテラスと弟スサノオ)と共同幻想の「同致」に起因する母系的、母権制的支配。
その後、大和朝廷の父権的支配。対幻想と共同幻想の新たな「同致」としての天皇制家族主義。
⑤「共同幻想」としての倫理:3つの段階(216頁)
第1段階:スサノオの段階。母系的な農耕世界を肯定。死んだ母イザナミの国に行きたいといい、父イザナミの怒りをかう。父系的な世界の構造の否定。
第2段階:サホ姫の段階。兄(同母の血縁)と夫たる天皇との板ばさみ。氏族的共同体から統一的部族制への推移期。
第3段階:ヤマトタケルの段階。天皇たる父に疎まれ征服の旅に送り出される。統一国家(部族国家)の倫理。
⑥罪なき罪障感
スサノオの罪なき罪障感。前の世代から続いて生存しているというだけでの「良心の疚しさ」、「罪障感」。
ニーチェはそこに「残虐の体系」を見る。「定言命法からは残虐さが臭う」(『道徳の系譜学』)。
罪なき罪障感(1):債権者と債務者の関係が時間的遅れとして存在するため。
罪なき罪障感(2):共同体の成員として自分の意思に関わりなく承認されること(債務)の裏面として生じる(217頁)
これについてニーチェ(『道徳の系譜学』):《共同体の恩恵(人は守られ大切にされる、平和と信頼のうちに生きる)=債権者たる共同体》に対し、成員は自らを抵当としていれ危害や敵意に備える義務を負う。
⑦ 『共同幻想論』:常民が「物語」的に共同幻想と「同致」することへの批判
常民が「物語」的に共同幻想と「同致」することへの批判が『共同幻想論』の意図。
「物語」との統合を拒むものとして、「大衆」が作り出す「像」。
4-3 自己言及的体系、自己差異的体系への批判:柄谷
柄谷は「構造を突き抜けるもの」を探す。
自己言及的体系、自己差異的体系は動的で、絶え間ないずれが生じる(自己差異化)。排中律が成立しない。多中心的、たえず不均衡、過剰。「差異」の無根拠性、決定不能性、過剰性。「差異」が差異として固定せず無際限に自己をさらに差異化していく。
ハイデッガーは哲学史を「存在」というひとつの主題で語ってしまう点で形而上学的。
ハイデガーは、はるかに普遍的なフッサールと比べると、西洋哲学に閉じ込められプロビンシャル。
4-4 外部でも内部でもない場所:「境界」、「間」(柄谷)
① 「境界」、「間」
柄谷は「内部」と「外部」をどう区別するか?
多種多様な言語ゲームがありその外部に出られないとウィトゲンシュタインが言うとき、彼は外部に立っている。(柄谷)
外部でも内部でもない場所を柄谷は「境界」、「間」と呼ぶ。
共同体に内属するという人間の条件は超えられない。(他者に育てられるしかない。)
「間」、「境界」は、「単独者」、「単独者」としての「他者」の、「場所」ないし「非場所」である。(230頁)
「境界」はそれ自体、境界を本質的に持たないので「実無限」である。かくて「社会的空間」「交通空間」として「展開」する。
共同体の「間」から「国家」が生まれる。(柄谷)
② 柄谷における「他者」
「他者」は神もしくはそれに類するものではない。「他者」は異形のもの、「異者=怪物」ではない。「他者」は「ありふれた世俗的な他者」である。
そもそも「共同体」の「牢獄」からの不可能な脱出を可能にするものとして「他者」が要請されている。
Cf. 任意の他者が想定されたら「共同体」は閉じた単一体系でない。
Cf. ウィトゲンシュタインは複数の言語ゲームの関係を「家族的類似性」と呼ぶ。そして「境界線など引かれていない」と言う。
③ 「交通空間」から「共同体」(&「間」)が生成する
内部でも外部でもない「交通空間」から、それが自らを「折りたたむ」ことで「共同体」が生成し、同時に「間」が生成した
交通空間は現在では、貨幣によって媒介され、たえず再組織される世界的な諸関係の網の目である。
ニクラス・ルーマンが語るような「システムと環境(あるいはカオス)」といった考えは誤り。
④ 二元的コードと、各要素のアイデンティの仮構
「折りたたみ」とともに「複雑性の縮減」(N・ルーマン)が起こる。善悪、正不正のような二元的コードと、各要素のアイデンティ(同一化的帰属)が仮構される。
⑤ 柵のこちら側にも同様の柵がいくつもある。
「折りたたみ」に際して、交通空間の複雑さは屈折しつつ織り込まれていく。柵の向こうにいけない特別な柵があるとして、柵のこちら側にも同様の柵がいくつもある。「他者」が「いたるところに出現」する限り、境界ないし間はいたるところにある。
⑥ 根源的分割ないし「分配」の問題
「折りたたみ」ないし「分節化」が境界の発生だとしたら、ここに根源的分割ないし分配の問題がある。「最初に分配がある」(ミシェル・セール)。ニーチェが「正義」の原義とみなしていた事態。
⑦ 「折りたたみ」は交通空間の自己差異化なのか?
4-5 柄谷の思想のキーワード
(1)他者=神であって、空=神ではない。
(2)差異が初めにある。同一性は始原ではない。
(3)非対称がまずある。そこから対称が生まれる。
(4)他者の先行。自己差異化が先行するのでない。
(5)愛が始原である。暴力が始原ではない。
(6)言語ゲームの先行。独我論は始まりにならない。
(7)共同体の「間」が先にある。共同体は後に分節化する。
(8)一切は歴史的に存在する。非歴史的に存在することはありえない。
(9)多数体系が事象の本性である。単一体系はありえない。
第5章 愛も正義もないところで倫理とは何か
Ⅰ 道徳(倫理)批判:吉本と柄谷
「倫理とは言わば存在することの中にある核の如きものである。」(吉本)
「大人」とは共同幻想を自己幻想に先立つ先験性として信じることである。倫理性を、ヘーゲルは「同調」において見出し、吉本は「逆立」(反逆)において見出す。(柄谷)
吉本の背後に太宰がいる。太宰は「無倫理」。(吉本)
柄谷の背後に坂口安吾がいる。安吾は「アモラル(非倫理)」、安吾の「堕落」は「倫理的」。(柄谷)
Ⅱ サルトルたちの先生:アラン
吉本が注目したシモーヌ・ヴェイユはアランの弟子。小林秀雄へのアランの圧倒的影響。
アラン1:「説教を垂れてはならない。そんな時間があれば汚れたものの体を洗い、・・・・」
アラン2:「正義の掟は愛がなければすべて虚しい。」しかし「愛は抱きしめる、愛はまた絞め殺す。・・・・最もよく己を犠牲にする英雄たちは、最もよく殺す者でもある。」
アラン3:「隣人をお前自身と同じように愛せ」と言うが「お前自身」(自我)とは誰か?「人間たちは必ず関係しあっている。」他から切り離された「自我」なるものは存在しない。
Ⅲ サルトル:自他関係の問題
① 自他関係
サルトルの出発点は自我の問題。
意識の非人称性を語っても自他関係の問題は解決されない。
対他関係の根幹は「相剋」(コンフリクト)。ヘーゲルの「主人と奴隷の弁証法」(※主人は奴隷に依存、奴隷がそれを知り主従の力関係逆転。)
② 贈与
サルトルはマルセル・モース『贈与論』に注目。返礼なき贈与は受贈者を永遠の債務者にする。Ex. 封建的主従関係。
③ 暴力
「暴力」とは見られることなく見ることである。Ex. カントの定言命法(無条件な命令)の「暴力」。
④ 選びたまえ
「君は自由だ。選びたまえ。つまりでっち上げたまえ。いかなる一般道徳も何をなすべきかを指示できない。」(サルトル)
⑤ 分配
「分配的正義」批判:「分配」においてそれにありつけない者が不可避的に出る。「分配の犠牲者」。
⑥ 交換
「交換的正義」批判:力が同じ者たちが、談合によって交換価値を定めた帰結。
⑦「友愛」、「相互性」、人類という「共通の母親」:サルトル
サルトルが「贈与」を再考。
いっそう根本的な人間相互の絆、「友愛」。
初期の研究では「相互性」、他者を欠いた意識の中に倫理を求めた。しかし今は違う。すべての意識は、おのれを意識として構成すると同時に、他者に対する意識としておのれを構成すると思う、とサルトル。
自己を他者に対するものとして考える、これが倫理的意識。
あいつは私と同じ起源。人類という「共通の母親」。真の友愛。
Ⅳ 「道徳」と「倫理」、善と悪
①「道徳」と「倫理」、善と悪
吉本:善悪は存在しない。→《評者の感想》そんなことはあり得ない。
柄谷:「道徳」とは善悪を決める共同体的規範。「倫理」は「自由」にかかわる。
サドは、人間は自然の意志に従うだけであり善も悪もなしえないと言う。
②吉本『マチウ書試論』
吉本は『マチウ書試論』で、後期ユダヤ教の社会的律法支配(「神よりもトーラーを愛す」、人間と現実との関係を優先する「世俗性」)に対するキリスト教の反逆=内面的律法支配を描いた。
③親鸞:「機縁」は命法で動かない
親鸞の立場は「非僧」「非俗」である。
心の底からの信心には貴賤、老少、男女、善行悪行、多念一念は関係がない。悪人正機の説。
「念仏」「信心」の解体。絶対他力。
絶対他力も解体する。
「殺すな」という命法は「機縁」(=必然)を動かすことができない。殺すべき機縁がなければ一人でも殺さない。殺害すまいと思っても機縁で百人・千人を殺す。
Ⅴ 新しい贈与制(吉本)
贈与と返礼の互酬性は愛と呼べる。(柄谷)
マリノフスキーを引用し、吉本が言う。母の側からの贈与が父の側の返礼より多いとき、こうした贈与は「貢納制」に転化すると。
現代における贈与の必要性。Ex. 先進国からアフリカへの贈与。
交換可能であれば経済が成り立つという観念は誤り。新しい贈与制が必要。贈与者が善で損をすると受贈者が助かるという図式の変更が必要。(吉本)
社会の構成のおもな過程が世界性としての経済過程である時代、ちちこまとした国家主義や民族主義を超えて国家を開くべきと吉本。
Ⅵ 蘇生した「互酬制」:「アソシエーション」(柄谷)
① 「贈与の互酬性」が回復されねばならない(柄谷)
援助は「分配的正義」の実現だが再分配する先進国の権力を正当化するだけで、南北の戦争状態を解決しない。(柄谷)
「贈与の互酬性」が回復されねばならない。(※つまり返礼できること?)
② 「市民社会(=資本=市場社会)、ネーション、ステート(国家)」:柄谷
帝国から「ナショナル」なものが分節されると同時に「トランスナショナル」なものが成立する。(柄谷)
「ナショナル」なものはネーション(国民、Ex. 農業共同体)とステート(国家、Ex. 封建国家)からなる。
ブルジョア革命によって「市民社会(=資本=市場社会)、ネーション、ステート(国家)」の三位一体が成立。(これに「自由、友愛、平等」のスローガンが対応。)
ブルジョア革命において成立した「ネーション」。
②-2 ボロメオの環
「市民社会(=資本=市場社会)、ネーション、ステート(国家)」は三位一体とはいえ、いずれの2項をとっても異質なボロメオの環をなす。
この三位一体を、柄谷は現実界・想像界・象徴界(ラカン)のボロメオの環、感性・想像力・知性(カント)のボロメオの環と対応させる。
(1)ネーションは「想像の共同体」(「幻想の共同体」)であり想像界、想像力とつながる。
(2)国家(ステート)は創設宣言としての憲法(言明)が本義であり、象徴界、知性(悟性)とつながる。
(3)資本(=市民社会=市場社会)が現実界、感性とつながる。
③ 世界共和国は「統制的理念」(=超越論的仮象)である:柄谷
世界共和国は、直接的・暴力的に社会を変えようとする「構成的理念」でなく、決して実現されないがゆえに批判的に機能する「統制的理念」(=超越論的仮象)である。
資本、国家、ネーションはいずれも超越論的仮象である。
統制的理念=超越論的仮象は、現実界ひいては物自体と区別がつかない。
④「互酬制」:柄谷の理論の鍵
「互酬」の本義は、共同体内また共同体間に、タテの階層化でなくヨコの関係を築くこと。それゆえ「国家」の形成を阻止すること。
柄谷の理論の鍵を握るのは「互酬制」である。
⑤ 国家による「再分配」(=「略取(収奪)-再分配」)の否定:柄谷
国家においては略取が再分配(Ex. 灌漑、社会福祉、治安)に先行する。
柄谷は、国家による「配分(分配)的正義」の実現(Ex. サン・シモン)は「国家社会主義」として否定。
国家間の「正義」を、「分配的正義」で実現することは、結局、列強による再分配で「世界帝国」に至ると柄谷。
カントの「正義」は「交換的正義」である。(柄谷)
⑥ プルードン:「交換の正義」への移行
プルードンは「交換の正義」(=「流通の正義」)への移行を主張。「分配的正義」を封建制的なもの、緊急時の配給ごときものとみなす。
流通過程を重視するプルードン。剰余価値は生産でなく、売買から生まれる。
⑦ 「分配」とは「運命」である(合田)
「分配」とは「運命」である。Ex.「場所」、「生存」そのものも「分配」された。Ex. 吉本の「存在倫理」。
⑧ 高次元で蘇生した「互酬制」:「アソシエーション」(柄谷)
「互酬制」、「略取-再分配」、「商品交換」に続く新たな交換様式として、柄谷は《蘇生した「互酬制」=「アソシエーション」》を主張。
商品交換は「自由な個人」を可能にしたが、そこには諸個人の不平等と分離がある。それを「互酬制」の良き面がただす。
高次元で蘇生した「互酬制」が諸個人の「アソシエーション」を可能にする。
協同組合組織諸団体による全国的生産の調整、つまり可能なるコミュニズムをマルクスが『フランスの内乱』で主張。柄谷のアソシエーションの観念のもととなる。
「アソシエーションとは、あくまでも個々人の主体性にもとづく。」(柄谷)
カントはコスモポリタン(世界市民)こそ「公的」と考え、国家を「私的」と考えた。コスモポリタンは実体的ではなく、国家や文化を「括弧に入れる」ことが出来る能力である。
あとがき
合田氏の考察を導いた3つの言葉。
(1)「おれはここにいない。そして路地はいたるところにある。」(中上健次)
(2)「故郷を甘美に思うものは、まだくちばしの黄色い未熟者である。あらゆる場所を故郷と感じられるものは、既にかなりの力を蓄えたものである。全世界を異郷と思うものこそ、完璧な人間である。」(柄谷行人)
(3)「言語」は「故郷を持たない放浪者」である。(吉本隆明)
4-1 吉本の「共同幻想」論批判
① 上部構造の語の放棄:吉本
共同幻想は、上部構造、イデオロギー、あるいは『経済学批判』の「上層建築」、「社会的意識形態」と言い換えられる。
吉本は下部による上部決定論を連想させる上部構造の語を放棄。共同幻想の語を作り上げる。(柳田の共同幻覚が参考。)
『共同幻想論』は「子供たちが感受する異空間の世界」についての書とも言える。(吉本)
廣松の共同主観性と「よく似た」問題意識を持っている。
② 柄谷の吉本批判(その1):「対幻想」も「共同幻想」から逃れられない
田辺元の「種の論理」の類と個の間の中間項としての種。その種にあたるのが吉本の対幻想。
柄谷は言う。「個人幻想」や「対幻想」を立てても「共同幻想」から逃れられない。すべては「共同体」の「共同幻想」の所産。
柄谷は、共同体からおしだされた「外部」「他者」、単独者、単独者との非対称的な関係が、共同体に「場所」を持たないものとして必然的に創出されると言う。「場所」なき場所が「交通空間」。
③ 柄谷の吉本批判(その2):共同幻想論は他の国家・他者からの視点を欠く
共同幻想は国家(家族と背反しつつ拡大)を想定する。
ところが他の国家の問題が消える。例えば、日本人が「平和憲法を持っている」と思っても(※日本人の共同幻想)、外から見れば「アジア随一の軍隊を持った国家」。
共同幻想は物語とその伝承であり創世・創設神話を含む。吉本は、それについての他者の視点を語らない。
④ 柄谷の吉本批判(その3):生産様式を交換様式と捉える(199頁)
吉本は下部構造に対して相対的に自立した「幻想」を語る。(上部構造の、下部構造による決定論を拒否。)
ところがここには上部-下部の二元論がある。
柄谷はこの二元論を壊す。
下部構造における「生産」を、「交換」の1形式と捉える。
国家(ステート)、ネーション、経済はそれぞれ「交換」の固有の形式を持つ。
生産様式を交換様式と捉える(柄谷)。
ルイ・アルチュセールに依拠しつつ、原始的氏族的生産様式は「互酬」、アジア的生産様式、古典古代的奴隷制、ゲルマン的封建制は「略取-再分配」、資本主義的生産様式は「商品交換」:3つの交換様式。
3つの交換様式の接合、その接合の仕方と濃淡が、多様な社会構成体をもたらす。
吉本は、共同体の重層化はもとになる共同体を大きく壊さずに接合されるとする。彼は共同体の古層・基層を追い求めるだけで単線的すぎる。(合田)
4-2 「個人幻想」「対幻想」「共同幻想」:吉本
① 対幻想と共同幻想の「同致」etc.
吉本は複雑系の思想家。だから丸山の公私の峻別を批判。
「錯合」の平面化の阻止のため「個人幻想」「対幻想」「共同幻想」のレベルを区別。
個人幻想と共同幻想の「同致」。Ex. 「私は日本人である」
対幻想と共同幻想の「同致」。国家をエロス的に捉える。対幻想の次元で大切な人のために共同幻想である国家に身を捧げる。(石原慎太郎『国家なる幻影』)
①-2 対幻想
対幻想と共同幻想が競合するとき、前者を選ぶのが女性。(吉本)
フロイトは対幻想の領域を共同幻想の領域まで拡大しすぎた。
男女だけでなく、親子、姉妹、兄弟も性的である:対幻想。
② 「憑依」または「同調」
自己幻想が共同幻想に憑く。または自己幻想が共同幻想に侵食される。
その理由は、①共同幻想が自己幻想に先立つ先験性だから:「生誕」の問題。②「死」も先験性である(ハイデガー)。
「超越論的なもの」の二つのアスペクト:「生誕」と「死」。
ただし「死」の共同幻想にはないが、「生誕」の共同幻想にのみ見られるのは、対幻想と村落の共同幻想が相互に移行すること。
巫女は対幻想と共同幻想との「同調」or「同致」。
③ 「死」の先験性
「その死に向かって存在している」現存在の時間性を、村落共同体の共同幻想が、空間の方向に疎外(※=表出)したものが他界との境目、「危機的な分界地帯」、共同体と共同体の「間」。Ex. 『遠野物語』の「デンデラ野」
④ 「生誕」の先験性
自己幻想に先立つ先験性は「生誕」では「母体」である。
「まだ自分自身の中に自己を持つに至っていない胎児の心は子の他人(※母体)のなかに自分の自己を見出す。」(ヘーゲル『精神哲学』)
対幻想(とりわけ兄妹 Ex. 姉アマテラスと弟スサノオ)と共同幻想の「同致」に起因する母系的、母権制的支配。
その後、大和朝廷の父権的支配。対幻想と共同幻想の新たな「同致」としての天皇制家族主義。
⑤「共同幻想」としての倫理:3つの段階(216頁)
第1段階:スサノオの段階。母系的な農耕世界を肯定。死んだ母イザナミの国に行きたいといい、父イザナミの怒りをかう。父系的な世界の構造の否定。
第2段階:サホ姫の段階。兄(同母の血縁)と夫たる天皇との板ばさみ。氏族的共同体から統一的部族制への推移期。
第3段階:ヤマトタケルの段階。天皇たる父に疎まれ征服の旅に送り出される。統一国家(部族国家)の倫理。
⑥罪なき罪障感
スサノオの罪なき罪障感。前の世代から続いて生存しているというだけでの「良心の疚しさ」、「罪障感」。
ニーチェはそこに「残虐の体系」を見る。「定言命法からは残虐さが臭う」(『道徳の系譜学』)。
罪なき罪障感(1):債権者と債務者の関係が時間的遅れとして存在するため。
罪なき罪障感(2):共同体の成員として自分の意思に関わりなく承認されること(債務)の裏面として生じる(217頁)
これについてニーチェ(『道徳の系譜学』):《共同体の恩恵(人は守られ大切にされる、平和と信頼のうちに生きる)=債権者たる共同体》に対し、成員は自らを抵当としていれ危害や敵意に備える義務を負う。
⑦ 『共同幻想論』:常民が「物語」的に共同幻想と「同致」することへの批判
常民が「物語」的に共同幻想と「同致」することへの批判が『共同幻想論』の意図。
「物語」との統合を拒むものとして、「大衆」が作り出す「像」。
4-3 自己言及的体系、自己差異的体系への批判:柄谷
柄谷は「構造を突き抜けるもの」を探す。
自己言及的体系、自己差異的体系は動的で、絶え間ないずれが生じる(自己差異化)。排中律が成立しない。多中心的、たえず不均衡、過剰。「差異」の無根拠性、決定不能性、過剰性。「差異」が差異として固定せず無際限に自己をさらに差異化していく。
ハイデッガーは哲学史を「存在」というひとつの主題で語ってしまう点で形而上学的。
ハイデガーは、はるかに普遍的なフッサールと比べると、西洋哲学に閉じ込められプロビンシャル。
4-4 外部でも内部でもない場所:「境界」、「間」(柄谷)
① 「境界」、「間」
柄谷は「内部」と「外部」をどう区別するか?
多種多様な言語ゲームがありその外部に出られないとウィトゲンシュタインが言うとき、彼は外部に立っている。(柄谷)
外部でも内部でもない場所を柄谷は「境界」、「間」と呼ぶ。
共同体に内属するという人間の条件は超えられない。(他者に育てられるしかない。)
「間」、「境界」は、「単独者」、「単独者」としての「他者」の、「場所」ないし「非場所」である。(230頁)
「境界」はそれ自体、境界を本質的に持たないので「実無限」である。かくて「社会的空間」「交通空間」として「展開」する。
共同体の「間」から「国家」が生まれる。(柄谷)
② 柄谷における「他者」
「他者」は神もしくはそれに類するものではない。「他者」は異形のもの、「異者=怪物」ではない。「他者」は「ありふれた世俗的な他者」である。
そもそも「共同体」の「牢獄」からの不可能な脱出を可能にするものとして「他者」が要請されている。
Cf. 任意の他者が想定されたら「共同体」は閉じた単一体系でない。
Cf. ウィトゲンシュタインは複数の言語ゲームの関係を「家族的類似性」と呼ぶ。そして「境界線など引かれていない」と言う。
③ 「交通空間」から「共同体」(&「間」)が生成する
内部でも外部でもない「交通空間」から、それが自らを「折りたたむ」ことで「共同体」が生成し、同時に「間」が生成した
交通空間は現在では、貨幣によって媒介され、たえず再組織される世界的な諸関係の網の目である。
ニクラス・ルーマンが語るような「システムと環境(あるいはカオス)」といった考えは誤り。
④ 二元的コードと、各要素のアイデンティの仮構
「折りたたみ」とともに「複雑性の縮減」(N・ルーマン)が起こる。善悪、正不正のような二元的コードと、各要素のアイデンティ(同一化的帰属)が仮構される。
⑤ 柵のこちら側にも同様の柵がいくつもある。
「折りたたみ」に際して、交通空間の複雑さは屈折しつつ織り込まれていく。柵の向こうにいけない特別な柵があるとして、柵のこちら側にも同様の柵がいくつもある。「他者」が「いたるところに出現」する限り、境界ないし間はいたるところにある。
⑥ 根源的分割ないし「分配」の問題
「折りたたみ」ないし「分節化」が境界の発生だとしたら、ここに根源的分割ないし分配の問題がある。「最初に分配がある」(ミシェル・セール)。ニーチェが「正義」の原義とみなしていた事態。
⑦ 「折りたたみ」は交通空間の自己差異化なのか?
4-5 柄谷の思想のキーワード
(1)他者=神であって、空=神ではない。
(2)差異が初めにある。同一性は始原ではない。
(3)非対称がまずある。そこから対称が生まれる。
(4)他者の先行。自己差異化が先行するのでない。
(5)愛が始原である。暴力が始原ではない。
(6)言語ゲームの先行。独我論は始まりにならない。
(7)共同体の「間」が先にある。共同体は後に分節化する。
(8)一切は歴史的に存在する。非歴史的に存在することはありえない。
(9)多数体系が事象の本性である。単一体系はありえない。
第5章 愛も正義もないところで倫理とは何か
Ⅰ 道徳(倫理)批判:吉本と柄谷
「倫理とは言わば存在することの中にある核の如きものである。」(吉本)
「大人」とは共同幻想を自己幻想に先立つ先験性として信じることである。倫理性を、ヘーゲルは「同調」において見出し、吉本は「逆立」(反逆)において見出す。(柄谷)
吉本の背後に太宰がいる。太宰は「無倫理」。(吉本)
柄谷の背後に坂口安吾がいる。安吾は「アモラル(非倫理)」、安吾の「堕落」は「倫理的」。(柄谷)
Ⅱ サルトルたちの先生:アラン
吉本が注目したシモーヌ・ヴェイユはアランの弟子。小林秀雄へのアランの圧倒的影響。
アラン1:「説教を垂れてはならない。そんな時間があれば汚れたものの体を洗い、・・・・」
アラン2:「正義の掟は愛がなければすべて虚しい。」しかし「愛は抱きしめる、愛はまた絞め殺す。・・・・最もよく己を犠牲にする英雄たちは、最もよく殺す者でもある。」
アラン3:「隣人をお前自身と同じように愛せ」と言うが「お前自身」(自我)とは誰か?「人間たちは必ず関係しあっている。」他から切り離された「自我」なるものは存在しない。
Ⅲ サルトル:自他関係の問題
① 自他関係
サルトルの出発点は自我の問題。
意識の非人称性を語っても自他関係の問題は解決されない。
対他関係の根幹は「相剋」(コンフリクト)。ヘーゲルの「主人と奴隷の弁証法」(※主人は奴隷に依存、奴隷がそれを知り主従の力関係逆転。)
② 贈与
サルトルはマルセル・モース『贈与論』に注目。返礼なき贈与は受贈者を永遠の債務者にする。Ex. 封建的主従関係。
③ 暴力
「暴力」とは見られることなく見ることである。Ex. カントの定言命法(無条件な命令)の「暴力」。
④ 選びたまえ
「君は自由だ。選びたまえ。つまりでっち上げたまえ。いかなる一般道徳も何をなすべきかを指示できない。」(サルトル)
⑤ 分配
「分配的正義」批判:「分配」においてそれにありつけない者が不可避的に出る。「分配の犠牲者」。
⑥ 交換
「交換的正義」批判:力が同じ者たちが、談合によって交換価値を定めた帰結。
⑦「友愛」、「相互性」、人類という「共通の母親」:サルトル
サルトルが「贈与」を再考。
いっそう根本的な人間相互の絆、「友愛」。
初期の研究では「相互性」、他者を欠いた意識の中に倫理を求めた。しかし今は違う。すべての意識は、おのれを意識として構成すると同時に、他者に対する意識としておのれを構成すると思う、とサルトル。
自己を他者に対するものとして考える、これが倫理的意識。
あいつは私と同じ起源。人類という「共通の母親」。真の友愛。
Ⅳ 「道徳」と「倫理」、善と悪
①「道徳」と「倫理」、善と悪
吉本:善悪は存在しない。→《評者の感想》そんなことはあり得ない。
柄谷:「道徳」とは善悪を決める共同体的規範。「倫理」は「自由」にかかわる。
サドは、人間は自然の意志に従うだけであり善も悪もなしえないと言う。
②吉本『マチウ書試論』
吉本は『マチウ書試論』で、後期ユダヤ教の社会的律法支配(「神よりもトーラーを愛す」、人間と現実との関係を優先する「世俗性」)に対するキリスト教の反逆=内面的律法支配を描いた。
③親鸞:「機縁」は命法で動かない
親鸞の立場は「非僧」「非俗」である。
心の底からの信心には貴賤、老少、男女、善行悪行、多念一念は関係がない。悪人正機の説。
「念仏」「信心」の解体。絶対他力。
絶対他力も解体する。
「殺すな」という命法は「機縁」(=必然)を動かすことができない。殺すべき機縁がなければ一人でも殺さない。殺害すまいと思っても機縁で百人・千人を殺す。
Ⅴ 新しい贈与制(吉本)
贈与と返礼の互酬性は愛と呼べる。(柄谷)
マリノフスキーを引用し、吉本が言う。母の側からの贈与が父の側の返礼より多いとき、こうした贈与は「貢納制」に転化すると。
現代における贈与の必要性。Ex. 先進国からアフリカへの贈与。
交換可能であれば経済が成り立つという観念は誤り。新しい贈与制が必要。贈与者が善で損をすると受贈者が助かるという図式の変更が必要。(吉本)
社会の構成のおもな過程が世界性としての経済過程である時代、ちちこまとした国家主義や民族主義を超えて国家を開くべきと吉本。
Ⅵ 蘇生した「互酬制」:「アソシエーション」(柄谷)
① 「贈与の互酬性」が回復されねばならない(柄谷)
援助は「分配的正義」の実現だが再分配する先進国の権力を正当化するだけで、南北の戦争状態を解決しない。(柄谷)
「贈与の互酬性」が回復されねばならない。(※つまり返礼できること?)
② 「市民社会(=資本=市場社会)、ネーション、ステート(国家)」:柄谷
帝国から「ナショナル」なものが分節されると同時に「トランスナショナル」なものが成立する。(柄谷)
「ナショナル」なものはネーション(国民、Ex. 農業共同体)とステート(国家、Ex. 封建国家)からなる。
ブルジョア革命によって「市民社会(=資本=市場社会)、ネーション、ステート(国家)」の三位一体が成立。(これに「自由、友愛、平等」のスローガンが対応。)
ブルジョア革命において成立した「ネーション」。
②-2 ボロメオの環
「市民社会(=資本=市場社会)、ネーション、ステート(国家)」は三位一体とはいえ、いずれの2項をとっても異質なボロメオの環をなす。
この三位一体を、柄谷は現実界・想像界・象徴界(ラカン)のボロメオの環、感性・想像力・知性(カント)のボロメオの環と対応させる。
(1)ネーションは「想像の共同体」(「幻想の共同体」)であり想像界、想像力とつながる。
(2)国家(ステート)は創設宣言としての憲法(言明)が本義であり、象徴界、知性(悟性)とつながる。
(3)資本(=市民社会=市場社会)が現実界、感性とつながる。
③ 世界共和国は「統制的理念」(=超越論的仮象)である:柄谷
世界共和国は、直接的・暴力的に社会を変えようとする「構成的理念」でなく、決して実現されないがゆえに批判的に機能する「統制的理念」(=超越論的仮象)である。
資本、国家、ネーションはいずれも超越論的仮象である。
統制的理念=超越論的仮象は、現実界ひいては物自体と区別がつかない。
④「互酬制」:柄谷の理論の鍵
「互酬」の本義は、共同体内また共同体間に、タテの階層化でなくヨコの関係を築くこと。それゆえ「国家」の形成を阻止すること。
柄谷の理論の鍵を握るのは「互酬制」である。
⑤ 国家による「再分配」(=「略取(収奪)-再分配」)の否定:柄谷
国家においては略取が再分配(Ex. 灌漑、社会福祉、治安)に先行する。
柄谷は、国家による「配分(分配)的正義」の実現(Ex. サン・シモン)は「国家社会主義」として否定。
国家間の「正義」を、「分配的正義」で実現することは、結局、列強による再分配で「世界帝国」に至ると柄谷。
カントの「正義」は「交換的正義」である。(柄谷)
⑥ プルードン:「交換の正義」への移行
プルードンは「交換の正義」(=「流通の正義」)への移行を主張。「分配的正義」を封建制的なもの、緊急時の配給ごときものとみなす。
流通過程を重視するプルードン。剰余価値は生産でなく、売買から生まれる。
⑦ 「分配」とは「運命」である(合田)
「分配」とは「運命」である。Ex.「場所」、「生存」そのものも「分配」された。Ex. 吉本の「存在倫理」。
⑧ 高次元で蘇生した「互酬制」:「アソシエーション」(柄谷)
「互酬制」、「略取-再分配」、「商品交換」に続く新たな交換様式として、柄谷は《蘇生した「互酬制」=「アソシエーション」》を主張。
商品交換は「自由な個人」を可能にしたが、そこには諸個人の不平等と分離がある。それを「互酬制」の良き面がただす。
高次元で蘇生した「互酬制」が諸個人の「アソシエーション」を可能にする。
協同組合組織諸団体による全国的生産の調整、つまり可能なるコミュニズムをマルクスが『フランスの内乱』で主張。柄谷のアソシエーションの観念のもととなる。
「アソシエーションとは、あくまでも個々人の主体性にもとづく。」(柄谷)
カントはコスモポリタン(世界市民)こそ「公的」と考え、国家を「私的」と考えた。コスモポリタンは実体的ではなく、国家や文化を「括弧に入れる」ことが出来る能力である。
あとがき
合田氏の考察を導いた3つの言葉。
(1)「おれはここにいない。そして路地はいたるところにある。」(中上健次)
(2)「故郷を甘美に思うものは、まだくちばしの黄色い未熟者である。あらゆる場所を故郷と感じられるものは、既にかなりの力を蓄えたものである。全世界を異郷と思うものこそ、完璧な人間である。」(柄谷行人)
(3)「言語」は「故郷を持たない放浪者」である。(吉本隆明)