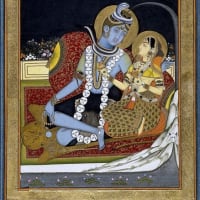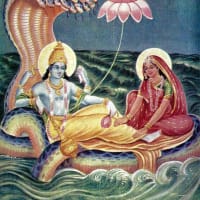序章 あなたと私が現象学だ
A フッサールの現象学への突破口、『論理学研究』(1900/1901)→1901年、ゲッティンゲン大学に在職:ミュンヘン・ゲッティンゲン現象学派。
B 諸学問の始原(アルケー)を捜す:フッサール。諸学問の基礎づけ。
B-2 現実、直接経験、「事象そのもの」へ帰る。
B-3 この始原は多層であるとわかる。一つの層を発掘すると次の層が現れる。
C 事象そのものは、直接に見られ、直接に経験される。哲学用語では「直観される」と言う。
D 覆い隠す思考を考え直し、事象そのものを明らかにし、始原をさがす。
E 『論理学研究』のあと、フッサールの「超越論的転回」→彼から多くの研究者が離れていく。
E-2 フッサール、1916年、フライブルク大学へ。若いハイデッガーに会う。「あなたと私が現象学だ!」とフッサール。
E-3 1920年頃から、フッサール、「発生」の観点、導入。
E-4 ハイデッガーもフッサールから離れていく。さらにハイデッガーはナチスに協力。フッサールはユダヤ系で迫害される。
F フッサール、孤立化。「哲学的隠者になってしまった」と感じる。
F-2 1938年、フッサール死去。ナチスからフッサールの4万頁の草稿救出。
G ハイデッガーの『存在と時間』での言葉:「事象そのものへ」(zu den Sachen selbst)!
第1章 現象学の誕生
第1節 数学から哲学へ
A ベルリン大学で数学の助手となる。
A-2 ブレンターノの講義を聴き哲学に向かう。「厳密学としての哲学」を目指す。
第2節 学問の危機
B ガリレイは「哲学」していた。ニュートンも「哲学」していた。「科学」の語は、まだない。
B-2 自然/世界は「数学」や「幾何学」の言語で書かれている。(ガリレイ)
B-3 数学的にとらえられた世界(理念化された世界)が「真の世界」「客観的な世界」とされる。直接経験の世界(生活世界)が「見かけの世界」「主観的な世界」とされる。ガリレイは「覆い隠す天才」とフッサール。
C 「直観」の要素を持つ幾何学でなく、「直観性」をもたない代数の発展。
C-2 19世紀後半、数学や論理学は、ライプニッツ的構想に従いつつ、経験から独立した公理体系として展開しようとしていた。
C-3 経験を「現実(性)」と言い換えるなら、数学や論理学は「可能性」だけを扱うと言える。つまり数学や論理学は、現実から離れて、それゆえまた現実に先だって(=アプリオリに)、可能性の領分を示す。
D 直接に経験・直観される現実からの数学・論理学・自然科学の遊離、地盤喪失。ヨーロッパ諸学の危機!
D-2 フッサールは数学や論理学の始原を取り戻そうとした。この始原は「直接経験」(ものを見る、ものに触るなど)にある。
D-3 E.マッハ:科学の唯一の基礎は「経験」、正確には「感覚」にあるとした。「現象学」!
D-4 ブレンターノらの「現象学」もあった。
D-4 フッサールの「純粋現象学」、「超越論的現象学」。純粋=超越論的と考えてよい。
[コーヒーブレイク] 現象学と分析哲学:「心理」、「論理」、「経験」の関係の問題
E フッサールは、言語(論理)は、経験に対して派生的とみなす。
E-2 「意味」や「思想」は、個人の心理内容でなく客観性を持つ:フレーゲ。
E-3 分析哲学は、言語の客観性・普遍妥当性あるいは公共性を重視する。経験を問う姿勢は弱い。
E-4 フッサールは『論理学研究』で、論理的なものがアプリオリであると認める。他方で、論理的なものを経験から基礎づけようとする。
第3節 フッサールの根源的着想
(1)学問の基礎は直接経験にある
A マッハの図2(左目の視野)が視覚の直接経験。マッハの図1(外部からの物理的刺激[=可視光線]を私が受け取り、知覚が成立する)は「客観的」と思われているが、実は図2のような直接経験から派生したものである。
A-2 図2は「主観的」と言われるが、これが図1の「客観性」の前提である。(45-46頁)
(2)超越論的還元
B 派生的な「客観性」を、根源的な「主観的な」光景に引き戻す(=還元する)。
B-2 そもそも私たちは、この光景(=表象)の外に出ることは出来ない。外に出られると考えるのは非学問的。
C実存する対象を持つ表象(Ex. 富士山)と、実存する対象を持たない表象(Ex. ペガサス)。
C-2 富士山が、私たちの表象の外(=表象の外部に存在する対象)では、確認されえない。
C-3 表象の外部に対象が存在することを疑わない自然的態度を停止(エポケー)。私たちの眼を、表象に引き戻す(超越論的還元)。
D 表象の外部(=「超越」的)に、なにかが「存在する」と思う「自然的態度」を問う。
D-2 存在=超越は、表象の内部から出られない私たちが、表象の内部で「構成」したもの!
D-3 超越を、このように問うことが、「超越論的」と呼ばれる。
D-4 空想対象も知覚対象も構成されたもの!
D-5 対象は、その存在=超越さえも、私たちの働きかけによって成立する。
E 還元された光景が「超越論的主観性」である。
E-2 科学的な(つまり数学と実証に依拠する)「客観科学」は「客観性」を標榜する。フッサールは客観性の基礎として、客観性に先立つ主観性を問う。
E-3 超越論的主観性とは、私たちが最も直接的に具体的に経験している光景そのもの、直接経験の領野(マッハ的な光景=図2)である。
F 心理学は自然的態度をとるのに対し、現象学は超越論的態度をとる。
F-2 現象学は、「超越論的態度の心理学」と言ってよい。
(3)「(知覚・経験される)現出者」と「(感覚・体験される)諸現出」:志向性の問題
A 机は「台形」に見えるが、私たちは「長方形」と思う。
A-2 私たちは、台形を「感覚」しているが、それを突破して、長方形を「知覚」している。
A-3 私たちは、台形の感覚・体験を突破して、その向こうに長方形を知覚・経験している。
A-4 言い換えれば、私たちは「現出」の感覚・体験を突破して、その向こうに「現出者」を知覚・経験している。
B 「(知覚・経験される)現出者」の同一性と「(感覚・体験される)現出」の多様性。
C 現出は、現出者の「記号」であるとも言える。
C-2 「現出者」は「諸現出」によって媒介されている。「諸現出」は「現出者」へと突破されている。
D 「現象」の語は、「諸現出」と「現出者」との二義性を孕む。
D-2 フッサールは、諸現出と現出者の関係を「普遍的な〈相関関係のアプリオリ〉」と捉える。
D-3 「私の生涯の仕事は、この相関関係のアプリオリを体系的に仕上げるという課題によって支配されてきた。」(フッサール)
E 「現象学」は、諸現出と現出者の関係から成り立つ「現象」を扱う学問。
E-2 現象学は、実体(本体)と現象(仮象)といった意味での現象(これは外部に実存する対象とその表象という図式のバリエーションにすぎない)を扱う学問ではない。
F 直接経験では、諸現出の体験(感覚)を媒介にし(突破して)現出者が知覚(経験)されるが、この媒介・突破の働きが志向性と呼ばれる。
F-2 それゆえ直接経験は、「志向的体験」と言い換えられる。
F-3 諸現出と現出者の(媒介・突破の)関係がそこで生じる場面、すなわち志向的体験が、「意識」と言われる。
G 「現出者(対象)」は経験(知覚)され意識の主題となるが、「現出」は体験(感覚)されるだけで「意識の非主題的成分」(その1)である。
H また意識は基本的に対象を主題的にとらえており、おのれ自身(=現出を突破する意識の「働き」)を意識するしかたは非主題的である。意識がおのれを主題化するのは「反省」(内部知覚)する場合である。すなわち、現出を突破する意識の「働き」そのものは、「意識の非主題的成分」(その2)である。
H-2 現出を突破する意識の「働き」は「作用(Akt)」と呼ばれる。のちにこの作用を支える働きがさらに発見され、その場合、作用は「能動性(Aktivität)」と呼ばれ、それを支える働きが「受動性(Passivität)」と呼ばれる。
《評者の感想》
反省的でない意識とは何か?それは、世界が受動的に開示されていることである。
(4)直観経過における志向と充実
I 諸現出は、現出者に向かって突破される。(66頁)
I-2 現出者と諸現出の相関関係は、いつも直観経過のなかに(あるいは時間意識のなかに)ある。(67頁)
I-3 予持は、いつも現出を「志向」しており、たいてい、それが次の原印象的現出によって「充実」される。(67頁)
[コーヒーブレイク] 絵画の遠近法
J フッサールは、現出を「射影」とも呼ぶ。射影は、「形態射影」と「色彩射影」に区別される。
J-2 ルネサンス期の遠近法は、形態射影に注目した。
J-3 印象派は、色彩射影に注目した。
J-4 キュビズムは、感覚される現出(形態射影と色彩射影)でなく、知覚される現出者に注目した。
《評者の感想》
●1 嗅覚射影、味覚射影、聴覚射影もあるはずだ。
●2 「形態射影」は、いわば触覚射影に相当する。触覚は、基本的に圧覚である。
●3 しかし触覚は、さらに広義には、温熱覚、痛覚も含むから、これらの射影もあるはずだ。
●4 「色彩射影」は、いわば、視覚射影に相当する。
●5 「形態射影」は、基礎を触覚射影にもつが、同時に視覚射影にも属する。
第4節 無前提性
A 諸学問の「下」(基礎)には直接経験=志向的体験がある。そして直接経験=志向的体験は、その外部から眺めることができず、その「内部」に還元する。
A-2 直接経験=志向的体験を解明する現象学は、「形而上学的、自然科学的、心理学的な無前提性を満たそうとする。」
第2章 現象学の学問論:現象学は直接経験=志向的体験からどのようにして諸学問/諸科学を基礎づけるのか
第1節 論理学と心理主義
A 数学と論理学が、諸学問/諸科学の基礎学である。
A-2 数学や論理学は、それら自体、基礎を持たないのか?
B 数学や論理学の基礎を心理学に求める心理主義。
B-2 心理主義は、「生物それぞれ、各人それぞれに、数学や論理学がある」との帰結にいたる。数学や論理学の普遍妥当性の否定。数学・論理学的真理は「各人各様」になる。
C 心理主義に反対したフレーゲ。論理学的なものは、直観や経験から独立。さらに自然的な日常言語からの解放・純化が必要。フレーゲの「概念記法」。
D フッサール『算術の哲学』(1891年)には心理主義的傾向があるが、フッサール自身が否定。「ほんとうのことを言えば、私がこれを出版したときには、私はすでにこれを乗り越えた地点にいた。」(フッサール)
D-2 プロレゴーメナ以後のフッサールは、数学や論理学がアプリオリな学問であることを認める。(フレーゲと同じ立場!)
D-3 ただしフッサールは、数学・論理学が、直観的・経験的な基礎を持つとする。(フレーゲと異なる!)その基礎が、直接経験=志向的体験である。
第2節 アプリオリ(76-84頁)
B 数学や論理学は「アプリオリ」である。(反対語が「アポステリオリ」!)
B-2 それは、ライプニッツの「理性の真理」である。「事実の真理」に対比される。
B-3 「汽車は最速の乗り物である」は「事実の真理」である。「汽車は最速の乗り物であった」と「時制変化」し、今では、当てはまらない。
B-4 これに対し「3たす3は6である」は、「時制変化」しない「永遠の真理」。つまり「理性の真理」である。
C カントは、論理的カテゴリーは、主観性に「あらかじめ」備え付けられ、「アプリオリ」だと言う。
C-2 フッサールは、主観性に「あらかじめ」備え付けられた「アプリオリ」を認めない。フッサールの現象学的アプリオリは、主観性の心理主義的認識装置(カント)ではない。
《評者の感想》:フッサールは主観性の「本質構造」、ノエシス、ノエマの構造について語る。これは現象学的「アプリオリ」である。
C-3 フッサールの「アプリオリ」は心理主義的概念でなく、存在論的概念であり、存在が時制変化しない特性を持つことである。存在が時制変化する特性を持てば、それは「アポステリオリ」である。
D 数学・論理学は、本質学であり、アプリオリ・理念的・本質的・普遍的・必然的という存在論的性格を持った存在についての学問である。「理性の真理」の学。
D-2 本質的なものの構造連関に基づく厳密学。
D-3 アプリオリなものは「いつでも性」(普遍性)を持つ。
E 心理学・物理学は、事実学であり、アポステリオリ・実在的・事実的・個別的・偶然的という存在論的性格を持った存在についての学問である。「事実の真理」の学。
E-2 事実的なものの測定に基づく精密学。
E-3 アポステリオリなものは「そのつど性」(ある時やある所でのみ妥当する)を持つ。
F アポステリオリな心理学で、アプリオリな数学・論理学を基礎づけることは出来ない。
G 経験はすべてアポステリオリなのではない:フッサール。
G-2 ヒュームは、「経験は普遍妥当性を基礎づけられない」とした。
G-3 カントは、アプリオリな成分を、主観性の中に備え付けた。一種の心理主義。
H フッサールは、「数学・論理学が、経験(直接経験=志向的体験)に基礎を持つ」とする。そして、経験(直接経験=志向的体験)は、アポステリオリな成分だけでなく、アプリオリな成分(あるいはその先行形態)を持つとする。
H-2 フッサールでは、「直観」が、経験(直接経験=志向的体験)から、アプリオリな成分を抽出し、論理的なものに仕上げる。
H-3 カントの「直観」は、感性的なものに限定されるが、フッサールでは違う。
H-4 アプリオリなものは、経験(直接経験=志向的体験)のうちにどのように含まれるのか?これを明らかにするのが、現象学の仕事である。
I フッサールは、純粋論理学(ライプニッツの方向での形式論理学)の上に、諸学問は基礎づけられるべきだとする。
I-2 その上でフッサールは、純粋論理学(形式論理学)を、直接経験=志向的体験に還元し、そこで論理学的諸理念(アプリオリな成分)の起源を証示する。これが「純粋に現象学的な解明」である!
第3節 論理学と存在論と真理論(84-115頁)
(1)「諸科学/諸学問の基礎づけという現象学的構想」の中での論理学の位置づけの問題
A 論理学は、諸学問の基礎学であり、諸学問の論理を明らかにする。
B 学問は「無意味」なものは扱わない。かくてフッサール的論理学の第1の条件は、「無意味」なものを排除することである。→純粋論理学あるいは形式論理学
C 学問は、それぞれ扱うべき対象領域(対象の意味領域)を持っている。フッサール的論理学の第2の条件は、
「対象の意味領域」の確定である。→領域存在論
C-2 論理学と存在論の結合。ここで存在論とは、論理学的な表現が指し示している当のものの理論、あるいは本質によって区別された限りでの対象論である。
C-3 論理学を存在論に結び付けるのは、アリストテレス以来の伝統。論理学が、存在論から独立の1学科になったのは、近代特有の出来事。
(2)「無意味」の排除:フッサール的論理学の第1の条件(形式論理学)
D 「無意味」の4種類
① そもそも「意味を持たない言葉」(Ex. アブラカタブラ)
② 「文法的に無意味」(Ex. 白いそして)
③ 意味が互いに矛盾する「反意味」(Ex. 丸い四角)
④ 対象が実在しない限りでの無意味(Ex. 黄金の山)
D-2 こうしたいろいろな無意味のうち、アプリオリに「対象の充実した直観に至りえないもの」をあらかじめ排除する。
(2)-2 形式存在論(代数学)と形式命題論:この両者が結びついたものが「純粋論理学」(形式論理学)
E もっぱら「言語」的な結合の仕方を考察する論理学の部門:「形式命題論」。
E-2 フッサールは、「無意味」を排除するため、「意味」を「形式的」にとらえ、それを支配する法則に照らし、不適切なものを排除する。
F フッサールは、論理学を存在論(対象論)と結合させる:「形式存在論」(代数学)。
G 「事象内容を持った本質」は、「質料」。「それは何であるか?」と問われた時、「何」にあたるもの。
G-2 「事象内容を持たない本質」は、「形式」。「数」は形式的な対象である。
H 「形式存在論」:代数(学)は「形式的対象」としての数を形式的に扱う。代入される数と無関係に、その法則だけで演算・操作が進められる。代数学は典型的な「形式存在論」!
H-2 「形式命題論」:「言語」を、「代数」的な考え方を拡張し捉えたもの。形式命題論は、もともと形式存在論(代数)的である。
H-3 形式命題論は、形式存在論と基本的に同じ法則である。
H-4 純粋論理学(形式論理学)は、形式存在論(代数学)と形式命題論の2側面が結びついて成り立つ。
I 形式命題論(形式存在論と一体的である)の法則による「無意味」の排除(90頁)
I-2 形式命題論は、最初に、言語を分類する。(名詞、形容詞など。)そして言語の結合、命題と命題の結合について、アプリオリな法則を示す。
I-3 「白いそして」(形容詞と接続詞の結合)は無意味として排除される。(D②)
I-3 矛盾律(Aは非Aでない)に反する結合、「非AであるA」は、無意味として排除される。
I-4 「木製の鉄」など意味同士が背反する無意味(「反意味」)も排除する。(D③)
I-5 「正64面体」は、数学(形式存在論)によって検証し、「無意味」と排除される。
I-6 「黄金の山」は形式命題論のレベルでは有意味。ただし実在的な対象を持たないので日常的には「無意味」。アポステリオリに現実の存在(実存)を確認する必要がある。
J 形式命題論により「無意味」な言語表現(命題)が排除される。
J-2 有意味な言語表現(命題)について、実在的に存在する対象、または理念的に存在する対象の充実した直観に対する場合、それは「真理」(真)される。
J-3 無意味は、そもそも、真理にも誤謬にもかかわることができない。
K 形式命題論と形式存在論(代数学)は等価的である。
K-2 フッサールの構想:形式命題論(=形式存在論の拡張)は「知」の領域に対応する。さらに他に形式存在論(代数学)を拡張したものとして、「形式価値論」は「情」に対応し、「形式実践論」は「意」に対応する。
K-3 従来のいわゆる知・情・意の能力3分法に対応する。
K-4 フッサールは、形式命題論(哲学)の諸法則を、「形式価値論」(美学)、「形式実践論」(倫理学)に拡張できるとした。
K-5 フッサールは、理性は一つと考える。理論理性、美的理性、実践理性などに分離しない。
L フッサールは、アプリオリな論理学の基礎を求める。論理学がさらに、「直接体験=志向的体験」に基礎を持つとされる。(94頁)
(3)「対象の意味領域」の確定(フッサール的論理学の第2の条件):領域存在論
M (広義の)論理学の第2の任務は、諸学問を区分する原理を与えること、諸学問にその領域を指定することである。これが領域存在論である。
M-2 フッサールは「形式的なもの」と「質料的なもの」を峻別する。
M-3 「一」や「二」は事象内容をもたない「形式的な本質」である。種・類としての「石」や「犬」は「質料的な本質」である。
M-3 形式存在論(形式対象論)は「形式的な本質」に関わる。領域存在論は「質料的な本質」に関わる。
N 事象内容を持つ「質料的な本質」は、最低種(スぺチエス)(Ex. 秋田犬)から最高類の「領域」まで、類(Ex.犬、哺乳類・・・・)の段階系列を持つ。これに対し「形式的な本質」はこうした段階系列を持たない。
N-2 領域は3つあり、①「物質的自然」(物理的な物)、②「生命的自然」(心理物理的生物)、③「精神世界」(人格)である。
N-3 3領域に対応し、①広義の物理学(自然科学1)、②広義の生物学(自然科学2)、③精神科学がある。
N-4 物質的自然、生命的自然、精神世界の順に基づけ関係がある。
《評者の感想》
「論理学」が、諸学問の基礎学である。「論理学」は、「形式存在論(代数学)」と「領域存在論」からなる。
(a) 「形式存在論(代数学)」は「形式的な本質」にかかわる。(Ex. 「一」「二」)「形式存在論(代数学)」は、「形式的対象」としての数を、形式的に扱う。
(a)-2 「形式存在論」は3部門に拡張される。「知」(哲学)に対応する「形式命題論」(言語の結合を代数的に扱う)、「情」(美学)に対応する「形式価値論」、「意」(倫理学)に対応する「形式実践論」。
(a)-3 「形式存在論(代数学)」を基礎とし、その拡張である3部門「形式命題論」「形式価値論」「形式実践論」を含む全体が、「純粋論理学(形式論理学)」である。
(b) 「領域存在論」は「質料的な本質」にかかわる。(Ex. 「石」「犬」)
(b)-2 「質料的な本質」は、最低種(スペチエス)から最高類の「領域」にいたる段階系列を持つ。
(b)-3 3つの「領域」は、物質的自然(物)、生命的自然(生物)、精神世界(人格)からなる。それぞれ、物理学、生物学、精神科学に対応する。
(3)-2 人格主義的態度(自然的態度)と生活世界
O 物質的自然や生命的自然に対応するのは自然科学的態度(自然主義的態度)であるが、これよりも精神世界における人格主義的態度(自然的態度)が先行する。
O-2 例えば、私たちが、最初に経験するのは、「道具」(Ex. 歯ブラシ)であって、物理的な物(Ex. プラスチック)ではない。あるいは私たちは最初に「あなた」と出会い、その後で「あなた」を心理物理的な生物(ヒト)と見る。
O-3 人格主義的態度における道具や人格が、根源的に経験される。物理的な物や心理物理的な生物は、派生的に経験される。
O-4 人格主義的態度の精神世界が「生活世界」である。
O-5 かくて「態度」の観点からすると3領域の基づけ関係が逆転する。精神世界/生活世界が根源的であり、物質的自然や生命的自然は派生的である。
(3)-3 生活世界概念の成立と展開
P フッサールは「生活世界」の考え方を、アヴェナリウスの「人間的世界概念」や、ディルタイの「精神科学」を取り入れつつ展開した。フッサールは、諸学問の基礎としての論理学のさらに基礎(直接経験)を求めたが、その発掘の手助けを、彼らの概念に見出した。
P-2 生活世界的経験は、超越論的還元をせずに、「生活世界の存在論」において解明できる。フッサールが「内的同盟」関係認めていたディルタイの言葉によれば「精神科学」において解明できる。こうした方向性は、フッサール以後の現象学者に受け継がれた。
Qハイデガー:「自然科学的な物」と「道具」の分析。
Q-2 適材適所におかれている限り「道具」は目立たない。適材適所性から切り離されると、道具は目立つ。
Q-3 「自然科学的な物」は、適材適所性から切り離され、単独でとらえられる。
Q-4 「道具」は「手元存在者」と呼ばれ、「自然科学的な物」は「手前存在者」と呼ばれる。
R メルロ=ポンティ:フッサール『イデーンⅡ』を読み、「生活世界」(仏訳「生きられる世界」)概念、身体の分析、間主観性の分析に興味を持つ。
R-2 人間(身体)は、世界とのあいだに、反射学説や行動主義心理学が見出すような(自然主義的な)対応関係を持つのでない。
R-3 人間(身体)は、世界に身を挺しつつ「意味」を受け入れ・形成する。
S アルフレッド・シュッツの現象学的社会学。超越論的分析は脇に置き、日常的な生活世界での社会の成員による「意味」の構成を問う。「生活世界の存在論」の発展形態。
T ハーバーマス。社会は、合理性を追求するシステムの側面と、メンバーたちの間主観的(=間モナド的)な合意が支える側面を持つ。前者による後者の浸食=植民地化に対し、後者を擁護する。
(4)超越論的論理学(⇔領域存在論、生活世界の存在論)
U 事象内容を持った本質にかかわるアプリオリな理論である領域存在論。また、そこから生まれた生活世界論。
V これに対し事象内容を持たない形式的成分に関わるアプリオリな理論がある。形式存在論・形式命題論など。
V-2 さらに存在の構成理論、時間の構成理論、空間の構成理論、間主観性(他者)の構成理論!
V-3 これらが、論理学・諸学問の基礎づけのために必要である。
V-4 しかも、これらはすべて直接経験=志向的体験の分析によって基礎づけられる。この分析が「超越論的論理学」である。
(5)そもそも学問が依拠する真理とは何か:真理論(学問論としての広義の論理学の課題)
A 真理の「整合説」と「対応説」。
① 真理の「整合説」:近代以降の数学は整合性を追求。現実との対応を考えず、論理的に整合的であることを真理の条件としてきた。学問の危機の一因となる。
② フッサールは、形式論理学で整合性も取り上げるが、これは真理の基準というより、「真理/誤謬に先だって無意味を排除するための基準」だった。フッサールの真理論は、大雑把に言えば「対応説」である。
(5)-1 存在論的条件
B 対応説的立場から、言語的意味(※命題など)が、真理であるための存在論的条件。
《評者の補足》:「音声(or文字)そのもの」としての言語ではなく、言語の「意味」であることに注意!
B-2 存在は3種類あり、それぞれについて真理の存在論的条件がある。
(1) 言語的意味(※命題など)が、アポステリオリなもの(事実的なもの)としての「実在的な存在」(時制変化する存在)に対応すれば、「事実の真理」が可能となる。
(2) 言語的意味(※命題など)が、アプリオリなもの(本質的なもの)としての「理念的な存在」(時制変化しないもの)に対応すれば、「理性の真理」が可能となる。
(3) ただし、言語的意味(※命題など)が、「中立的な存在」(想像的・空想的なもの)に対応しても、真理は成立しない。
(5)-2 認識論的な条件
C 言語的意味(※命題など)が、真理であるための認識論的条件。フッサールによれば、真理とは「思念されているものと、与えられているものそれ自体との、完全な一致」である。
C-2 例えば、「言語(的判断)の意味」(思念されているもの)と、「知覚された事態」(与えられているものそれ自体)との一致。
C-3 さらに具体的に言えば「千鳥ヶ淵に桜が咲いている」という「言語(的判断)の意味」と、「千鳥ヶ淵に桜が咲いている」という「知覚された事態」(※これもまた「意味」である)との一致である
《評者の感想1》
① ここで「完全な一致」とは、「同一」であるということである。そうだとすれば、一方で「思念されているもの」が「意味」なら、他方で「与えられているものそれ自体」も「意味」である。
② 一方で「言語(的判断)の意味」(思念されているもの)、これが「意味」なのは分かりやすい。他方で「知覚された事態」(与えられているものそれ自体)、これもまた「意味」であることに注意したい。この両「意味」の「完全な一致」こそが、「言語(的判断)の意味」(思念されているもの)が真理である条件である。
D 「思念されているもの」と「与えられているものそれ自体」の一致は、「明証性において体験される」(フッサール)。
D-2 ここの例では、「言語の意味」と「知覚」(※意味がそこから形成される素材としての知覚的事態)の一致が、明るくはっきり(明晰・判明に)見えることである。
D-3 ただし明証性は程度を持つ。この例では、昼間なら、言語的意味と知覚的事態の(事実としての)一致は、より明証的に確認される。夜間なら、あまり明証的に確認できない。夕方は中間の明証性。
D-4 この例では、言語的意味と知覚的事態の一致が、完全に明証的に確認されれば、「十全的明証性」(⇔不十全的明証性)。
D-5 学問の真理は、十全的明証性において得られなければならない。
《評者の感想2》
③ 厳密には「知覚された事態」は一方で「意味」であり、他方で「意味」でない、世界それ自体あるいは素材としての「知覚された事態」である。それらは「モナド」内にある。「モナド」の外に、世界それ自体あるいは素材としての「知覚された事態」はない。
③-2 基盤に、《「物自体」の世界が「モナド」から切り離されて存在する》ということはない。「物自体」の世界を、「モナド」が映し出すのではない。モナドは、世界それ自体である。
④ 「モナド」としての世界は「意味」の世界と、「意味」以前の世界との、両方からなる。そして、そもそも意味が構成できるように世界ができている!つまり、時間的に産出される世界に、重なりが生じるようにできている。その重なりが、意味である。
④-2 基礎づけられた学問の体系とは、完全で真なる意味の世界であり、いわば神の意味世界である。
《評者の感想2-2》
⑤ 「モナド」はそれ自体、世界である。他の「モナド」も含めて、「モナド」の全体が、より広い世界そのものである。
⑤-2 しかし、この場合、ヒュレー的素材については、どう考えたらよいのか?ヒュレー的素材は、どこかからやって来るのか?どこかからやって来るのではない!(上述③、③-2参照)
⑤-3 ヒュレー的素材は、世界そのものである。「モナド」において、つまり「モナド」内に、世界そのものであるヒュレー的素材が、そこに現れている。
《評者の感想2-3》
⑤-4 「モナド」において自我が構成する「意味」的世界は、一種の世界の「像」ではあるが、実は、それもまた世界そのものである。
⑤-5 世界は「実在的な存在」、「理念的な存在」、「中立的な存在」からなる。
⑤-6 「モナド」は世界そのものであり、「モナド」と別に世界があるわけではない。ヒュレー的素材が、意味構成の基盤になる「物自体」と言ってもよいが、それは不可知でなく、そのものとして「モナド」内に姿を現す(=現出する。)(上述③、③-2、⑤参照)
《評者の感想3》
⑥ 世界は、「モナド」を作り、しかも多数の「モナド」を作り、同時に、全体として一つの「モナド」でありつつ、各「モナド」において姿を現す。
⑥-2 「モナド」において構成される「意味」も、それ自体、世界である。
⑥-3 「モナド」に含まれる自我とその働き自身も、世界そのものである。
⑦ この私は「モナド」である。
《評者の感想3-2》
⑦-2 「モナド」は窓を持つ。他なるもろもろの「モナド」との調和。《「モナド」間の共通の意味構成物、つまり身体境界面》が属す物理的世界の構成。
⑦-3 感情移入が成立する根拠は、(b)感情そのものの一体化である。(a)感覚の一体化と並んで、これ(b)もまた「モナド」間の調和である。
⑦-4 「モナド」間の調和のうち、(a)感覚の一体化が、《「モナド」間の共通の意味構成物、つまり身体境界面》が属す物理的世界の構成である。
⑦-5 「モナド」間の調和には、さらに(b)感情の一体化がある。感情の一体化とは、「モナド」間の調和の感情、つまり他「モナド」(他我)の出現の感情、他「モナド」(他我)との出会いの感情、あるいは最も始原的な相互了解の感情である。
⑦-6 具体的には、《他なる身体と連関する感情》(超越論的他我の感情)と《ここにあるこの身体と連関する感情》(超越論的自我の感情)の一体化が生じる。例えば、《ここにあるこの身体と連関する欲望・欲求感情》を満たしてくれる他なる物体(例えば、母親物体)の特別化、そこで生じる満足感・喜びの共有感情(感情の一体化)。この感情の一体化の出来事が、「モナド」間の調和、つまり他「モナド」(他我)の出現、他「モナド」(他我)との出会い、あるいは最も始原的な相互了解という出来事そのものである。
⑦-7 感情は、意味ではなく、意味構成を可能とする自発性である。Ex. 知覚における注視をささえる自発性感情。
《評者の感想4》
⑧ 意味とは何なのか?フッサールによれば、真理とは「思念されているものと、与えられているものそれ自体との、完全な一致」である。
ここで「思念されているもの」とは、過ぎ去った世界経験のことであり、それは意味化されることもあれば、意味化以前のこともある。
また「与えられているもの」とは、今、ここにおける世界経験(これは実は開かれている世界そのもの)である。注意すべきは、経験の外に、世界はないことである。世界そのものが、経験において、現れている=開かれている=与えられている。
⑧-2 「思念されているもの」が、言語(的判断)の「意味」の場合、いったい、何が思念されているのか。音声が思い起こされるが、その音声自身がすでに意味化されている、つまり意味である。さらにその音声が呼び起こすものもまた、思念されているもの、つまり意味だが、そもそも意味とはいったい何なのか?
⑧-3 言語(的判断)の「意味」とは、ある音声(記号)をいわば、ペグとして、引き寄せられる一切の知覚的に現前化される、または想起的、想像的、予期的に準現前化される「事態または対象」の経験の重なりである。⑧-4 「意味」は、重なる核的部分(この重なりも種々である)と、多様で重なり合わない無数の地平をもつ。意味は、曖昧さ・揺らぎをもつ。
(5)-3 知覚の「直観経過」における認識論的な対応関係:予持が原印象に対応していく
E (上記の「言語の意味」と「知覚」との「対応」関係とは別に、)言語以前の「知覚」(直接経験=志向的体験)そのものにおいて、根源的な「対応」関係がある。
E-2 知覚においては、「直観経過」が生じている。
E-3 この「直観経過」のなかで、(一種の「思念されたもの」としての)「志向(予持)されたもの」が、次々に(一種の「与えられているもの」としての)「充実されたもの(原印象)」に対応していく。かくて真理がなんらかの程度の明証性において体験されている。
F ただし、つねに次々と「新たな」志向(予持)が生じ、それは当然、まだ充実されていない(原印象と対応していない)ので、かくて現出者そのものは「十全的明証性」において知覚されえない。例えば、家の知覚において、まだ見ていない側面がつねにある。
(5)-4 「原印象的現出」は、全く意識されていないわけでない(「原意識」)としても、反省によって主題的にとらえられるのは「把持された現出」だけである
G (「現出者」は「十全的明証性」において知覚されえないとしても、)「現出」はどうだろう?
G-2 充実されている諸現出(⇒E-3原印象による予持の充実)も、実は、「非主題的に」体験されているだけである。明証的に認識するためには、「内在的知覚」(=「反省」)が必要である。
G-3 「把持のおかげで、われわれは意識を客観にする[=反省する]ことができる。」(フッサール)
G-4 把持された諸現出は十全的明証性において捉えられるとしても、原印象的現出は、そのようにとらえられない。
H 「原印象的現出」は、「把持された現出」へと移行してはじめて、反省される。
H-2 主題化する反省は、意識の現場(=原印象的現出=原意識)を捉えられない。
H-3 外的知覚(=意識の現場=原印象的現出=原意識)と内的知覚(反省)は同時に成立しない。
I 「把持された現出」も実は、十全的に明証ではない。「把持された諸現出」も、遠さが介在するので、不十全性が残る。(もっとも近い「原印象的現出」は、そもそも反省的にとらえられない。⇒G-H)
(6)必当然的明証性:アプリオリなものがもつ明証性
J 現象学が「反省」という方法をとる限り、十全的明証性は不可能である。これはフッサールを悩ませた。
K しかし「アプリオリなもの=本質」が持つ明証性は、それ以外がありえないという「必当然的明証性」であると、される。
K-2 例えば、「色は広がりをもつ」は、いつでもどこでも明証的に認識される。
K-3 フッサールは現象学がアプリオリなものを扱う「本質学」(厳密には「超越論的本質学」)であることを強調し、「必当然的明証性」を見出すことに比重をかけた。
《評者の感想》
① アプリオリなものとは、経験が独断的に一般化されたもののように思える。
② K-2の例では、「色」は多くの経験に由来する。「広がり」も多くの経験に由来する。「は」は主題(主語)を示すが、これも多くの経験の一般化である。「を」は主題(主語)との一定の関係を示すが、これも多くの経験の一般化。「もつ」も多くの経験の一般化である。
(※追伸:この感想について検討が必要!)
(7)原事実
L 最晩年のフッサールは、アプリオリな「本質」さえも、ある最も始原(起源根源)的な事実に依拠すると認める。これが「原事実」である。
L-2 必然性を持たないので、「原事実」も一種の事実である。
L-3 通常の「事実」は、経験の枠内で生じる。「原事実」は、経験そのものの成立を支える。なお経験とは、直接経験=志向的体験のことである。
M 「アポステリオリな事実」も、「アプリオリな本質」も、直接経験=志向的体験から成立する。
M-2 この直接経験=志向的体験を、「原事実」が支える。
M-3 かくてアプリオリな本質も、「原事実」なしに不可能である。アプリオリな本質が持つ「必当然的明証性」の基礎に「原事実」がある。
M-4 「原事実」は、経験そのものを可能にするのだから、超越論的な事実である。
N 「原事実」とは何か?フッサールは以下のことを原事実と認める。
(1) 私が存在する(あるいは経験の中心化が生じている)ということ。
(2) 流れつつ立ちとどまる現在が生じている(あるいは世界がある安定性をもって開かれている)ということ。
(3) 他者が存在するということ。
《評者の感想》世界がここに現在において開かれている。これが「原事実」である。
(1) 「世界がここに開かれている」が、「ここ」とはどこか?「ここ」とは私(超越論的主観性あるいはモナド)である。つまり「経験の中心化」!世界経験の中心に、常に身体が、現れる。
(2) 「世界がここに開かれている」が、どのようにか?「流れつつ立ちとどまる現在」として。世界は自己開示or自己産出を続けている。つまり内的時間or内的持続。
(2)-2 「世界が開かれる」ことが「意識」と呼ばれる。つまり「原意識」(⇒(5)-4「原印象的現出」は、全く意識されていないわけでない)および「反省」的意識。
(3) 他者が存在するということ。他者は物的世界に属す身体としてのみ姿を現す。超越論的他者=他なるモナド。
(8)原事実と新たな事実学(形而上学)
O フッサールは、超越論的な事実学としての「形而上学」を求めていた。
O-2 形而上学(Metaphysik)とは、自然学(Physik)を「後から」(meta)基礎づける学の意味。
P フッサールの形而上学は2義ある。
① 基礎づける超越論的現象学が「第1哲学」(=形而上学)!基礎づけられる自然学/事実学は「第2哲学」。
② 「第1哲学」としての超越論的現象学の基盤を問ういわば「第0哲学」(=形而上学):「原事実」を扱う学問。フッサールの第7デカルト的省察(形而上学)の構想。Cf. 第6デカルト的省察:超越論的方法論(1933年、フィンク)
P-2 かくて今や、(1)通常の事実に関わる十全的明証性(フッサールの出発点で対応説的な真理観)でもなく、(2)本質にかかわる必当然的明証性(フッサールが後に重視)でもない、(3)原事実に関わる新たな明証性概念が登場せねばならない。ハイデガー的な非-隠蔽性としての真理とも、いくらか関係する明証性かもしれない。フッサールはこれを十分に展開できなかった。
A フッサールの現象学への突破口、『論理学研究』(1900/1901)→1901年、ゲッティンゲン大学に在職:ミュンヘン・ゲッティンゲン現象学派。
B 諸学問の始原(アルケー)を捜す:フッサール。諸学問の基礎づけ。
B-2 現実、直接経験、「事象そのもの」へ帰る。
B-3 この始原は多層であるとわかる。一つの層を発掘すると次の層が現れる。
C 事象そのものは、直接に見られ、直接に経験される。哲学用語では「直観される」と言う。
D 覆い隠す思考を考え直し、事象そのものを明らかにし、始原をさがす。
E 『論理学研究』のあと、フッサールの「超越論的転回」→彼から多くの研究者が離れていく。
E-2 フッサール、1916年、フライブルク大学へ。若いハイデッガーに会う。「あなたと私が現象学だ!」とフッサール。
E-3 1920年頃から、フッサール、「発生」の観点、導入。
E-4 ハイデッガーもフッサールから離れていく。さらにハイデッガーはナチスに協力。フッサールはユダヤ系で迫害される。
F フッサール、孤立化。「哲学的隠者になってしまった」と感じる。
F-2 1938年、フッサール死去。ナチスからフッサールの4万頁の草稿救出。
G ハイデッガーの『存在と時間』での言葉:「事象そのものへ」(zu den Sachen selbst)!
第1章 現象学の誕生
第1節 数学から哲学へ
A ベルリン大学で数学の助手となる。
A-2 ブレンターノの講義を聴き哲学に向かう。「厳密学としての哲学」を目指す。
第2節 学問の危機
B ガリレイは「哲学」していた。ニュートンも「哲学」していた。「科学」の語は、まだない。
B-2 自然/世界は「数学」や「幾何学」の言語で書かれている。(ガリレイ)
B-3 数学的にとらえられた世界(理念化された世界)が「真の世界」「客観的な世界」とされる。直接経験の世界(生活世界)が「見かけの世界」「主観的な世界」とされる。ガリレイは「覆い隠す天才」とフッサール。
C 「直観」の要素を持つ幾何学でなく、「直観性」をもたない代数の発展。
C-2 19世紀後半、数学や論理学は、ライプニッツ的構想に従いつつ、経験から独立した公理体系として展開しようとしていた。
C-3 経験を「現実(性)」と言い換えるなら、数学や論理学は「可能性」だけを扱うと言える。つまり数学や論理学は、現実から離れて、それゆえまた現実に先だって(=アプリオリに)、可能性の領分を示す。
D 直接に経験・直観される現実からの数学・論理学・自然科学の遊離、地盤喪失。ヨーロッパ諸学の危機!
D-2 フッサールは数学や論理学の始原を取り戻そうとした。この始原は「直接経験」(ものを見る、ものに触るなど)にある。
D-3 E.マッハ:科学の唯一の基礎は「経験」、正確には「感覚」にあるとした。「現象学」!
D-4 ブレンターノらの「現象学」もあった。
D-4 フッサールの「純粋現象学」、「超越論的現象学」。純粋=超越論的と考えてよい。
[コーヒーブレイク] 現象学と分析哲学:「心理」、「論理」、「経験」の関係の問題
E フッサールは、言語(論理)は、経験に対して派生的とみなす。
E-2 「意味」や「思想」は、個人の心理内容でなく客観性を持つ:フレーゲ。
E-3 分析哲学は、言語の客観性・普遍妥当性あるいは公共性を重視する。経験を問う姿勢は弱い。
E-4 フッサールは『論理学研究』で、論理的なものがアプリオリであると認める。他方で、論理的なものを経験から基礎づけようとする。
第3節 フッサールの根源的着想
(1)学問の基礎は直接経験にある
A マッハの図2(左目の視野)が視覚の直接経験。マッハの図1(外部からの物理的刺激[=可視光線]を私が受け取り、知覚が成立する)は「客観的」と思われているが、実は図2のような直接経験から派生したものである。
A-2 図2は「主観的」と言われるが、これが図1の「客観性」の前提である。(45-46頁)
(2)超越論的還元
B 派生的な「客観性」を、根源的な「主観的な」光景に引き戻す(=還元する)。
B-2 そもそも私たちは、この光景(=表象)の外に出ることは出来ない。外に出られると考えるのは非学問的。
C実存する対象を持つ表象(Ex. 富士山)と、実存する対象を持たない表象(Ex. ペガサス)。
C-2 富士山が、私たちの表象の外(=表象の外部に存在する対象)では、確認されえない。
C-3 表象の外部に対象が存在することを疑わない自然的態度を停止(エポケー)。私たちの眼を、表象に引き戻す(超越論的還元)。
D 表象の外部(=「超越」的)に、なにかが「存在する」と思う「自然的態度」を問う。
D-2 存在=超越は、表象の内部から出られない私たちが、表象の内部で「構成」したもの!
D-3 超越を、このように問うことが、「超越論的」と呼ばれる。
D-4 空想対象も知覚対象も構成されたもの!
D-5 対象は、その存在=超越さえも、私たちの働きかけによって成立する。
E 還元された光景が「超越論的主観性」である。
E-2 科学的な(つまり数学と実証に依拠する)「客観科学」は「客観性」を標榜する。フッサールは客観性の基礎として、客観性に先立つ主観性を問う。
E-3 超越論的主観性とは、私たちが最も直接的に具体的に経験している光景そのもの、直接経験の領野(マッハ的な光景=図2)である。
F 心理学は自然的態度をとるのに対し、現象学は超越論的態度をとる。
F-2 現象学は、「超越論的態度の心理学」と言ってよい。
(3)「(知覚・経験される)現出者」と「(感覚・体験される)諸現出」:志向性の問題
A 机は「台形」に見えるが、私たちは「長方形」と思う。
A-2 私たちは、台形を「感覚」しているが、それを突破して、長方形を「知覚」している。
A-3 私たちは、台形の感覚・体験を突破して、その向こうに長方形を知覚・経験している。
A-4 言い換えれば、私たちは「現出」の感覚・体験を突破して、その向こうに「現出者」を知覚・経験している。
B 「(知覚・経験される)現出者」の同一性と「(感覚・体験される)現出」の多様性。
C 現出は、現出者の「記号」であるとも言える。
C-2 「現出者」は「諸現出」によって媒介されている。「諸現出」は「現出者」へと突破されている。
D 「現象」の語は、「諸現出」と「現出者」との二義性を孕む。
D-2 フッサールは、諸現出と現出者の関係を「普遍的な〈相関関係のアプリオリ〉」と捉える。
D-3 「私の生涯の仕事は、この相関関係のアプリオリを体系的に仕上げるという課題によって支配されてきた。」(フッサール)
E 「現象学」は、諸現出と現出者の関係から成り立つ「現象」を扱う学問。
E-2 現象学は、実体(本体)と現象(仮象)といった意味での現象(これは外部に実存する対象とその表象という図式のバリエーションにすぎない)を扱う学問ではない。
F 直接経験では、諸現出の体験(感覚)を媒介にし(突破して)現出者が知覚(経験)されるが、この媒介・突破の働きが志向性と呼ばれる。
F-2 それゆえ直接経験は、「志向的体験」と言い換えられる。
F-3 諸現出と現出者の(媒介・突破の)関係がそこで生じる場面、すなわち志向的体験が、「意識」と言われる。
G 「現出者(対象)」は経験(知覚)され意識の主題となるが、「現出」は体験(感覚)されるだけで「意識の非主題的成分」(その1)である。
H また意識は基本的に対象を主題的にとらえており、おのれ自身(=現出を突破する意識の「働き」)を意識するしかたは非主題的である。意識がおのれを主題化するのは「反省」(内部知覚)する場合である。すなわち、現出を突破する意識の「働き」そのものは、「意識の非主題的成分」(その2)である。
H-2 現出を突破する意識の「働き」は「作用(Akt)」と呼ばれる。のちにこの作用を支える働きがさらに発見され、その場合、作用は「能動性(Aktivität)」と呼ばれ、それを支える働きが「受動性(Passivität)」と呼ばれる。
《評者の感想》
反省的でない意識とは何か?それは、世界が受動的に開示されていることである。
(4)直観経過における志向と充実
I 諸現出は、現出者に向かって突破される。(66頁)
I-2 現出者と諸現出の相関関係は、いつも直観経過のなかに(あるいは時間意識のなかに)ある。(67頁)
I-3 予持は、いつも現出を「志向」しており、たいてい、それが次の原印象的現出によって「充実」される。(67頁)
[コーヒーブレイク] 絵画の遠近法
J フッサールは、現出を「射影」とも呼ぶ。射影は、「形態射影」と「色彩射影」に区別される。
J-2 ルネサンス期の遠近法は、形態射影に注目した。
J-3 印象派は、色彩射影に注目した。
J-4 キュビズムは、感覚される現出(形態射影と色彩射影)でなく、知覚される現出者に注目した。
《評者の感想》
●1 嗅覚射影、味覚射影、聴覚射影もあるはずだ。
●2 「形態射影」は、いわば触覚射影に相当する。触覚は、基本的に圧覚である。
●3 しかし触覚は、さらに広義には、温熱覚、痛覚も含むから、これらの射影もあるはずだ。
●4 「色彩射影」は、いわば、視覚射影に相当する。
●5 「形態射影」は、基礎を触覚射影にもつが、同時に視覚射影にも属する。
第4節 無前提性
A 諸学問の「下」(基礎)には直接経験=志向的体験がある。そして直接経験=志向的体験は、その外部から眺めることができず、その「内部」に還元する。
A-2 直接経験=志向的体験を解明する現象学は、「形而上学的、自然科学的、心理学的な無前提性を満たそうとする。」
第2章 現象学の学問論:現象学は直接経験=志向的体験からどのようにして諸学問/諸科学を基礎づけるのか
第1節 論理学と心理主義
A 数学と論理学が、諸学問/諸科学の基礎学である。
A-2 数学や論理学は、それら自体、基礎を持たないのか?
B 数学や論理学の基礎を心理学に求める心理主義。
B-2 心理主義は、「生物それぞれ、各人それぞれに、数学や論理学がある」との帰結にいたる。数学や論理学の普遍妥当性の否定。数学・論理学的真理は「各人各様」になる。
C 心理主義に反対したフレーゲ。論理学的なものは、直観や経験から独立。さらに自然的な日常言語からの解放・純化が必要。フレーゲの「概念記法」。
D フッサール『算術の哲学』(1891年)には心理主義的傾向があるが、フッサール自身が否定。「ほんとうのことを言えば、私がこれを出版したときには、私はすでにこれを乗り越えた地点にいた。」(フッサール)
D-2 プロレゴーメナ以後のフッサールは、数学や論理学がアプリオリな学問であることを認める。(フレーゲと同じ立場!)
D-3 ただしフッサールは、数学・論理学が、直観的・経験的な基礎を持つとする。(フレーゲと異なる!)その基礎が、直接経験=志向的体験である。
第2節 アプリオリ(76-84頁)
B 数学や論理学は「アプリオリ」である。(反対語が「アポステリオリ」!)
B-2 それは、ライプニッツの「理性の真理」である。「事実の真理」に対比される。
B-3 「汽車は最速の乗り物である」は「事実の真理」である。「汽車は最速の乗り物であった」と「時制変化」し、今では、当てはまらない。
B-4 これに対し「3たす3は6である」は、「時制変化」しない「永遠の真理」。つまり「理性の真理」である。
C カントは、論理的カテゴリーは、主観性に「あらかじめ」備え付けられ、「アプリオリ」だと言う。
C-2 フッサールは、主観性に「あらかじめ」備え付けられた「アプリオリ」を認めない。フッサールの現象学的アプリオリは、主観性の心理主義的認識装置(カント)ではない。
《評者の感想》:フッサールは主観性の「本質構造」、ノエシス、ノエマの構造について語る。これは現象学的「アプリオリ」である。
C-3 フッサールの「アプリオリ」は心理主義的概念でなく、存在論的概念であり、存在が時制変化しない特性を持つことである。存在が時制変化する特性を持てば、それは「アポステリオリ」である。
D 数学・論理学は、本質学であり、アプリオリ・理念的・本質的・普遍的・必然的という存在論的性格を持った存在についての学問である。「理性の真理」の学。
D-2 本質的なものの構造連関に基づく厳密学。
D-3 アプリオリなものは「いつでも性」(普遍性)を持つ。
E 心理学・物理学は、事実学であり、アポステリオリ・実在的・事実的・個別的・偶然的という存在論的性格を持った存在についての学問である。「事実の真理」の学。
E-2 事実的なものの測定に基づく精密学。
E-3 アポステリオリなものは「そのつど性」(ある時やある所でのみ妥当する)を持つ。
F アポステリオリな心理学で、アプリオリな数学・論理学を基礎づけることは出来ない。
G 経験はすべてアポステリオリなのではない:フッサール。
G-2 ヒュームは、「経験は普遍妥当性を基礎づけられない」とした。
G-3 カントは、アプリオリな成分を、主観性の中に備え付けた。一種の心理主義。
H フッサールは、「数学・論理学が、経験(直接経験=志向的体験)に基礎を持つ」とする。そして、経験(直接経験=志向的体験)は、アポステリオリな成分だけでなく、アプリオリな成分(あるいはその先行形態)を持つとする。
H-2 フッサールでは、「直観」が、経験(直接経験=志向的体験)から、アプリオリな成分を抽出し、論理的なものに仕上げる。
H-3 カントの「直観」は、感性的なものに限定されるが、フッサールでは違う。
H-4 アプリオリなものは、経験(直接経験=志向的体験)のうちにどのように含まれるのか?これを明らかにするのが、現象学の仕事である。
I フッサールは、純粋論理学(ライプニッツの方向での形式論理学)の上に、諸学問は基礎づけられるべきだとする。
I-2 その上でフッサールは、純粋論理学(形式論理学)を、直接経験=志向的体験に還元し、そこで論理学的諸理念(アプリオリな成分)の起源を証示する。これが「純粋に現象学的な解明」である!
第3節 論理学と存在論と真理論(84-115頁)
(1)「諸科学/諸学問の基礎づけという現象学的構想」の中での論理学の位置づけの問題
A 論理学は、諸学問の基礎学であり、諸学問の論理を明らかにする。
B 学問は「無意味」なものは扱わない。かくてフッサール的論理学の第1の条件は、「無意味」なものを排除することである。→純粋論理学あるいは形式論理学
C 学問は、それぞれ扱うべき対象領域(対象の意味領域)を持っている。フッサール的論理学の第2の条件は、
「対象の意味領域」の確定である。→領域存在論
C-2 論理学と存在論の結合。ここで存在論とは、論理学的な表現が指し示している当のものの理論、あるいは本質によって区別された限りでの対象論である。
C-3 論理学を存在論に結び付けるのは、アリストテレス以来の伝統。論理学が、存在論から独立の1学科になったのは、近代特有の出来事。
(2)「無意味」の排除:フッサール的論理学の第1の条件(形式論理学)
D 「無意味」の4種類
① そもそも「意味を持たない言葉」(Ex. アブラカタブラ)
② 「文法的に無意味」(Ex. 白いそして)
③ 意味が互いに矛盾する「反意味」(Ex. 丸い四角)
④ 対象が実在しない限りでの無意味(Ex. 黄金の山)
D-2 こうしたいろいろな無意味のうち、アプリオリに「対象の充実した直観に至りえないもの」をあらかじめ排除する。
(2)-2 形式存在論(代数学)と形式命題論:この両者が結びついたものが「純粋論理学」(形式論理学)
E もっぱら「言語」的な結合の仕方を考察する論理学の部門:「形式命題論」。
E-2 フッサールは、「無意味」を排除するため、「意味」を「形式的」にとらえ、それを支配する法則に照らし、不適切なものを排除する。
F フッサールは、論理学を存在論(対象論)と結合させる:「形式存在論」(代数学)。
G 「事象内容を持った本質」は、「質料」。「それは何であるか?」と問われた時、「何」にあたるもの。
G-2 「事象内容を持たない本質」は、「形式」。「数」は形式的な対象である。
H 「形式存在論」:代数(学)は「形式的対象」としての数を形式的に扱う。代入される数と無関係に、その法則だけで演算・操作が進められる。代数学は典型的な「形式存在論」!
H-2 「形式命題論」:「言語」を、「代数」的な考え方を拡張し捉えたもの。形式命題論は、もともと形式存在論(代数)的である。
H-3 形式命題論は、形式存在論と基本的に同じ法則である。
H-4 純粋論理学(形式論理学)は、形式存在論(代数学)と形式命題論の2側面が結びついて成り立つ。
I 形式命題論(形式存在論と一体的である)の法則による「無意味」の排除(90頁)
I-2 形式命題論は、最初に、言語を分類する。(名詞、形容詞など。)そして言語の結合、命題と命題の結合について、アプリオリな法則を示す。
I-3 「白いそして」(形容詞と接続詞の結合)は無意味として排除される。(D②)
I-3 矛盾律(Aは非Aでない)に反する結合、「非AであるA」は、無意味として排除される。
I-4 「木製の鉄」など意味同士が背反する無意味(「反意味」)も排除する。(D③)
I-5 「正64面体」は、数学(形式存在論)によって検証し、「無意味」と排除される。
I-6 「黄金の山」は形式命題論のレベルでは有意味。ただし実在的な対象を持たないので日常的には「無意味」。アポステリオリに現実の存在(実存)を確認する必要がある。
J 形式命題論により「無意味」な言語表現(命題)が排除される。
J-2 有意味な言語表現(命題)について、実在的に存在する対象、または理念的に存在する対象の充実した直観に対する場合、それは「真理」(真)される。
J-3 無意味は、そもそも、真理にも誤謬にもかかわることができない。
K 形式命題論と形式存在論(代数学)は等価的である。
K-2 フッサールの構想:形式命題論(=形式存在論の拡張)は「知」の領域に対応する。さらに他に形式存在論(代数学)を拡張したものとして、「形式価値論」は「情」に対応し、「形式実践論」は「意」に対応する。
K-3 従来のいわゆる知・情・意の能力3分法に対応する。
K-4 フッサールは、形式命題論(哲学)の諸法則を、「形式価値論」(美学)、「形式実践論」(倫理学)に拡張できるとした。
K-5 フッサールは、理性は一つと考える。理論理性、美的理性、実践理性などに分離しない。
L フッサールは、アプリオリな論理学の基礎を求める。論理学がさらに、「直接体験=志向的体験」に基礎を持つとされる。(94頁)
(3)「対象の意味領域」の確定(フッサール的論理学の第2の条件):領域存在論
M (広義の)論理学の第2の任務は、諸学問を区分する原理を与えること、諸学問にその領域を指定することである。これが領域存在論である。
M-2 フッサールは「形式的なもの」と「質料的なもの」を峻別する。
M-3 「一」や「二」は事象内容をもたない「形式的な本質」である。種・類としての「石」や「犬」は「質料的な本質」である。
M-3 形式存在論(形式対象論)は「形式的な本質」に関わる。領域存在論は「質料的な本質」に関わる。
N 事象内容を持つ「質料的な本質」は、最低種(スぺチエス)(Ex. 秋田犬)から最高類の「領域」まで、類(Ex.犬、哺乳類・・・・)の段階系列を持つ。これに対し「形式的な本質」はこうした段階系列を持たない。
N-2 領域は3つあり、①「物質的自然」(物理的な物)、②「生命的自然」(心理物理的生物)、③「精神世界」(人格)である。
N-3 3領域に対応し、①広義の物理学(自然科学1)、②広義の生物学(自然科学2)、③精神科学がある。
N-4 物質的自然、生命的自然、精神世界の順に基づけ関係がある。
《評者の感想》
「論理学」が、諸学問の基礎学である。「論理学」は、「形式存在論(代数学)」と「領域存在論」からなる。
(a) 「形式存在論(代数学)」は「形式的な本質」にかかわる。(Ex. 「一」「二」)「形式存在論(代数学)」は、「形式的対象」としての数を、形式的に扱う。
(a)-2 「形式存在論」は3部門に拡張される。「知」(哲学)に対応する「形式命題論」(言語の結合を代数的に扱う)、「情」(美学)に対応する「形式価値論」、「意」(倫理学)に対応する「形式実践論」。
(a)-3 「形式存在論(代数学)」を基礎とし、その拡張である3部門「形式命題論」「形式価値論」「形式実践論」を含む全体が、「純粋論理学(形式論理学)」である。
(b) 「領域存在論」は「質料的な本質」にかかわる。(Ex. 「石」「犬」)
(b)-2 「質料的な本質」は、最低種(スペチエス)から最高類の「領域」にいたる段階系列を持つ。
(b)-3 3つの「領域」は、物質的自然(物)、生命的自然(生物)、精神世界(人格)からなる。それぞれ、物理学、生物学、精神科学に対応する。
(3)-2 人格主義的態度(自然的態度)と生活世界
O 物質的自然や生命的自然に対応するのは自然科学的態度(自然主義的態度)であるが、これよりも精神世界における人格主義的態度(自然的態度)が先行する。
O-2 例えば、私たちが、最初に経験するのは、「道具」(Ex. 歯ブラシ)であって、物理的な物(Ex. プラスチック)ではない。あるいは私たちは最初に「あなた」と出会い、その後で「あなた」を心理物理的な生物(ヒト)と見る。
O-3 人格主義的態度における道具や人格が、根源的に経験される。物理的な物や心理物理的な生物は、派生的に経験される。
O-4 人格主義的態度の精神世界が「生活世界」である。
O-5 かくて「態度」の観点からすると3領域の基づけ関係が逆転する。精神世界/生活世界が根源的であり、物質的自然や生命的自然は派生的である。
(3)-3 生活世界概念の成立と展開
P フッサールは「生活世界」の考え方を、アヴェナリウスの「人間的世界概念」や、ディルタイの「精神科学」を取り入れつつ展開した。フッサールは、諸学問の基礎としての論理学のさらに基礎(直接経験)を求めたが、その発掘の手助けを、彼らの概念に見出した。
P-2 生活世界的経験は、超越論的還元をせずに、「生活世界の存在論」において解明できる。フッサールが「内的同盟」関係認めていたディルタイの言葉によれば「精神科学」において解明できる。こうした方向性は、フッサール以後の現象学者に受け継がれた。
Qハイデガー:「自然科学的な物」と「道具」の分析。
Q-2 適材適所におかれている限り「道具」は目立たない。適材適所性から切り離されると、道具は目立つ。
Q-3 「自然科学的な物」は、適材適所性から切り離され、単独でとらえられる。
Q-4 「道具」は「手元存在者」と呼ばれ、「自然科学的な物」は「手前存在者」と呼ばれる。
R メルロ=ポンティ:フッサール『イデーンⅡ』を読み、「生活世界」(仏訳「生きられる世界」)概念、身体の分析、間主観性の分析に興味を持つ。
R-2 人間(身体)は、世界とのあいだに、反射学説や行動主義心理学が見出すような(自然主義的な)対応関係を持つのでない。
R-3 人間(身体)は、世界に身を挺しつつ「意味」を受け入れ・形成する。
S アルフレッド・シュッツの現象学的社会学。超越論的分析は脇に置き、日常的な生活世界での社会の成員による「意味」の構成を問う。「生活世界の存在論」の発展形態。
T ハーバーマス。社会は、合理性を追求するシステムの側面と、メンバーたちの間主観的(=間モナド的)な合意が支える側面を持つ。前者による後者の浸食=植民地化に対し、後者を擁護する。
(4)超越論的論理学(⇔領域存在論、生活世界の存在論)
U 事象内容を持った本質にかかわるアプリオリな理論である領域存在論。また、そこから生まれた生活世界論。
V これに対し事象内容を持たない形式的成分に関わるアプリオリな理論がある。形式存在論・形式命題論など。
V-2 さらに存在の構成理論、時間の構成理論、空間の構成理論、間主観性(他者)の構成理論!
V-3 これらが、論理学・諸学問の基礎づけのために必要である。
V-4 しかも、これらはすべて直接経験=志向的体験の分析によって基礎づけられる。この分析が「超越論的論理学」である。
(5)そもそも学問が依拠する真理とは何か:真理論(学問論としての広義の論理学の課題)
A 真理の「整合説」と「対応説」。
① 真理の「整合説」:近代以降の数学は整合性を追求。現実との対応を考えず、論理的に整合的であることを真理の条件としてきた。学問の危機の一因となる。
② フッサールは、形式論理学で整合性も取り上げるが、これは真理の基準というより、「真理/誤謬に先だって無意味を排除するための基準」だった。フッサールの真理論は、大雑把に言えば「対応説」である。
(5)-1 存在論的条件
B 対応説的立場から、言語的意味(※命題など)が、真理であるための存在論的条件。
《評者の補足》:「音声(or文字)そのもの」としての言語ではなく、言語の「意味」であることに注意!
B-2 存在は3種類あり、それぞれについて真理の存在論的条件がある。
(1) 言語的意味(※命題など)が、アポステリオリなもの(事実的なもの)としての「実在的な存在」(時制変化する存在)に対応すれば、「事実の真理」が可能となる。
(2) 言語的意味(※命題など)が、アプリオリなもの(本質的なもの)としての「理念的な存在」(時制変化しないもの)に対応すれば、「理性の真理」が可能となる。
(3) ただし、言語的意味(※命題など)が、「中立的な存在」(想像的・空想的なもの)に対応しても、真理は成立しない。
(5)-2 認識論的な条件
C 言語的意味(※命題など)が、真理であるための認識論的条件。フッサールによれば、真理とは「思念されているものと、与えられているものそれ自体との、完全な一致」である。
C-2 例えば、「言語(的判断)の意味」(思念されているもの)と、「知覚された事態」(与えられているものそれ自体)との一致。
C-3 さらに具体的に言えば「千鳥ヶ淵に桜が咲いている」という「言語(的判断)の意味」と、「千鳥ヶ淵に桜が咲いている」という「知覚された事態」(※これもまた「意味」である)との一致である
《評者の感想1》
① ここで「完全な一致」とは、「同一」であるということである。そうだとすれば、一方で「思念されているもの」が「意味」なら、他方で「与えられているものそれ自体」も「意味」である。
② 一方で「言語(的判断)の意味」(思念されているもの)、これが「意味」なのは分かりやすい。他方で「知覚された事態」(与えられているものそれ自体)、これもまた「意味」であることに注意したい。この両「意味」の「完全な一致」こそが、「言語(的判断)の意味」(思念されているもの)が真理である条件である。
D 「思念されているもの」と「与えられているものそれ自体」の一致は、「明証性において体験される」(フッサール)。
D-2 ここの例では、「言語の意味」と「知覚」(※意味がそこから形成される素材としての知覚的事態)の一致が、明るくはっきり(明晰・判明に)見えることである。
D-3 ただし明証性は程度を持つ。この例では、昼間なら、言語的意味と知覚的事態の(事実としての)一致は、より明証的に確認される。夜間なら、あまり明証的に確認できない。夕方は中間の明証性。
D-4 この例では、言語的意味と知覚的事態の一致が、完全に明証的に確認されれば、「十全的明証性」(⇔不十全的明証性)。
D-5 学問の真理は、十全的明証性において得られなければならない。
《評者の感想2》
③ 厳密には「知覚された事態」は一方で「意味」であり、他方で「意味」でない、世界それ自体あるいは素材としての「知覚された事態」である。それらは「モナド」内にある。「モナド」の外に、世界それ自体あるいは素材としての「知覚された事態」はない。
③-2 基盤に、《「物自体」の世界が「モナド」から切り離されて存在する》ということはない。「物自体」の世界を、「モナド」が映し出すのではない。モナドは、世界それ自体である。
④ 「モナド」としての世界は「意味」の世界と、「意味」以前の世界との、両方からなる。そして、そもそも意味が構成できるように世界ができている!つまり、時間的に産出される世界に、重なりが生じるようにできている。その重なりが、意味である。
④-2 基礎づけられた学問の体系とは、完全で真なる意味の世界であり、いわば神の意味世界である。
《評者の感想2-2》
⑤ 「モナド」はそれ自体、世界である。他の「モナド」も含めて、「モナド」の全体が、より広い世界そのものである。
⑤-2 しかし、この場合、ヒュレー的素材については、どう考えたらよいのか?ヒュレー的素材は、どこかからやって来るのか?どこかからやって来るのではない!(上述③、③-2参照)
⑤-3 ヒュレー的素材は、世界そのものである。「モナド」において、つまり「モナド」内に、世界そのものであるヒュレー的素材が、そこに現れている。
《評者の感想2-3》
⑤-4 「モナド」において自我が構成する「意味」的世界は、一種の世界の「像」ではあるが、実は、それもまた世界そのものである。
⑤-5 世界は「実在的な存在」、「理念的な存在」、「中立的な存在」からなる。
⑤-6 「モナド」は世界そのものであり、「モナド」と別に世界があるわけではない。ヒュレー的素材が、意味構成の基盤になる「物自体」と言ってもよいが、それは不可知でなく、そのものとして「モナド」内に姿を現す(=現出する。)(上述③、③-2、⑤参照)
《評者の感想3》
⑥ 世界は、「モナド」を作り、しかも多数の「モナド」を作り、同時に、全体として一つの「モナド」でありつつ、各「モナド」において姿を現す。
⑥-2 「モナド」において構成される「意味」も、それ自体、世界である。
⑥-3 「モナド」に含まれる自我とその働き自身も、世界そのものである。
⑦ この私は「モナド」である。
《評者の感想3-2》
⑦-2 「モナド」は窓を持つ。他なるもろもろの「モナド」との調和。《「モナド」間の共通の意味構成物、つまり身体境界面》が属す物理的世界の構成。
⑦-3 感情移入が成立する根拠は、(b)感情そのものの一体化である。(a)感覚の一体化と並んで、これ(b)もまた「モナド」間の調和である。
⑦-4 「モナド」間の調和のうち、(a)感覚の一体化が、《「モナド」間の共通の意味構成物、つまり身体境界面》が属す物理的世界の構成である。
⑦-5 「モナド」間の調和には、さらに(b)感情の一体化がある。感情の一体化とは、「モナド」間の調和の感情、つまり他「モナド」(他我)の出現の感情、他「モナド」(他我)との出会いの感情、あるいは最も始原的な相互了解の感情である。
⑦-6 具体的には、《他なる身体と連関する感情》(超越論的他我の感情)と《ここにあるこの身体と連関する感情》(超越論的自我の感情)の一体化が生じる。例えば、《ここにあるこの身体と連関する欲望・欲求感情》を満たしてくれる他なる物体(例えば、母親物体)の特別化、そこで生じる満足感・喜びの共有感情(感情の一体化)。この感情の一体化の出来事が、「モナド」間の調和、つまり他「モナド」(他我)の出現、他「モナド」(他我)との出会い、あるいは最も始原的な相互了解という出来事そのものである。
⑦-7 感情は、意味ではなく、意味構成を可能とする自発性である。Ex. 知覚における注視をささえる自発性感情。
《評者の感想4》
⑧ 意味とは何なのか?フッサールによれば、真理とは「思念されているものと、与えられているものそれ自体との、完全な一致」である。
ここで「思念されているもの」とは、過ぎ去った世界経験のことであり、それは意味化されることもあれば、意味化以前のこともある。
また「与えられているもの」とは、今、ここにおける世界経験(これは実は開かれている世界そのもの)である。注意すべきは、経験の外に、世界はないことである。世界そのものが、経験において、現れている=開かれている=与えられている。
⑧-2 「思念されているもの」が、言語(的判断)の「意味」の場合、いったい、何が思念されているのか。音声が思い起こされるが、その音声自身がすでに意味化されている、つまり意味である。さらにその音声が呼び起こすものもまた、思念されているもの、つまり意味だが、そもそも意味とはいったい何なのか?
⑧-3 言語(的判断)の「意味」とは、ある音声(記号)をいわば、ペグとして、引き寄せられる一切の知覚的に現前化される、または想起的、想像的、予期的に準現前化される「事態または対象」の経験の重なりである。⑧-4 「意味」は、重なる核的部分(この重なりも種々である)と、多様で重なり合わない無数の地平をもつ。意味は、曖昧さ・揺らぎをもつ。
(5)-3 知覚の「直観経過」における認識論的な対応関係:予持が原印象に対応していく
E (上記の「言語の意味」と「知覚」との「対応」関係とは別に、)言語以前の「知覚」(直接経験=志向的体験)そのものにおいて、根源的な「対応」関係がある。
E-2 知覚においては、「直観経過」が生じている。
E-3 この「直観経過」のなかで、(一種の「思念されたもの」としての)「志向(予持)されたもの」が、次々に(一種の「与えられているもの」としての)「充実されたもの(原印象)」に対応していく。かくて真理がなんらかの程度の明証性において体験されている。
F ただし、つねに次々と「新たな」志向(予持)が生じ、それは当然、まだ充実されていない(原印象と対応していない)ので、かくて現出者そのものは「十全的明証性」において知覚されえない。例えば、家の知覚において、まだ見ていない側面がつねにある。
(5)-4 「原印象的現出」は、全く意識されていないわけでない(「原意識」)としても、反省によって主題的にとらえられるのは「把持された現出」だけである
G (「現出者」は「十全的明証性」において知覚されえないとしても、)「現出」はどうだろう?
G-2 充実されている諸現出(⇒E-3原印象による予持の充実)も、実は、「非主題的に」体験されているだけである。明証的に認識するためには、「内在的知覚」(=「反省」)が必要である。
G-3 「把持のおかげで、われわれは意識を客観にする[=反省する]ことができる。」(フッサール)
G-4 把持された諸現出は十全的明証性において捉えられるとしても、原印象的現出は、そのようにとらえられない。
H 「原印象的現出」は、「把持された現出」へと移行してはじめて、反省される。
H-2 主題化する反省は、意識の現場(=原印象的現出=原意識)を捉えられない。
H-3 外的知覚(=意識の現場=原印象的現出=原意識)と内的知覚(反省)は同時に成立しない。
I 「把持された現出」も実は、十全的に明証ではない。「把持された諸現出」も、遠さが介在するので、不十全性が残る。(もっとも近い「原印象的現出」は、そもそも反省的にとらえられない。⇒G-H)
(6)必当然的明証性:アプリオリなものがもつ明証性
J 現象学が「反省」という方法をとる限り、十全的明証性は不可能である。これはフッサールを悩ませた。
K しかし「アプリオリなもの=本質」が持つ明証性は、それ以外がありえないという「必当然的明証性」であると、される。
K-2 例えば、「色は広がりをもつ」は、いつでもどこでも明証的に認識される。
K-3 フッサールは現象学がアプリオリなものを扱う「本質学」(厳密には「超越論的本質学」)であることを強調し、「必当然的明証性」を見出すことに比重をかけた。
《評者の感想》
① アプリオリなものとは、経験が独断的に一般化されたもののように思える。
② K-2の例では、「色」は多くの経験に由来する。「広がり」も多くの経験に由来する。「は」は主題(主語)を示すが、これも多くの経験の一般化である。「を」は主題(主語)との一定の関係を示すが、これも多くの経験の一般化。「もつ」も多くの経験の一般化である。
(※追伸:この感想について検討が必要!)
(7)原事実
L 最晩年のフッサールは、アプリオリな「本質」さえも、ある最も始原(起源根源)的な事実に依拠すると認める。これが「原事実」である。
L-2 必然性を持たないので、「原事実」も一種の事実である。
L-3 通常の「事実」は、経験の枠内で生じる。「原事実」は、経験そのものの成立を支える。なお経験とは、直接経験=志向的体験のことである。
M 「アポステリオリな事実」も、「アプリオリな本質」も、直接経験=志向的体験から成立する。
M-2 この直接経験=志向的体験を、「原事実」が支える。
M-3 かくてアプリオリな本質も、「原事実」なしに不可能である。アプリオリな本質が持つ「必当然的明証性」の基礎に「原事実」がある。
M-4 「原事実」は、経験そのものを可能にするのだから、超越論的な事実である。
N 「原事実」とは何か?フッサールは以下のことを原事実と認める。
(1) 私が存在する(あるいは経験の中心化が生じている)ということ。
(2) 流れつつ立ちとどまる現在が生じている(あるいは世界がある安定性をもって開かれている)ということ。
(3) 他者が存在するということ。
《評者の感想》世界がここに現在において開かれている。これが「原事実」である。
(1) 「世界がここに開かれている」が、「ここ」とはどこか?「ここ」とは私(超越論的主観性あるいはモナド)である。つまり「経験の中心化」!世界経験の中心に、常に身体が、現れる。
(2) 「世界がここに開かれている」が、どのようにか?「流れつつ立ちとどまる現在」として。世界は自己開示or自己産出を続けている。つまり内的時間or内的持続。
(2)-2 「世界が開かれる」ことが「意識」と呼ばれる。つまり「原意識」(⇒(5)-4「原印象的現出」は、全く意識されていないわけでない)および「反省」的意識。
(3) 他者が存在するということ。他者は物的世界に属す身体としてのみ姿を現す。超越論的他者=他なるモナド。
(8)原事実と新たな事実学(形而上学)
O フッサールは、超越論的な事実学としての「形而上学」を求めていた。
O-2 形而上学(Metaphysik)とは、自然学(Physik)を「後から」(meta)基礎づける学の意味。
P フッサールの形而上学は2義ある。
① 基礎づける超越論的現象学が「第1哲学」(=形而上学)!基礎づけられる自然学/事実学は「第2哲学」。
② 「第1哲学」としての超越論的現象学の基盤を問ういわば「第0哲学」(=形而上学):「原事実」を扱う学問。フッサールの第7デカルト的省察(形而上学)の構想。Cf. 第6デカルト的省察:超越論的方法論(1933年、フィンク)
P-2 かくて今や、(1)通常の事実に関わる十全的明証性(フッサールの出発点で対応説的な真理観)でもなく、(2)本質にかかわる必当然的明証性(フッサールが後に重視)でもない、(3)原事実に関わる新たな明証性概念が登場せねばならない。ハイデガー的な非-隠蔽性としての真理とも、いくらか関係する明証性かもしれない。フッサールはこれを十分に展開できなかった。