都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
ハーディングをFMで聴く NHK音楽祭2006
NHK-FM ベストオブクラシック(10/5 19:00 - ) NHK音楽祭2006(1)
曲 モーツァルト 交響曲第6番 K.43
ピアノ協奏曲第20番 K.466
ブラームス 交響曲第2番 作品73
指揮 ダニエル・ハーディング
演奏 マーラー・チェンバー・オーケストラ
ピアノ ラルス・フォークト
収録:NHKホール(生中継) 2006/10/5
実際にホールへ足を運びたかったのですが、都合がつかなかったので録音で楽しむことにしました。今日から始まったNHK音楽祭より、ハーディング&マーラー・チェンバー・オーケストラの演奏会です。

ハーディングは聴衆へのサービス精神に溢れた指揮者だと思います。これほど音楽をダイナミックに分かり易い形で、しかもそれこそ楽しく演奏出来る方も珍しいのではないでしょうか。K.466では、第二楽章をロマン風味にこってりと味付け、その一方で三楽章を颯爽に流していました。もちろん、単なるインテンポ系の演奏ではありません。時折揺れ動くフレージングがまるでジャズのスイングのような効果をもたらし、時に音の流れを断ち切るかのような乾いた金管が緊張感を与えている。聴かせどころはテンポを落として、とても丁寧に演奏していたのが印象的でした。明暗の表裏一体となったモーツァルトです。
ブラームスでは響きのバランス感が優れています。音の情報量が極めて多い演奏です。木管と弦、それに金管が、それぞれに主張しながらも美しく合わせ重なって聞こえてきました。木管を強調する際には弦を控えめに、また金管を強めに吹かせる際は一瞬の間合いを入れる。音量バランスへの配慮が絶妙です。フォルテでも単に音が増幅するわけではありません。
刹那的な第二楽章がとても濃厚でした。特に終結部では、まるで煙のようにもやもやと立ち上がりながらも分厚い響きが訪れるワーグナーのような音楽になっていたのには驚きました。贅肉を徹底して削ぎ落とし、鮮烈な音の渦を作り出す古楽器系の演奏の面白さだけでなく、時に往年の名指揮者が聴かせたようなロマン的な音楽を加味するのもハーディングの良さなのかもしれません。(後者への志向が強いとさえ思いました。)
ノリントン、ルイージ、そしてアーノンクールと続く今年のNHK音楽祭は聞き逃せません。今後もチェックしていきたいです。
曲 モーツァルト 交響曲第6番 K.43
ピアノ協奏曲第20番 K.466
ブラームス 交響曲第2番 作品73
指揮 ダニエル・ハーディング
演奏 マーラー・チェンバー・オーケストラ
ピアノ ラルス・フォークト
収録:NHKホール(生中継) 2006/10/5
実際にホールへ足を運びたかったのですが、都合がつかなかったので録音で楽しむことにしました。今日から始まったNHK音楽祭より、ハーディング&マーラー・チェンバー・オーケストラの演奏会です。

ハーディングは聴衆へのサービス精神に溢れた指揮者だと思います。これほど音楽をダイナミックに分かり易い形で、しかもそれこそ楽しく演奏出来る方も珍しいのではないでしょうか。K.466では、第二楽章をロマン風味にこってりと味付け、その一方で三楽章を颯爽に流していました。もちろん、単なるインテンポ系の演奏ではありません。時折揺れ動くフレージングがまるでジャズのスイングのような効果をもたらし、時に音の流れを断ち切るかのような乾いた金管が緊張感を与えている。聴かせどころはテンポを落として、とても丁寧に演奏していたのが印象的でした。明暗の表裏一体となったモーツァルトです。
ブラームスでは響きのバランス感が優れています。音の情報量が極めて多い演奏です。木管と弦、それに金管が、それぞれに主張しながらも美しく合わせ重なって聞こえてきました。木管を強調する際には弦を控えめに、また金管を強めに吹かせる際は一瞬の間合いを入れる。音量バランスへの配慮が絶妙です。フォルテでも単に音が増幅するわけではありません。
刹那的な第二楽章がとても濃厚でした。特に終結部では、まるで煙のようにもやもやと立ち上がりながらも分厚い響きが訪れるワーグナーのような音楽になっていたのには驚きました。贅肉を徹底して削ぎ落とし、鮮烈な音の渦を作り出す古楽器系の演奏の面白さだけでなく、時に往年の名指揮者が聴かせたようなロマン的な音楽を加味するのもハーディングの良さなのかもしれません。(後者への志向が強いとさえ思いました。)
ノリントン、ルイージ、そしてアーノンクールと続く今年のNHK音楽祭は聞き逃せません。今後もチェックしていきたいです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
70万人のモーツァルト音楽祭全記録 「熱狂の日 2006」
今更ではありますが、今年の「熱狂の日音楽祭」を振り返る記録冊子、「70万人のモーツァルト音楽祭 全記録」(リンクはpdfです。)をいただいて来ました。タワーレコード(クラシック取り扱い店舗のみ。)や新星堂、それにぴあステーションや国際フォーラムの総合案内所などで、今月中旬から無料で配布されています。
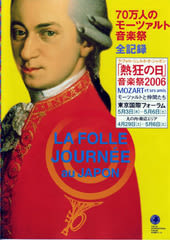

冊子は、A4サイズ、オールカラー全24ページとなかなか豪華でしたが、中は殆どコンサートの様子を捉えた写真で構成されていました。私も楽しんだベルリン古楽アカデミー&ルクスや、コルボ&ローザンヌ声楽アンサンブルなどの写真を拝見すると、その美しい響きが改めて頭の中に甦ってきます。またその他には、どの「熱狂の日」よりも東京を重要視していく息巻くマルタン(音楽祭の仕掛人です。)の挨拶や、当日の丸の内界隈の賑わいなどが紹介されていました。パラパラとめくるのに最適です。
紙面で一番興味深いのは、やはり最後に掲載されていたアンケート結果でした。ここにその一部を、昨年の数字と比較する形で引用させていただきます。(カッコ内は昨年の数字です。)
Q.音楽祭の感想をお聞かせ下さい
大変良かった 56.1% (47.1%)
よかった 33.7% (36.35%)
あまりよくなかった 3.6% (1.4%)
よくなかった 2.7% (0.47%)
「大変良かった」と「よかった」を合わせた満足度が昨年よりもあがっています。その一方で、否定的な意見も僅かながら増加していました。これは二極化でしょうか。(?!)
Q.お聴きになった有料公演数はいくつですか
1公演 15.6% (32.29%)
2公演 15.3% (24.02%)
3公演 9.1% (15.13%)
4公演 7.2% (6.55%)
5公演 5.5% (3.43%)
6公演 4.7% (5公演以上 10.45%)
7公演 3.0%
8公演 2.8%
9公演 1.7%
10公演 2.3%
それ以上 6.6%
平均4.7公演だそうです。10公演以上の方が6%もいらっしゃるとは驚きました。昨年よりもハシゴする方が明らかに増えています。これは「昨年来て良かったので、今年はもっと聴こう。」と思った方が多かったからではないでしょうか。前売段階にてチケットがかなり売り切れていたことにも納得させられます。
Q.これまでクラシックコンサートに何回いらっしゃいましたか
初めて 7.9% (14.66%)
1-2回 21.1% (35.88%)
3-5回 22.7% (26.83%)
6-10回 14.4% (9.98%)
それ以上 16.5% (11.86%)
いわゆるビギナーが多いのも事実ですが、コアなクラシックファンも増えています。モーツァルトでこの結果だとすると、来年(国民学派)はさらにその傾向が強まりそうです。
Q.性別
男性 34.7% (29.02%)
女性 61.6% (68.02%)
昨年より男性客が増えたとは言え、圧倒的に女性客が多くなっています。また、実際に会場を歩いても、一般的なクラシックコンサートと比べてかなり女性が目立っていました。これは、通常のコンサートでは殆ど無視されているファミリー層の存在や、休日の銀座・丸の内という立地特性などが影響しているからだと思います。
Q.年齢
10代 6.9% (5.77%)
20代 12.2% (22.78%)
30代 22.7% (22.78%)
40代 18.9% (17.63%)
50代 18.1% (15.6%)
60代 11.5% (8.11%)
70代 5% (2.81%)
80代 0.2% (0%)
高齢化が進むクラシックコンサートとしては異例なほど、40代以下の若い層が多いようです。ただ気になるのは20代の激減ぶりです。ほぼ半分に減っています。何故でしょうか…。
Q.同伴者
なし 29.3% (15.28%)
家族 47.8% (42.75%)
親戚 1.9% (1.54%)
友人・知人 17.9% (34.72%)
音楽仲間 1.4% (1.85%)
学校 0.1% (0%)
メインはやはりファミリーです。このイベントが、ゴールデンウィーク中の一行楽スポットとして認知されている証拠かと思います。ただし、「友人・知人」が減少し、その一方で「なし」がほぼ倍増していることも見逃せません。やはりコアなファン層が増えているからでしょうか。イベントはイベントらしく皆で楽しむのがピッタリかと…。(と言う私も、一人で出かけたコンサートがありましたが…。)
Q.今後、音楽祭で取り上げて欲しい作曲家があればお書き下さい
バッハ 21.4%
ショパン 13.9%
チャイコフスキー 12%
ブラームス 9.2%
シューベルト 6.3%
ベートーヴェン 4.2%
モーツァルト 3.6%
ドヴォルザーク 2.4%
その他 26.9%
*昨年のベスト10:モーツァルト、ショパン、バッハ、チャイコフスキー、ブラームス、シューベルト、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、ヨハンシュトラウス、マーラー、リスト
やはり抜群の知名度がものを言うのでしょう。バッハが圧倒的な一位の座に輝きました。バッハだけではなく、有りがちな「バロックの調べ」などというテーマで、バロック音楽を一括りにして開催するのも面白いと思います。ちなみに、チャイコフスキーやドヴォルザークは来年のテーマ作曲家です。あちこちで、新世界と、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の冒頭部分が高らかに鳴り響くことが予想されます。それにしても、昨年のアンケートでマーラーが挙がっていたのには驚きました。また、個人的には苦手のショパンが、昨年に続いて二位というのにもその根強い人気を思わせます。当然ながらどうしてもピアノ曲ばかりになってしまうので、他の作曲家と合わせての開催となりそうです。
私がいただいた時にはまだ冊子はたくさん残っていました。ご興味のある方は一度手に取ってみては如何でしょうか。
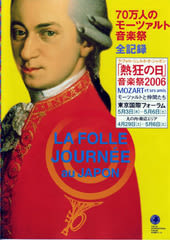

冊子は、A4サイズ、オールカラー全24ページとなかなか豪華でしたが、中は殆どコンサートの様子を捉えた写真で構成されていました。私も楽しんだベルリン古楽アカデミー&ルクスや、コルボ&ローザンヌ声楽アンサンブルなどの写真を拝見すると、その美しい響きが改めて頭の中に甦ってきます。またその他には、どの「熱狂の日」よりも東京を重要視していく息巻くマルタン(音楽祭の仕掛人です。)の挨拶や、当日の丸の内界隈の賑わいなどが紹介されていました。パラパラとめくるのに最適です。
紙面で一番興味深いのは、やはり最後に掲載されていたアンケート結果でした。ここにその一部を、昨年の数字と比較する形で引用させていただきます。(カッコ内は昨年の数字です。)
Q.音楽祭の感想をお聞かせ下さい
大変良かった 56.1% (47.1%)
よかった 33.7% (36.35%)
あまりよくなかった 3.6% (1.4%)
よくなかった 2.7% (0.47%)
「大変良かった」と「よかった」を合わせた満足度が昨年よりもあがっています。その一方で、否定的な意見も僅かながら増加していました。これは二極化でしょうか。(?!)
Q.お聴きになった有料公演数はいくつですか
1公演 15.6% (32.29%)
2公演 15.3% (24.02%)
3公演 9.1% (15.13%)
4公演 7.2% (6.55%)
5公演 5.5% (3.43%)
6公演 4.7% (5公演以上 10.45%)
7公演 3.0%
8公演 2.8%
9公演 1.7%
10公演 2.3%
それ以上 6.6%
平均4.7公演だそうです。10公演以上の方が6%もいらっしゃるとは驚きました。昨年よりもハシゴする方が明らかに増えています。これは「昨年来て良かったので、今年はもっと聴こう。」と思った方が多かったからではないでしょうか。前売段階にてチケットがかなり売り切れていたことにも納得させられます。
Q.これまでクラシックコンサートに何回いらっしゃいましたか
初めて 7.9% (14.66%)
1-2回 21.1% (35.88%)
3-5回 22.7% (26.83%)
6-10回 14.4% (9.98%)
それ以上 16.5% (11.86%)
いわゆるビギナーが多いのも事実ですが、コアなクラシックファンも増えています。モーツァルトでこの結果だとすると、来年(国民学派)はさらにその傾向が強まりそうです。
Q.性別
男性 34.7% (29.02%)
女性 61.6% (68.02%)
昨年より男性客が増えたとは言え、圧倒的に女性客が多くなっています。また、実際に会場を歩いても、一般的なクラシックコンサートと比べてかなり女性が目立っていました。これは、通常のコンサートでは殆ど無視されているファミリー層の存在や、休日の銀座・丸の内という立地特性などが影響しているからだと思います。
Q.年齢
10代 6.9% (5.77%)
20代 12.2% (22.78%)
30代 22.7% (22.78%)
40代 18.9% (17.63%)
50代 18.1% (15.6%)
60代 11.5% (8.11%)
70代 5% (2.81%)
80代 0.2% (0%)
高齢化が進むクラシックコンサートとしては異例なほど、40代以下の若い層が多いようです。ただ気になるのは20代の激減ぶりです。ほぼ半分に減っています。何故でしょうか…。
Q.同伴者
なし 29.3% (15.28%)
家族 47.8% (42.75%)
親戚 1.9% (1.54%)
友人・知人 17.9% (34.72%)
音楽仲間 1.4% (1.85%)
学校 0.1% (0%)
メインはやはりファミリーです。このイベントが、ゴールデンウィーク中の一行楽スポットとして認知されている証拠かと思います。ただし、「友人・知人」が減少し、その一方で「なし」がほぼ倍増していることも見逃せません。やはりコアなファン層が増えているからでしょうか。イベントはイベントらしく皆で楽しむのがピッタリかと…。(と言う私も、一人で出かけたコンサートがありましたが…。)
Q.今後、音楽祭で取り上げて欲しい作曲家があればお書き下さい
バッハ 21.4%
ショパン 13.9%
チャイコフスキー 12%
ブラームス 9.2%
シューベルト 6.3%
ベートーヴェン 4.2%
モーツァルト 3.6%
ドヴォルザーク 2.4%
その他 26.9%
*昨年のベスト10:モーツァルト、ショパン、バッハ、チャイコフスキー、ブラームス、シューベルト、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、ヨハンシュトラウス、マーラー、リスト
やはり抜群の知名度がものを言うのでしょう。バッハが圧倒的な一位の座に輝きました。バッハだけではなく、有りがちな「バロックの調べ」などというテーマで、バロック音楽を一括りにして開催するのも面白いと思います。ちなみに、チャイコフスキーやドヴォルザークは来年のテーマ作曲家です。あちこちで、新世界と、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の冒頭部分が高らかに鳴り響くことが予想されます。それにしても、昨年のアンケートでマーラーが挙がっていたのには驚きました。また、個人的には苦手のショパンが、昨年に続いて二位というのにもその根強い人気を思わせます。当然ながらどうしてもピアノ曲ばかりになってしまうので、他の作曲家と合わせての開催となりそうです。
私がいただいた時にはまだ冊子はたくさん残っていました。ご興味のある方は一度手に取ってみては如何でしょうか。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ショスタコーヴィチイヤー 祝・生誕100周年!
今日9月25日は、旧ソビエトの作曲家で、20世紀最大のシンフォニストでもある、ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906/9/25-1975/8/9)の100歳の誕生日です。モーツァルトの生誕250年を祝っておきながら、このもう一人の偉大な作曲家の生誕に触れないわけにはまいりません。まずはおめでとうございます!

実は昨年までショスタコーヴィチは、私の苦手な作曲家の一人でした。ただこれもメモリアルイヤーの効果(?)でしょうか、今年に入ってようやく、一連の交響曲と弦楽四重奏曲を面白く聴けるようになってきました。それにしても生誕100年だというのに、国内の一般メディアでは殆ど取り上げられていません。次のメモリアルイヤーの時には、それこそ手のひらを返したように「人気沸騰」となっていることを願いたいです。(?!)聴き手が彼に近づくのももうすぐでしょうか。

私はショスタコーヴィチの積極的な聴き手ではないので、自信を持ってと言うほどではないのですが、最近頻繁に聴いているのは、今年ヴェネツィア・レーベルから再発されたコンドラシンの全集です。ナイフの刃先のような鋭利な響きが音楽を凍らせ、また音をミクロにまで濃縮した上で解放したようなアタックが、時に音楽を暴発させるように冴え渡ります。そして生まれた、全く色のない、それでいて背筋が凍るほど恐ろしいショスタコーヴィチの世界。それにしても何故この演奏にかかると、ショスタコーヴィチはこうも乾き、また激しく、そして冷たいのでしょうか。巨大な氷の彫刻が制作されたかと思いきや、それが演奏の過程において粉々に砕け散っていく様を見るかのようです。
お馴染みのgoogleのロゴがそのままでした。これも次回のメモリアルの際にはきっと…。

実は昨年までショスタコーヴィチは、私の苦手な作曲家の一人でした。ただこれもメモリアルイヤーの効果(?)でしょうか、今年に入ってようやく、一連の交響曲と弦楽四重奏曲を面白く聴けるようになってきました。それにしても生誕100年だというのに、国内の一般メディアでは殆ど取り上げられていません。次のメモリアルイヤーの時には、それこそ手のひらを返したように「人気沸騰」となっていることを願いたいです。(?!)聴き手が彼に近づくのももうすぐでしょうか。

私はショスタコーヴィチの積極的な聴き手ではないので、自信を持ってと言うほどではないのですが、最近頻繁に聴いているのは、今年ヴェネツィア・レーベルから再発されたコンドラシンの全集です。ナイフの刃先のような鋭利な響きが音楽を凍らせ、また音をミクロにまで濃縮した上で解放したようなアタックが、時に音楽を暴発させるように冴え渡ります。そして生まれた、全く色のない、それでいて背筋が凍るほど恐ろしいショスタコーヴィチの世界。それにしても何故この演奏にかかると、ショスタコーヴィチはこうも乾き、また激しく、そして冷たいのでしょうか。巨大な氷の彫刻が制作されたかと思いきや、それが演奏の過程において粉々に砕け散っていく様を見るかのようです。
お馴染みのgoogleのロゴがそのままでした。これも次回のメモリアルの際にはきっと…。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「発見、クラシック音楽。」 Esquire(エスクァイア)9月号
これまで殆ど手に取って見たことのない雑誌でしたが、「庭は夏の日ざかり」のSonnenfleckさんのエントリを拝見して買ってみました。一見、クラシック音楽をカジュアルに紹介しているようで、実は随分とマニアックに纏められています。「エスクァイア」の9月号です。700円でした。
 Esquire (エスクァイア)2006年09月号
Esquire (エスクァイア)2006年09月号
まずはアーノンクールのインタビューから特集が始まります。今年の来日の宣伝を兼ねた企画なのかもしれません。いやに畏まった鈴木淳史の文章が、演奏界におけるアーノンクールの地位を手堅く纏めていました。その後はロシアピアニズムからチュルリョーニス(かなりマニアック?画家としても活躍したそうです。)、そして古楽へ。その間に、モーツァルトがお好きだと仰る杉本博司のインタビュー(私は、むしろマイルスがアドリブをやっているようなところが好きです!)や、お手軽なイラストとともに紹介されるバロック作曲家の一覧、または著名作曲家(プッチーニがあってヴェルディがない!これは残念…。)の実にオーソドックスな推薦CD(フルヴェンの第9から、藤井一興の武満ピアノ集まで。)などの記事が挟まれていました。また古楽では、ナイーブなどのレーベルも丁寧に紹介されています。ともかく、あれもこれもとでも言うようなごった煮状態です。(良い意味で。)全く焦点を絞らない構成がかえって新鮮なのかもしれません。時にかなりマニア路線へ傾きながらも、専門誌に有りがちな近寄り難い雰囲気がない。マニア心をオシャレな感覚で包み込んでくれました。
ごった煮と言うことで、最後にはクラシックの花形でもあるオペラが紹介されています。美しい写真とともに紹介されるグラインドボーン(見ているだけでくつろげる?)の他に、ワーグナーはパルジファルから聞くべしと宣う黒田恭一氏の記事、そして先日、新国立劇場にて鮮烈な「ティート」を見てくれたコンヴィチュニーのインタビューなどが掲載されていました。そして最後に忘れてはならないのが付録のCDです。ここではそれまでのごった煮状態が鳴りを潜め、「ALPHA」の専門的なセンスの良さが光っています。いつもあまりにも長く、もしくはあまりにもてんでバラバラな選曲なので聞き通すのが疲れてしまうレコ芸の付録CDよりは魅力的です。CDの欲しくなるようなサンプラー。これはとっておこうかと思います。
一体どのような方を想定して記事を纏めたのかが非常に謎めいていますが、価格を鑑みれば十分に楽しめると思います。ちなみにロシアピアニズムについては全く知りませんでした。これからじっくり読んでみたいです。
 Esquire (エスクァイア)2006年09月号
Esquire (エスクァイア)2006年09月号まずはアーノンクールのインタビューから特集が始まります。今年の来日の宣伝を兼ねた企画なのかもしれません。いやに畏まった鈴木淳史の文章が、演奏界におけるアーノンクールの地位を手堅く纏めていました。その後はロシアピアニズムからチュルリョーニス(かなりマニアック?画家としても活躍したそうです。)、そして古楽へ。その間に、モーツァルトがお好きだと仰る杉本博司のインタビュー(私は、むしろマイルスがアドリブをやっているようなところが好きです!)や、お手軽なイラストとともに紹介されるバロック作曲家の一覧、または著名作曲家(プッチーニがあってヴェルディがない!これは残念…。)の実にオーソドックスな推薦CD(フルヴェンの第9から、藤井一興の武満ピアノ集まで。)などの記事が挟まれていました。また古楽では、ナイーブなどのレーベルも丁寧に紹介されています。ともかく、あれもこれもとでも言うようなごった煮状態です。(良い意味で。)全く焦点を絞らない構成がかえって新鮮なのかもしれません。時にかなりマニア路線へ傾きながらも、専門誌に有りがちな近寄り難い雰囲気がない。マニア心をオシャレな感覚で包み込んでくれました。
ごった煮と言うことで、最後にはクラシックの花形でもあるオペラが紹介されています。美しい写真とともに紹介されるグラインドボーン(見ているだけでくつろげる?)の他に、ワーグナーはパルジファルから聞くべしと宣う黒田恭一氏の記事、そして先日、新国立劇場にて鮮烈な「ティート」を見てくれたコンヴィチュニーのインタビューなどが掲載されていました。そして最後に忘れてはならないのが付録のCDです。ここではそれまでのごった煮状態が鳴りを潜め、「ALPHA」の専門的なセンスの良さが光っています。いつもあまりにも長く、もしくはあまりにもてんでバラバラな選曲なので聞き通すのが疲れてしまうレコ芸の付録CDよりは魅力的です。CDの欲しくなるようなサンプラー。これはとっておこうかと思います。
一体どのような方を想定して記事を纏めたのかが非常に謎めいていますが、価格を鑑みれば十分に楽しめると思います。ちなみにロシアピアニズムについては全く知りませんでした。これからじっくり読んでみたいです。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
ネットラジオで聴くバイロイトとザルツブルク音楽祭 2006
いよいよ明後日からバイロイト音楽祭が始まりますが、今年も昨年に引き続きインターネットラジオの生放送があるようです。一部タイムシフトの中継があるとのことですが、音質良好なBartokRadioでまた楽しみたいと思います。


昨年ダウンロードしたバイロイト音楽祭の録音もまだ全てしっかりと耳を通せていません。と言うことで、今年も全部聴けるかどうか分からないのですが、やはりティーレマンの「リング」に一番注目してみたいと思います。私としては今ひとつ良く分からない指揮者の一人なのですが、ここはじっくりと聴いてみるつもりです。
ちなみにインターネットラジオでは、メモリアルイヤーで盛り上がりそうなザルツブルク音楽祭も楽しむことが出来ます。ここで指揮するのが今回で最後ともいうアーノンクールの「フィガロ」で開幕し、その後は初期のオペラまで網羅したスケジュールが怒濤のように続くようです。こちらもBartokRadioが公演のほぼ全てをカバーしています。読響でもお馴染みのホーネックの「コジ」や、強烈なテンポ感を楽しませてくれそうなハーディングの「ドン・ジョバンニ」、さらには秋に来日もあるノリントンの「イドメネオ」から、ミンコフスキの「ポントの王ミドリダーテ」、そして大御所ムーティの「魔笛」など、さすがに聞き所も満載です。これは前もってハードディスクの整理(?)をして、余裕をもって備えておかなくてはなりません。
ネットラジオの放送スケジュール等については、ブログ「オペラキャスト」様の情報がいつもながら群を抜いています。詳細はそちらをご参照下さい。


昨年ダウンロードしたバイロイト音楽祭の録音もまだ全てしっかりと耳を通せていません。と言うことで、今年も全部聴けるかどうか分からないのですが、やはりティーレマンの「リング」に一番注目してみたいと思います。私としては今ひとつ良く分からない指揮者の一人なのですが、ここはじっくりと聴いてみるつもりです。
ちなみにインターネットラジオでは、メモリアルイヤーで盛り上がりそうなザルツブルク音楽祭も楽しむことが出来ます。ここで指揮するのが今回で最後ともいうアーノンクールの「フィガロ」で開幕し、その後は初期のオペラまで網羅したスケジュールが怒濤のように続くようです。こちらもBartokRadioが公演のほぼ全てをカバーしています。読響でもお馴染みのホーネックの「コジ」や、強烈なテンポ感を楽しませてくれそうなハーディングの「ドン・ジョバンニ」、さらには秋に来日もあるノリントンの「イドメネオ」から、ミンコフスキの「ポントの王ミドリダーテ」、そして大御所ムーティの「魔笛」など、さすがに聞き所も満載です。これは前もってハードディスクの整理(?)をして、余裕をもって備えておかなくてはなりません。
ネットラジオの放送スケジュール等については、ブログ「オペラキャスト」様の情報がいつもながら群を抜いています。詳細はそちらをご参照下さい。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
モーツァルトの妻、コンスタンツェの写真が発見される
モーツァルトの未亡人の写真を発見=ドイツ(yahoo)


モーツァルトの妻、コンスタンツェの写真がドイツで発見されたそうです。もちろん撮影されたのは、モーツァルトの死後から約半世紀ほど経過した1840年。彼女と親交のあった作曲家ケラーの自宅での一コマだそうです。この時のコンスタンツェは既に78歳。(ちなみに彼女が亡くなるのはこの2年後です。)どうでしょうか。肖像画と見比べて見るのもまた一興です。(「悪妻」から「良妻」への変化が読み取れる?!)
写真へのリンク。(前列左からコンスタンツェ、ケラー、ケラー夫人だそうです。)


モーツァルトの妻、コンスタンツェの写真がドイツで発見されたそうです。もちろん撮影されたのは、モーツァルトの死後から約半世紀ほど経過した1840年。彼女と親交のあった作曲家ケラーの自宅での一コマだそうです。この時のコンスタンツェは既に78歳。(ちなみに彼女が亡くなるのはこの2年後です。)どうでしょうか。肖像画と見比べて見るのもまた一興です。(「悪妻」から「良妻」への変化が読み取れる?!)
写真へのリンク。(前列左からコンスタンツェ、ケラー、ケラー夫人だそうです。)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
NHK-FMは存続へ
一連のNHK「改革」にて、先日当然打ち出されたNHK-FMの廃止話ですが、どうやら見送られる方向が強まったようです。NHKのFM放送は、最近、縮小傾向にあったにしろ、唯一、クラシック音楽を身近に楽しめる媒体でした。もちろんNHKを全面的に応援するつもりはありませんが、こればかりはまず一安心とでも言ったところかもしれません。
NHKのFMラジオ削減盛り込まず 政府・与党合意(asahi.com)
WEBの時代を迎えたとは言え、依然として既存のメディアが大きな力を持っています。それと同様に、インターネットラジオが普及しつつあるにしろ、まだFM放送で聴くクラシック音楽の味わいは失われていません。大上段に構えて申し上げれば、政府の狙いはただ一つ、受信料不払いへの罰則導入にあるのでしょう。FMやBSの削減を打ち出した例の懇談会の答申も、そのごく一部が実現されてひとまず終りと言うことになるのではないでしょうか。ともかくNHKは貴重な音源をいくつも抱えています。この合意に安心しきることなく、ネット放送を使った試みなど、さらなるクラシック音楽の財産を生かした取り組みをしていただきたいものです。
NHKのFMラジオ削減盛り込まず 政府・与党合意(asahi.com)
WEBの時代を迎えたとは言え、依然として既存のメディアが大きな力を持っています。それと同様に、インターネットラジオが普及しつつあるにしろ、まだFM放送で聴くクラシック音楽の味わいは失われていません。大上段に構えて申し上げれば、政府の狙いはただ一つ、受信料不払いへの罰則導入にあるのでしょう。FMやBSの削減を打ち出した例の懇談会の答申も、そのごく一部が実現されてひとまず終りと言うことになるのではないでしょうか。ともかくNHKは貴重な音源をいくつも抱えています。この合意に安心しきることなく、ネット放送を使った試みなど、さらなるクラシック音楽の財産を生かした取り組みをしていただきたいものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
東京フィルが公式ブログを開設!
ありそうでなかったプロオーケストラの公式ブログですが、先日、東京フィルハーモニー交響楽団が「オーケストラをゆく」というブログをスタートさせました。おそらく在京プロオーケストラでは初めての試みではないでしょうか。(間違っていたら申し訳ありません。)「普段は見れないオーケストラの裏側、たっぷりとお見せします。」とのことで、ライターには楽団員の方々も予定されているそうです。既に数多くある奏者の方のブログとはまたひと味違った方向性。これはなかなか楽しみです。
「オーケストラをゆく」(東京フィルハーモニー交響楽団公式ブログ)
最近は音楽だけに限らず、一企業や公的機関がブログで情報発信することが増えています。美術館でも、あまり更新されていないとは言え横浜美術館が展覧会情報をブログで公開(「イサムズ・ウィークリー 担当学芸員とボランティアのブログ」)していました。また、東博の若冲展に先駆けたブログ(「若冲と江戸絵画展コレクションブログ」)なども有名なところです。東フィルのブログにも注意書きがあるように、TBや、特にコメントの取り扱いが難しいところではありますが、初めから一定のルールを決めておけばそう問題もないでしょう。聴き手それぞれのコンサートの感想が、TBによってダイレクトにオーケストラへ繋がる可能性もあります。(東京シティ・フィルのBBSも一つの手段かもしれません。ここは丁寧に運営されています。)
この東フィルの試み、他のオーケストラへも広がると嬉しいところです。しばらくチェックしていきたいと思います。
「オーケストラをゆく」(東京フィルハーモニー交響楽団公式ブログ)
最近は音楽だけに限らず、一企業や公的機関がブログで情報発信することが増えています。美術館でも、あまり更新されていないとは言え横浜美術館が展覧会情報をブログで公開(「イサムズ・ウィークリー 担当学芸員とボランティアのブログ」)していました。また、東博の若冲展に先駆けたブログ(「若冲と江戸絵画展コレクションブログ」)なども有名なところです。東フィルのブログにも注意書きがあるように、TBや、特にコメントの取り扱いが難しいところではありますが、初めから一定のルールを決めておけばそう問題もないでしょう。聴き手それぞれのコンサートの感想が、TBによってダイレクトにオーケストラへ繋がる可能性もあります。(東京シティ・フィルのBBSも一つの手段かもしれません。ここは丁寧に運営されています。)
この東フィルの試み、他のオーケストラへも広がると嬉しいところです。しばらくチェックしていきたいと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
今週の「ベストオブクラシック」はショスタコーヴィチ・ウィーク!
今週のNHK-FMベストオブクラシックは、生誕100年(没後30年)を迎えたメモリアルイヤーのショスタコーヴィチが特集されます。お馴染みのシンフォニーや弦楽四重奏曲だけではなく、あまり聞き慣れない曲までがカバーされたプログラムです。なかなか魅力的です。(私の苦手な指揮者がチラホラといらっしゃるのはさておいて…。)
ベストオブクラシック ショスタコーヴィチ・ウィーク(19:30-21:10)
19日(月)
交響曲第1番 作品10 マリインスキー劇場管弦楽団/ワレリー・ゲルギエフ
弦楽四重奏曲第4番 作品83 エマーソン弦楽四重奏団
アレクサンドル・ブロークの7つの詩 作品127 ランディ・ステネ/トリオ・コン・ブリオ
20日(火)
チェロ協奏曲第1番 作品107 グザヴィエ・フィリップス/ロシア・ナショナル・フィルハーモニック/ウラディーミル・スピヴァコフ
交響曲第4番 作品43 フランス国立管弦楽団/ウラディーミル・アシュケナージ
21日(水)
タヒチ・トロット 作品16 アイスランド交響楽団/ラモン・ガンバ
ピアノ五重奏曲 作品57 ドミニク・モレル/ルノアール四重奏団
交響曲第5番 作品47 バイエルン放送交響楽団/マリス・ヤンソンス
22日(木)
「バラエティ・オーケストラのための組曲」から アイスランド交響楽団/ラモン・ガンバ
交響曲第7番「レニングラード」 作品60 フランス国立管弦楽団/クルト・マズア
23日(金)
交響詩「十月」 作品131 フランクフルト放送交響楽団/ヒュー・ウルフ
バイオリン協奏曲第2番 作品129 ジャニーヌ・ヤンセン/スウェーデン放送交響楽団/アンドレス・オロスコ・エストラーダ
交響曲第12番「1917年」 作品112 スウェーデン放送交響楽団/ダーヴィッド・ビェルクマン
総務省による例の懇親会の一件で何やら急に雲行きが怪しくなってきたNHK-FMですが、ここは素直に楽しみたいところです。常にタイムリーにとはいきません。録音などして聴いていきたいと思います。
ベストオブクラシック ショスタコーヴィチ・ウィーク(19:30-21:10)
19日(月)
交響曲第1番 作品10 マリインスキー劇場管弦楽団/ワレリー・ゲルギエフ
弦楽四重奏曲第4番 作品83 エマーソン弦楽四重奏団
アレクサンドル・ブロークの7つの詩 作品127 ランディ・ステネ/トリオ・コン・ブリオ
20日(火)
チェロ協奏曲第1番 作品107 グザヴィエ・フィリップス/ロシア・ナショナル・フィルハーモニック/ウラディーミル・スピヴァコフ
交響曲第4番 作品43 フランス国立管弦楽団/ウラディーミル・アシュケナージ
21日(水)
タヒチ・トロット 作品16 アイスランド交響楽団/ラモン・ガンバ
ピアノ五重奏曲 作品57 ドミニク・モレル/ルノアール四重奏団
交響曲第5番 作品47 バイエルン放送交響楽団/マリス・ヤンソンス
22日(木)
「バラエティ・オーケストラのための組曲」から アイスランド交響楽団/ラモン・ガンバ
交響曲第7番「レニングラード」 作品60 フランス国立管弦楽団/クルト・マズア
23日(金)
交響詩「十月」 作品131 フランクフルト放送交響楽団/ヒュー・ウルフ
バイオリン協奏曲第2番 作品129 ジャニーヌ・ヤンセン/スウェーデン放送交響楽団/アンドレス・オロスコ・エストラーダ
交響曲第12番「1917年」 作品112 スウェーデン放送交響楽団/ダーヴィッド・ビェルクマン
総務省による例の懇親会の一件で何やら急に雲行きが怪しくなってきたNHK-FMですが、ここは素直に楽しみたいところです。常にタイムリーにとはいきません。録音などして聴いていきたいと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
岩城宏之さんが死去
リゲティ死去のニュースを耳にしたばかりだと言うのに、また信じられない訃報が飛び込んできました。指揮者の岩城宏之さんが亡くなられたそうです。73歳。あまりにも早過ぎます。

指揮者・岩城宏之氏が死去(YOMIURI ONLINE)
指揮者・岩城さんの死、音楽界から悼む声相次ぐ(YOMIURI ONLINE)
何度も病魔克服、岩城宏之さんの“棒ふり人生”に幕(YOMIURI ONLINE)
岩城宏之さん:亡くなる3日前まで、ベートーベンを勉強(mainichi-msn)
指揮者の岩城宏之さん死去 エッセーでも活躍(asahi.com)
岩城宏之氏、最後まで妥協せず 70歳超え“振る”マラソン(Sankei Web)
訃報 指揮者の岩城宏之氏死去(ぶらあぼ)
あれだけご活躍なさっていた方なのに、残念ながら一度も実演に接することが出来ませんでした。私にとっての岩城さんとは、やはりテレビなどで幅広く活躍されるというマルチな方です。ベートーヴェンの交響曲を一日で演奏するというような話題性抜群の企画を立ち上げながら、その一方では長年に渡り日本の現代音楽の発展に尽力されていた。こんなに多彩な活動を見せていた指揮者は他に思いつきません。あまりにも大きな方を亡くしてしまいました。

実演を聴けなかったのが自分で悔しいとすら思います。本当に無念です。ご冥福をお祈り致します。

指揮者・岩城宏之氏が死去(YOMIURI ONLINE)
指揮者・岩城さんの死、音楽界から悼む声相次ぐ(YOMIURI ONLINE)
何度も病魔克服、岩城宏之さんの“棒ふり人生”に幕(YOMIURI ONLINE)
岩城宏之さん:亡くなる3日前まで、ベートーベンを勉強(mainichi-msn)
指揮者の岩城宏之さん死去 エッセーでも活躍(asahi.com)
岩城宏之氏、最後まで妥協せず 70歳超え“振る”マラソン(Sankei Web)
訃報 指揮者の岩城宏之氏死去(ぶらあぼ)
あれだけご活躍なさっていた方なのに、残念ながら一度も実演に接することが出来ませんでした。私にとっての岩城さんとは、やはりテレビなどで幅広く活躍されるというマルチな方です。ベートーヴェンの交響曲を一日で演奏するというような話題性抜群の企画を立ち上げながら、その一方では長年に渡り日本の現代音楽の発展に尽力されていた。こんなに多彩な活動を見せていた指揮者は他に思いつきません。あまりにも大きな方を亡くしてしまいました。

実演を聴けなかったのが自分で悔しいとすら思います。本当に無念です。ご冥福をお祈り致します。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
ジェルジ・リゲティ氏が死去
ハンガリー生まれの現代音楽作曲家、ジェルジ・リゲティ氏が亡くなられました。83歳だったそうです。
現代作曲家、ジェルジ・リゲティさん死去(asahi.com)
作曲家のジェルジ・リゲティ氏が死去 第3回世界文化賞受賞(Sankei Web)
追悼のエントリを書けるほど氏の音楽を聴き込んでいないのですが、リゲティと言えば、やはりキューブリックの「2001年宇宙の旅」の挿入音楽が挙げられると思います。私も子供心にこの映画を見て、初めてかの曲を耳にした時、まずこれが「音楽」だということに驚かされるとともに、背筋が凍るような恐怖感を感じました。リゲティはいわゆる「前衛」の中でも、忘れ去られることなく後世に残る作曲家です。今後は、一般的なコンサートでも頻繁に取り上げられることを願いたいです。

リゲティのCDは、ワーナーから発売されたシリーズくらいしか聴いたことがありません。ヴァイオリン協奏曲などは比較的素直に聴けます。これを機会に再度、リゲティの研ぎすまされ、そして凝縮された濃密な音楽に耳を傾けたいものです。
ご冥福をお祈りします。
現代作曲家、ジェルジ・リゲティさん死去(asahi.com)
作曲家のジェルジ・リゲティ氏が死去 第3回世界文化賞受賞(Sankei Web)
追悼のエントリを書けるほど氏の音楽を聴き込んでいないのですが、リゲティと言えば、やはりキューブリックの「2001年宇宙の旅」の挿入音楽が挙げられると思います。私も子供心にこの映画を見て、初めてかの曲を耳にした時、まずこれが「音楽」だということに驚かされるとともに、背筋が凍るような恐怖感を感じました。リゲティはいわゆる「前衛」の中でも、忘れ去られることなく後世に残る作曲家です。今後は、一般的なコンサートでも頻繁に取り上げられることを願いたいです。

リゲティのCDは、ワーナーから発売されたシリーズくらいしか聴いたことがありません。ヴァイオリン協奏曲などは比較的素直に聴けます。これを機会に再度、リゲティの研ぎすまされ、そして凝縮された濃密な音楽に耳を傾けたいものです。
ご冥福をお祈りします。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「目白バ・ロック音楽祭」 いよいよ開幕まであと10日!
「翠松庵no散歩道」のるるさんに教えていただけるまで全く知らなかったので、私がここで偉そうに紹介するのもおこがましいのですが、初夏の目白を飾る音楽の祭典「目白バ・ロック音楽祭」が、いよいよ来月2日から始まります。私も一公演だけ予定していますが、未知の音楽祭なのでとても楽しみです。(17日に目白聖公会で行われる、寺神戸亮のチェロ組曲を聴く予定です。)
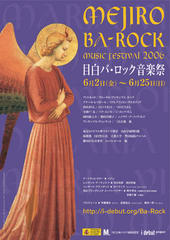
東京の音楽祭と言えば、このブログでもしつこく追っかけた「熱狂の日」がすぐに思い当たります。ゴールデンウィークの東京都心にて怒濤のように繰り広げられた巨大な祭典。その抜群の企画力や集客力は、二回目でありながら、既にクラシックコンサートを超えた大イベントとして認められたところです。そしてこの「目白バ・ロック音楽祭」も、昨年に引き続いての二度目の開催。テーマはもちろんバロック音楽です。喧噪と賑わいに包まれた「熱狂の日」とは逆に、目白の静寂に囲まれた控えめな音楽祭のイメージがわいてきます。小さくともキラリと光るような音楽祭かもしれません。


会期は6月2日から25日までの約一ヶ月間です。予定されているコンサートは約15。二、三日に一度のペースでバロック音楽が高らかに鳴り渡ります。そしてこの音楽祭の最大の特徴は、おそらくその会場にあるでしょう。単なるコンサートホールで音楽を演奏することにとどまらない、目白界隈の多くの由緒ある施設を取り込んだ企画。その一例として、東京カテドラル聖マリア大聖堂(丹下建築の名作としても有名です。)や目白聖公会、または自由学園明日館などを挙げれば十分です。まさに趣きある目白の風を感じとれるような、街歩きの醍醐味すら味わえる音楽の祭典。バロック音楽の似合う街目白。そんなキャッチセールスすら聞こえてくるような音楽祭です。
チケット価格も3000円から5000円前後と、一般的なコンサートよりは若干抑えられています。無知な私は参加アーティストの方をあまり存じ上げないので、おすすめのコンサートなどを無責任に書くことは出来ませんが、まずは建物見たさに、さらには目白の雰囲気を楽しむために、気軽に参加してみるのも良いと思います。また目白界隈では、商店街による各種イベントもあるとのことです。地元が一つとなった手作り感のある音楽祭。住民の方がこのイベントにかける思いも伝わってきます。初夏の東京の暑さを和らげる涼し気なバロックの調べ。それをまず目白にて楽しむのは如何でしょうか。
集客を第一にしたイベントではないようです。各会場の定員はかなり少なくなっています。まずはチケットの残席を確認されることをおすすめします。
関連リンク
目白バ・ロック音楽祭公式サイト
ブログ「目白バ・ロック音楽祭」
ぴあによるチケット残席情報(主催のアルケミスタへ問い合わせるのも確実です。)
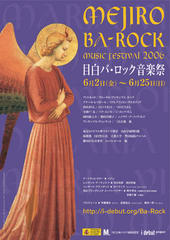
東京の音楽祭と言えば、このブログでもしつこく追っかけた「熱狂の日」がすぐに思い当たります。ゴールデンウィークの東京都心にて怒濤のように繰り広げられた巨大な祭典。その抜群の企画力や集客力は、二回目でありながら、既にクラシックコンサートを超えた大イベントとして認められたところです。そしてこの「目白バ・ロック音楽祭」も、昨年に引き続いての二度目の開催。テーマはもちろんバロック音楽です。喧噪と賑わいに包まれた「熱狂の日」とは逆に、目白の静寂に囲まれた控えめな音楽祭のイメージがわいてきます。小さくともキラリと光るような音楽祭かもしれません。


会期は6月2日から25日までの約一ヶ月間です。予定されているコンサートは約15。二、三日に一度のペースでバロック音楽が高らかに鳴り渡ります。そしてこの音楽祭の最大の特徴は、おそらくその会場にあるでしょう。単なるコンサートホールで音楽を演奏することにとどまらない、目白界隈の多くの由緒ある施設を取り込んだ企画。その一例として、東京カテドラル聖マリア大聖堂(丹下建築の名作としても有名です。)や目白聖公会、または自由学園明日館などを挙げれば十分です。まさに趣きある目白の風を感じとれるような、街歩きの醍醐味すら味わえる音楽の祭典。バロック音楽の似合う街目白。そんなキャッチセールスすら聞こえてくるような音楽祭です。
チケット価格も3000円から5000円前後と、一般的なコンサートよりは若干抑えられています。無知な私は参加アーティストの方をあまり存じ上げないので、おすすめのコンサートなどを無責任に書くことは出来ませんが、まずは建物見たさに、さらには目白の雰囲気を楽しむために、気軽に参加してみるのも良いと思います。また目白界隈では、商店街による各種イベントもあるとのことです。地元が一つとなった手作り感のある音楽祭。住民の方がこのイベントにかける思いも伝わってきます。初夏の東京の暑さを和らげる涼し気なバロックの調べ。それをまず目白にて楽しむのは如何でしょうか。
集客を第一にしたイベントではないようです。各会場の定員はかなり少なくなっています。まずはチケットの残席を確認されることをおすすめします。
関連リンク
目白バ・ロック音楽祭公式サイト
ブログ「目白バ・ロック音楽祭」
ぴあによるチケット残席情報(主催のアルケミスタへ問い合わせるのも確実です。)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
スマートなゲルギエフ
NHK-FM ベストオブクラシック(5/11 19:30~)
曲 モーツァルト ピアノ協奏曲第20番K.466
ショスタコーヴィチ 交響曲第9番作品70
指揮 ワレリー・ゲルギエフ
演奏 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ピアノ マルクス・シルマー
収録:オーストリア・ウィーン学友協会 2006/4/23
久々にベストオブクラシックへ耳を傾けてみました。(時間の関係で2曲目のモーツァルトからです。)ゲルギエフとウィーンフィルという豪華なコンビによるモーツァルトのピアノ協奏曲と、ショスタコーヴィチの第9交響曲です。メモリアルイヤー同士の組み合わせでした。
ピアノ協奏曲は終始落ち着いた演奏です。ゲルギエフというと、どこか殺伐とした音作りをするイメージがあるのですが、その表情はここには見られません。中庸のテンポで、オーケストラを少しだけ煽り立てながらキビキビと音楽を進めていく。上昇音型での控えめなクレッシェンドは爽快です。それにヴァイオリンを所々浮き上がらせて、(第1楽章の終結部など。)音楽に厚みを持たせるのも印象的でした。また、第2楽章などの伸びやかなリズム感などは、ゲルギエフと言うよりも、ウィーンフィル自体の美感によるものかもしれません。特に木管楽器とピアノが絡み合う中間部での美しさは見事でした。あくまでも穏やかです。
マルクス・シルマーのピアノはまるでフォルテピアノのようでした。ピアノをあまり強く鳴らさずに、淡々と音楽を奏でていく。ただしカデンツァでの力の入れようだけは別です。彼の自作のカデンツァはあまり良いものに聴こえませんでしたが、その部分だけは何かが取り憑いたようにガンガン鳴らしていました。これには非常に違和感を感じます。
ショスタコーヴィチの第9交響曲は、その成立過程などからして何やらきな臭いものが感じられますが、純粋に音楽だけへ耳を傾ければ、これほど楽しめる曲もなかなかありません。気味が悪いほどに明るい第1楽章も、ゲルギエフはストレートに音を鳴らしていきます。続いての第2楽章ではやや腰を落として丁寧に表現していたでしょうか。ただ、そこに暗鬱な響きはありません。沈着でありながらも情緒的にならない、冷ややかな姿勢を感じます。また木管主導の旋律などは素直に牧歌的でした。随分とストレートに音楽を作ります。

第3楽章のスケルツォでは音楽が全く熱くなりません。もちろんリズミカルに音楽を進めていくのですが、途中出てくる印象的な金管のファンファーレもやや抑制的。この辺の処理は、殺伐としたゲルギエフのイメージにやや近いかもしれません。それに続く木管のソロもすこぶる沈着でした。
第5楽章はやや大人し過ぎたかもしれません。スピード感は抜群ですが、私としてはもっとハメを外して、この音楽の不気味な盛り上がりを聴かせて欲しかったと思います。どうもスマートにまとまってしまって、諧謔的な泥臭い部分が聴こえてきません。これは物足りない。辛口な感想になってしまいました…。

ゲルギエフはショスタコーヴィチの録音を積極的にリリースしています。それらはまさに新時代の名盤なのかもしれませんが、私にとってのショスタコーヴィチとは昔からコンドラシン。ずっと苦手だったショスタコーヴィチの音楽を、初めて楽しんで聴くことが出来た録音です。先日も全集が輸入盤にて発売されましたが、やはり何度聴いても飽きません。ゲルギエフの録音はどうなのでしょうか。また機会があれば聴いてみたいと思います。
曲 モーツァルト ピアノ協奏曲第20番K.466
ショスタコーヴィチ 交響曲第9番作品70
指揮 ワレリー・ゲルギエフ
演奏 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ピアノ マルクス・シルマー
収録:オーストリア・ウィーン学友協会 2006/4/23
久々にベストオブクラシックへ耳を傾けてみました。(時間の関係で2曲目のモーツァルトからです。)ゲルギエフとウィーンフィルという豪華なコンビによるモーツァルトのピアノ協奏曲と、ショスタコーヴィチの第9交響曲です。メモリアルイヤー同士の組み合わせでした。
ピアノ協奏曲は終始落ち着いた演奏です。ゲルギエフというと、どこか殺伐とした音作りをするイメージがあるのですが、その表情はここには見られません。中庸のテンポで、オーケストラを少しだけ煽り立てながらキビキビと音楽を進めていく。上昇音型での控えめなクレッシェンドは爽快です。それにヴァイオリンを所々浮き上がらせて、(第1楽章の終結部など。)音楽に厚みを持たせるのも印象的でした。また、第2楽章などの伸びやかなリズム感などは、ゲルギエフと言うよりも、ウィーンフィル自体の美感によるものかもしれません。特に木管楽器とピアノが絡み合う中間部での美しさは見事でした。あくまでも穏やかです。
マルクス・シルマーのピアノはまるでフォルテピアノのようでした。ピアノをあまり強く鳴らさずに、淡々と音楽を奏でていく。ただしカデンツァでの力の入れようだけは別です。彼の自作のカデンツァはあまり良いものに聴こえませんでしたが、その部分だけは何かが取り憑いたようにガンガン鳴らしていました。これには非常に違和感を感じます。
ショスタコーヴィチの第9交響曲は、その成立過程などからして何やらきな臭いものが感じられますが、純粋に音楽だけへ耳を傾ければ、これほど楽しめる曲もなかなかありません。気味が悪いほどに明るい第1楽章も、ゲルギエフはストレートに音を鳴らしていきます。続いての第2楽章ではやや腰を落として丁寧に表現していたでしょうか。ただ、そこに暗鬱な響きはありません。沈着でありながらも情緒的にならない、冷ややかな姿勢を感じます。また木管主導の旋律などは素直に牧歌的でした。随分とストレートに音楽を作ります。

第3楽章のスケルツォでは音楽が全く熱くなりません。もちろんリズミカルに音楽を進めていくのですが、途中出てくる印象的な金管のファンファーレもやや抑制的。この辺の処理は、殺伐としたゲルギエフのイメージにやや近いかもしれません。それに続く木管のソロもすこぶる沈着でした。
第5楽章はやや大人し過ぎたかもしれません。スピード感は抜群ですが、私としてはもっとハメを外して、この音楽の不気味な盛り上がりを聴かせて欲しかったと思います。どうもスマートにまとまってしまって、諧謔的な泥臭い部分が聴こえてきません。これは物足りない。辛口な感想になってしまいました…。

ゲルギエフはショスタコーヴィチの録音を積極的にリリースしています。それらはまさに新時代の名盤なのかもしれませんが、私にとってのショスタコーヴィチとは昔からコンドラシン。ずっと苦手だったショスタコーヴィチの音楽を、初めて楽しんで聴くことが出来た録音です。先日も全集が輸入盤にて発売されましたが、やはり何度聴いても飽きません。ゲルギエフの録音はどうなのでしょうか。また機会があれば聴いてみたいと思います。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「熱狂の日音楽祭2006」閉幕!
「熱狂の日」音楽祭閉幕、チケット売り上げ16万枚(yomiuri on-line)
東京・有楽町の東京国際フォーラムで3日から開かれていたクラシック音楽の祭典「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン『熱狂の日』音楽祭2006」(東京国際フォーラム主催、読売新聞社特別協力)が6日、大盛況のうちに閉幕した。
有楽町から丸の内界隈に人の波を築いた「熱狂の日音楽祭2006」。私は集中して音楽を聴くことがあまり出来ない性質なもので、初めは2公演だけを予定していましたが、「ノイマンが良い!」との評判を聞き、急遽最終日の「ノイマン+コレギウム・カルトゥシアヌム」を追加して聴いてきました。結局3公演です。
5/5 13:00(B7) ベルリン古楽アカデミー 「ディヴェルティメント」K.137など
5/5 16:30(C) コルボ・ローザンヌ声楽アンサンブル 「レクイエム」
5/6 19:15(A) ノイマン・ケルン室内合唱団 「ヴェスペレ」K.339など
まだ感想を一つも挙げておりません…。(無精者です。)拙いですが追々アップしていきたいと思います。(P.S アップしました。5/11)
ともかく今回の音楽祭は、事前認知度が高かったせいか、前売段階にてチケットがかなりはけてしまいました。ただ、その分(と言っては問題かもしれませんが)、昨年見られたようなチケットブースでの混乱などは皆無で、会場全体もかなりスムーズに流れていたかと思います。また、全体来場者もチケット販売枚数も昨年を大きく上回ったそうです。これは「大成功」でしょう。
さて、早くも来年についてのアナウンスが出ています。それによるとテーマは「国民学派」。おそらくこの名称は、イベントにしては硬派過ぎるので変わると思いますが、チャイコフスキーやドヴォルザーク、またはグリーグからシベリウス、それにバルトークやドビュッシー、ラヴェルなどの名前が怒濤のように挙がっています。何やら選り取りみどりの状態で、聴く方も大変になってしまいそうですが、個人的には大好きなシベリウスに期待したいです。純度の高いアンサンブルにてシンフォニーをまとめて聴ければとも思いました。(もちろん出来ればCホールで…。)
ベートーヴェン、モーツァルトとビックネームが続いて、一気に東京のゴールデンウィークの一大イベントとして認知された「熱狂の日音楽祭」。来年も楽しみです。
*会場にて、こもへじさん(ブログ『10億人が楽しめる手描き文字絵』)にいただいたモーツァルトの可愛い文字絵カードです。


*関連エントリ
「熱狂の日」の展覧会?! 「モーツァルト展」(5/6)
モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 「熱狂の日音楽祭2006」(5/5)
「熱狂の日音楽祭」のあとは「ぶらあぼ」で!(5/4)
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006」、ついに開幕!(4/30)
東京・有楽町の東京国際フォーラムで3日から開かれていたクラシック音楽の祭典「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン『熱狂の日』音楽祭2006」(東京国際フォーラム主催、読売新聞社特別協力)が6日、大盛況のうちに閉幕した。
有楽町から丸の内界隈に人の波を築いた「熱狂の日音楽祭2006」。私は集中して音楽を聴くことがあまり出来ない性質なもので、初めは2公演だけを予定していましたが、「ノイマンが良い!」との評判を聞き、急遽最終日の「ノイマン+コレギウム・カルトゥシアヌム」を追加して聴いてきました。結局3公演です。
5/5 13:00(B7) ベルリン古楽アカデミー 「ディヴェルティメント」K.137など
5/5 16:30(C) コルボ・ローザンヌ声楽アンサンブル 「レクイエム」
5/6 19:15(A) ノイマン・ケルン室内合唱団 「ヴェスペレ」K.339など
まだ感想を一つも挙げておりません…。(無精者です。)拙いですが追々アップしていきたいと思います。(P.S アップしました。5/11)
ともかく今回の音楽祭は、事前認知度が高かったせいか、前売段階にてチケットがかなりはけてしまいました。ただ、その分(と言っては問題かもしれませんが)、昨年見られたようなチケットブースでの混乱などは皆無で、会場全体もかなりスムーズに流れていたかと思います。また、全体来場者もチケット販売枚数も昨年を大きく上回ったそうです。これは「大成功」でしょう。
さて、早くも来年についてのアナウンスが出ています。それによるとテーマは「国民学派」。おそらくこの名称は、イベントにしては硬派過ぎるので変わると思いますが、チャイコフスキーやドヴォルザーク、またはグリーグからシベリウス、それにバルトークやドビュッシー、ラヴェルなどの名前が怒濤のように挙がっています。何やら選り取りみどりの状態で、聴く方も大変になってしまいそうですが、個人的には大好きなシベリウスに期待したいです。純度の高いアンサンブルにてシンフォニーをまとめて聴ければとも思いました。(もちろん出来ればCホールで…。)
ベートーヴェン、モーツァルトとビックネームが続いて、一気に東京のゴールデンウィークの一大イベントとして認知された「熱狂の日音楽祭」。来年も楽しみです。
*会場にて、こもへじさん(ブログ『10億人が楽しめる手描き文字絵』)にいただいたモーツァルトの可愛い文字絵カードです。


*関連エントリ
「熱狂の日」の展覧会?! 「モーツァルト展」(5/6)
モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 「熱狂の日音楽祭2006」(5/5)
「熱狂の日音楽祭」のあとは「ぶらあぼ」で!(5/4)
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006」、ついに開幕!(4/30)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「熱狂の日」の展覧会?! 「モーツァルト展」
丸ビル・丸ビルホール(千代田区丸の内2-4-1 丸ビル7F)
「海老沢敏コレクション モーツァルト展」
5/3~7
今日で全コンサートを終えた「熱狂の日音楽祭」ですが、丸の内地区全域を巻き込んだお祭りと言うことで、国際フォーラムだけでなく、この界隈の各所にて様々なイベントが開催されています。その中でも特に興味深かったのが、この「海老沢敏コレクション モーツァルト展」でした。
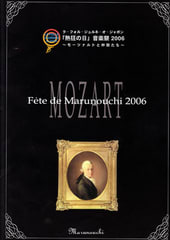
会場には、モーツァルト研究家として有名な海老沢敏氏の個人コレクションがズラリと並んでいます。モーツァルトの油彩肖像画一点「15歳のモーツァルト」(チニャローリ作。上の画像のものです。)と、自筆譜や初版譜、もしくはそれらの複製、さらにはモーツァルトと関係を持った人物たちの自筆書簡。これらの品々がガラスケース越しに展示されていました。全体の構成は写真パネルによる解説がメインなので、見るべき展示品の数は決して多いとは言えませんが、モーツァルトの自筆楽譜はもちろんのこと、ダ・ポンテやサリエーリの自筆書簡などはなかなか見る機会がありません。モーツァルト好きなら一度は見たい内容かと思います。
私が興味深かったのは、今も挙げたダ・ポンテやサリエーリらの自筆書簡です。文字は人を表すとでも言うのでしょうか。とっても可愛らしい丸字のダ・ポンテや、実に神経質そうな細かい字を書くサリエリ、またはビシッと整然と並んだヨーゼフ2世の文字などは、まさに彼らのイメージ通りでした。
また、美術好きにもおすすめしたい展示があります。それはモーツァルトにちなんだ版画やリトグラフ作品(数点)です。その中ではシャガールのリトグラフ「魔笛」(1966)が目立ちました。青を基調にしたシャガールならではの美しい画面に、まさにメルヘンの「魔笛」を体現したかのような愉快な人物たち。シャガールが、このオペラをモチーフにして作品を制作していたとは知りませんでした。意外な場所で出会えた佳い作品です。
展示は明日、日曜日までです。わざわざ出向くほどではないかもしれませんが、東京駅近辺に用事のある方なら、立ち寄ってみても損はないかと思います。また会場では、展示されたフォルテピアノによるレクチャー、もしくはミニコンサートも行われています。(それぞれ13:30、15:30、17:30より。)入場無料です。
「海老沢敏コレクション モーツァルト展」
5/3~7
今日で全コンサートを終えた「熱狂の日音楽祭」ですが、丸の内地区全域を巻き込んだお祭りと言うことで、国際フォーラムだけでなく、この界隈の各所にて様々なイベントが開催されています。その中でも特に興味深かったのが、この「海老沢敏コレクション モーツァルト展」でした。
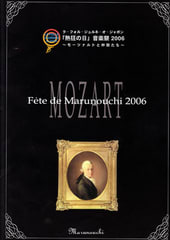
会場には、モーツァルト研究家として有名な海老沢敏氏の個人コレクションがズラリと並んでいます。モーツァルトの油彩肖像画一点「15歳のモーツァルト」(チニャローリ作。上の画像のものです。)と、自筆譜や初版譜、もしくはそれらの複製、さらにはモーツァルトと関係を持った人物たちの自筆書簡。これらの品々がガラスケース越しに展示されていました。全体の構成は写真パネルによる解説がメインなので、見るべき展示品の数は決して多いとは言えませんが、モーツァルトの自筆楽譜はもちろんのこと、ダ・ポンテやサリエーリの自筆書簡などはなかなか見る機会がありません。モーツァルト好きなら一度は見たい内容かと思います。
私が興味深かったのは、今も挙げたダ・ポンテやサリエーリらの自筆書簡です。文字は人を表すとでも言うのでしょうか。とっても可愛らしい丸字のダ・ポンテや、実に神経質そうな細かい字を書くサリエリ、またはビシッと整然と並んだヨーゼフ2世の文字などは、まさに彼らのイメージ通りでした。
また、美術好きにもおすすめしたい展示があります。それはモーツァルトにちなんだ版画やリトグラフ作品(数点)です。その中ではシャガールのリトグラフ「魔笛」(1966)が目立ちました。青を基調にしたシャガールならではの美しい画面に、まさにメルヘンの「魔笛」を体現したかのような愉快な人物たち。シャガールが、このオペラをモチーフにして作品を制作していたとは知りませんでした。意外な場所で出会えた佳い作品です。
展示は明日、日曜日までです。わざわざ出向くほどではないかもしれませんが、東京駅近辺に用事のある方なら、立ち寄ってみても損はないかと思います。また会場では、展示されたフォルテピアノによるレクチャー、もしくはミニコンサートも行われています。(それぞれ13:30、15:30、17:30より。)入場無料です。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |









