どうでもいいことだが、私のガラケーの待ち受け画面は、今でもタカマツペアの松友ちゃんである。
 理知的な処がいい
理知的な処がいい
そして松友ちゃんといえば、徳島県藍住町出身で、小学校の頃から地元のバドミントンクラブ「藍住エンジェル」に入ってメキメキと上達したのだった。
オリンピックの後、彼女が地元のローカル番組にゲスト出演している動画があって、Youtube で観ると、当時の仲間たちが松友ちゃんの小さい時のことを語っていた。その仲間たちも今や皆さんいいお年頃の女性で、これがまたみんな美人ばかりなのだ。
私は、ここから、勝手に徳島県は美人の多いところなんだと思うようになっていた。
先週の土曜日に徳島市に着いてから、すぐに徳島駅の裏手の川内町にある、「阿波十郎兵衛屋敷」に向かった。
 入り口は質素そのもの
入り口は質素そのもの
浄瑠璃の公演まで時間があったので、資料館で人形浄瑠璃の情報を仕入れて、その横にある土産物店をブラブラしたりしていた。資料館には、後期高齢者風のボランティアガイドが男女1名ずついて、知識をひけらかしてくれた。
ここは公的な施設なんですか、それとも個人的な施設なんですか、と尋ねると答えが分らなかったようで、慌てて別の支配人らしい女性に聞いていた。建物は徳島県のもので、運営はNPO法人となっているとのことだった。入場料410円と破格なのはその所為だった。
 資料館内
資料館内
愛想のいいご婦人がいるみやげ物店で藍染めの手ぬぐいを買った。「どちらから来られたんですか?」と聞かれたので、静岡からついさっき着いたばかりだと答えると、少し驚いていた。
私は、聞かれもしないのに「昨年のオリンピック以来、徳島には来よう来ようと思っていたんです。
バドミントンの松友選手のファンになったからで、さっき徳島駅前についてバスを降りた時は、『きっと、松友ちゃんのような美人がたくさん歩いているんだろうなあ』って勝手にワクワクしたんですけど、ちょっと裏切られた感じです。」
そう言うと、ご婦人は「松友さんはここからちょっと行った藍住町の出身なんですよ。実は、私もそこの生まれなんですけど・・・ガッカリさせてしまって、すみません。」
こう言ってペコンと頭を下げたのだった。私は、慌てて「ああ・・そうだったんですか。どうりでおきれいなご婦人だと思いました・・。」と言って笑ったのだが、何ともバツが悪かった。
毎日午前11時と午後2時から、人形浄瑠璃の公演が至近距離で観られて、入場料410円とは。今の時代こんな良心的な文化施設は他にあるだろうか。
もし近くにあったら、私は毎週訪れるのではないかと思った。
 理知的な処がいい
理知的な処がいいそして松友ちゃんといえば、徳島県藍住町出身で、小学校の頃から地元のバドミントンクラブ「藍住エンジェル」に入ってメキメキと上達したのだった。
オリンピックの後、彼女が地元のローカル番組にゲスト出演している動画があって、Youtube で観ると、当時の仲間たちが松友ちゃんの小さい時のことを語っていた。その仲間たちも今や皆さんいいお年頃の女性で、これがまたみんな美人ばかりなのだ。
私は、ここから、勝手に徳島県は美人の多いところなんだと思うようになっていた。
先週の土曜日に徳島市に着いてから、すぐに徳島駅の裏手の川内町にある、「阿波十郎兵衛屋敷」に向かった。
 入り口は質素そのもの
入り口は質素そのもの浄瑠璃の公演まで時間があったので、資料館で人形浄瑠璃の情報を仕入れて、その横にある土産物店をブラブラしたりしていた。資料館には、後期高齢者風のボランティアガイドが男女1名ずついて、知識をひけらかしてくれた。
ここは公的な施設なんですか、それとも個人的な施設なんですか、と尋ねると答えが分らなかったようで、慌てて別の支配人らしい女性に聞いていた。建物は徳島県のもので、運営はNPO法人となっているとのことだった。入場料410円と破格なのはその所為だった。
 資料館内
資料館内愛想のいいご婦人がいるみやげ物店で藍染めの手ぬぐいを買った。「どちらから来られたんですか?」と聞かれたので、静岡からついさっき着いたばかりだと答えると、少し驚いていた。
私は、聞かれもしないのに「昨年のオリンピック以来、徳島には来よう来ようと思っていたんです。
バドミントンの松友選手のファンになったからで、さっき徳島駅前についてバスを降りた時は、『きっと、松友ちゃんのような美人がたくさん歩いているんだろうなあ』って勝手にワクワクしたんですけど、ちょっと裏切られた感じです。」
そう言うと、ご婦人は「松友さんはここからちょっと行った藍住町の出身なんですよ。実は、私もそこの生まれなんですけど・・・ガッカリさせてしまって、すみません。」
こう言ってペコンと頭を下げたのだった。私は、慌てて「ああ・・そうだったんですか。どうりでおきれいなご婦人だと思いました・・。」と言って笑ったのだが、何ともバツが悪かった。
毎日午前11時と午後2時から、人形浄瑠璃の公演が至近距離で観られて、入場料410円とは。今の時代こんな良心的な文化施設は他にあるだろうか。
もし近くにあったら、私は毎週訪れるのではないかと思った。










 妖艶な女踊り
妖艶な女踊り 巡礼歌の段より
巡礼歌の段より 「傾城阿波の鳴門」
「傾城阿波の鳴門」 妖艶な阿波踊り
妖艶な阿波踊り よさこい踊り
よさこい踊り YOSAKOIソーラン
YOSAKOIソーラン 女性ならではの動き
女性ならではの動き ミスター引退
ミスター引退 長嶋大権現
長嶋大権現 ボクは紳士です!
ボクは紳士です! (ブログとは無関係です。)
(ブログとは無関係です。) (ブログとは無関係です。)
(ブログとは無関係です。) (ブログとは無関係です。)
(ブログとは無関係です。) 山桜の木
山桜の木 葉桜の生命感
葉桜の生命感 花いかだの美しさ
花いかだの美しさ 木蓮の花
木蓮の花 モクレンの若葉たち
モクレンの若葉たち ハナミズキの可憐な花
ハナミズキの可憐な花 ハナミズキの若葉
ハナミズキの若葉 我家の痛々しいハナミズキ
我家の痛々しいハナミズキ 腕を高く上げて勝利を喜ぶのがいい
腕を高く上げて勝利を喜ぶのがいい 左右下方に赤旗三つ
左右下方に赤旗三つ 支那軍コーチ・孔令輝さん
支那軍コーチ・孔令輝さん 相当ショックを受けました
相当ショックを受けました 表情がまともじゃない
表情がまともじゃない 八田與一像アップ
八田與一像アップ 子沢山の家族だった
子沢山の家族だった 妻、外代樹(とよき)と、
妻、外代樹(とよき)と、 ユニークな像である
ユニークな像である この気取らぬ天真爛漫さがいい!
この気取らぬ天真爛漫さがいい! 痛快なオヤジ!
痛快なオヤジ! 抱腹絶倒!!
抱腹絶倒!! 観たいようで観たくもない・・・
観たいようで観たくもない・・・ 遣欧少年使節の四名
遣欧少年使節の四名 日本二十六聖人の磔の絵
日本二十六聖人の磔の絵 長篠城址史跡保存館
長篠城址史跡保存館 長篠城本丸跡
長篠城本丸跡 強右衛門、磔の絵
強右衛門、磔の絵 岡崎出身、志賀重昂
岡崎出身、志賀重昂 
 衝撃のラストシーン!
衝撃のラストシーン!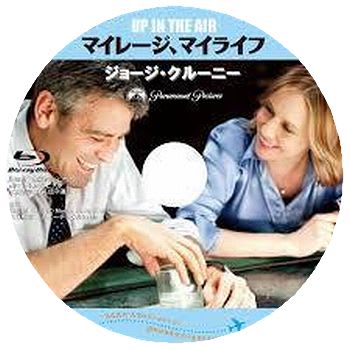 原題: Up in the Air
原題: Up in the Air 若さみなぎる、アリスの頃のベーヤン
若さみなぎる、アリスの頃のベーヤン 演歌歌手、堀内孝雄。むくみが気になる
演歌歌手、堀内孝雄。むくみが気になる 居酒屋の臨場感たっぷり
居酒屋の臨場感たっぷり 更生する決意はまったく感じられなかった
更生する決意はまったく感じられなかった
 本が私に声をかけてきた・・
本が私に声をかけてきた・・ 御歳93
御歳93 御歳94
御歳94