親類との付き合いを父から引き継いだのは、多分20年ほど前だったと思うが、何せ私の父は10人兄弟の9番目だったため、私の従兄弟は50人近かったようだ。(正直言って、今でも全員の名前と顔は一致しない)
従って、私が親戚づきあいを父から引き継いだ当初は、法事などに参列しても誰がどこのどういう関係の方なのか、さっぱり分からず困ったものだった。
突然、後ろから肩を小突かれて、「よう!久しぶりだな。今何やってんだ?」と話しかけられても、その方が誰なのかまったく記憶に無く、「はあ・・まあ相変わらずですよ・・。」などと、曖昧な返事をしてその場をしのぐのが精一杯だった。
多いときには、葬式や法事が立て続けにあって、あちこちの市町に散らばっている親戚の家にたどり着くのさえ、非常に苦労したものだった。
そんな時興味深かったことの一つに、その地区ごとの風習やしきたりがこうまで異なるものなのか、そして、葬儀のような親類縁者の集まる場では、いわゆる「長老」挌の人に、しきたりを確認しながら事を進めるものなのだ、ということだった。
当事者が、やり方が分からずオロオロしていると、大抵長老がお出ましになって、「それはああだ、これはこうだ」と指図していた。特にその指図に異論を挟む人も出ずに、その長老もまんざらではないという表情でその場を仕切っていた。
しかし、一度葬儀で自宅から出棺のため、そのお宅へ朝早く出向いたときのことだった。
 田舎は自宅での通夜が多い
田舎は自宅での通夜が多い
葬儀社の方の指示に従って、鼻を棺桶に順番に入れていき、蓋をして釘を打ち、親類の男手8人ほどで棺桶を持ち上げ、出棺となったときのことだった。
その場にいた親類の長老挌の方が、「出す時は足の方からじゃなくて頭からだぞ。」と、念を押した。私は、「へぇー、そういうしきたりなのか。」と思った。
しかし、外に運び出されて霊柩車に載せられるときは、葬儀社の方が、「すみませんが、足の方から載せてください」と小声で指図していたのが気になった。
間もなくして、別の町の親戚の葬儀出棺に立ち会った時は、出棺も霊柩車へも足の方からだったので、あの時の長老の指図はなんだったんだ?と疑問に感jた。
また、勤め先の同僚の祖父が他界した際に、通夜に焼香に行った時のこと。
ご遺体が寝かされている和室に案内され、その様子を観たとき、私は「なにこれ?」と思わずにはいられなかった。その布団の位置は、部屋の畳や壁に平行ではなく、奇妙に斜めの位置であったのだ。
そう感じたのは、私だけでなく、一緒に通夜に出向いた同僚たちも、帰路口々に不思議がっていたが、恐らく「北枕」を意識してのことだろう、という結論に達した。
「北枕」。つまり、死者は、頭を北の方角に向けるものなのだそうだ。
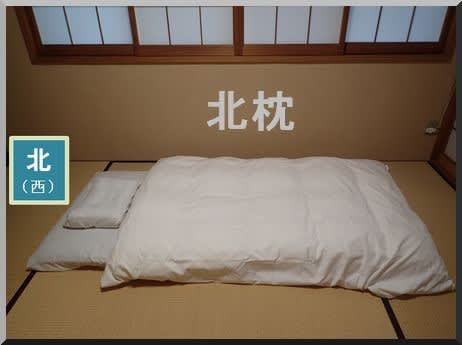 真北でなくてもいいんじゃない?
真北でなくてもいいんじゃない?
これも、多分親戚の長老が、口を挟んだ結果だったのかもしれない。
一般的に「地区の長老」は、経験も知識も豊富なので、若輩者や余所から来た人は、とりあえず長老の言うことに従わざるを得ないもののようである。
私は、疑問を抱くとすぐにでもそれを解消したくなる性分なので、遠慮せずにそういう場合は、歳を重ねた長老に聞くことにしている。
例えば、数年前に秋祭の当番になった際も、しめ縄に挟む和紙はなんと呼ぶのか?とか、そもそもしめ縄とは何でこういうデザインなのか?とか聞いてみたが、「さあ?知らんなあ」とか、「そんなの考えたことも無いなあ」と返事は素っ気無かった。
私は、地区や親類の長老を責めるつもりなど毛頭ないが、意外と長老の経験や知識には普遍性や一貫性が伴わないことがある。
それは、日本の文化や風習を調べていても感ずることで、よく目にするのは、「これにはいくつか説があって・・・」とか、「地方によっても解釈は違うが・・・」という前置きである。
マア、それは当然のことだとしても、何でも感でも言われたままに長老の言うことを何の疑問も挟まず盲信してしまう姿勢は、果たして如何なものかと私は感じてしまうのである。
従って、私が親戚づきあいを父から引き継いだ当初は、法事などに参列しても誰がどこのどういう関係の方なのか、さっぱり分からず困ったものだった。
突然、後ろから肩を小突かれて、「よう!久しぶりだな。今何やってんだ?」と話しかけられても、その方が誰なのかまったく記憶に無く、「はあ・・まあ相変わらずですよ・・。」などと、曖昧な返事をしてその場をしのぐのが精一杯だった。
多いときには、葬式や法事が立て続けにあって、あちこちの市町に散らばっている親戚の家にたどり着くのさえ、非常に苦労したものだった。
そんな時興味深かったことの一つに、その地区ごとの風習やしきたりがこうまで異なるものなのか、そして、葬儀のような親類縁者の集まる場では、いわゆる「長老」挌の人に、しきたりを確認しながら事を進めるものなのだ、ということだった。
当事者が、やり方が分からずオロオロしていると、大抵長老がお出ましになって、「それはああだ、これはこうだ」と指図していた。特にその指図に異論を挟む人も出ずに、その長老もまんざらではないという表情でその場を仕切っていた。
しかし、一度葬儀で自宅から出棺のため、そのお宅へ朝早く出向いたときのことだった。
 田舎は自宅での通夜が多い
田舎は自宅での通夜が多い葬儀社の方の指示に従って、鼻を棺桶に順番に入れていき、蓋をして釘を打ち、親類の男手8人ほどで棺桶を持ち上げ、出棺となったときのことだった。
その場にいた親類の長老挌の方が、「出す時は足の方からじゃなくて頭からだぞ。」と、念を押した。私は、「へぇー、そういうしきたりなのか。」と思った。
しかし、外に運び出されて霊柩車に載せられるときは、葬儀社の方が、「すみませんが、足の方から載せてください」と小声で指図していたのが気になった。
間もなくして、別の町の親戚の葬儀出棺に立ち会った時は、出棺も霊柩車へも足の方からだったので、あの時の長老の指図はなんだったんだ?と疑問に感jた。
また、勤め先の同僚の祖父が他界した際に、通夜に焼香に行った時のこと。
ご遺体が寝かされている和室に案内され、その様子を観たとき、私は「なにこれ?」と思わずにはいられなかった。その布団の位置は、部屋の畳や壁に平行ではなく、奇妙に斜めの位置であったのだ。
そう感じたのは、私だけでなく、一緒に通夜に出向いた同僚たちも、帰路口々に不思議がっていたが、恐らく「北枕」を意識してのことだろう、という結論に達した。
「北枕」。つまり、死者は、頭を北の方角に向けるものなのだそうだ。
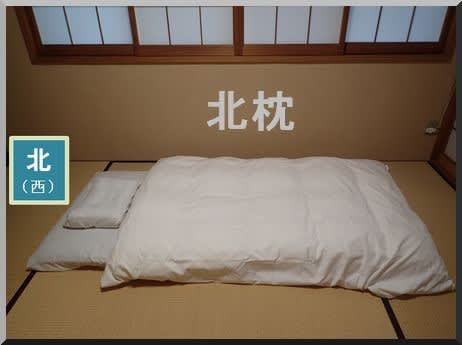 真北でなくてもいいんじゃない?
真北でなくてもいいんじゃない?これも、多分親戚の長老が、口を挟んだ結果だったのかもしれない。
一般的に「地区の長老」は、経験も知識も豊富なので、若輩者や余所から来た人は、とりあえず長老の言うことに従わざるを得ないもののようである。
私は、疑問を抱くとすぐにでもそれを解消したくなる性分なので、遠慮せずにそういう場合は、歳を重ねた長老に聞くことにしている。
例えば、数年前に秋祭の当番になった際も、しめ縄に挟む和紙はなんと呼ぶのか?とか、そもそもしめ縄とは何でこういうデザインなのか?とか聞いてみたが、「さあ?知らんなあ」とか、「そんなの考えたことも無いなあ」と返事は素っ気無かった。
私は、地区や親類の長老を責めるつもりなど毛頭ないが、意外と長老の経験や知識には普遍性や一貫性が伴わないことがある。
それは、日本の文化や風習を調べていても感ずることで、よく目にするのは、「これにはいくつか説があって・・・」とか、「地方によっても解釈は違うが・・・」という前置きである。
マア、それは当然のことだとしても、何でも感でも言われたままに長老の言うことを何の疑問も挟まず盲信してしまう姿勢は、果たして如何なものかと私は感じてしまうのである。










 外国語は英語だけでいい
外国語は英語だけでいい ここまで必要ですか?
ここまで必要ですか? この動き、賛成!
この動き、賛成! そもそもこれが変だった。こんなの日本人の所作じゃない。
そもそもこれが変だった。こんなの日本人の所作じゃない。 ザギトワみたいだけど・・
ザギトワみたいだけど・・ ゆずるなよ!
ゆずるなよ! 矢印は山岳救助隊員
矢印は山岳救助隊員 交番勤務の警官
交番勤務の警官
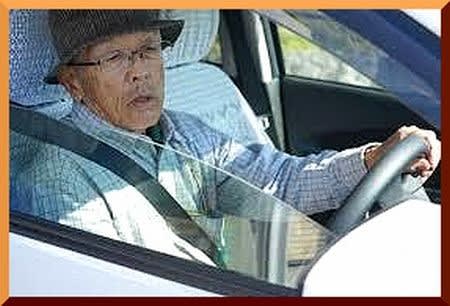
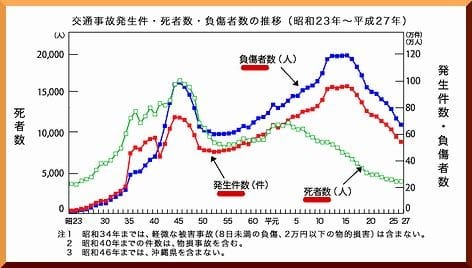


 リニューアル完了?
リニューアル完了? 4畳程の小部屋
4畳程の小部屋 メッカはこちら
メッカはこちら どっちもエマヌエル
どっちもエマヌエル 皆さん、垢抜けてます!
皆さん、垢抜けてます! 苦痛を和らげる?
苦痛を和らげる? コンコルド広場
コンコルド広場 断頭台へ・・
断頭台へ・・
 ビーンもびっくりゴーンが逮捕
ビーンもびっくりゴーンが逮捕 主に文房具類
主に文房具類 見た目はきれいだが
見た目はきれいだが 便利なカッターナイフ
便利なカッターナイフ 使い方別に種類も多い
使い方別に種類も多い 切れ味抜群
切れ味抜群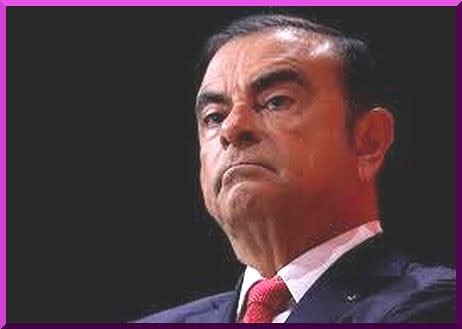 レバノン人の顔?
レバノン人の顔?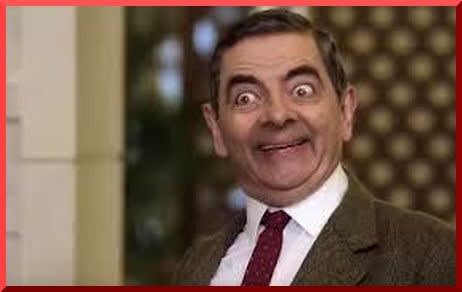 目をむくMr.ビーン
目をむくMr.ビーン 国籍は日本でしょう
国籍は日本でしょう 通夜の夜の玄関
通夜の夜の玄関 弔問客の駐車場が問題
弔問客の駐車場が問題 Before
Before After
After コンビニ弁当
コンビニ弁当 家庭ごみ(約3日分)
家庭ごみ(約3日分) 手放しの喜び
手放しの喜び 見よ、トヨタの自動運転車を
見よ、トヨタの自動運転車を SRS ??
SRS ?? SRS AIRBAG の意味は?
SRS AIRBAG の意味は? AIが悪い?
AIが悪い? この方、日本人?
この方、日本人?