五木寛之『私訳・歎異抄』(PHP文庫)
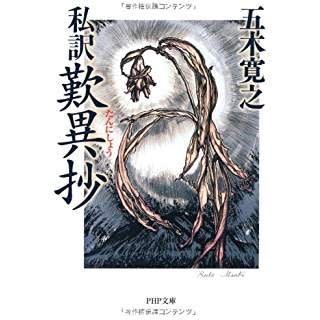
鎌倉幕府から弾圧を受けながら、真の仏の道を求めた浄土真宗の開祖・親鸞。その教えを弟子の唯円が「正しく伝えたい」と願って書き残し、時代を超えて読み継がれたのが『歎異抄』である。本書は、親鸞の生涯に作家として正面から向き合い、三部作の大長編に挑んできた著者が、自らの心で深く受け止めた『歎異抄』を、滋味あふれる平易な文体で現代語訳した名著。ベストセラー、待望の文庫化! (「BOOK」データベースより)
◎心の浄化という世界
『歎異抄(たんにしょう)』は以前に、阿満利麿訳『歎異抄』(ちくま学芸文庫)と野間宏『歎異抄』(ちくま文庫)を読んでいます。読んでいますというよりは、とおりすぎていますと書いた方が正確かもしれません。なにしろ、ちんぷんかんぷんだったのです。
あまりにも情けないので、倉田百三『親鸞』(角川文庫)を読みました。『歎異抄』は「山本藤光の文庫で読む500+α」のメンツにかけて、絶対に避けてはとおれない1冊です。なんとか理解しようと必死でした。そんなときに、五木寛之『私訳・歎異抄』(PHP文庫)と出逢ったのです。五木寛之は「まえがき」でつぎのように書いています。
――他人を蹴落とし、弱者をおしのけて生きのびてきた自分。敗戦から引き揚げまでの数年間を、私は人間としてではなく生きていた。その黒い記憶の闇を照らす光として、私は歎異抄と出会ったのだ。(本書「まえがき」より)
「人間としてではなく生きていた」のところに、目が釘づけになりました。五木寛之はその理由を、「他人を蹴落とし、弱者をおしのけ」て、と書いています。終戦後の自分を顧みての文章ですが、これって企業人時代の私につうじることです。自分は意図していなかったにもかかわらず、OB会などで露骨に指摘されたことがあります。同期で一番出世したので、おそらく天狗になっていたのでしょう。
五木寛之『私訳・歎異抄』は、実にわかりやすい言葉で語りかけてくれました。心が洗われるような、すがすがしい読後感でした。薄い本なので、何度もくりかえして読みました。まるで毎朝祖母が仏壇に向かって、念仏をとなえているかのようでした。
毎年正月には近所の神社へ出かけます。神殿に向かって賽銭を投じ、願いを伝えます。企業人時代は、家内安全と仕事がうまくいきますように、と祈りました。隠居した現在は仕事がうまくいきますようにのかわりに、健康でありつづけますように、となっています。
ところが仏さまについて、手を合わせる場はありません。せいぜい両親の命日に、仏壇にろうそくをともして感謝を告げるくらいです。あるいは年に1度墓参にいって、孫たちが健やかに育っていることを報告するのが関の山です。
『歎異抄』にふれて、心の浄化というこれまでとは次元のちがう、世界に迷いこみました。これまでぼんやりとしていた「易行(いぎょう)の念仏」を、理解することができました。
――親鸞さまの師、法然上人のお説きになったのは、易行の念仏、ということだった。貧しい者も、字の読めない者も、誰でもがやさしく行うことのできる教えである。これを易行という。(本文P10より)
◎悪人こそ救われる
ずっと理解できなかった、教えがあります。第三条のつぎの言葉です。「悪人こそ救われる」という真逆の言葉が、どうしてもぴんとこないのです。
――善人なほもつて往生をとぐ。いはんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいはく、「悪人なほ往生す。いかにいはんや善人をや」。(『歎異抄』原典より)
――善人ですら救われるのだ。まして悪人が救われぬわけはない。しかし、世間の人びとは、そんなことは夢にも考えないし、いわないはずだ。(五木寛之『私訳・歎異抄』P20より)
五木寛之はこの法語に、「自力」と「他力」をもちいて説明しています。「自力」とは「自分の力を信じ、自分の善い行いの見返りも疑わない」こととなります。いっぽう「他力」とは、「ほかにたよるものがなく、ただひとすじに仏の約束のちから、すなわち他力に身をまかせようという」ことです。つまり「自力におぼれる心をあらためて、他力の本願にかえるならば、必ず真の救いをうることができる」ということなのです。
斎藤孝は著作のなかで、第三条をつぎのように解説しています。
――病気の子には親は特別世話をする。自力ではどうしょうもない。他力をたのむところに阿弥陀仏の救いの手が伸びる。愚かな自分(親鸞)は法然上人にだまされて念仏で地獄行きでも後悔はない。念仏を信じるか信じないかはあなた次第、という。やさしいようで突き放す距離感が絶妙。(斎藤孝『古典力』岩波新書P215より)
さらに阿刀田高の解釈をつづけさせていただきます。少しながくなりますが、やっともやもやが晴れた気持ちになりました。
――第一条で、阿弥陀如来は老人か若者か善人か悪人かを問わず、ただ信心のある者を救うことが本願であり、特に、罪が著しく深い者、煩悩の強い者を助けることを誓願とすると説いている。つまり、悪人を救うことこそ弥陀の願いなのだから、善人でさえ救われるのなら悪人が救われるのは当然なのである。どんな罪悪であっても、弥陀の本願が及ばないほどのものはない。(阿刀田高監修『日本の古典50冊』知的生きかた文庫P223より)
――「他力本願」という言葉は、日常生活では、自力でがんばらないで他人任せにするという意味で使われがちだが、本来、「他力本願」とは、弥陀の本願にすがるという意味なのである。(阿刀田高監修『日本の古典50冊』知的生きかた文庫P224より)
『歎異抄』は親鸞の教えを、弟子の唯円がまとめたものです。あるとき親鸞は唯円に、「私のことを信じているなら、いうとおりにできるな」と念押しします。そして「千人殺せ」(第十三条)と命じます。当然、唯円はそんなことはできるはずはありません。この問いの意味についても、五木寛之はていねいに説明してくれました。
これから、五木寛之『親鸞・激動篇』(上下巻、講談社文庫)を読みます。五木寛之『親鸞(上下巻、講談社文庫)は読み終わりました。いずれ「+α」として書いてみたいと思っています。
◎追記2015.03.01
中沢新一の最新刊『日本文学の大地』(角川学芸出版2015年)のなかに「歎異抄」の章があります。読んで共感する箇所がありました。紹介させていただきます。
――親鸞の教えは、その大地に深く根を下ろすことのできた、日本では数少ない、宗教思想なのである。思想や観念が、そういう大地に根を下ろして、そこから栄養を吸収して、大地に内蔵されている生命そのものに、表現をあたえることができた、という例は少ない。いつの時代にも、学問とか観念とか思想とかに夢中になっている人たちは、大地から浮き上がったままなので、美しいけれどか弱い、観念の空中花を咲かすことができるだけだ。(中沢新一『日本文学の大地』角川学芸出版より)
親鸞は、フィールドワークの人だったことが実感できました。倉田百三『出家とその弟子』(新潮文庫、「山本藤光の文庫で読む500+α」推薦作)のなかに、猛吹雪の大地を歩く親鸞と弟子たちの場面があります。中沢新一の文章にふれて、あの場面が腑に落ちました。
(山本藤光2014.12.25初稿、2018.02.23改稿)
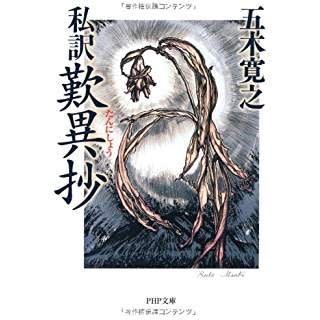
鎌倉幕府から弾圧を受けながら、真の仏の道を求めた浄土真宗の開祖・親鸞。その教えを弟子の唯円が「正しく伝えたい」と願って書き残し、時代を超えて読み継がれたのが『歎異抄』である。本書は、親鸞の生涯に作家として正面から向き合い、三部作の大長編に挑んできた著者が、自らの心で深く受け止めた『歎異抄』を、滋味あふれる平易な文体で現代語訳した名著。ベストセラー、待望の文庫化! (「BOOK」データベースより)
◎心の浄化という世界
『歎異抄(たんにしょう)』は以前に、阿満利麿訳『歎異抄』(ちくま学芸文庫)と野間宏『歎異抄』(ちくま文庫)を読んでいます。読んでいますというよりは、とおりすぎていますと書いた方が正確かもしれません。なにしろ、ちんぷんかんぷんだったのです。
あまりにも情けないので、倉田百三『親鸞』(角川文庫)を読みました。『歎異抄』は「山本藤光の文庫で読む500+α」のメンツにかけて、絶対に避けてはとおれない1冊です。なんとか理解しようと必死でした。そんなときに、五木寛之『私訳・歎異抄』(PHP文庫)と出逢ったのです。五木寛之は「まえがき」でつぎのように書いています。
――他人を蹴落とし、弱者をおしのけて生きのびてきた自分。敗戦から引き揚げまでの数年間を、私は人間としてではなく生きていた。その黒い記憶の闇を照らす光として、私は歎異抄と出会ったのだ。(本書「まえがき」より)
「人間としてではなく生きていた」のところに、目が釘づけになりました。五木寛之はその理由を、「他人を蹴落とし、弱者をおしのけ」て、と書いています。終戦後の自分を顧みての文章ですが、これって企業人時代の私につうじることです。自分は意図していなかったにもかかわらず、OB会などで露骨に指摘されたことがあります。同期で一番出世したので、おそらく天狗になっていたのでしょう。
五木寛之『私訳・歎異抄』は、実にわかりやすい言葉で語りかけてくれました。心が洗われるような、すがすがしい読後感でした。薄い本なので、何度もくりかえして読みました。まるで毎朝祖母が仏壇に向かって、念仏をとなえているかのようでした。
毎年正月には近所の神社へ出かけます。神殿に向かって賽銭を投じ、願いを伝えます。企業人時代は、家内安全と仕事がうまくいきますように、と祈りました。隠居した現在は仕事がうまくいきますようにのかわりに、健康でありつづけますように、となっています。
ところが仏さまについて、手を合わせる場はありません。せいぜい両親の命日に、仏壇にろうそくをともして感謝を告げるくらいです。あるいは年に1度墓参にいって、孫たちが健やかに育っていることを報告するのが関の山です。
『歎異抄』にふれて、心の浄化というこれまでとは次元のちがう、世界に迷いこみました。これまでぼんやりとしていた「易行(いぎょう)の念仏」を、理解することができました。
――親鸞さまの師、法然上人のお説きになったのは、易行の念仏、ということだった。貧しい者も、字の読めない者も、誰でもがやさしく行うことのできる教えである。これを易行という。(本文P10より)
◎悪人こそ救われる
ずっと理解できなかった、教えがあります。第三条のつぎの言葉です。「悪人こそ救われる」という真逆の言葉が、どうしてもぴんとこないのです。
――善人なほもつて往生をとぐ。いはんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいはく、「悪人なほ往生す。いかにいはんや善人をや」。(『歎異抄』原典より)
――善人ですら救われるのだ。まして悪人が救われぬわけはない。しかし、世間の人びとは、そんなことは夢にも考えないし、いわないはずだ。(五木寛之『私訳・歎異抄』P20より)
五木寛之はこの法語に、「自力」と「他力」をもちいて説明しています。「自力」とは「自分の力を信じ、自分の善い行いの見返りも疑わない」こととなります。いっぽう「他力」とは、「ほかにたよるものがなく、ただひとすじに仏の約束のちから、すなわち他力に身をまかせようという」ことです。つまり「自力におぼれる心をあらためて、他力の本願にかえるならば、必ず真の救いをうることができる」ということなのです。
斎藤孝は著作のなかで、第三条をつぎのように解説しています。
――病気の子には親は特別世話をする。自力ではどうしょうもない。他力をたのむところに阿弥陀仏の救いの手が伸びる。愚かな自分(親鸞)は法然上人にだまされて念仏で地獄行きでも後悔はない。念仏を信じるか信じないかはあなた次第、という。やさしいようで突き放す距離感が絶妙。(斎藤孝『古典力』岩波新書P215より)
さらに阿刀田高の解釈をつづけさせていただきます。少しながくなりますが、やっともやもやが晴れた気持ちになりました。
――第一条で、阿弥陀如来は老人か若者か善人か悪人かを問わず、ただ信心のある者を救うことが本願であり、特に、罪が著しく深い者、煩悩の強い者を助けることを誓願とすると説いている。つまり、悪人を救うことこそ弥陀の願いなのだから、善人でさえ救われるのなら悪人が救われるのは当然なのである。どんな罪悪であっても、弥陀の本願が及ばないほどのものはない。(阿刀田高監修『日本の古典50冊』知的生きかた文庫P223より)
――「他力本願」という言葉は、日常生活では、自力でがんばらないで他人任せにするという意味で使われがちだが、本来、「他力本願」とは、弥陀の本願にすがるという意味なのである。(阿刀田高監修『日本の古典50冊』知的生きかた文庫P224より)
『歎異抄』は親鸞の教えを、弟子の唯円がまとめたものです。あるとき親鸞は唯円に、「私のことを信じているなら、いうとおりにできるな」と念押しします。そして「千人殺せ」(第十三条)と命じます。当然、唯円はそんなことはできるはずはありません。この問いの意味についても、五木寛之はていねいに説明してくれました。
これから、五木寛之『親鸞・激動篇』(上下巻、講談社文庫)を読みます。五木寛之『親鸞(上下巻、講談社文庫)は読み終わりました。いずれ「+α」として書いてみたいと思っています。
◎追記2015.03.01
中沢新一の最新刊『日本文学の大地』(角川学芸出版2015年)のなかに「歎異抄」の章があります。読んで共感する箇所がありました。紹介させていただきます。
――親鸞の教えは、その大地に深く根を下ろすことのできた、日本では数少ない、宗教思想なのである。思想や観念が、そういう大地に根を下ろして、そこから栄養を吸収して、大地に内蔵されている生命そのものに、表現をあたえることができた、という例は少ない。いつの時代にも、学問とか観念とか思想とかに夢中になっている人たちは、大地から浮き上がったままなので、美しいけれどか弱い、観念の空中花を咲かすことができるだけだ。(中沢新一『日本文学の大地』角川学芸出版より)
親鸞は、フィールドワークの人だったことが実感できました。倉田百三『出家とその弟子』(新潮文庫、「山本藤光の文庫で読む500+α」推薦作)のなかに、猛吹雪の大地を歩く親鸞と弟子たちの場面があります。中沢新一の文章にふれて、あの場面が腑に落ちました。
(山本藤光2014.12.25初稿、2018.02.23改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます