東野圭吾『秘密』(文春文庫)その1
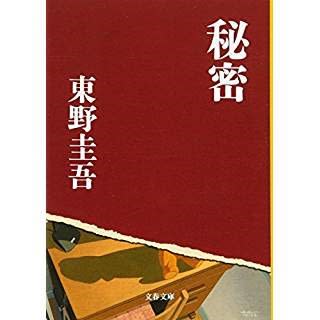
妻・直子と小学5年生の娘・藻奈美を乗せたバスが崖から転落。妻の葬儀の夜、意識を取り戻した娘の体に宿っていたのは、死んだはずの妻だった。その日から杉田家の切なく奇妙な〈秘密〉の生活が始まった。映画「秘密」の原作であり、98年度のベストミステリーとして話題をさらった長篇。(「BOOK」データベースより)
◎長い長い『秘密』の舞台裏に挑む
これから紹介するのは、私の最長の書評です。私はこれを「ミステリーZ」(2001年)というメルマガに連載しました。以下連載したものを引用させていただきます。
1.東野作品には、実体験がふんだんに反映されている
話題の作品『秘密』が文庫化されました。これを機会に何回かに分けて、『秘密』(文春文庫)の「秘密」に迫ってみたいと思います。すでに読んでしまった読者は多いと思いますが、東野圭吾をもっと深く知る一助になれば幸いです。断っておきますが、私は著者の追っかけではありません。読んだ作品もかぎられています。だから全作品を通しての作品論は書けません。
書棚をあさって出てきた初期作品は、『放課後』『卒業・雪月花殺人ゲーム』『学生街の殺人』(いずれも講談社文庫)と『白馬山荘殺人事件』(光文社文庫)だけでした。あとは単行本の最近の作品『白夜行』(集英社1999年)『片想い』(文藝春秋2001年3月)などです。こんな乏しい東野圭吾の読書体験で、『秘密』を語るのはおこがましいのですけれど、どうしても本質に迫ってみたい作品が『秘密』でした。
『秘密』の初出は、1998年9月文藝春秋刊です。文庫化されるまでに約3年を要しています。それだけ単行本が売れていたのでしょう。さもなければ、もっと早くに文庫化されているはずです。ちなみに本日、東京堂書店で確認してきました。書棚にあったのは、2001年2月印刷の28刷でした。
東京堂書店は、神田の古本屋街の裏通りにあり、私の知っているなかでは品揃え、書店としての美学・哲学などの面でナンバーワンの書店です。書泉グランデの真裏に位置していますので、一度のぞいてみていただきたいと思います。これぞ書店とうならせられるはずです。
話が横道にそれました。本題に入ります。『秘密』には東野圭吾の人生の断片が、いくつも埋め込まれています。東野圭吾のプロフィールを知るには、著者自身が書いているホームページを見ることをお薦めします。それを作品に重ねると、『秘密』のなかから著者自身の思いが見えてきます。
東野自身が書いたプロフィールを眺めてみます(文中のかぎカッコ内は引用部分)。東野圭吾は1958年「大阪市生野区にある、しけた時計メガネ貴金属の小売店で、3人姉弟の末っ子として生まれ」ました。
1962年自宅から1キロほど離れた公園で迷子になります。「迷子になった公園は、1999年発表の『白夜行』の冒頭に登場」します。両親は大相撲に夢中になり、気がつかなかったようです。1964年「大阪市立小路小学校に入学します。(中略)この年、東京オリンピックがあったはずだ」。「給食については苦い思い出が多々ある」。詳しく知りたい方は『あの頃ぼくらはアホでした』(集英社文庫)を読んで下さい」
プロフィールは、実にていねいに書かれています。コピーをとったら、A4サイズで5枚にもなりました。ここまでの引用は、まだ1枚目のコピーの半分だけです。東野圭吾は自分の過去を、重要なファクターとして描きます。そのあたりのことを、著者自身はつぎのように語っています。
――作品には今までの生き方や、経験がかなり反映されています。意識の中にある何らかの記憶なり、想い出なりに基づいて、ある部分を引き出し、拡大して、という作業で作品を仕上げることもありますし。無意識のうちに、過去の自分も投影されていると思いますし。作品と自分の経験が無関係ですとは決して言えないですね。(「ダ・ヴィンチ」2000年2月号「『秘密』がおしえるココロのヒミツ」栗田昌裕との対談)
東野自身の書いたプロフィールのなかからも、前記のごとく実体験と作品の関係が2つもでてきます。次回は『秘密』のなかから、東野圭吾の過去と重なる部分を拾ってみたいと思います。東野の人生がどう作品に反映されているのか。そのあたりを検証してみますのでお楽しみに。
(2009.06.11)
2.とことん「時計」にこだわりを示す『秘密』
松野時計店、懐中時計、壁時計、腕時計、札幌の時計台と、『秘密』のなかには数多くの「時計」が登場します。これは東野自身が、時計メガネ貴金属の小売店で生まれたためだけではありません。東野はとことん「時計」にたいするこだわりをもっています。東野自身の「時計」に関するエピソードを紹介しましょう。
東野は少なくとも1999年夏までは、文字盤の大きなクオーツの腕時計を愛用しています。就職祝に父親からもらったものです。ブランド品ではありません。(「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」を参照しました)
今でも愛用しているのか否かはわかりません。なぜなら東野圭吾の写真は、いずれも長袖シャツを着用していて、袖口が確認できないからです。どなたか腕時計が写っている写真をおもちでしたら、教えていただきたいと思います。私はいまだに、文字盤の大きなクオーツを身につけていると思っています。
主人公・平介は、もちろん腕時計くらいはしています。しかし、平介が腕時計に目をやることはあまりありません。どうして、と思う場面でも腕時計には目をやりません。作品のなかで、平介が腕時計を見るのは2回だけです。それも建物や食べ物に対するディテールに比べると、腕時計に関する説明はあまりにもそっけないものです。まるで詳細を書くことを避けているように、投げやりな記述になっています。
――彼(平介)は腕時計を見た。午前十一時を回ったところだった。今から急いで会社に戻っても、すぐに昼休みだ。(本文174ページより)
――翌日、平介は帰りが少し遅くなった。腕時計の針は八時十五分を指している。(本文209ページより)
腕時計ではなく、壁時計に目をやる場面は何度かあります。あるいは、時間の確認をした対象を明確にしないままの記述もあります。壁時計についても、ディテールは明確にされていません。東野が大切にしているのは、過去の思い出が染み込んだ時計のみのようです。あとは時計は単なる時を刻む道具として、大きな価値を認めていないといえます。
――祭壇をセットし終えると、彼(平介)は喪服から普段着に着替えた。壁の時計は午後五時三十五分を指している。(本文より)
――時刻は午後二時を少し回っていた。パンフレットによれば文化祭は五時までだ。彼は急いで支度を始めた。(本文より)
――受話器を置いた平介の胃袋には、しこりのようなものが生じていた。彼は時計を見た。(本文より)
いかがでしょうか。他にも目覚まし時計を見たりと、時刻を確認する場面はあります。しかしいずれも、前記の引用部分と差異はありません。時計に関しては、東野らしくないあっさりし過ぎの表現しか見つからないのです。
ところが懐中時計については、とことんこだわりを示します。実に詳細な記述がつづきます。これは単に、時を刻むものではないからです。就職祝いに父親からもらった腕時計を、東野は「文字盤の大きな、ブランド品ではない、クオーツ」とディテールを説明していることと考え合わせていただきたいと思います。
東野にとって、思い出につながる時計にこそ価値があるのです。事故を起こしたバス運転手・故梶川の妻は、夫のあとを追うように死亡します。平介は梶川の形見である懐中時計を、孤児・逸美より託されます。
――大きさは直径が五センチほどだ。銀色をしている。斜め上に竜頭がついていた。蓋を開けようとした。ところが金具がひっかかっているのか、指先にどんな力を込めても開けられなかった。(本文217ページより)
腕時計や壁時計とは比較にならないほど、詳細を書きこんでいます。さらに「時計」にまつわる、つぎのような場面があります。札幌へ出張した平介は、時間潰しも兼ねて有名な時計台を訪れます。
――タクシーは間もなく太い道路脇に止まった。なぜこんなところに止まったのだろうと思っていると、「あれです」と運転手が道の反対側を指差した。/「あれか……」平介は苦笑した。たしかに写真などから描いたイメージとは大違いだった。屋根についた、ただの白い洋風家屋といえた。(本文238ページより)
札幌の時計台も、陳腐なものにしか過ぎません。平介に一笑にふされた札幌時計台の描写は、松野時計店のそれと比べると違いは歴然としています。松野時計店や懐中時計については、次回にもっと掘り下げてみたいと思います。
(2001.06.30)
3.松野時計店は、東野の生家そのもの
遅くなりましたが、『秘密』のストーリーを確認しておきたいと思います。主人公・杉田平介は、自動車部品メーカーに勤務する40歳前の働き盛り。妻・直子と娘・藻奈美に囲まれ、都内のマイホームで幸せに暮しています。そこへ突然の災難がふりかかります。妻と娘がバス事故にまきこまれ、病院へ搬入されるのです。
妻・直子は死亡し、娘・藻奈美だけが奇跡的に一命をとどめます。目覚めた藻奈美は、平介に自分は直子だと主張します。肉体は娘のものですが、人格は妻・直子のものなのです。主人公・平介の奇妙な日常がはじまります。
このなかで生家の時計メガネ貴金属店は、重要な役割として登場します。
――出張を明日に控えた木曜日、平介は定時で会社を抜けさせてもらい、その足で荻窪に行った。そこにある一軒の時計屋に用があった。(本文より)
時計屋の場面は、作品のなかで2回使われています。背中を丸めた古臭い松野時計店の主人は、まぎれもなく東野の父親そのものです。この時計店の主人は、やがて『秘密』の作品全体を左右する告白をおこないます。詳細については、ネタばらしになりますのでふれません。時計店の主人が、秘密を告白する場面は圧巻です。
東野作品は、常に読者を意識して描かれています。その根底には、客商売のプロだった父親の姿があります。プロの小説家としての東野圭吾は、父親を尊敬しています。客商売にたいする父親の思想が、読者のためにというプロ作家の哲学となって生きているのです。東野自身に語っていただきます。
――落ち着かない食事だったですよ。箸をとって、さあ一口食べようとすると、扉がギッと開く。今みたいに電子レンジなんかなかった時代ですから、親父はしょっちゅう冷めた味噌汁と御飯。かわいそうでしたけれど、客商売だったですからねぇ。(「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」より)
平介が預かった懐中時計をめぐって、松野時計店の主人・浩三と交わす会話を紹介します。
――昔よく出回った懐中時計だよ。しかも何度か修理している。悪いけど、骨董的な価値はないねえ」「そうなんですか……」「だけど、別の価値はあるよ。これでなきゃだめだっていう人もいるかもしれない」「どういうことですか?」「おまけが付いているんだよ、ほら」。浩三は立ち上がり、蓋を開けたまま懐中時計を平介の前に置いた。(本文より)
最近の時計は、使い捨てみたいに扱われています。東野圭吾にはそれが許せないのです。時計は時を刻むものですが、同時に1人の人生の生きざまをも刻んでいます。東野圭吾はそのことを実感しています。お客さんの思い出のときを再生する父親。時計は未来に向って進みますが、それは持ち主の歴史を内包してのものなのです。
松野浩三が告げた「おまけ」とはなにか。ここでは形としての「おまけ」がついているけれど、懐中時計にはすべからく見えない「おまけ」がついているんだよ。東野はそう信じているのでしょう。そうでなければ、腕時計や壁時計との温度差が説明できません。
(2009.06.13)
4.異なる二つの「実験」
東野圭吾は、大阪府立大学工学部を卒業しています。その後、自動車部品メーカーに勤めました。このときの体験も『秘密』に色濃く投影されています。
東野圭吾は大学時代の「実験」と、社会人になってからの「実験」は180度ちがうといいます。前者は実験によって導かれる結果が、最初からわかっています。わかっている結果どおりになれば、成功なのです。この退屈で単純で偶発性のない実験を、東野は嫌っていました。後者はなにもないところから、試行錯誤のすえになにかを見だす実験です。東野は熱心にとりくんだのは当然のことでしょう。
東野作品は、自動車部品メーカー勤務時代の「実験」に似ています。事実としての社会現象をベースとした、ミステリーは数多くあります。ところが東野はそれを好みません。素材としてあるのは、自分自身の過去の体験。そこから何かを構築するのが東野流なのです。
「実験」に関して、東野を象徴する資料があります。『探偵ガリレオ』(文春文庫、初出文藝春秋1998年)にたいする東野自身のコメントです。
――他の現象もすべて、一応科学的根拠に基づいて描いたつもりである。ただし実験はしていない。というより、現実問題として実験不可能な現象ばかりを扱っている。物理的に不可能なのではなく、道徳的に不可能なのだ。/実験はできないから、仮にやったとしたらこうなるだろうという予想が、本書の生命である。/たぶん確認実験などは誰にもされないだろうとタカをくくっている。」(「本の話」1998年6月号)
東野作品は、周到に容易された結末に向って書き進められてはいません。ぼんやりと思い描いた結末に向って、試行錯誤をくりかえします。社会人時代の「実験」と同じ手法で、作品をつむぎだしているのです。
また『秘密』のなかには、多くの「一応科学的根拠に基づいて描いたつもり」を象徴する場面が登場します。下請け会社に関する描写を引用してみましょう。なんのことなのかさっぱりわかりません。ただし『秘密』の構図を際立たせる効果はあります。
――D型インジェクタというのは、来年本格的にスタートする予定の製品だ。現在はそれを田端製作所で作っている。その試作品を使ってビグッドの研究者たちがテストを繰り返し、最終的な確認を行っているわけだ。」(本文117ページより)
(2001.06.30)
5.結婚生活への鎮魂歌
『秘密』には、もう一つ重要な体験が見え隠れしています。東野圭吾は25歳のときに結婚し、『秘密』の執筆前に離婚しています。その当時のことを、東野自身がつぎのように語っています。
――たぶん僕のなかで変わったものがあるとすれば、力が抜けたんだと思います。/夫として、妻の気持ちをわかろうというのは必要だと思うんです。でも、難しいですよね。/夫婦という関係を解消してしまったあとのほうが、相手の気持ちが見えてくるというか。一歩下がって見られるようになったというか……。( 「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」より)
夫婦の機微をみごとに描きだした『秘密』は、先に引用した言葉とは無縁ではありません。離婚の痛みを、新たなエネルギーにおきかえる。この作品は、東野圭吾の結婚生活への鎮魂歌なのかもしれません。
平介は若さを手に入れた直子に、嫉妬しはじめます。そしてすこしずつ夫婦の亀裂が深まってゆきます。私がもっとも心を動かされた場面があります。ちょっと長くなりますが、引用してみたいと思います。夫婦の危うい機微を、これほどまで的確に描き上げた文章をほかにはしりません。
――この夜の食事は、直子と結婚して以来最悪の晩餐となった。どちらも一言も口をきかず、ただ黙々と箸を動かした。かって何度か夫婦喧嘩をした時と決定的に違っていたのは、気まずさの底にあるのが怒りではなく悲しみだという点だ。平介は腹を立ててはいなかった。直子と自分との間にある、未来永劫埋まることのない溝の存在を認識し、たまらなく悲しくなっていた。そして同様の思いを彼女も抱いていることは、身体から発せられる雰囲気でわかった。皮肉なことに、こんな時だけ夫婦特有の以心伝心というものが働くのだった。(本文276ページより)
おそらくこの文章は、離婚を経験していなければ書けないでしょう。東野自身が書いているように、「相手を一歩下がってみられるようになった」ための所産といえるからです。
(2001.07.07)
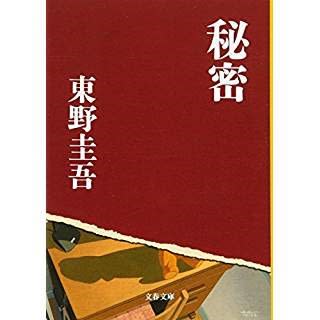
妻・直子と小学5年生の娘・藻奈美を乗せたバスが崖から転落。妻の葬儀の夜、意識を取り戻した娘の体に宿っていたのは、死んだはずの妻だった。その日から杉田家の切なく奇妙な〈秘密〉の生活が始まった。映画「秘密」の原作であり、98年度のベストミステリーとして話題をさらった長篇。(「BOOK」データベースより)
◎長い長い『秘密』の舞台裏に挑む
これから紹介するのは、私の最長の書評です。私はこれを「ミステリーZ」(2001年)というメルマガに連載しました。以下連載したものを引用させていただきます。
1.東野作品には、実体験がふんだんに反映されている
話題の作品『秘密』が文庫化されました。これを機会に何回かに分けて、『秘密』(文春文庫)の「秘密」に迫ってみたいと思います。すでに読んでしまった読者は多いと思いますが、東野圭吾をもっと深く知る一助になれば幸いです。断っておきますが、私は著者の追っかけではありません。読んだ作品もかぎられています。だから全作品を通しての作品論は書けません。
書棚をあさって出てきた初期作品は、『放課後』『卒業・雪月花殺人ゲーム』『学生街の殺人』(いずれも講談社文庫)と『白馬山荘殺人事件』(光文社文庫)だけでした。あとは単行本の最近の作品『白夜行』(集英社1999年)『片想い』(文藝春秋2001年3月)などです。こんな乏しい東野圭吾の読書体験で、『秘密』を語るのはおこがましいのですけれど、どうしても本質に迫ってみたい作品が『秘密』でした。
『秘密』の初出は、1998年9月文藝春秋刊です。文庫化されるまでに約3年を要しています。それだけ単行本が売れていたのでしょう。さもなければ、もっと早くに文庫化されているはずです。ちなみに本日、東京堂書店で確認してきました。書棚にあったのは、2001年2月印刷の28刷でした。
東京堂書店は、神田の古本屋街の裏通りにあり、私の知っているなかでは品揃え、書店としての美学・哲学などの面でナンバーワンの書店です。書泉グランデの真裏に位置していますので、一度のぞいてみていただきたいと思います。これぞ書店とうならせられるはずです。
話が横道にそれました。本題に入ります。『秘密』には東野圭吾の人生の断片が、いくつも埋め込まれています。東野圭吾のプロフィールを知るには、著者自身が書いているホームページを見ることをお薦めします。それを作品に重ねると、『秘密』のなかから著者自身の思いが見えてきます。
東野自身が書いたプロフィールを眺めてみます(文中のかぎカッコ内は引用部分)。東野圭吾は1958年「大阪市生野区にある、しけた時計メガネ貴金属の小売店で、3人姉弟の末っ子として生まれ」ました。
1962年自宅から1キロほど離れた公園で迷子になります。「迷子になった公園は、1999年発表の『白夜行』の冒頭に登場」します。両親は大相撲に夢中になり、気がつかなかったようです。1964年「大阪市立小路小学校に入学します。(中略)この年、東京オリンピックがあったはずだ」。「給食については苦い思い出が多々ある」。詳しく知りたい方は『あの頃ぼくらはアホでした』(集英社文庫)を読んで下さい」
プロフィールは、実にていねいに書かれています。コピーをとったら、A4サイズで5枚にもなりました。ここまでの引用は、まだ1枚目のコピーの半分だけです。東野圭吾は自分の過去を、重要なファクターとして描きます。そのあたりのことを、著者自身はつぎのように語っています。
――作品には今までの生き方や、経験がかなり反映されています。意識の中にある何らかの記憶なり、想い出なりに基づいて、ある部分を引き出し、拡大して、という作業で作品を仕上げることもありますし。無意識のうちに、過去の自分も投影されていると思いますし。作品と自分の経験が無関係ですとは決して言えないですね。(「ダ・ヴィンチ」2000年2月号「『秘密』がおしえるココロのヒミツ」栗田昌裕との対談)
東野自身の書いたプロフィールのなかからも、前記のごとく実体験と作品の関係が2つもでてきます。次回は『秘密』のなかから、東野圭吾の過去と重なる部分を拾ってみたいと思います。東野の人生がどう作品に反映されているのか。そのあたりを検証してみますのでお楽しみに。
(2009.06.11)
2.とことん「時計」にこだわりを示す『秘密』
松野時計店、懐中時計、壁時計、腕時計、札幌の時計台と、『秘密』のなかには数多くの「時計」が登場します。これは東野自身が、時計メガネ貴金属の小売店で生まれたためだけではありません。東野はとことん「時計」にたいするこだわりをもっています。東野自身の「時計」に関するエピソードを紹介しましょう。
東野は少なくとも1999年夏までは、文字盤の大きなクオーツの腕時計を愛用しています。就職祝に父親からもらったものです。ブランド品ではありません。(「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」を参照しました)
今でも愛用しているのか否かはわかりません。なぜなら東野圭吾の写真は、いずれも長袖シャツを着用していて、袖口が確認できないからです。どなたか腕時計が写っている写真をおもちでしたら、教えていただきたいと思います。私はいまだに、文字盤の大きなクオーツを身につけていると思っています。
主人公・平介は、もちろん腕時計くらいはしています。しかし、平介が腕時計に目をやることはあまりありません。どうして、と思う場面でも腕時計には目をやりません。作品のなかで、平介が腕時計を見るのは2回だけです。それも建物や食べ物に対するディテールに比べると、腕時計に関する説明はあまりにもそっけないものです。まるで詳細を書くことを避けているように、投げやりな記述になっています。
――彼(平介)は腕時計を見た。午前十一時を回ったところだった。今から急いで会社に戻っても、すぐに昼休みだ。(本文174ページより)
――翌日、平介は帰りが少し遅くなった。腕時計の針は八時十五分を指している。(本文209ページより)
腕時計ではなく、壁時計に目をやる場面は何度かあります。あるいは、時間の確認をした対象を明確にしないままの記述もあります。壁時計についても、ディテールは明確にされていません。東野が大切にしているのは、過去の思い出が染み込んだ時計のみのようです。あとは時計は単なる時を刻む道具として、大きな価値を認めていないといえます。
――祭壇をセットし終えると、彼(平介)は喪服から普段着に着替えた。壁の時計は午後五時三十五分を指している。(本文より)
――時刻は午後二時を少し回っていた。パンフレットによれば文化祭は五時までだ。彼は急いで支度を始めた。(本文より)
――受話器を置いた平介の胃袋には、しこりのようなものが生じていた。彼は時計を見た。(本文より)
いかがでしょうか。他にも目覚まし時計を見たりと、時刻を確認する場面はあります。しかしいずれも、前記の引用部分と差異はありません。時計に関しては、東野らしくないあっさりし過ぎの表現しか見つからないのです。
ところが懐中時計については、とことんこだわりを示します。実に詳細な記述がつづきます。これは単に、時を刻むものではないからです。就職祝いに父親からもらった腕時計を、東野は「文字盤の大きな、ブランド品ではない、クオーツ」とディテールを説明していることと考え合わせていただきたいと思います。
東野にとって、思い出につながる時計にこそ価値があるのです。事故を起こしたバス運転手・故梶川の妻は、夫のあとを追うように死亡します。平介は梶川の形見である懐中時計を、孤児・逸美より託されます。
――大きさは直径が五センチほどだ。銀色をしている。斜め上に竜頭がついていた。蓋を開けようとした。ところが金具がひっかかっているのか、指先にどんな力を込めても開けられなかった。(本文217ページより)
腕時計や壁時計とは比較にならないほど、詳細を書きこんでいます。さらに「時計」にまつわる、つぎのような場面があります。札幌へ出張した平介は、時間潰しも兼ねて有名な時計台を訪れます。
――タクシーは間もなく太い道路脇に止まった。なぜこんなところに止まったのだろうと思っていると、「あれです」と運転手が道の反対側を指差した。/「あれか……」平介は苦笑した。たしかに写真などから描いたイメージとは大違いだった。屋根についた、ただの白い洋風家屋といえた。(本文238ページより)
札幌の時計台も、陳腐なものにしか過ぎません。平介に一笑にふされた札幌時計台の描写は、松野時計店のそれと比べると違いは歴然としています。松野時計店や懐中時計については、次回にもっと掘り下げてみたいと思います。
(2001.06.30)
3.松野時計店は、東野の生家そのもの
遅くなりましたが、『秘密』のストーリーを確認しておきたいと思います。主人公・杉田平介は、自動車部品メーカーに勤務する40歳前の働き盛り。妻・直子と娘・藻奈美に囲まれ、都内のマイホームで幸せに暮しています。そこへ突然の災難がふりかかります。妻と娘がバス事故にまきこまれ、病院へ搬入されるのです。
妻・直子は死亡し、娘・藻奈美だけが奇跡的に一命をとどめます。目覚めた藻奈美は、平介に自分は直子だと主張します。肉体は娘のものですが、人格は妻・直子のものなのです。主人公・平介の奇妙な日常がはじまります。
このなかで生家の時計メガネ貴金属店は、重要な役割として登場します。
――出張を明日に控えた木曜日、平介は定時で会社を抜けさせてもらい、その足で荻窪に行った。そこにある一軒の時計屋に用があった。(本文より)
時計屋の場面は、作品のなかで2回使われています。背中を丸めた古臭い松野時計店の主人は、まぎれもなく東野の父親そのものです。この時計店の主人は、やがて『秘密』の作品全体を左右する告白をおこないます。詳細については、ネタばらしになりますのでふれません。時計店の主人が、秘密を告白する場面は圧巻です。
東野作品は、常に読者を意識して描かれています。その根底には、客商売のプロだった父親の姿があります。プロの小説家としての東野圭吾は、父親を尊敬しています。客商売にたいする父親の思想が、読者のためにというプロ作家の哲学となって生きているのです。東野自身に語っていただきます。
――落ち着かない食事だったですよ。箸をとって、さあ一口食べようとすると、扉がギッと開く。今みたいに電子レンジなんかなかった時代ですから、親父はしょっちゅう冷めた味噌汁と御飯。かわいそうでしたけれど、客商売だったですからねぇ。(「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」より)
平介が預かった懐中時計をめぐって、松野時計店の主人・浩三と交わす会話を紹介します。
――昔よく出回った懐中時計だよ。しかも何度か修理している。悪いけど、骨董的な価値はないねえ」「そうなんですか……」「だけど、別の価値はあるよ。これでなきゃだめだっていう人もいるかもしれない」「どういうことですか?」「おまけが付いているんだよ、ほら」。浩三は立ち上がり、蓋を開けたまま懐中時計を平介の前に置いた。(本文より)
最近の時計は、使い捨てみたいに扱われています。東野圭吾にはそれが許せないのです。時計は時を刻むものですが、同時に1人の人生の生きざまをも刻んでいます。東野圭吾はそのことを実感しています。お客さんの思い出のときを再生する父親。時計は未来に向って進みますが、それは持ち主の歴史を内包してのものなのです。
松野浩三が告げた「おまけ」とはなにか。ここでは形としての「おまけ」がついているけれど、懐中時計にはすべからく見えない「おまけ」がついているんだよ。東野はそう信じているのでしょう。そうでなければ、腕時計や壁時計との温度差が説明できません。
(2009.06.13)
4.異なる二つの「実験」
東野圭吾は、大阪府立大学工学部を卒業しています。その後、自動車部品メーカーに勤めました。このときの体験も『秘密』に色濃く投影されています。
東野圭吾は大学時代の「実験」と、社会人になってからの「実験」は180度ちがうといいます。前者は実験によって導かれる結果が、最初からわかっています。わかっている結果どおりになれば、成功なのです。この退屈で単純で偶発性のない実験を、東野は嫌っていました。後者はなにもないところから、試行錯誤のすえになにかを見だす実験です。東野は熱心にとりくんだのは当然のことでしょう。
東野作品は、自動車部品メーカー勤務時代の「実験」に似ています。事実としての社会現象をベースとした、ミステリーは数多くあります。ところが東野はそれを好みません。素材としてあるのは、自分自身の過去の体験。そこから何かを構築するのが東野流なのです。
「実験」に関して、東野を象徴する資料があります。『探偵ガリレオ』(文春文庫、初出文藝春秋1998年)にたいする東野自身のコメントです。
――他の現象もすべて、一応科学的根拠に基づいて描いたつもりである。ただし実験はしていない。というより、現実問題として実験不可能な現象ばかりを扱っている。物理的に不可能なのではなく、道徳的に不可能なのだ。/実験はできないから、仮にやったとしたらこうなるだろうという予想が、本書の生命である。/たぶん確認実験などは誰にもされないだろうとタカをくくっている。」(「本の話」1998年6月号)
東野作品は、周到に容易された結末に向って書き進められてはいません。ぼんやりと思い描いた結末に向って、試行錯誤をくりかえします。社会人時代の「実験」と同じ手法で、作品をつむぎだしているのです。
また『秘密』のなかには、多くの「一応科学的根拠に基づいて描いたつもり」を象徴する場面が登場します。下請け会社に関する描写を引用してみましょう。なんのことなのかさっぱりわかりません。ただし『秘密』の構図を際立たせる効果はあります。
――D型インジェクタというのは、来年本格的にスタートする予定の製品だ。現在はそれを田端製作所で作っている。その試作品を使ってビグッドの研究者たちがテストを繰り返し、最終的な確認を行っているわけだ。」(本文117ページより)
(2001.06.30)
5.結婚生活への鎮魂歌
『秘密』には、もう一つ重要な体験が見え隠れしています。東野圭吾は25歳のときに結婚し、『秘密』の執筆前に離婚しています。その当時のことを、東野自身がつぎのように語っています。
――たぶん僕のなかで変わったものがあるとすれば、力が抜けたんだと思います。/夫として、妻の気持ちをわかろうというのは必要だと思うんです。でも、難しいですよね。/夫婦という関係を解消してしまったあとのほうが、相手の気持ちが見えてくるというか。一歩下がって見られるようになったというか……。( 「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」より)
夫婦の機微をみごとに描きだした『秘密』は、先に引用した言葉とは無縁ではありません。離婚の痛みを、新たなエネルギーにおきかえる。この作品は、東野圭吾の結婚生活への鎮魂歌なのかもしれません。
平介は若さを手に入れた直子に、嫉妬しはじめます。そしてすこしずつ夫婦の亀裂が深まってゆきます。私がもっとも心を動かされた場面があります。ちょっと長くなりますが、引用してみたいと思います。夫婦の危うい機微を、これほどまで的確に描き上げた文章をほかにはしりません。
――この夜の食事は、直子と結婚して以来最悪の晩餐となった。どちらも一言も口をきかず、ただ黙々と箸を動かした。かって何度か夫婦喧嘩をした時と決定的に違っていたのは、気まずさの底にあるのが怒りではなく悲しみだという点だ。平介は腹を立ててはいなかった。直子と自分との間にある、未来永劫埋まることのない溝の存在を認識し、たまらなく悲しくなっていた。そして同様の思いを彼女も抱いていることは、身体から発せられる雰囲気でわかった。皮肉なことに、こんな時だけ夫婦特有の以心伝心というものが働くのだった。(本文276ページより)
おそらくこの文章は、離婚を経験していなければ書けないでしょう。東野自身が書いているように、「相手を一歩下がってみられるようになった」ための所産といえるからです。
(2001.07.07)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます