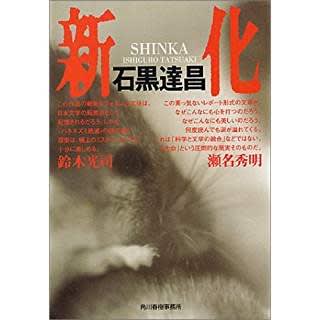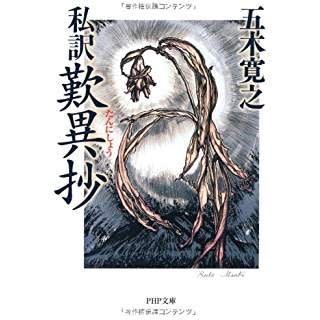池田晶子『14歳からの哲学』(トランスビュー)

人には14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある!今の学校教育に欠けている、14、5歳からの「考える」ための教科書。 「言葉」「自分とは何か」「死」「心」「体」「他人」「家族」「社会」「規則」「理想と現実」「友情と愛情」「恋愛と性」「仕事と生活」「メディアと書物」「人生」など30のテーマを取り上げる。読書感想文の定番,中高大学入試にも頻出の必読書。年代を超えて読み継がれる著者の代表作。(本書案内より)
◎哲学することの意味
本書はちまたの「哲学」関連本とは、まったくちがっています。私の書棚にはたくさんの「わかりやすい哲学」「哲学入門」などの書籍があります。大学時代はそれこそ「デカンショー」を読んでいなければ、恥ずかしいという強迫観念にかられていました。読んでみてもさっぱりわかりませんでした。そのあげく簡便本でお茶をにごしていたのでしょう。デカンショーが、「デカンショ」は、「デカルト」「カント」「ショーペンハウエル」の略であることは、年配の人ならご存知でしょう。
私が本書を読んだのは、年金受給者になってからです。孫にプレゼントするような顔をして、自分のために買い求めました。読んでみました。「1.考える」のページから、早くもストンとなにかが腑におちてきました。
――生きていることが素晴らしかったりつまらなかったりするのは、自分がそれを素晴らしいと思ったり、つまらないと思ったりしているからなんだ。(本文P5より)
――君は、つまらないことをつまらないと思わないこともできるはず。(本文P5より)
私が営業リーダー時代、不愉快そうにしている部下がいました。私は笑いながら彼の肩をたたいて、「声にだして、不愉快だ、と10回くりかえしてごらん」といいます。呪文のように「不愉快だ」をいっている彼は、途中から「愉快だ」といっています。「ほら、不愉快が愉快になっただろう」。若いころのこんな場面がよみがえってきました。
池田晶子が説いている世界は、心の中のこと、あるいは考え方についてですが、じつにわかりやすい言葉で諭してくれます。
――自分では正しいと思っているんだけど、本当は間違っているという場合は、どうしたものだろう。自分では絶対に正しいと思っているんだけど、本当はまったく間違っていて、そのこと気がつかずに、大きな声でそれを主張しているとしたら、これはすごく恥ずかしいことなんじゃないだろうか。(本文P13より)
池田晶子は「考えよう」とくりかえします。そして「思う」と「考える」のちがいについて、言及してみせます。井上ひさしの著作にもこの2つのちがいにふれているものがあります。出典はわすれましたが、こんな感じです。
「マンションを買おうと思う」
「マンションを買おうかと考えている」
ちがいを説明できますか?
前者は漠然としている心理状態です。後者はAかBかなどと、選択にまよっているレベルの表現です。
◎「友情と愛情」をじっくりと考える
池田晶子は難解な哲学用語を、いっさい封印しています。また先達の哲学者の言葉を、寸借することもしていません。まるで目の前の14歳に、話しかけているような感じです。後半は「17歳からの哲学」という章となり、「自由」や「宗教」などについても示唆してくれます。
「15友情と愛情」の章をくわしく紹介させていただきます。本書が従前の哲学書とは、ちがうことを実感していただくためです。14歳というと「友だち関係で悩んでいる人が多いみたいだ」と前おきしてから、「友だちが少ない」などと具体例を列挙します。そして「単なる遊び友だち」と「大事なことを語り合える友だち」との違いを示してみせます。
――本当の友情というのは、自分の孤独に耐えられる者同士の間でなければ、生まれるものでは決してないんだ。なぜだと思う?/自分の孤独に耐えられるということは、自分で自分を認めることができる、自分を愛することができるということなんだ。そして、自分を愛することができない人に、どうして他人を愛することができるだろう。(本文P100より)
――孤独というのはいいものだ。友情もいいけど、孤独というのも本当にいいものなんだ。今は孤独というとイヤなもの、逃避か引きこもりとしか思われていないけれども、それはその人が自分を愛する仕方を知らないからなんだ。自分を愛する、つまり自分で自分を味わう仕方を覚えると、その面白さは、つまらない友だちといることなんかより、はるかに面白い。(本文P100-101より)
――自分を愛し、孤独を味わえる者同士が、幸運にも出会うことができたなら、そこに生まれる友情こそが素晴らしい。お互いにそれまで一人で考え、考えを深めてきた大事な事柄について、語り合い、確認し、触発し合うことで、いっそう考えを深めてゆくことが出来るんだ。(本文P101より)
この流れは、心底いいなと思います。おしつけがましくなく、断定形でもなく、池田晶子は病床に見舞いにきた人のように、静かに淡々と語ります。私は若い営業マンや営業リーダーに向けて、たくさんの本を書いています。『14歳からの哲学』にふれてみて、絶叫調の自分の著作が恥ずかしくなりました。
「愛情」についても、こんなヒユがありなのか、と思わず納得してしまいました。引用してみます。
――もしも君が、犬や猫やハムスターや、自分のペットを買っているなら、彼らに対する気持ち、あれが愛情の原点だ。大事で、いとおしくて、何がどうなのであれ、居てくれればそれでいいと思うだろう。少々噛みつかれたりひっかかれたりしても、まあコイツのすることならいいやって、許しちゃうだろ。つまり、彼らのすべてを丸ごと受け容れて認めること、無条件の愛情だ。愛情というのは無条件であるものなんだ。ただ、ペットの場合は、彼らの方が無条件でなついてくるから、人間の方も無条件で受け容れやすい。(本文P101より)
「自分を愛する」のは、とてもたいせつなことです。それは最終的に社会や世界を愛することになります。
池田晶子の『14歳からの哲学』の「あとがき」を、紹介させていただきます。あとがきは、「14歳の人へ」と「14歳以上の人へ」と区分されています。
あとがきの「14歳のきみへ」では書店や図書館へいけば、おびただしい数の「哲学」と出会うことができる、と書きだされています。
――でも、たとえ今の君がそれらの本を手に取って読んでみても、聞きなれない言葉や変な言い回しがいっぱい出てきて、おそらくちんぷんかんぷんでしょう。。
――君が求めているのは、「考えて、知る」ことであって、「読んで、覚える」ことではないからです。自分で考えて知るために、他人の本を読んで覚える必要はありません。
「14歳以上の人へ」のポイントも、紹介させていただきます。
――対象はいちおう14歳の人、語り口もそのように工夫しましたが、内容的なレベルは少しも落としていません。落とせるはずがありません。なぜなら、ともに考えようとしているのは、万人もしくは人類に共通の「存在の謎」だからです。
――子供とともに、生徒とともに、あるいは一人で、なお謎を考えて知りたいという意欲をおもちのいかなる年齢の人にも、何らかお役に立てるものと思っております。
『14歳からの哲学』(トランスビュー)は、地道に売れています。やさしい本ではありません。私自身も3回読み直し、書評を書いています。「自分とはだれか」「他人とはなにか」「死をどう考えるか」など、避けてはとおれない難解なテーマが、びっしりとならんでいます。本書の初出は2003年なのですが、哲学の古典みたいに評価は高まるいっぽうです。
一つひとつの問いかけごとに、活字から目を離して考えてみました。こんな世界を、まともに考えたことはありませんでした。それゆえ、おおいなる刺激をあたえられました。
◎自分の頭で考えなさい
――生命体を維持するための食欲、子孫を繁殖するための性欲、じゃあ恋愛は、何のためにするものだろう。自然法則にとっては恋愛なんて、無用のものでしかないはずだ。もし恋愛が自然の本能だったら、恋愛の相手は、誰でもいいのでなければおかしいね。子孫を増やすためだけなのだったら、雄と雌であればいいはずだよね。(本文P106より)
著者の問いかけのひとつを紹介してみました。では生きるってなにか。読者は、ひたすら考えまくることになります。14歳には難しい設問ですが、一度は考えておきたいテーマです。
本書は、自分の頭で「考えなさい」と一貫しています。水辺まで読者をつれていき、そこで放りだします。考える習慣をつけるためには、うってつけの「教科書」だと思います。そういえば本書のサブタイトルは、「考えるための教科書」でした。
池田晶子の著作は、文庫化されているものもたくさんあります。「哲学」は敷居が高いと考えているのなら、何冊か手にしていただきたいと思います。ざっとあげてみます。
『ソクラテスよ、哲学は悪妻に訊け』(新潮文庫)
『メタフィジカル・バンチー 形而上より愛をこめて』(文春文庫)
『考える人・口伝西洋哲学史』(中公文庫)
『帰ってきたソクラテス』(新潮文庫)
『さようならソクラテス』(新潮文庫絶版)
本書を卒業したら、すばらしいアンソロジーがあります。北上次郎編『14歳の本棚』(新潮文庫)です。本書は「部活学園編」「初恋友情編」「家族兄弟編」とテーマごとに3冊になっています。とりあげている作品に味があります。本書は「知・教養・古典ジャンル」の125+αとしてとりあげる予定です。
(山本藤光:2010.05.13初稿、2018.03.02改稿)

人には14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある!今の学校教育に欠けている、14、5歳からの「考える」ための教科書。 「言葉」「自分とは何か」「死」「心」「体」「他人」「家族」「社会」「規則」「理想と現実」「友情と愛情」「恋愛と性」「仕事と生活」「メディアと書物」「人生」など30のテーマを取り上げる。読書感想文の定番,中高大学入試にも頻出の必読書。年代を超えて読み継がれる著者の代表作。(本書案内より)
◎哲学することの意味
本書はちまたの「哲学」関連本とは、まったくちがっています。私の書棚にはたくさんの「わかりやすい哲学」「哲学入門」などの書籍があります。大学時代はそれこそ「デカンショー」を読んでいなければ、恥ずかしいという強迫観念にかられていました。読んでみてもさっぱりわかりませんでした。そのあげく簡便本でお茶をにごしていたのでしょう。デカンショーが、「デカンショ」は、「デカルト」「カント」「ショーペンハウエル」の略であることは、年配の人ならご存知でしょう。
私が本書を読んだのは、年金受給者になってからです。孫にプレゼントするような顔をして、自分のために買い求めました。読んでみました。「1.考える」のページから、早くもストンとなにかが腑におちてきました。
――生きていることが素晴らしかったりつまらなかったりするのは、自分がそれを素晴らしいと思ったり、つまらないと思ったりしているからなんだ。(本文P5より)
――君は、つまらないことをつまらないと思わないこともできるはず。(本文P5より)
私が営業リーダー時代、不愉快そうにしている部下がいました。私は笑いながら彼の肩をたたいて、「声にだして、不愉快だ、と10回くりかえしてごらん」といいます。呪文のように「不愉快だ」をいっている彼は、途中から「愉快だ」といっています。「ほら、不愉快が愉快になっただろう」。若いころのこんな場面がよみがえってきました。
池田晶子が説いている世界は、心の中のこと、あるいは考え方についてですが、じつにわかりやすい言葉で諭してくれます。
――自分では正しいと思っているんだけど、本当は間違っているという場合は、どうしたものだろう。自分では絶対に正しいと思っているんだけど、本当はまったく間違っていて、そのこと気がつかずに、大きな声でそれを主張しているとしたら、これはすごく恥ずかしいことなんじゃないだろうか。(本文P13より)
池田晶子は「考えよう」とくりかえします。そして「思う」と「考える」のちがいについて、言及してみせます。井上ひさしの著作にもこの2つのちがいにふれているものがあります。出典はわすれましたが、こんな感じです。
「マンションを買おうと思う」
「マンションを買おうかと考えている」
ちがいを説明できますか?
前者は漠然としている心理状態です。後者はAかBかなどと、選択にまよっているレベルの表現です。
◎「友情と愛情」をじっくりと考える
池田晶子は難解な哲学用語を、いっさい封印しています。また先達の哲学者の言葉を、寸借することもしていません。まるで目の前の14歳に、話しかけているような感じです。後半は「17歳からの哲学」という章となり、「自由」や「宗教」などについても示唆してくれます。
「15友情と愛情」の章をくわしく紹介させていただきます。本書が従前の哲学書とは、ちがうことを実感していただくためです。14歳というと「友だち関係で悩んでいる人が多いみたいだ」と前おきしてから、「友だちが少ない」などと具体例を列挙します。そして「単なる遊び友だち」と「大事なことを語り合える友だち」との違いを示してみせます。
――本当の友情というのは、自分の孤独に耐えられる者同士の間でなければ、生まれるものでは決してないんだ。なぜだと思う?/自分の孤独に耐えられるということは、自分で自分を認めることができる、自分を愛することができるということなんだ。そして、自分を愛することができない人に、どうして他人を愛することができるだろう。(本文P100より)
――孤独というのはいいものだ。友情もいいけど、孤独というのも本当にいいものなんだ。今は孤独というとイヤなもの、逃避か引きこもりとしか思われていないけれども、それはその人が自分を愛する仕方を知らないからなんだ。自分を愛する、つまり自分で自分を味わう仕方を覚えると、その面白さは、つまらない友だちといることなんかより、はるかに面白い。(本文P100-101より)
――自分を愛し、孤独を味わえる者同士が、幸運にも出会うことができたなら、そこに生まれる友情こそが素晴らしい。お互いにそれまで一人で考え、考えを深めてきた大事な事柄について、語り合い、確認し、触発し合うことで、いっそう考えを深めてゆくことが出来るんだ。(本文P101より)
この流れは、心底いいなと思います。おしつけがましくなく、断定形でもなく、池田晶子は病床に見舞いにきた人のように、静かに淡々と語ります。私は若い営業マンや営業リーダーに向けて、たくさんの本を書いています。『14歳からの哲学』にふれてみて、絶叫調の自分の著作が恥ずかしくなりました。
「愛情」についても、こんなヒユがありなのか、と思わず納得してしまいました。引用してみます。
――もしも君が、犬や猫やハムスターや、自分のペットを買っているなら、彼らに対する気持ち、あれが愛情の原点だ。大事で、いとおしくて、何がどうなのであれ、居てくれればそれでいいと思うだろう。少々噛みつかれたりひっかかれたりしても、まあコイツのすることならいいやって、許しちゃうだろ。つまり、彼らのすべてを丸ごと受け容れて認めること、無条件の愛情だ。愛情というのは無条件であるものなんだ。ただ、ペットの場合は、彼らの方が無条件でなついてくるから、人間の方も無条件で受け容れやすい。(本文P101より)
「自分を愛する」のは、とてもたいせつなことです。それは最終的に社会や世界を愛することになります。
池田晶子の『14歳からの哲学』の「あとがき」を、紹介させていただきます。あとがきは、「14歳の人へ」と「14歳以上の人へ」と区分されています。
あとがきの「14歳のきみへ」では書店や図書館へいけば、おびただしい数の「哲学」と出会うことができる、と書きだされています。
――でも、たとえ今の君がそれらの本を手に取って読んでみても、聞きなれない言葉や変な言い回しがいっぱい出てきて、おそらくちんぷんかんぷんでしょう。。
――君が求めているのは、「考えて、知る」ことであって、「読んで、覚える」ことではないからです。自分で考えて知るために、他人の本を読んで覚える必要はありません。
「14歳以上の人へ」のポイントも、紹介させていただきます。
――対象はいちおう14歳の人、語り口もそのように工夫しましたが、内容的なレベルは少しも落としていません。落とせるはずがありません。なぜなら、ともに考えようとしているのは、万人もしくは人類に共通の「存在の謎」だからです。
――子供とともに、生徒とともに、あるいは一人で、なお謎を考えて知りたいという意欲をおもちのいかなる年齢の人にも、何らかお役に立てるものと思っております。
『14歳からの哲学』(トランスビュー)は、地道に売れています。やさしい本ではありません。私自身も3回読み直し、書評を書いています。「自分とはだれか」「他人とはなにか」「死をどう考えるか」など、避けてはとおれない難解なテーマが、びっしりとならんでいます。本書の初出は2003年なのですが、哲学の古典みたいに評価は高まるいっぽうです。
一つひとつの問いかけごとに、活字から目を離して考えてみました。こんな世界を、まともに考えたことはありませんでした。それゆえ、おおいなる刺激をあたえられました。
◎自分の頭で考えなさい
――生命体を維持するための食欲、子孫を繁殖するための性欲、じゃあ恋愛は、何のためにするものだろう。自然法則にとっては恋愛なんて、無用のものでしかないはずだ。もし恋愛が自然の本能だったら、恋愛の相手は、誰でもいいのでなければおかしいね。子孫を増やすためだけなのだったら、雄と雌であればいいはずだよね。(本文P106より)
著者の問いかけのひとつを紹介してみました。では生きるってなにか。読者は、ひたすら考えまくることになります。14歳には難しい設問ですが、一度は考えておきたいテーマです。
本書は、自分の頭で「考えなさい」と一貫しています。水辺まで読者をつれていき、そこで放りだします。考える習慣をつけるためには、うってつけの「教科書」だと思います。そういえば本書のサブタイトルは、「考えるための教科書」でした。
池田晶子の著作は、文庫化されているものもたくさんあります。「哲学」は敷居が高いと考えているのなら、何冊か手にしていただきたいと思います。ざっとあげてみます。
『ソクラテスよ、哲学は悪妻に訊け』(新潮文庫)
『メタフィジカル・バンチー 形而上より愛をこめて』(文春文庫)
『考える人・口伝西洋哲学史』(中公文庫)
『帰ってきたソクラテス』(新潮文庫)
『さようならソクラテス』(新潮文庫絶版)
本書を卒業したら、すばらしいアンソロジーがあります。北上次郎編『14歳の本棚』(新潮文庫)です。本書は「部活学園編」「初恋友情編」「家族兄弟編」とテーマごとに3冊になっています。とりあげている作品に味があります。本書は「知・教養・古典ジャンル」の125+αとしてとりあげる予定です。
(山本藤光:2010.05.13初稿、2018.03.02改稿)