
『暑中お見舞い申し上げます』といえば、我々の世代だとキャンディーズの「ウ~ゥフン♪」になってしまいます。けれども(前にも書いたけど)私が好きなのは前年76年の『夏が来た!』。幅広い年齢層に受け入れられ大ヒットした『春一番』の次のシングル曲でしたが、「春の次は夏かよ」と安易に思われてしまったのか、『春一番』に続くことはできませんでした。
(『夏が来た』の不振を考慮して?次のシングル『ハート泥棒』では、キャンディーズを不動の地位に押し上げた『年下の男の子』路線に戻り、以後『哀愁のシンフォニー』『やさしい悪魔』『暑中お見舞い申し上げます』『アン・ドゥ・トロワ』『わな』『微笑がえし』と、解散までヒット曲が目白押し)
キャンディーズのシングル曲は全部で17曲。
(『つばさ』は彼女たちの意向に反して解散後に発売されたものなのでカウントしない)
『夏が来た!』はちょうど10曲目になります。スタンダードになった『春一番』の陰に隠れてしまっていますが、意外とこの曲のファンが多かったんですね。【YouTube】でも、ツーバージョンの『夏が来た!』を見ることができます。「おおっ!」と思ったのですが、歌っている姿を見たのは初めてかもしれません。
『夏が来た!』を聴くと、その夏の自転車旅行をところどころ鮮明に思い出します。
高校に入って最初の夏休みに、中学時代の友人と6泊7日の行程で伊豆半島を一周しました。原則野宿ということで、事前に宿を予約したのは二日目の修善寺ユースホステル(YH)だけ、後は行き当たりばったりの旅行です。
今となっては、修善寺YHだけ予約した理由がよくわからないのですが、幽霊スポットとして当時有名だった旧天城トンネルを走ろうということから修善寺に宿泊する必要があったのか、修善寺YHの評判が良かったのか、そんなところでしょう。いざ、小雨降る旧天城トンネルの前に立つと足がすくんでしまい、一同顔を見合わせるやUターンして新トンネルを走りました・・・。
(修善寺ユースホステルを調べたら、当時と同じつくりで今も健在でした!)
初めての自転車旅行は、体力面では全く問題なかったのですが、精神面では腰砕けの連続でした。旅の初日に真鶴の海岸で野宿したときは、あまりの暑さと蚊に悩まされて(それに、夜の海は真っ黒で怖い)ろくに眠れず、翌日はヒイヒイ言いながら峠を登ったら、その先は自転車通行禁止の有料道路でUターンを余議なくされ、「誰がこんな道を選んだんだ~」と険悪な雰囲気になりました。
(でも、修善寺YHが良いところで、和やかに戻る)
三日目は天城を越えて雨降る下田の神社で野宿することになったのですが、23時頃になって夜の神社のあまりの恐ろしさに一同尻尾を巻いて逃げ出し、最終電車が行った後だからと、伊豆急「下田」駅の改札前で毛布代わりにテントをかぶって泥のように眠っていたら、始発電車が走る頃でしょうか、駅員に「大丈夫ですか?」と起こされ、体よく追い出されました(当たり前です)。
これですっかり野宿に懲りてしまい、四日目&五日目はバンガローや民宿(YHだったかもしれない)に泊まったのですが、あまりの快適さに感激すると同時に猛省して、最後ぐらいはちゃんとテントを張って寝ようと、大瀬の海水浴場で野宿し、翌日、三島から一気に箱根の山を越え、その日の深夜、帰宅しました。
だらだらと夏の思い出話を綴ってしまいましたが、快適な宿のいささかカビ臭い畳の上に寝転んで漫画などを読んでいるときに聴こえてきたのが、キャンディーズの『夏が来た!』だったのです。
「夏が来れば思い出す~♪ 」青春のひとコマかな?
緑が空の青さに輝いて 部屋のカーテンと同じ色になっても
少しどこかが違うのは きっと生きているからだろうなんて考えて
なぜか君に逢いたい
砂の上に髪を広げて 寝ころんで 夢を見て
こんな不思議な出来事が あっていいものかと思うくらい
幸せな雲が風に踊るよ
季節が僕の背中に焼きついて 白いサンダルが似合うようになったら
今日はそうだよ少しだけ 大人のふりしてみようなんて考えて
君に電話かけるよ
波の上に体浮かべて 思いきり背伸びして
こんな不思議な出来事が あっていいものかと思うくらい
爽やかな雲が風に踊るよ
 「夏が来た」 → クリックすると曲が聴けます
「夏が来た」 → クリックすると曲が聴けます 君に電話はしなかったけど、Tシャツが汗で背中に貼りつき、波の上に体浮かべて白い雲を眺め、サザエを採って食べたっけ。ああっ、あの日に帰りたい?
君に電話はしなかったけど、Tシャツが汗で背中に貼りつき、波の上に体浮かべて白い雲を眺め、サザエを採って食べたっけ。ああっ、あの日に帰りたい?













 思いがけず、高校時代のミューズに再会できて感激するニワトリ・・・当時、山崎ハコの曲を聴くというより、彼女がDJを務めていた「オールナイト・ニッポン」(2部=3:00~5:00am)を毎週欠かさず聴いていました(確か火曜の深夜だったと思う)。おかげで、学校に遅刻しまくって・・・。
思いがけず、高校時代のミューズに再会できて感激するニワトリ・・・当時、山崎ハコの曲を聴くというより、彼女がDJを務めていた「オールナイト・ニッポン」(2部=3:00~5:00am)を毎週欠かさず聴いていました(確か火曜の深夜だったと思う)。おかげで、学校に遅刻しまくって・・・。
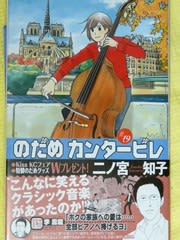
 今年のお正月に『のだめカンタービレ新春スペシャル(仮)~パリ篇』が放送されます。ドラマの方では、峰&清良はもちろん、真澄ちゃんも見られるそうです。噂のキャストで、今一つ不安なのがフランクとターニャ。彼&彼女しかいないと言われれば確かにその通りなんだけど・・・
今年のお正月に『のだめカンタービレ新春スペシャル(仮)~パリ篇』が放送されます。ドラマの方では、峰&清良はもちろん、真澄ちゃんも見られるそうです。噂のキャストで、今一つ不安なのがフランクとターニャ。彼&彼女しかいないと言われれば確かにその通りなんだけど・・・


 (それから、黒木君をもっと登場させて~~)
(それから、黒木君をもっと登場させて~~)




 『プレミアム10 ~サウンド・オブ・ミュージック マリアが語る一家の物語』の再放送が決定しました! サチさん、ようやく見られます。バンザ~イ!! → 3月21日(水)午後1時05分~2時33分放送予定。
『プレミアム10 ~サウンド・オブ・ミュージック マリアが語る一家の物語』の再放送が決定しました! サチさん、ようやく見られます。バンザ~イ!! → 3月21日(水)午後1時05分~2時33分放送予定。








