「律法学者ゼナスとアポロが何も不足することがないように、その旅立ちをしっかりと支えてあげてください。」(テトス3:13新改訳)
ローマ帝国中に次々と形成される家の教会群、それらを霊的・知識的に養うため、多くの巡回伝道者や教師たちが地方を旅していた。ゼナスやアポロもその仲間だったと思われる。たぶん彼らのなかにはパウロに協力する者も、独自に行動する者もいたに違いない。だがパウロは大きな心をもってそれらを受け入れ、自分もできるかぎり援助したのであろう。▼ともあれ、こうしてからだを巡る血液のように、有名無名の人々によって公同の教会は広がり、成長して行った。当時の旅行はどんなに危険で困難なものであったか、後にヨハネも記している。「あなたが彼らを、神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いです。彼らは御名のために、異邦人からは何も受けずに出て行ったのです。私たちはこのような人々を受け入れるべきです。」(Ⅲヨハネ6~8)▼やがて主の御国が来た時、星のようにこれらの働き人たちが栄光に輝くことであろう。新エルサレムを飾る宝石となって・・。
私を救いに導いて下さったのはT師だが、師は中田重治につながり、中田はメソジストのH師に、H師は米国のそれに、そしてヨーロッパのキリスト教に、そして結局は初代教会のパウロやその他の使徒たちにつながっており、最後は主イエス・キリストに至るのである。それは一本の鎖のようにたどることができるのだ。なんと胸が熱くなる事実であろう。▼今は分からないが、天に行った時、おそらく一個一個の鎖すべてを知り、その信仰者たちに会えるのではなかろうか。御聖霊はいのちの電流のように、イエス・キリストご自身から流れ伝わって、私にも及ぶ。歴史的にもそれが言えるとは、まさに公同の教会である。▼電流といえば高校のとき物理の先生がひとつの実験をしてくれた。先生はクラス全員(40名ぐらいいたと思う)に、手と手をつながせ、初めの生徒と最後の生徒の手を先生のからだにタッチさせた。つまりじゅず繋ぎにさせたのである。それから先生は高圧電源に触れた。高圧といっても電流自体は微小なもので、危険はまったくない。しかしその瞬間、全員のからだに電気が走り、みんな驚いて叫び声を上げた。つまり人による電気回路が出来ていたので、電流が一瞬のうちに流れたのである。▼私は今もときどきこの実験を思い出す。キリスト教会はあらゆる時代とすべての信仰者を結んで一つの回路を作っている。もちろん初めと終わりはキリストご自身であられ、その回路をいのちとして流れておられるのが御聖霊である。だから文字通り、教会はイエスを頭とするひとつのからだそのものである。なんと喜ばしい事実であろう。このからだが、やがて栄光の内に姿を現わす。新しい天と新しい地の間に。










 「それは、私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠のいのちの望みを抱く相続人となるためでした。」(テトス3:7新改訳)
「それは、私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠のいのちの望みを抱く相続人となるためでした。」(テトス3:7新改訳)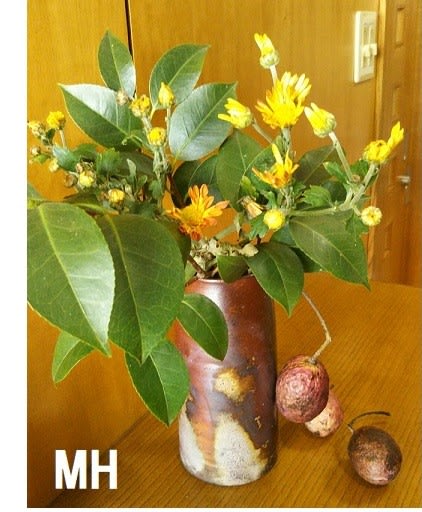 「実に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。」(テトス2:11新改訳)
「実に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。」(テトス2:11新改訳)