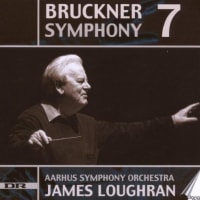パーヴォ・ヤルヴィ/N響のCプロ。1曲目はエストニアの作曲家(つまりパーヴォと同国人の)エルッキ・スヴェン・トゥール(1959‐)の「アディトゥス」(2000/2002)。パーヴォは2005年6月のN響初登場のときにもこの曲を取り上げた。だが、どんな曲だったか、まったく覚えていない。情けない。
高橋智子氏のプログラム・ノートによると、「トゥールの考案した「ベクトル書法」が曲全体を司る」そうだ。ベクトル書法とは「和音の声部誘導・連結方法。変異と増殖を繰り返しながら曲全体のテクスチュアを生成する和音は、遺伝子のような螺旋状の構造を想起させる」。う~ん、難しい。
実際に聴いてみると、ある一定の方向性(ベクトル)をもった音が並び、そのベクトルが角度を変えながら動き、さらに別の方向性(ベクトル)をもつ音の一群が割って入るといった印象だ。
だが、そういったアイデアの先になにがあったか、聴き終わった後では心許ない想いが残ったことも事実だ。
2曲目はショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番。ヴァイオリン独奏は五嶋みどり。4楽章構成のこの曲のパッサカリアで書かれた第3楽章で、五嶋みどりのヴァイオリンは胸も張り裂けんばかりの悲しみの旋律を紡いだ。何度も聴いたこの曲だが、こんなに痛切な演奏を聴くのは初めてだ。ショスタコーヴィチがこの曲に込めた心情が探り当てられたような想いがした。
パッサカリアから長大なカデンツァに入り、切れ目なく第4楽章になだれ込んでいく演奏には、まさに五嶋みどりの独壇場といった観があった。わたしは身も心も揺さぶられた。身体を大きく揺さぶりながら演奏する五嶋みどりの、その演奏への並外れた没入は、まるで巫女のようだった。
3曲目はバルトークの「管弦楽のための協奏曲」。何度も聴いて(正直なところ)食傷気味のこの曲が、まるで違った曲に聴こえた。あるフレーズの入りの音、終わりの音、それらの硬軟、強弱といったあらゆるニュアンスが考え抜かれた演奏だ。演奏におけるドラマトゥルギーとはこういうものかと教えられる想いがした。
パーヴォの指揮は、バルトークのこの曲と、Aプロのマーラー「復活」と、2月の「巨人」と(ショスタコーヴィチの5番は印象が薄いが)、どれもみんなアプローチが違う。今はN響に対していろいろなアプローチを試しているのかもしれない。
(2015.10.24.NHKホール)
高橋智子氏のプログラム・ノートによると、「トゥールの考案した「ベクトル書法」が曲全体を司る」そうだ。ベクトル書法とは「和音の声部誘導・連結方法。変異と増殖を繰り返しながら曲全体のテクスチュアを生成する和音は、遺伝子のような螺旋状の構造を想起させる」。う~ん、難しい。
実際に聴いてみると、ある一定の方向性(ベクトル)をもった音が並び、そのベクトルが角度を変えながら動き、さらに別の方向性(ベクトル)をもつ音の一群が割って入るといった印象だ。
だが、そういったアイデアの先になにがあったか、聴き終わった後では心許ない想いが残ったことも事実だ。
2曲目はショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番。ヴァイオリン独奏は五嶋みどり。4楽章構成のこの曲のパッサカリアで書かれた第3楽章で、五嶋みどりのヴァイオリンは胸も張り裂けんばかりの悲しみの旋律を紡いだ。何度も聴いたこの曲だが、こんなに痛切な演奏を聴くのは初めてだ。ショスタコーヴィチがこの曲に込めた心情が探り当てられたような想いがした。
パッサカリアから長大なカデンツァに入り、切れ目なく第4楽章になだれ込んでいく演奏には、まさに五嶋みどりの独壇場といった観があった。わたしは身も心も揺さぶられた。身体を大きく揺さぶりながら演奏する五嶋みどりの、その演奏への並外れた没入は、まるで巫女のようだった。
3曲目はバルトークの「管弦楽のための協奏曲」。何度も聴いて(正直なところ)食傷気味のこの曲が、まるで違った曲に聴こえた。あるフレーズの入りの音、終わりの音、それらの硬軟、強弱といったあらゆるニュアンスが考え抜かれた演奏だ。演奏におけるドラマトゥルギーとはこういうものかと教えられる想いがした。
パーヴォの指揮は、バルトークのこの曲と、Aプロのマーラー「復活」と、2月の「巨人」と(ショスタコーヴィチの5番は印象が薄いが)、どれもみんなアプローチが違う。今はN響に対していろいろなアプローチを試しているのかもしれない。
(2015.10.24.NHKホール)