新国立劇場の新制作、リヒャルト・シュトラウスのオペラ「アラベッラ」をみた。「アラベッラ」というと同劇場の1998年9月の公演を思い出す。あまりにも古色蒼然とした舞台で忘れられない。それから12年後の今回は現代という時代に追いついた舞台だった。
演出・美術・照明はフィリップ・アルロー。色彩感豊かな舞台を作りだす点では定評のある人だ。今回は青のグラデーションで目を楽しませてくれた。くわえて空間造形にもセンスがあった。また第3幕の装置が、上手側は第1幕(居間)を、下手側は第2幕(舞踏会の大階段)を回想させるのも洒落ていた。
演出では、アルロー自身がプログラム誌で語っているように、音楽のききどころでは動きを止めて、音楽に集中できるように配慮していた。これが無策に映らない点がさすがだ。ウルフ・シルマーの指揮もその演出にぴったり合っていた。ききどころの選択にはシルマーも深く関与しているように感じられた。
歌手ではアラベッラ役のミヒャエラ・カウネとマンドリカ役のトーマス・ヨハネス・マイヤーが世界の主要劇場レベルだった。ズデンカ役のアグネーテ・ムンク・ラスムッセンも第1幕前半をよく支えていた。1998年の公演にも出ていたフィアッカミッリ役の天羽明恵さんはもう少し軽いとよい。
プログラム誌ではアルローが、ズデンカのほうがアラベッラよりも興味のあるキャラクターだという趣旨のことを述べている。解説をかいた田辺秀樹さんも、原作となったホフマンスタールの小説「ルーツィドル」では男装の妹(=ズデンカ)が主人公だったと述べて、「愛しのズデンカ」という別稿をおこしている。
それぞれの趣旨はわかるが、オペラをみた印象では、アラベッラの存在感が圧倒的だ。これは音楽的な濃さに起因する。
おそらくシュトラウスはアラベッラの音楽をかきたかったのだと思う。それはどういう音楽かというと、自らに充足した音楽。外の出来事によって波紋が起きることはあっても、内面の深いところでは動揺せずに、自らに満たされた音楽。
考えてみると、「アラベッラ」の初演の指揮者がクレメンス・クラウスだったのは象徴的だ。クラウスはやがてシュトラウス最後のオペラ「カプリッチョ」の台本を――シュトラウスとともに――かくことになる。詩人と作曲家の双方から求愛され、自らを守る言葉をもたずに、ただひたすら存在する若き未亡人マドレーヌは、アラベッラの成熟した姿のようだ。
(2010.10.8.新国立劇場)
演出・美術・照明はフィリップ・アルロー。色彩感豊かな舞台を作りだす点では定評のある人だ。今回は青のグラデーションで目を楽しませてくれた。くわえて空間造形にもセンスがあった。また第3幕の装置が、上手側は第1幕(居間)を、下手側は第2幕(舞踏会の大階段)を回想させるのも洒落ていた。
演出では、アルロー自身がプログラム誌で語っているように、音楽のききどころでは動きを止めて、音楽に集中できるように配慮していた。これが無策に映らない点がさすがだ。ウルフ・シルマーの指揮もその演出にぴったり合っていた。ききどころの選択にはシルマーも深く関与しているように感じられた。
歌手ではアラベッラ役のミヒャエラ・カウネとマンドリカ役のトーマス・ヨハネス・マイヤーが世界の主要劇場レベルだった。ズデンカ役のアグネーテ・ムンク・ラスムッセンも第1幕前半をよく支えていた。1998年の公演にも出ていたフィアッカミッリ役の天羽明恵さんはもう少し軽いとよい。
プログラム誌ではアルローが、ズデンカのほうがアラベッラよりも興味のあるキャラクターだという趣旨のことを述べている。解説をかいた田辺秀樹さんも、原作となったホフマンスタールの小説「ルーツィドル」では男装の妹(=ズデンカ)が主人公だったと述べて、「愛しのズデンカ」という別稿をおこしている。
それぞれの趣旨はわかるが、オペラをみた印象では、アラベッラの存在感が圧倒的だ。これは音楽的な濃さに起因する。
おそらくシュトラウスはアラベッラの音楽をかきたかったのだと思う。それはどういう音楽かというと、自らに充足した音楽。外の出来事によって波紋が起きることはあっても、内面の深いところでは動揺せずに、自らに満たされた音楽。
考えてみると、「アラベッラ」の初演の指揮者がクレメンス・クラウスだったのは象徴的だ。クラウスはやがてシュトラウス最後のオペラ「カプリッチョ」の台本を――シュトラウスとともに――かくことになる。詩人と作曲家の双方から求愛され、自らを守る言葉をもたずに、ただひたすら存在する若き未亡人マドレーヌは、アラベッラの成熟した姿のようだ。
(2010.10.8.新国立劇場)


















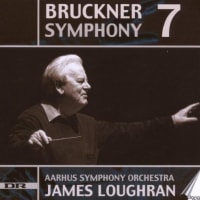








ブルーが印象的でした。ズデンカがもう少し頑張ってくれたら、とは思いましたが、
新しいシーズンに気持ちのいい音楽を聴けたと思います。