
先週話題にした映画「死刑台のエレベーター」を観るとじっくりマイルスを聴きたくなる。まずはサントラ盤だ。完全版CDにはオリジナル・マスターテープに入っていたものが16曲収録されているが、ここは飛ばして実際に映画で使われた音源を聴く。この10曲はスクリーンで効果的に響き、且つシーンとマッチするようにエコーがかけられているので、本来のマイルスの音と違うとはいえ臨場感たっぷりだ。
ここから公式盤を辿ると次は58年の「Milestones」、キャノンボール名義の「Somethin' Else」、ミシェル・ルグランの「Legrand Jazz」、マイルスとモンクが共演していると騙される「Miles & Monk at Newport」、ギル・エヴァンスと組んだ「Porgy and Bess」、ビル・エヴァンスが参加した「Jazz at the Plaza」、そして59年の「Kind of Blue」。名盤読本に書いてあるモード云々というのはどうでもいい。問答無用のジャズ史上最高の名盤である。あのレコードはいいとか、このアルバムは素晴らしいと絶賛されてもせいぜい片面か1曲だ。極論を言うとワンフレーズだ。ところが「Kind of Blue」は個々の曲がそれぞれに完成されている。筋金入りのジャズファンでも並び順に全曲すらすら出てくるのはこのレコードぐらいだろう。
A面を聴き終えてB面にひっくり返したときの興奮と感動が今でも甦るのが「All Blues」だ。多くのカバーから「Introducing Eric Kloss」を出してみた。タイトルの如くデビューアルバムで、パイプをくわえているので大人びて見えるが驚く勿れ若干16歳だ。サングラスをかけているので気付かれたかも知れないが盲目のテナーもアルトもこなすサックス奏者である。11歳でトリスターノと共演したというから天才といっていい。ドン・パターソンのオルガンのバックからやんわりとテーマに入ったあとのアドリブが凄い。上下、左右と音がクロスするのだ。粗削りではあるがその後数多くのリーダー作を発表するだけのサムシングが聴こえる。
「Kind of Blue」が発表されてから60年近く経つ。ジャズを聴きだして50年ほどになるが、その前の10年溯っても、リアルタイムで聴いた50年を振り返ってもこれを超えたジャズアルバムを聴いたことがない。CD時代になってから手軽にアルバムを作れることも手伝っておびただしい量の作品が出ているが、それらを100枚聴くより、これを100回聴いたほうがジャズの本質に触れることができる。何度聴いてもゾクゾクするレコードはざらにはない。
ここから公式盤を辿ると次は58年の「Milestones」、キャノンボール名義の「Somethin' Else」、ミシェル・ルグランの「Legrand Jazz」、マイルスとモンクが共演していると騙される「Miles & Monk at Newport」、ギル・エヴァンスと組んだ「Porgy and Bess」、ビル・エヴァンスが参加した「Jazz at the Plaza」、そして59年の「Kind of Blue」。名盤読本に書いてあるモード云々というのはどうでもいい。問答無用のジャズ史上最高の名盤である。あのレコードはいいとか、このアルバムは素晴らしいと絶賛されてもせいぜい片面か1曲だ。極論を言うとワンフレーズだ。ところが「Kind of Blue」は個々の曲がそれぞれに完成されている。筋金入りのジャズファンでも並び順に全曲すらすら出てくるのはこのレコードぐらいだろう。
A面を聴き終えてB面にひっくり返したときの興奮と感動が今でも甦るのが「All Blues」だ。多くのカバーから「Introducing Eric Kloss」を出してみた。タイトルの如くデビューアルバムで、パイプをくわえているので大人びて見えるが驚く勿れ若干16歳だ。サングラスをかけているので気付かれたかも知れないが盲目のテナーもアルトもこなすサックス奏者である。11歳でトリスターノと共演したというから天才といっていい。ドン・パターソンのオルガンのバックからやんわりとテーマに入ったあとのアドリブが凄い。上下、左右と音がクロスするのだ。粗削りではあるがその後数多くのリーダー作を発表するだけのサムシングが聴こえる。
「Kind of Blue」が発表されてから60年近く経つ。ジャズを聴きだして50年ほどになるが、その前の10年溯っても、リアルタイムで聴いた50年を振り返ってもこれを超えたジャズアルバムを聴いたことがない。CD時代になってから手軽にアルバムを作れることも手伝っておびただしい量の作品が出ているが、それらを100枚聴くより、これを100回聴いたほうがジャズの本質に触れることができる。何度聴いてもゾクゾクするレコードはざらにはない。










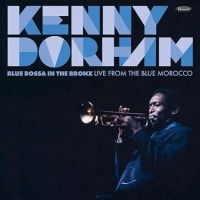

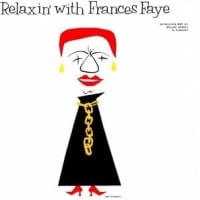

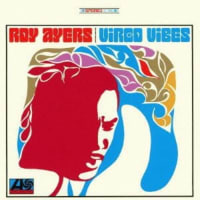

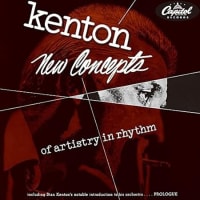


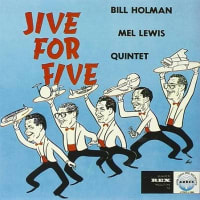





「オール・ブルース」はマイルスの美学がつまった曲で、多くのカバーがあります。今週はこの曲のお気に入りをお寄せください。尚、マイルスは殿堂入りですので、マイルスを除いてお寄せください。
管理人 All Blues Best 3
Kenny Drew / Dark Beauty (SteepleChase)
Ron Carter / All Blues (CTI)
Chet Baker, Jim Hall & Hubert Laws / Studio Trieste (CTI)
他にもミルト・ジャクソンをはじめレイ・ブライアント、アル・ヘイグ、GJT等々、多くの名演があります。
今週も皆様のコメントをお待ちしております。
Brian Bromberg upright bass solo: All Blues intro to Sunday Mornin'
https://www.youtube.com/watch?v=qmLSL1wClxk
本人も周りも納得のソロ
これは、マイルスの演奏があればいいので、他のものは意識して聴いていないので、どれにしようか迷いました。ブルース寄りでいこうかと、
Kenny Drew / Dark Beauty (SteepleChase)
Oscar Peterson / Face to Face (Pablo)
Ron Carter / All Blues (CTI)
ドリューのものは、思い出深い一枚です。ピーターソンとフレディ・ハバードの組み合わせを入れました。パブロのものは玉石混交ですが、ここではハバードが素晴らしい。3つめは、ロン・カーターで。
ヨーロッパのミュージシャンも取り上げていて、ジョルジュ・アルバニ―タス、カーステン・ダール、レイン・デ・グラフといったピアニストもやっていました。あと、フレッド・ハーシュやハワード・ロバーツもレコードやCDがあるはずですが、にわかに探し出せなくて(笑)。人気曲でヴァージョン多いですね。
マイルス以外となるとやはりケニー・ドリューですね。アメリカ時代のハングリーさはありませんが、精神的に余裕を感じる演奏です。ペデルセンが凄い。
次にピーターソンとフレディ・ハバード、これもペデルセンですね。ノーマン・グランツお得意の顔合わせセッションですが、気取らず楽しんでいるのが大物らしい。
ロン・カーターもCTIも積極的に聴きませんが、これはいいですね。ペデルセンがカーターのチューニングはミステリアスとコケにしておりましたが、これがアメリカスタイルなのでしょう。
ヨーロッパのミュージシャンに好まれる曲ですが、特に印象に残るものはありませんでした。
フレッド・ハーシュは、やたらと持ち上げる批評家がいました。いいピアノですが、試聴だけで十分でした。
ハワード・ロバーツはコンコード盤ですね。変わらぬスタイルは安心します。
All Blues Best 3
Kenny Drew / Dark Beauty (SteepleChase)
Ron Carter / All Blues (CTI)
Oscar Peterson / Face to Face (Pablo)
マイルスを外すと次が出てこない「オール・ブルース」ですが、ケニー・ドリュー、ロン・カーター、オスカー・ピーターソンが挙がりました。どの演奏もマイルスへの深い愛情を感じます。
今宵はお気に入りの「オール・ブルース」をお楽しみください。