社会人の方々は明日から新年の仕事始めだと思う
私も同様なのだ
遠出はしなかったが充分に休養が取れたのでエンジン全開!という感じなのだ
今回は『オクターブ調整』について語りたいと思うのだ
オクターブ調整という言葉を耳にする機会は多いと思う

意味が分からないという方は是非とも検索して理解を深めていただきたい
その手順や方法について触れているサイトは星の数ほどあるのだ
個人的にはエレキギターが楽器である為の最低条件のメンテの一つだと考えているのだ
実は先日、ちょっとした検索(ギター関連)をしていて、あるギター弾きのブログをみつけたのだ
キャリア10年にして最近になってオクターブ調整の存在を知ったというのだ
どこまでが本当なのか?は眉唾ものだが・・・
少なくともオクターブ調整に無頓着な人が多いのも事実なのだ
楽器店に修理依頼として持ち込まれるギターの多くが
ネックコンディションとオクターブ調整に不備を抱えているという
もちろん調整にはそれなり工賃が発生するのだ
修理箇所として依頼された部分はその他(電気系など)の部分なのだ
楽器店のお兄さんとしては常連さんには簡単なアドバイスをするようだが・・
「ネック調整とオクターブ調整、サドルの面取りもしておきますか?」
というような事は言わないのだ
基本的に余計な事は言わないという立ち位置らしい
「何だか弾き難いんですけど・・・」
「音程も合わないような気もするんですけど・・」
という相談を受けた場合、真っ先に疑うのはネックとサドルの状態だという
オクターブ調整の幾つかの間違いについて触れたいと思う
”一度調整したオクターブは弦のゲージを変更しないかぎり狂わない・・・”
とい信じている人があまりにも多いのだ
厳密にはその狂いが少ないが・・
ピッチの狂いに気付く人が少ないというのが私の率直な感想なのだ
僅かな音程の狂いを聴き逃さない耳が不可欠なのだ
弦の太さを変更した場合にはオクターブ調整は必須なのだ
先にも述べたように同一サイズの弦を継続的に使用した場合はどうか?
演奏中に僅かにサドルが前後する場合があるのだ
チューニングをする為にペグをクルクルと回している時にもサドルは影響を受けている
レスポールのブリッジの構造の欠点の一つになっているのだ
レスポールの開発当初からデザインに大きな変更はないのだ
調整のし難さや少々の不具合を踏まえた上でこの形を採用し続けるには意味があるようだ
弦の振動の『美味しい部分』をボディに伝達するギブソンの答えがこのブリッジ形状なのだ
当然ながらコピーモデルの多くは右へ倣え!で製品をリリースしているという流れなのだ
少々脱線したが・・・
常にオクターブに気を使うのはギター弾きの常識という事なのだ
まぁ、日々の練習は良いとしてもライブ本番や録音の際にはチェックすべき部分の筆頭だと思う
世の中には面白い人がいるもので・・・
オクターブ調整の方法は知っているのだが手順を間違って理解しているのだ
正しい流れはこうなのだ
1、弦を張った後にネックを正しい状態に調整(やや順反り気味)するのだ
2、その後に弦高を好みの高さに調整する
3、そして、いよいよ最後の調整としてオクターブ調整という事になるのだ
その人の場合にはこんな感じなのだ
「オクターブ調整をしてたらサドルが後ろまで回り切っちゃう事あるよね?」
「そんな場合にはネックを反りとか弦高で何とか逃げ切っちゃうんだよね?」
読者の皆さんはこの文章に違和感を覚えただろうか?
「特に気になる部分はないけど・・」
という方は少々問題なのだ
調整の順番がメチャクチャなのだ
いつまでたっても調整が完了しないのだ
「え~こんな人っているの?」
初心者から中級者に多いのだが・・
自分でメンテに挑戦した結果として弄り壊してしまうのだ
最終手段として楽器屋さんに入院する事になるのだ
割に多いケースのようだ
読者の皆さんは演奏前の入念なメンテを行っていただきたいと思う
万全に調整されたギターは弾いていて気持ち良い!のだ
設計が古いと言われているレスポールのブリッジ構造だが・・
実はメーカーも試行錯誤しながら進化を続けているのだ
私が所有しているレスポールタイプのギターのブリッジとサドルをご紹介したい
ミニレスポール


トーカイのレスカス

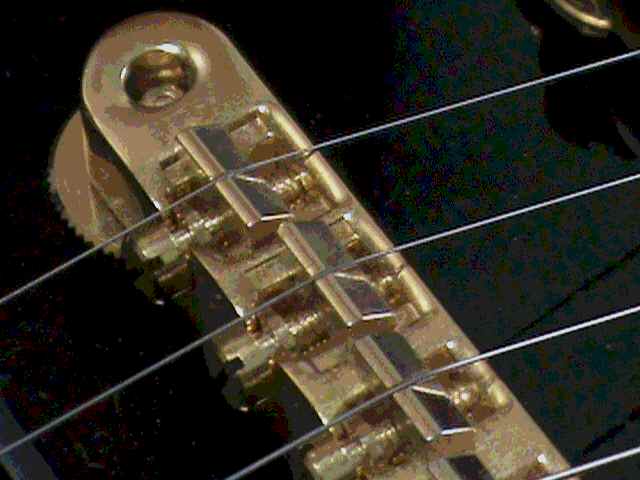
ギブソンレスポール


トーカイはヴィンテージタイプなのだ
ギブソンのカスタムショップ系のヴィンテージコピーモデルはこのタイプを採用しているのだ
一方のミニとギブソンのブリッジに注目していただきたい
サドルの『可変範囲』が大きいのがお分かりいただけると思う
ヴィンテージタイプはサドルの取り外しが可能なのだ
それ故にサドルの向きを変えることが出来るのだ
「後ろまで回し切っちゃったなぁ・・」
という場合にサドルの向きを逆向きに取り付ける事で急場を凌ぐことが可能なのだ
一方の可変範囲が広いタイプはサドルを取り外すことができない
出来ない・・というよりはその必要がないのだ
どんな弦にも弦高にも対応できるように設計されているのだ
『サドルの向き』について疑問を抱いている人も多いように感じる
オクターブ調整を最優先するという前提で向きに決まりはないとされているが・・・
ブリッジからテールピースの角度を考えればやはり適正な向きがあるといえるのだ

私のトーカイは幸いにもすべて同じ向きでサドルをセットできたのだ
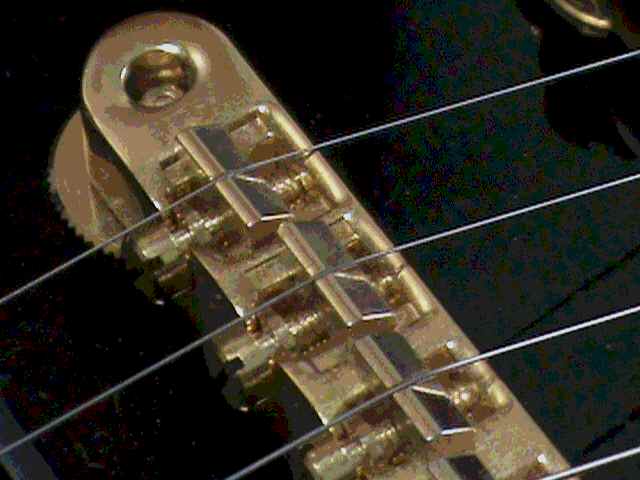
”サドルの向きも変更してもオクターブが合わない・・”
というギターも少なからず存在する
対処の方法はあるのか?
同一のサドルでは残念ながら解決策はないのだ
僅かな音程の狂いを我慢しながら使うしかないのだ
もっと音程を極めたい!
という場合には社外の可変範囲が広いブリッジに交換する事で解決するのだ
ボリュームノブのようにインチ?ミリ?という簡単なものではないようだ
機種によって取り付けが困難な場合があるので注意が必要なのだ
知識がない楽器店での購入にも注意が必要なのだ
「たぶん・・これで大丈夫だと思いますけど・・・」
という曖昧な店員さんは危ないなのだ
近年では無改造のギターを愛用している店員さんも増えているのだ
「電気系統も苦手だし・・特に問題もないので・・・」
やはり良くも悪くもカスタム経験が豊富な店員さんには『データー』が蓄積されているのだ
ましてや多少値段が安い事を理由にネットでブリッジやテールピースを購入する事による失敗も多いのだ
当然ながら開封後の返品など常識外なのだ
ネット通販の場合、発送側の不備のみ返品、返金が可能なのだ
・・というわけで微妙なパーツのカスタムの際には信頼おけるお近くの楽器店に依頼していただきたい
実際のオクターブ調整の方法について触れてみたい
「弦を張ったまま調整できるの?」
「弦が邪魔でドライバーが回し難いんだけど・・」
基本的にレスポールタイプの場合には弦を緩めるということが前提になるのだ
弦を張ったままオクターブの狂いを確認、弦を緩めて調整、再び弦を張って確認・・・
非常に面倒な作業工程だがこれがレスポールなのだ
その際に精度が低いブリッジ&サドルは弦を張ったり緩めたりする都度、
前後にサドルが動いてしまうのだ
「俺のレスポールってどうなのかな?」
弦を張っていない状態でサドルを指で動かしていただきたい
僅かな遊びはヴィンテージタイプでは不可欠なのだ
力を入れずとも簡単にサドルの取り外しが可能な場合にはかなりガタが出ている事になる
サドルを単体で交換することでリフレッシュする事ができるのだ
取り外しに少々力を要するくらが丁度良いのだ
ワイヤーでサドルを押さえているタイプのブリッジはさらに設計が古いタイプなのだ
ヴィンテージ雰囲気を醸し出すアイテムとしては必須アイテムなのだ
しかしながら、楽器としてあるいは音楽的にメリットは皆無なのだ
雰囲気を取るか?
楽器としての品質を取るか?
弾き手の判断に委ねられるのだ
近年のギブソンの場合にはレギュラーラインとカスタムラインで方針がまったく異なるのだ
カスタムショップ製はあくまでも古き良き時代のレスポールを再現する事に尽力しているように感じられる
「もっと品質よいパーツは山ほどあるさ・・」
「でもこれで良いんだ・・あの音を出すには」
というような事を開発担当者が語っていた
一方のレギュラーラインは楽器としてより進化したレスポールを念頭に置いて開発しているように感じられる
その一つの方向性がブリッジ構造なのだ
あくまでもヴィンテージ!という人には興味ないパーツだと思う
レギュラーラインでは2000年以降音質と音程の向上を図る試みが行われているのだ

個人的にはこの差別化は非常に良いと思うのだ

私が最優先するのは楽器としてのクオリティなのだ
ブランドや所有感というのはその後に続くものだと考えているのだ

余談だが・・・
ギブソンの不備を補う形でデビューしたフェンダー系ギターのパーツは秀逸なのだ

これはアリアのブリッジだが基本構造はストラトと同様なのだ
弦を張ったままオクターブ調整が可能なのだ

さらにサドルの可変範囲のレスポールとは比較にならないくらいに広いなのだ
弦をボディに裏通しする事でレスポールに負けないサスティンを得ているのだ

”似て非なり・・・”
で両者はまったく異なる発想と音だがこれも一つの進化形の形だといえる
最近はミニレスポールにハマっているのだ

新年もちょっとしたイベントの余興に活躍したのだ

巷では・・
”ミニギター≒オモチャ・・”
という考えが浸透しているようだ
オモチャたる所以はやはりピッチの悪さに尽きるのだ
先日、某メーカーのミニギターを弾く機会に恵まれたのだ
サイズは私のミニよりも小さいなのだ
ストラトタイプのボディ構造なのだ
一人前にアーム棒も付いているのだ
「可愛いね~もう一本買っちゃおうかな?」
と思わず口走るほどのルックスなのだ
実際の音と演奏性はどうか?
ウクレレの愛用している私にとっては大きさはさほど気にならないのだ
弦のテンションもミニレスポールよりも一音上げで稼げるのだ
チョーキングを少ししただけで音が狂ってしまうのだ
さらには和音を作り出した時の音が微妙なのだ
言い方は悪いが・・
和音が気持ち悪いのだ
それでもオクターブ調整済だというのだ
結局、フレットをいい加減に処理している証なのだ
チョーキングやビブラートで音程が狂うギターの場合、アーム一発で全弦が崩壊してしまうのだ
「これじゃ使えないね・・・」
他のミニを弾いた事で私のミニレスポールが楽器としていかに優れてが再認識できたのだ
その一番のポイントが先にも述べたブリッジの構造なのだ

さらにフレット打ち込み精度が高いように感じられる
アジア生産とは言いながらもESPブランドの品質が随所に感じられるのだ
コンデンサーうあピックアップなど今回は出費0円で抑えられたことも良かったと思うのだ
厳密にはフロントピックアップのコンデンサーもオレンジドロップに換装したいと思うが・・
ミニだけにこれ以上手間をかけるのもどうか?とも思うのだ
まぁ、現状でも『飾りギター』を越えた実機としての風格を感じているのだ
「ミニなのに良い仕事をするね~」
という感じなのだ
オクターブ調整も完璧に追い込めるのだ
オクターブ調整が効いてくるのは12フレットよりも上の音域なのだ
厳密にはローポジでも音のバランスに影響を与えるが・・・
如実に感じられるのはやはりハイポジなのだ
読者の皆さんも簡単な確認方法を試していただきたい
3弦と4弦を使い12フレット以降のポジションで2音も和音を作るのだ
それを押弦したままその他の開放を鳴らしてみるのだ
これは私がアルペジオやコードストロークで良く用いる手法なのだ
一本のギターで12弦ギターのような響きを得ることができるのだ
コードブックに載っていないコードという事になる
その他にも遊びながらマスターしたコードが数多くあるのだ
これが私の引き出しになっているのだ
「どんな風に押さえているのかな?」
「独特な響きだなぁ・・イイ感じだね」
と感じている読者の方も多いと思う
すべての前提は
”ピッチ感が良いギター・・”
の上に成り立っているのだ
私も同様なのだ
遠出はしなかったが充分に休養が取れたのでエンジン全開!という感じなのだ

今回は『オクターブ調整』について語りたいと思うのだ
オクターブ調整という言葉を耳にする機会は多いと思う

意味が分からないという方は是非とも検索して理解を深めていただきたい
その手順や方法について触れているサイトは星の数ほどあるのだ
個人的にはエレキギターが楽器である為の最低条件のメンテの一つだと考えているのだ
実は先日、ちょっとした検索(ギター関連)をしていて、あるギター弾きのブログをみつけたのだ
キャリア10年にして最近になってオクターブ調整の存在を知ったというのだ

どこまでが本当なのか?は眉唾ものだが・・・
少なくともオクターブ調整に無頓着な人が多いのも事実なのだ
楽器店に修理依頼として持ち込まれるギターの多くが
ネックコンディションとオクターブ調整に不備を抱えているという
もちろん調整にはそれなり工賃が発生するのだ
修理箇所として依頼された部分はその他(電気系など)の部分なのだ
楽器店のお兄さんとしては常連さんには簡単なアドバイスをするようだが・・
「ネック調整とオクターブ調整、サドルの面取りもしておきますか?」
というような事は言わないのだ
基本的に余計な事は言わないという立ち位置らしい
「何だか弾き難いんですけど・・・」
「音程も合わないような気もするんですけど・・」
という相談を受けた場合、真っ先に疑うのはネックとサドルの状態だという
オクターブ調整の幾つかの間違いについて触れたいと思う
”一度調整したオクターブは弦のゲージを変更しないかぎり狂わない・・・”
とい信じている人があまりにも多いのだ
厳密にはその狂いが少ないが・・
ピッチの狂いに気付く人が少ないというのが私の率直な感想なのだ
僅かな音程の狂いを聴き逃さない耳が不可欠なのだ
弦の太さを変更した場合にはオクターブ調整は必須なのだ
先にも述べたように同一サイズの弦を継続的に使用した場合はどうか?
演奏中に僅かにサドルが前後する場合があるのだ
チューニングをする為にペグをクルクルと回している時にもサドルは影響を受けている
レスポールのブリッジの構造の欠点の一つになっているのだ
レスポールの開発当初からデザインに大きな変更はないのだ
調整のし難さや少々の不具合を踏まえた上でこの形を採用し続けるには意味があるようだ
弦の振動の『美味しい部分』をボディに伝達するギブソンの答えがこのブリッジ形状なのだ
当然ながらコピーモデルの多くは右へ倣え!で製品をリリースしているという流れなのだ
少々脱線したが・・・
常にオクターブに気を使うのはギター弾きの常識という事なのだ
まぁ、日々の練習は良いとしてもライブ本番や録音の際にはチェックすべき部分の筆頭だと思う
世の中には面白い人がいるもので・・・
オクターブ調整の方法は知っているのだが手順を間違って理解しているのだ
正しい流れはこうなのだ
1、弦を張った後にネックを正しい状態に調整(やや順反り気味)するのだ
2、その後に弦高を好みの高さに調整する
3、そして、いよいよ最後の調整としてオクターブ調整という事になるのだ
その人の場合にはこんな感じなのだ
「オクターブ調整をしてたらサドルが後ろまで回り切っちゃう事あるよね?」
「そんな場合にはネックを反りとか弦高で何とか逃げ切っちゃうんだよね?」
読者の皆さんはこの文章に違和感を覚えただろうか?
「特に気になる部分はないけど・・」
という方は少々問題なのだ
調整の順番がメチャクチャなのだ

いつまでたっても調整が完了しないのだ
「え~こんな人っているの?」
初心者から中級者に多いのだが・・
自分でメンテに挑戦した結果として弄り壊してしまうのだ
最終手段として楽器屋さんに入院する事になるのだ
割に多いケースのようだ
読者の皆さんは演奏前の入念なメンテを行っていただきたいと思う
万全に調整されたギターは弾いていて気持ち良い!のだ

設計が古いと言われているレスポールのブリッジ構造だが・・
実はメーカーも試行錯誤しながら進化を続けているのだ
私が所有しているレスポールタイプのギターのブリッジとサドルをご紹介したい
ミニレスポール


トーカイのレスカス

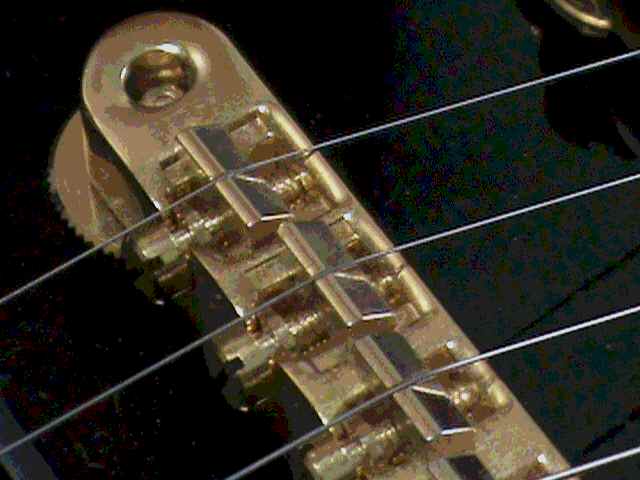
ギブソンレスポール


トーカイはヴィンテージタイプなのだ
ギブソンのカスタムショップ系のヴィンテージコピーモデルはこのタイプを採用しているのだ
一方のミニとギブソンのブリッジに注目していただきたい
サドルの『可変範囲』が大きいのがお分かりいただけると思う
ヴィンテージタイプはサドルの取り外しが可能なのだ
それ故にサドルの向きを変えることが出来るのだ
「後ろまで回し切っちゃったなぁ・・」
という場合にサドルの向きを逆向きに取り付ける事で急場を凌ぐことが可能なのだ
一方の可変範囲が広いタイプはサドルを取り外すことができない
出来ない・・というよりはその必要がないのだ
どんな弦にも弦高にも対応できるように設計されているのだ
『サドルの向き』について疑問を抱いている人も多いように感じる
オクターブ調整を最優先するという前提で向きに決まりはないとされているが・・・
ブリッジからテールピースの角度を考えればやはり適正な向きがあるといえるのだ

私のトーカイは幸いにもすべて同じ向きでサドルをセットできたのだ
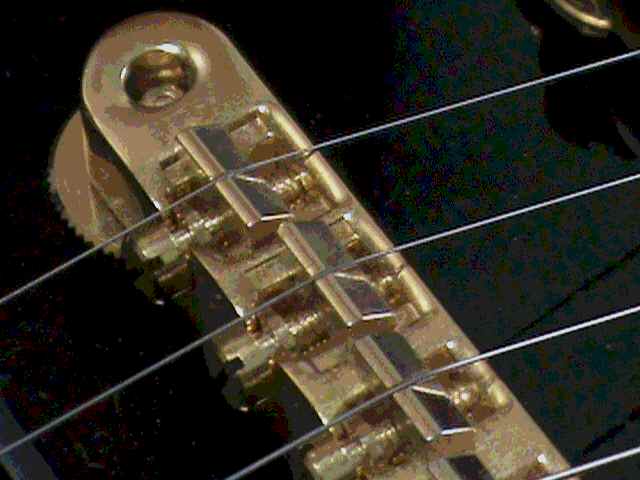
”サドルの向きも変更してもオクターブが合わない・・”
というギターも少なからず存在する
対処の方法はあるのか?
同一のサドルでは残念ながら解決策はないのだ
僅かな音程の狂いを我慢しながら使うしかないのだ
もっと音程を極めたい!
という場合には社外の可変範囲が広いブリッジに交換する事で解決するのだ
ボリュームノブのようにインチ?ミリ?という簡単なものではないようだ
機種によって取り付けが困難な場合があるので注意が必要なのだ
知識がない楽器店での購入にも注意が必要なのだ
「たぶん・・これで大丈夫だと思いますけど・・・」
という曖昧な店員さんは危ないなのだ
近年では無改造のギターを愛用している店員さんも増えているのだ
「電気系統も苦手だし・・特に問題もないので・・・」
やはり良くも悪くもカスタム経験が豊富な店員さんには『データー』が蓄積されているのだ
ましてや多少値段が安い事を理由にネットでブリッジやテールピースを購入する事による失敗も多いのだ
当然ながら開封後の返品など常識外なのだ
ネット通販の場合、発送側の不備のみ返品、返金が可能なのだ
・・というわけで微妙なパーツのカスタムの際には信頼おけるお近くの楽器店に依頼していただきたい
実際のオクターブ調整の方法について触れてみたい
「弦を張ったまま調整できるの?」
「弦が邪魔でドライバーが回し難いんだけど・・」
基本的にレスポールタイプの場合には弦を緩めるということが前提になるのだ
弦を張ったままオクターブの狂いを確認、弦を緩めて調整、再び弦を張って確認・・・
非常に面倒な作業工程だがこれがレスポールなのだ
その際に精度が低いブリッジ&サドルは弦を張ったり緩めたりする都度、
前後にサドルが動いてしまうのだ
「俺のレスポールってどうなのかな?」
弦を張っていない状態でサドルを指で動かしていただきたい
僅かな遊びはヴィンテージタイプでは不可欠なのだ
力を入れずとも簡単にサドルの取り外しが可能な場合にはかなりガタが出ている事になる
サドルを単体で交換することでリフレッシュする事ができるのだ
取り外しに少々力を要するくらが丁度良いのだ
ワイヤーでサドルを押さえているタイプのブリッジはさらに設計が古いタイプなのだ
ヴィンテージ雰囲気を醸し出すアイテムとしては必須アイテムなのだ
しかしながら、楽器としてあるいは音楽的にメリットは皆無なのだ
雰囲気を取るか?
楽器としての品質を取るか?
弾き手の判断に委ねられるのだ
近年のギブソンの場合にはレギュラーラインとカスタムラインで方針がまったく異なるのだ
カスタムショップ製はあくまでも古き良き時代のレスポールを再現する事に尽力しているように感じられる
「もっと品質よいパーツは山ほどあるさ・・」
「でもこれで良いんだ・・あの音を出すには」
というような事を開発担当者が語っていた
一方のレギュラーラインは楽器としてより進化したレスポールを念頭に置いて開発しているように感じられる
その一つの方向性がブリッジ構造なのだ
あくまでもヴィンテージ!という人には興味ないパーツだと思う
レギュラーラインでは2000年以降音質と音程の向上を図る試みが行われているのだ

個人的にはこの差別化は非常に良いと思うのだ

私が最優先するのは楽器としてのクオリティなのだ
ブランドや所有感というのはその後に続くものだと考えているのだ

余談だが・・・
ギブソンの不備を補う形でデビューしたフェンダー系ギターのパーツは秀逸なのだ

これはアリアのブリッジだが基本構造はストラトと同様なのだ
弦を張ったままオクターブ調整が可能なのだ

さらにサドルの可変範囲のレスポールとは比較にならないくらいに広いなのだ
弦をボディに裏通しする事でレスポールに負けないサスティンを得ているのだ

”似て非なり・・・”
で両者はまったく異なる発想と音だがこれも一つの進化形の形だといえる
最近はミニレスポールにハマっているのだ

新年もちょっとしたイベントの余興に活躍したのだ

巷では・・
”ミニギター≒オモチャ・・”
という考えが浸透しているようだ
オモチャたる所以はやはりピッチの悪さに尽きるのだ
先日、某メーカーのミニギターを弾く機会に恵まれたのだ
サイズは私のミニよりも小さいなのだ
ストラトタイプのボディ構造なのだ
一人前にアーム棒も付いているのだ
「可愛いね~もう一本買っちゃおうかな?」
と思わず口走るほどのルックスなのだ
実際の音と演奏性はどうか?
ウクレレの愛用している私にとっては大きさはさほど気にならないのだ
弦のテンションもミニレスポールよりも一音上げで稼げるのだ
チョーキングを少ししただけで音が狂ってしまうのだ
さらには和音を作り出した時の音が微妙なのだ
言い方は悪いが・・
和音が気持ち悪いのだ
それでもオクターブ調整済だというのだ
結局、フレットをいい加減に処理している証なのだ
チョーキングやビブラートで音程が狂うギターの場合、アーム一発で全弦が崩壊してしまうのだ
「これじゃ使えないね・・・」
他のミニを弾いた事で私のミニレスポールが楽器としていかに優れてが再認識できたのだ
その一番のポイントが先にも述べたブリッジの構造なのだ

さらにフレット打ち込み精度が高いように感じられる
アジア生産とは言いながらもESPブランドの品質が随所に感じられるのだ
コンデンサーうあピックアップなど今回は出費0円で抑えられたことも良かったと思うのだ
厳密にはフロントピックアップのコンデンサーもオレンジドロップに換装したいと思うが・・
ミニだけにこれ以上手間をかけるのもどうか?とも思うのだ
まぁ、現状でも『飾りギター』を越えた実機としての風格を感じているのだ
「ミニなのに良い仕事をするね~」
という感じなのだ
オクターブ調整も完璧に追い込めるのだ
オクターブ調整が効いてくるのは12フレットよりも上の音域なのだ
厳密にはローポジでも音のバランスに影響を与えるが・・・
如実に感じられるのはやはりハイポジなのだ
読者の皆さんも簡単な確認方法を試していただきたい
3弦と4弦を使い12フレット以降のポジションで2音も和音を作るのだ
それを押弦したままその他の開放を鳴らしてみるのだ
これは私がアルペジオやコードストロークで良く用いる手法なのだ
一本のギターで12弦ギターのような響きを得ることができるのだ
コードブックに載っていないコードという事になる
その他にも遊びながらマスターしたコードが数多くあるのだ
これが私の引き出しになっているのだ
「どんな風に押さえているのかな?」
「独特な響きだなぁ・・イイ感じだね」
と感じている読者の方も多いと思う
すべての前提は
”ピッチ感が良いギター・・”
の上に成り立っているのだ
















