
台湾で人気を呼んだホラーゲームの映画化だそうである。おそらく、そうとは知らず見に行った人も多いのではないかと思った。私も実は見るまで知らなかった。映画の謳い文句に「牯嶺街少年殺人事件」に続く・・・などと書いてあるから、それにつられて見に来た老年世代もかなりいたと見受けられた。
まあ、しかし台湾の歴史を知るうえでは勉強になる。
もともと台湾は日清戦争に勝った日本が遼東半島などとともに清国から割譲され大日本帝国の植民地となった。太平洋戦争の末期に、まだ大陸中国の代表権を認められていた蒋介石が英米と取り決めたポツダム宣言によって日清戦争以前の領土に戻すべしとの勧告(カイロ宣言)の履行を日本に突きつけた。ポツダム宣言は10条あまりの簡単な文書なので一読をお薦めする。日本はこれを受け入れて台湾を返還したのである。
周知のとおり毛沢東率いる共産党と蒋介石の国民党が再び内戦に陥り、国民党一派は大陸で全権を掌握した毛沢東に追われるようにして台湾に逃れた。
さて、1962年の台湾。大陸からの侵攻を恐れる蒋介石政権は1949年以来、台湾全土に戒厳令を布いて、共産主義や自由主義的思想の流布を抑え込むために、そうした書籍を発禁処分として徹底的に取り締まった。とある高校では、教師と教え子たちが発禁本を書き写して秘匿する非合法の読書クラブを組織する。学校内部にも官憲の手先がいて絶えず監視下に置かれている。冒頭の中国語タイトル「返校」の下にdetention(英題)と出た。英語の辞書を引くと拘束とか抑留と書いてあるが、教育用語として居残り、つまり先生に命じられて放課後も残ることをいうらしい。たしかに、この映画では禁書を書き写す作業を放課後にやっていた。そういう意味だろう。
ある日、何ものかの密告によって組織の存在が明らかとなり、指導者の教師や関係していた生徒が拘束され、過酷な拷問にあう。いったい、だれが密告したのか。現実のサスペンスフルな人間関係の描写の間隙を縫うように、超自然的な幻想風のホラー場面が挿入され、ゲームの映画化であったことを思い出させる。
いわば、ゲーム感覚で台湾の負の歴史をあぶり出そうというわけだが、若い人びとにどれほどの訴求力があるか、わからない。とくに日本の若者が見れば単なるホラーの題材のひとつにしか見えず、きな臭い時代の警鐘だとは感じないかもしれない。
そこで、ふと考えた。まだそのような報告は幸いにして聞かないが、たとえば公立図書館から特定の思想に関する図書が消える、購入リストから外される、過去の蔵書リストから省かれ廃棄される。そういうことが起きないとも限らない。闇夜に霜の降るごとく、自由の制限はわれわれが気づかないうちに刻々と実行されるのである。(健)
原題:返校
監督:ジョン・スー
脚本:ジョン・スー、フー・カーリン、チエン・シーケン
撮影:チョウ・イーシェン
出演:ワン・ジン、ツォン・ジンファ、フー・モンボー、チョイ・シーワン











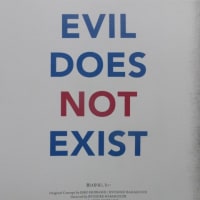


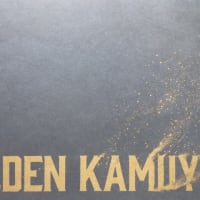


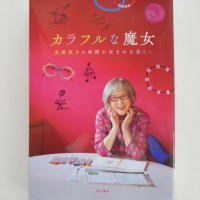

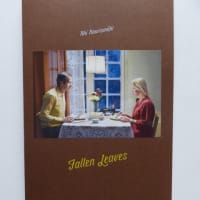

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます