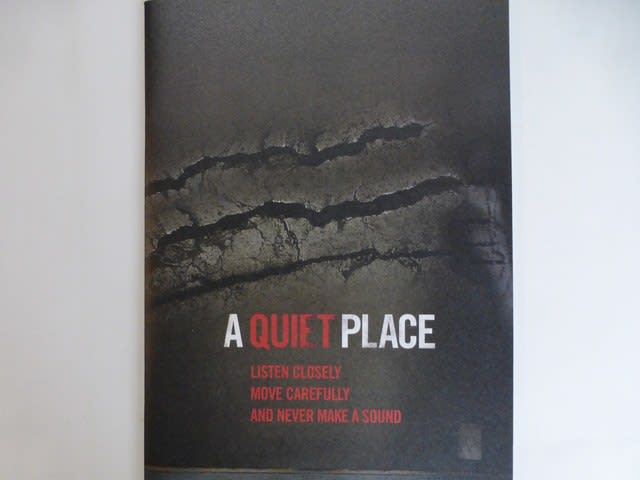樹木希林が亡くなって2ヶ月がたとうとしているが、2018年は出演作が相次ぎ「モリのいる場所」「万引き家族」に続き本作で3作目。しかし、遺作ではない。さらに2作が公開予定というから驚く。死期が近づく自分をさらけ出して、最後の最後まで演じ続けるという役者根性には恐れ入るとしか言いようがない。
樹木希林が今回演じたのはお茶の先生。彼女が開く茶道教室に主人公の典子と従姉妹の美智子が通い始める。二人とも二十歳を過ぎ、大学生のうちに一生をかけられるような何かを見つけたいと思っていたのだがなかなか見つからない。「お茶でもやってみたら?!」母からの突然の勧めと、「一緒にやろうよ!」という美智子の誘いで、全く乗り気なく始めた典子だったのだが、それからずっと茶道とともに人生を歩み続けることになろうとは・・・。
茶道に関してはおよそ知識のない自分なのだが、この作品、冒頭から同じように全く初心者の二人と一緒に、樹木演じる武田先生の指導を受けることとなる。帛紗さばきからお茶の入れ方、いただき方、そして茶室での色々な作法を学ぶのだが、「意味なんてわからなくていい。お茶はまず『形』から。先にその『形』を作って、その入れ物の中に心がはいっていくの。」という先生の言葉に、なるほどと頷きながら新鮮な気持ちで「お茶」の世界に引き込まれていく。
それにしても樹木希林の存在感はすごい。お茶の経験は全くなかったそうだが、前日に本職から指導を受けただけできちんと師匠の役がこなせるのだからさすがだ。病に冒されているというのに背筋はシャンと伸び、細かな所作にも余裕さえ感じられる。主人公の典子には主演作が続く黒木華。いま、もっとも輝いている若手女優といえばこの人。樹木希林も「主演が黒木さんなら共演したい。」と今回の役を引き受けたというから、ラストシーンも含め、何か次の世代に伝えたいものがあったのではと推測してしまう。この二人を引き合わせたのは大森立嗣監督の大手柄。茶道に関するディテールにもこだわり、掛け軸から、茶碗、茶花、和菓子に至るまで"本物”が使用され、それを見ているだけでも心が癒される。
『日日是好日』とは「幸不幸や結果の善し悪しにとらわれず、かけがいのない一日一日を大切にして、感謝の気持ちで過ごすこと」と説いた禅語だそうだが、若いときはこんな心境にはなかなかなれなかった自分も、そろそろわかってくる歳となった。さて、今からでも何かやってみるか。
(HIRO)
監督:大森立嗣
脚本:大森立嗣
撮影:槇憲治
出演:黒木華、樹木希林、多部未華子、鶴田真由、鶴見辰吾