太平洋戦争の末期に存在した、日本の原爆開発研究を背景に、そこにかかわった青年科学者石村修(柳楽優弥)、その弟で一時帰宅中の陸軍下士官、石村裕之(三浦春馬)、兄弟から思いを寄せられる幼馴染の朝倉世津(有村架純)の3人の若者を描いている。
監督が広島の図書館で偶然見つけた科学者の日記をもとに、10年の構想を経て日米合作で制作され、昨年夏にはドラマとしても話題になった。
テーマが壮大。いくつもの視点で考えさせられる。はたして私にこの作品を語りきれるのか、とても消化しきれない思いを抱えたまま、印象に残ったシーンを取り上げたい。
買い出しという名の小旅行を母(田中裕子)に与えられた3人が出かけた丹後半島の海の美しさ。バスのエンストの為に野宿をするが、そこで静かに歌われる「ゴンドラの歌」の悲しい響き。夜中の海で、初めて裕之は死の恐怖を訴える。「戦争なんか終わってしまえ、勝ち負けなんか関係ない!」と世津が叫ぶ。
裕之の出発前夜、3人が縁側で語り合うシーンも秀逸。
世津だけは「戦争のあと」のことを考えている。「早よ結婚して、たくさん子どもを産んでお国に捧げたい」と無邪気に語る少女たちの話を二人に聞かせた後、「子どもらにそう言わせてるのはうちら大人や」と。だから戦争が終わったら私は教師になるんやと宣言する。
「そうや、いっぱい未来の話をしよう」という裕之(三浦春馬)の言葉と笑顔が心に残る。三浦春馬自身の未来をいっぱい見たかった。この作品が遺作になってしまった。
科学者の責任も問いかける。
実験道具や材料の貧困さに、無理に決まってるやん!と突っ込みを入れてしまった。
研究材料の調達先は清水焼の窯元。陶芸家が放射性物質が生み出す色の美しさを語る。修に分けてくれる硝酸ウランは黄色の釉薬。しかし、今は焼き物に色を付けることすら許されず、真っ白な骨壺を焼き続けている。それが娘のお骨を入れることになろうとは。「間が悪かっただけや」と語るが、こらえきれず、「はよ行ってくれ!」と叫ぶイッセー尾形の陶芸家の背中が痛々しい。
荒勝教授は、核爆弾を作ることよりも、軍の命令を「受け入れるふり」をすることで、若い研究者たちの出征をとどめ、未来を守ろうとした。
実験バカと言われた修が広島の地に立ち、自分たちの研究の結果をおもい知らされ、
次は京都に落とされると噂される原爆の一部始終を見届けたい、比叡山に観察基地を作るのだと登っていく。科学者の狂気をはらんだ眼を見た母は「科学者を息子に持った母の責任、疎開はしない、お前の勝手にしなさい」と突き放すが、翌朝、おにぎりの包みを玄関にそっと置いて送り出す。
数か月前、次男の裕之を戦地に送り出す日も、母はおにぎりを作っていた。そして玄関で裕之を抱きしめるのでなく、そっと息子の耳に触れ、その左手のぬくもりを失うまいと右手で大事に覆い、息子の背中を無言で見送った。ドラマでも映画でも、ここは涙が止まらなかった。田中裕子の提案による仕草だったそうだが、ずっと記憶に残る名シーンだと思う。
修が比叡山の中腹でおにぎりを黙々と食べ続ける、長回しのシーン。虫の声、鳥の声、風の音が次第に消え、なおも食べ続けている修の目の色が変わっていく。一切の台詞もなく。初見では気づかなかったが、無音のシーンが続く。突然、修が立ち上がり、おにぎりを放り出して、山を駆け下りていく。科学者の狂気から現実に立ち返っていくのか。世津が修を呼ぶ声がかすかに聞こえる。
台詞も何もなかったが、戦争が終わったことを世津が伝えに来たのである。
ノベライズを読んでいたので、その背景にあるものを十分にくみ取れたが、なかなかに深遠な場面だった。柳楽優弥の演技に引き込まれる。
私の両親世代は、この作品の主人公たちより少し上だったのではないか。父は師範学校の新任教師として、多くの学生を送り出したことに責任を感じていた。母も、「すでに大人だったから私たちにも戦争を止められなかった責任がある」と、長らく戦争体験を語ることを避けていた。東京大空襲の被害者だったにも関わらず。市井の若い平凡な人間にまで責任を感じさせていたのに、本当の戦争責任者はどうしていたのかと問い続けたい。
現代日本のコロナ禍、今も先が見えない。
核兵器廃止条約に参加しない日本。広島の平和集会でのあいさつ文を、特にこの条約についての一節を意図してか否か、読み飛ばした菅首相には唖然とする。戦争だけはもう二度と無い世の中であってほしい。科学はそのために貢献してほしい。研究の自由は保障されていてほしい。日本学術会議の任命拒否など、あってはならない。
コロナ禍も戦争も、一見異なるように見えて、国の指導者の本質は何も変わっていない気がして、そこが恐ろしい。
「この国の未来を明るくするには、自分の頭で考え、自分で見つめながら、自問自答するくらいの考えの人が一人でも増えること」と荒勝教授を演じた國村隼がトークイベントで、語っている。
この作品に参加した若い俳優さんたちが、真剣に当時の事を学び、自分で考え、台詞に命を吹き込んでいる。
公開初日は広島の原爆忌。舞台あいさつで柳楽優弥が、当日の朝の広島の式典で子どもたちが語った平和宣言に触れていた。彼ら世代の誠実な学びの姿勢に、未来を信じられる。
若い世代にこそ、見て感じて考えてほしい作品。
(アロママ)
監督、脚本:黒崎博
撮影:相馬和典
出演:柳楽優弥、有村架純、三浦春馬、田中裕子、國村隼、イッセー尾形
監督が広島の図書館で偶然見つけた科学者の日記をもとに、10年の構想を経て日米合作で制作され、昨年夏にはドラマとしても話題になった。
テーマが壮大。いくつもの視点で考えさせられる。はたして私にこの作品を語りきれるのか、とても消化しきれない思いを抱えたまま、印象に残ったシーンを取り上げたい。
買い出しという名の小旅行を母(田中裕子)に与えられた3人が出かけた丹後半島の海の美しさ。バスのエンストの為に野宿をするが、そこで静かに歌われる「ゴンドラの歌」の悲しい響き。夜中の海で、初めて裕之は死の恐怖を訴える。「戦争なんか終わってしまえ、勝ち負けなんか関係ない!」と世津が叫ぶ。
裕之の出発前夜、3人が縁側で語り合うシーンも秀逸。
世津だけは「戦争のあと」のことを考えている。「早よ結婚して、たくさん子どもを産んでお国に捧げたい」と無邪気に語る少女たちの話を二人に聞かせた後、「子どもらにそう言わせてるのはうちら大人や」と。だから戦争が終わったら私は教師になるんやと宣言する。
「そうや、いっぱい未来の話をしよう」という裕之(三浦春馬)の言葉と笑顔が心に残る。三浦春馬自身の未来をいっぱい見たかった。この作品が遺作になってしまった。
科学者の責任も問いかける。
実験道具や材料の貧困さに、無理に決まってるやん!と突っ込みを入れてしまった。
研究材料の調達先は清水焼の窯元。陶芸家が放射性物質が生み出す色の美しさを語る。修に分けてくれる硝酸ウランは黄色の釉薬。しかし、今は焼き物に色を付けることすら許されず、真っ白な骨壺を焼き続けている。それが娘のお骨を入れることになろうとは。「間が悪かっただけや」と語るが、こらえきれず、「はよ行ってくれ!」と叫ぶイッセー尾形の陶芸家の背中が痛々しい。
荒勝教授は、核爆弾を作ることよりも、軍の命令を「受け入れるふり」をすることで、若い研究者たちの出征をとどめ、未来を守ろうとした。
実験バカと言われた修が広島の地に立ち、自分たちの研究の結果をおもい知らされ、
次は京都に落とされると噂される原爆の一部始終を見届けたい、比叡山に観察基地を作るのだと登っていく。科学者の狂気をはらんだ眼を見た母は「科学者を息子に持った母の責任、疎開はしない、お前の勝手にしなさい」と突き放すが、翌朝、おにぎりの包みを玄関にそっと置いて送り出す。
数か月前、次男の裕之を戦地に送り出す日も、母はおにぎりを作っていた。そして玄関で裕之を抱きしめるのでなく、そっと息子の耳に触れ、その左手のぬくもりを失うまいと右手で大事に覆い、息子の背中を無言で見送った。ドラマでも映画でも、ここは涙が止まらなかった。田中裕子の提案による仕草だったそうだが、ずっと記憶に残る名シーンだと思う。
修が比叡山の中腹でおにぎりを黙々と食べ続ける、長回しのシーン。虫の声、鳥の声、風の音が次第に消え、なおも食べ続けている修の目の色が変わっていく。一切の台詞もなく。初見では気づかなかったが、無音のシーンが続く。突然、修が立ち上がり、おにぎりを放り出して、山を駆け下りていく。科学者の狂気から現実に立ち返っていくのか。世津が修を呼ぶ声がかすかに聞こえる。
台詞も何もなかったが、戦争が終わったことを世津が伝えに来たのである。
ノベライズを読んでいたので、その背景にあるものを十分にくみ取れたが、なかなかに深遠な場面だった。柳楽優弥の演技に引き込まれる。
私の両親世代は、この作品の主人公たちより少し上だったのではないか。父は師範学校の新任教師として、多くの学生を送り出したことに責任を感じていた。母も、「すでに大人だったから私たちにも戦争を止められなかった責任がある」と、長らく戦争体験を語ることを避けていた。東京大空襲の被害者だったにも関わらず。市井の若い平凡な人間にまで責任を感じさせていたのに、本当の戦争責任者はどうしていたのかと問い続けたい。
現代日本のコロナ禍、今も先が見えない。
核兵器廃止条約に参加しない日本。広島の平和集会でのあいさつ文を、特にこの条約についての一節を意図してか否か、読み飛ばした菅首相には唖然とする。戦争だけはもう二度と無い世の中であってほしい。科学はそのために貢献してほしい。研究の自由は保障されていてほしい。日本学術会議の任命拒否など、あってはならない。
コロナ禍も戦争も、一見異なるように見えて、国の指導者の本質は何も変わっていない気がして、そこが恐ろしい。
「この国の未来を明るくするには、自分の頭で考え、自分で見つめながら、自問自答するくらいの考えの人が一人でも増えること」と荒勝教授を演じた國村隼がトークイベントで、語っている。
この作品に参加した若い俳優さんたちが、真剣に当時の事を学び、自分で考え、台詞に命を吹き込んでいる。
公開初日は広島の原爆忌。舞台あいさつで柳楽優弥が、当日の朝の広島の式典で子どもたちが語った平和宣言に触れていた。彼ら世代の誠実な学びの姿勢に、未来を信じられる。
若い世代にこそ、見て感じて考えてほしい作品。
(アロママ)
監督、脚本:黒崎博
撮影:相馬和典
出演:柳楽優弥、有村架純、三浦春馬、田中裕子、國村隼、イッセー尾形











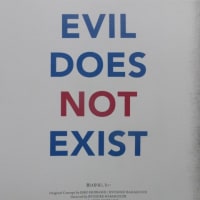


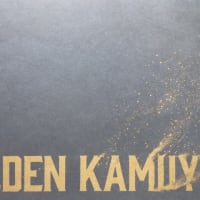


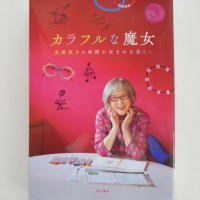

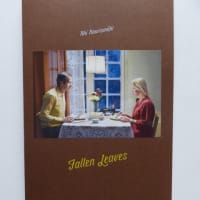

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます