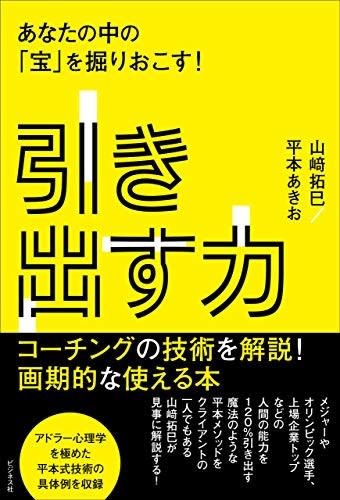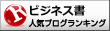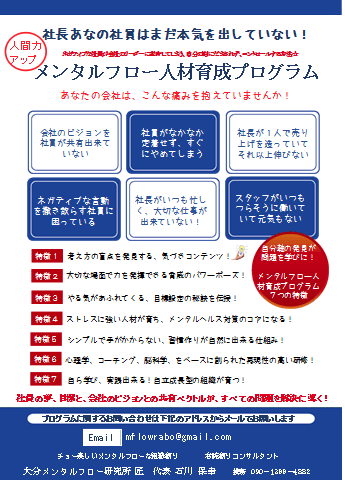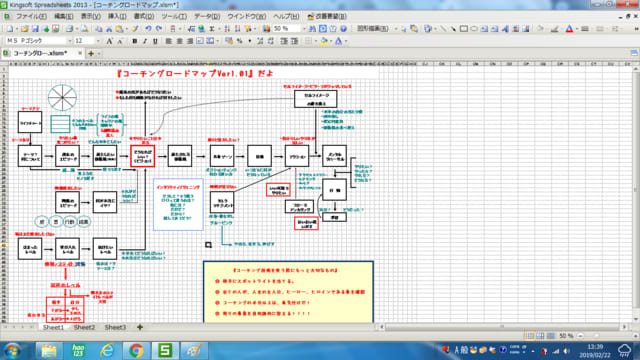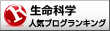【今回の重要なキーワード】
1、メンタルヘルスの導入は、まずは研修から
2、人はきつくいわなければ変わらないという思い込みは、最初に排除する
3、しかる前に一呼吸おく!感情に任せて怒るは、相手を支配するのが目的になっている
4、反省をさせるのが目的ではない、どうやったらできるようになるのか?目的だ!
5、行動に焦点をあて、一緒に何に取り組めば良いのか?を作り出す。
6、指導したことが、きちんと伝わったかを確認する
『ブラック企業・パワハラ企業と呼ばせないために!』
ほとんどの企業はご存じないと思いますが、現在急ピッチで、厚生労働省の、
メンタルヘルスに関するページが充実していっています。
ストレスチェック、メンタルヘルス対策、パワハラ、
それぞれ、動画やマニアル、研修資料のレジュメまで用意されているという、
至れり尽せりの徹底ぶりで、国の本気度が伝わってくる内容になっています。
2015年の12月に50人以上の社員を使用している事業所を対象に、
ストレスチェックの義務化が実施されるのをきっかけに、
2017年全企業の80%、2020年には、100%の事業所が
メンタルヘルス対策に取り組むことが計画で決まっています。
ページを閲覧していただくとびっくりするほど膨大な量の資料や、
情報、ツールがあって何から手をつけたらよいのか、迷うほどですが、
先日、直接厚生労働省の担当者に電話で質問したところ、
50人以下の事業所は、まず手始めに研修から行ってくださいと指導していただきました。
ここで最重要なポイントを1つだけご紹介します。
日本の企業の中だけでなく、日本人のほとんどの人が持っている、間違った思い込みです。
これを変えなければ、ほかの何をやってもうまくいきません、まずこの強烈な社会的思い込みを変えましょう。
それは、
『人はきつく言わなければ変わらない!』
自分はこの仕事が得意でできるという自己肯定感が高まっていない人に、
きつい言葉をかければ、つぶれてしまいます、はっきり言いますが、
この思い込みは、あまりにも指導方法としては幼稚で、まったく間違っています。

ページ内のパワハラ対策の研修内容を、少しだけ紹介すると!
パワーハラスメントにならない指導のポイント
管理職は部下を指導・育成する責務があり、時には厳しい指導や叱ることが必要な場合があります。
自身が権力・パワー を持っていることを自覚し、パワーハラスメントがもたらす自身や職場全体への影響、
デメリットを理解し、パワーハラスメントと とられない指導の方法を身に着け、常に意識していることが必要です。
① 叱る前に一呼吸おく。
まず一番に気を付けるべきなのは、冷静になることです。
感情的に叱ると、言葉もきつくなりますし、余計なことまで口 走る可能性もあります。
その場で指導するときは、一呼吸、深呼吸をして気持ちを抑えてから話始めましょう。
抑えき れない状況の時は、少し時間をおいて、改めて指導する場を設けるとよいでしょう。
② 指導が必要な具体的な行動に焦点をあてる。
部下のとった行動が、どのように、どの程度、
職場のルールや組織の共通目標に照らして不十分か、望ましくないのか
を具体的に示しましょう。
そして次にどのような行動をとるべきなのかを明確に示すことが大切です。
部下がなぜ叱られて いるのか、何を改善する必要があるのか、
理解できるように説明し、納得させてください。
③ 性格の非難や人格の否定はNG。
部下の誤った行動などを具体的に指導する場合にも、
その行動を一般化して「それだからお前はダメなんだ!」とか
「マネジャー失格だ!」など、部下の人格を否定したり、
性格まで言及することは避けなければなりません。
叱るときも部下の人格を尊重し、部下を育てる気持ちで接してください。
④ 指導が部下にどう伝わったか確認する。
指導・叱責をした後のフォローや声掛けが行われているかどうかも重要です。
叱りっ放しにせず、翌日などに様子を確認 して、
励ましの言葉をかけるなどの心遣いがあると嬉しいものです。
以上指導のポイントは、具体的な行動のほうに焦点を当てる、・・・すばらしいと思います。
研修のレジュメは、下記のURLからダウンロードできます。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download…
![[野田 俊作]の勇気づけの方法 アドラー心理学を語る](https://m.media-amazon.com/images/I/41h1oLrbK4L.jpg)
![[野田 俊作]の劣等感と人間関係 アドラー心理学を語る](https://m.media-amazon.com/images/I/41O-WEnE0gL.jpg)

参考文献:野田俊作著『勇気づけの方法』 『劣等感と人間関係』
まずは、社内で研修可能か?チャレンジしてみることをお勧めします、
もしも時間が取れない、研修できる人材がいないといわれる事業所さんは、
外注することになりますが、研修業者を選ぶポイントを3つ紹介しておきます。
1、研修指導される講師が、テキストに添ってわかりやすく説明できるだけでなく、
なぜ部下に研修で学んだやり方で指導したほうが、より良いのか、
それを指導した時部下の中でどういう事が起こるのか、それななぜなのか?、
研修内容を、習慣にしていくために何を工夫すればよいのか?明確に出来る講師であること!
2、ただメンタルヘルスの対策のための研修と捕らえるのではない、
コミュニケーション能力のアッが、会社の経営上、これからの業績アップに絶対必要なスキルであると理解し、
実際に社外の現場で使うことも想定した指導が出来るのか?ということ!
3、メンタルヘルスは、健康への問題も考えられることから、
ストレスが、脳機能、自律神経、免疫にどのような影響が出て、
またそれをいかに予防するのか、実践レベルのスキルを伝達できる、
経験を持った講師か?ということが最低条件として必要になってきます。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download…
https://ameblo.jp/isikawayasuyuki/
そしてnoteはじめました。
よろしければ、遊びに来てください!
https://note.com/c3421yxy