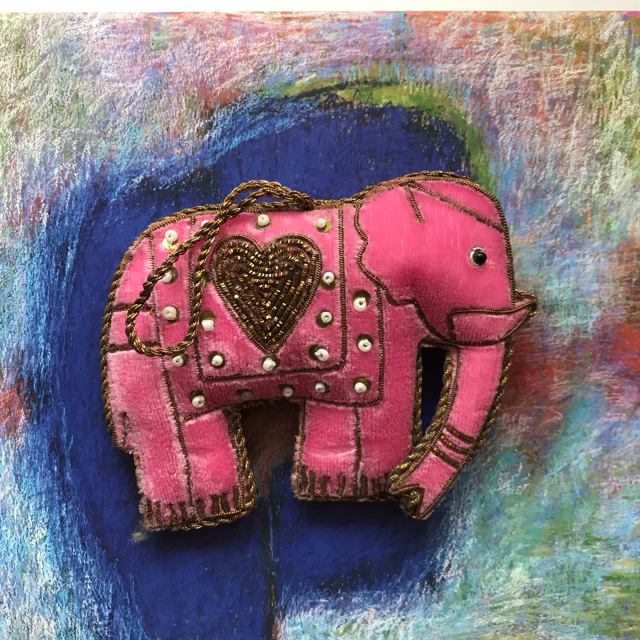没後50年を迎えた藤田嗣治の大回顧展が、今、東京都美術館で開催されています。こちら関西では、京都国立近代美術館で10月19日から始まります。すっごく待ち遠しい!
実はこのブログで藤田嗣治のことは、展覧会や書籍等、けっこう取り上げています。(一番多いかもしれない)
<展覧会>①レオナール・フジタとパリ ②藤田嗣治、全所蔵作品展示。 ③生誕130年「藤田嗣治展」 ④「藤田嗣治 本の仕事」
<書籍>⑤藤田嗣治 手仕事の家 ⑥藤田に魅かれる!
数奇な人生を生き、日本の美術史においても特異な存在に位置づけられてきた藤田。2009年に初めて展覧会を訪れ、その後もいろいろな側面にスポットを当てた展覧会を見たり、書籍で人生を辿ったりしてきたことで、私の中の藤田像は、かなりクッキリしてきたように思います。今回の大回顧展は、史上最大級の規模、しかも欧米からの初来日の作品も多数あるとのことで、また新しい一面を発見できるのでは、とワクワクしています。
今回の展覧会にあわせて発刊された美術手帖の特集号を購入。
サブタイトルに「世界への扉を最初に開いた日本の画家 ―現代アーティストが解き明かす、作品と人生」とあるように、執筆陣が豪華です。森村泰昌さん、諏訪敦さん、会田誠さんと小沢剛の対談、気鋭の批評家やキュレイターの鼎談、そして藤田研究の第一人者で、本展覧会の企画も担っている林洋子さん、などなど。
林さんが「これまでの展覧会は、(奥様の)君代さんがご存命だったこともあり、彼女の持ち物を優先する傾向がありました。本展は、初めて作品本位で世界各地から代表作を選んだものです」と書かれていたのが印象的でした。藤田の想いが、今にもつながっているんだな、と実感するとともに、新しい境地を開いた本展への期待も高まります。
技術や戦略がうまかったり、うまくなかったり…執筆者の皆さんが必要以上にリスペクトすることなく(むしろこき下ろしたり…)してるのが、おもしろいです。蔵屋美香さん・黒瀬陽平さん・梅津庸一さんの鼎談で、初期の「風景画」の重要性が語られているのが興味深く…。本展でもテーマの一つに「風景画」が取り上げられているのが、少し意外でもあったのですが、見るのがとっても楽しみになりました。
人としての人生と作品が、ここまで絡み合って魅力を放っている画家はそういないんじゃないかな、と私は思います。展覧会の作品を通して、その魅力をまるごと感じてきたいと思います!
東京展は、10月8日(月祝)まで。そして、いよいよ京都です!