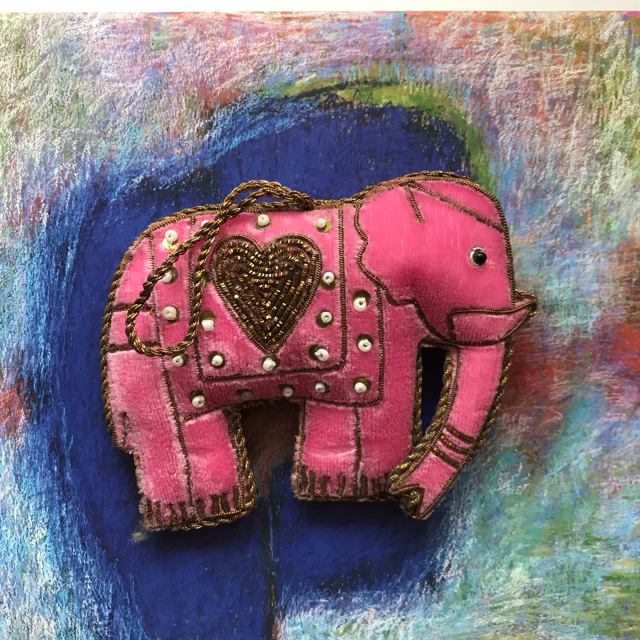<今日 世界は死んだ もしかすると昨日かもしれない>
東京都写真美術館が2年間の休館を経て、9月にリニューアル・オープン。そのオープニングと開館20周年の記念展として、現代美術家・杉本博司が創出する「異世界」を体験できる展覧会が開催されました。(11月13日で終了)
展覧会は2フロア。まず、迷い込むのは、一見テーマパークを思わせるほど作り込まれたインスタレーション。錆び付いたトタン板や古びた木材で区切られたブースに、人間の文明が終焉を迎える33のストーリーが展開されています。このストーリーは、33人のさまざまな職業人が語るという形がとられていて、手書きのキャプションがついているのだが、これを実際に書いたのは、杉本さんが依頼した著名な方々、例えば、「理想主義者」に浅田彰さん、「古代生物者」に福岡伸一さん、「ロボット工学者」に豊竹咲甫太夫さん、「ラブラドール・アンジェ」に束芋さん等々で、そのマッチングと筆跡を見るだけでもとても興味深いです。
展示されているのは、主に杉本さんご自身が蒐集されてきたコレクションで、そのストーリーを体現するような、古代生物の化石や石器時代の土器の破片から、歴史を証言する資料類、古美術品、歌って踊るロブスター、人ゲノムの遺伝子資料、隕石、宇宙食まで、夥しい「モノ」の数々…。以前、大阪で見た展覧会でも、素晴らしい古美術品のコレクションを披露されていましたが、杉本さんは美術品に留まらず、まさに「歴史」そのものを蒐集されているんだなあと、その多様さに驚きました。
33のストーリーは、すべて「今日、世界は死んだ。もしかすると昨日かもしれない。」という言葉から始まり、現代が抱える文明の危機、例えば人口増加、環境破壊、天変地異、生殖不能、戦争、ロボットの発達など、その萌芽が暴走し、ついに文明が滅んでしまうというもの。荒唐無稽で「ハハハ」と苦笑いしてしまうけど、実はあり得ないことではないことにも、うっすら気付いている…。なぜなら、そこに「モノ」があるから。長い年月を背負い、それにまつわる数多の人の手垢にまみれた、歴史の証言者ともいえる「モノ」が無言で語る力には、すごく強く重いものがあります。展示を見ている人たちの沈鬱な表情が印象的でした。
次のフロアでは、杉本さんの写真作品、新シリーズである「廃墟劇場」が9点、暗い会場に浮かび上がっていました。これは、以前からの「劇場」シリーズの発展形で、主にアメリカの廃墟と化した映画館にスクリーンを張り直し、映画をまるまる1本投影している間、長時間露光して写し取ったもの。ボロボロの劇場の中に、白く輝くスクリーンだけが、在りし日の輝きを放っているかのよう。一瞬を切り取る写真というものに、映画の上映時間が閉じ込められているという逆説もオモシロイ。
その背後の空間には、三十三間堂の千体千手観音を撮影した「仏の海」。1000年近く前の世の中の不安が、このような数え切れないほどの仏たちを作らせたとすれば、荘厳さがありながら、上のフロアから続く悪夢の先のようでもあり…。
なんだか、すっぽり異世界にはまったような鑑賞を終え、スマホを見たら、アメリカ大統領にトランプ氏が当選していて、思わず悪夢の続きか?!思ってしまいました!33のストーリーの中に、資本主義を追求し薔薇色の未来を喧伝して世界を滅亡に導いた「政治家」の話があり、カストロ議長のポートレイトと、歴代のアメリカ大統領が表紙に掲載されたタイム誌が展示されていて、最後にクリントン氏とトランプ氏が並んでいたのを、複雑な気持ちで眺めていたからです。
この先、人間が生きる未来はどうなっていくのでしょうか。私たちの近い未来と、その先の遠い未来と。