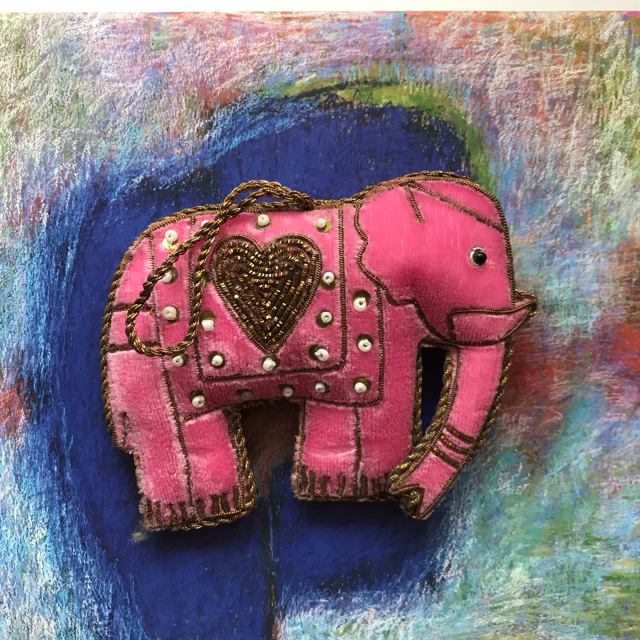ちょっと時間がたってしまった話題ですが、昨年11月に私が敬愛するミュージシャン、矢野顕子さんの新しいCD「Soft Landing」が発売されました。以前の記事にも書いたように、私が最初に矢野さんの音楽にしびれたのが「SUPER FOLK SONG」というピアノと歌だけの弾き語りアルバム。それ以来、いくつもの名作が生まれ、今作が7年ぶり5作目の弾き語りアルバムとなります。
この作品には、「SUPER FOLK SONG」という名曲に歌われている恋愛ストーリーの後日談となる「SUPER FOLK SONG RETURNED」が収録されているのも注目だったんですが、私がすごく気になったのが、矢野さんがこのアルバムを「ベヒシュタイン」というピアノで録音したということ。これまで矢野さんが愛用してきたのはスタインウェイ、そのブリリアントな音が矢野さんの声や演奏にピッタリだったのですが、それを変えたんですと?!
ベヒシュタインと聞いて思い出したのが、この本。なんと15年以上も前に購入したので、久し振りに手に取ってみるとページが茶色くなってました。(まだ売られているようでよかった!)
パリ左岸の裏通りにあるピアノ工房を舞台に、ピアノの魅惑的で深遠な世界にはまったアメリカ人の著者が、慈愛に満ちた眼差しで、ピアノという楽器とそれを巡るパリの人々について描いており、読んでいてとても幸せな気持ちになれる一冊です。
そこには、いろいろなピアノが登場するのですが、有名なスタインウェイやベーゼンドルファーの他、エラール、プレイエル、ガヴォー、シュティングル、ファツィオーリ、そしてベヒシュタイン!複雑かつ精巧な音の出る仕組みは同じでも、それぞれメーカーごとに独自の工夫が施され、実に個性的な音色が生み出されるというのです。
ドイツのベヒシュタインはピアノの世界三大メーカーのひとつで、伝統の技術に支えられた透明感のある音が特徴です。今回このピアノを使うことを勧めたのが、矢野さんの長年の盟友であるエンジニアの吉野金次さん。矢野さんが奏でるベヒシュタインの音は、私には少し湿り気を帯びたような、愁いと優しさと暖かさが交じり合った味わい深い響きに聞こえる。この新しいパートナーと対話を深めながら、ベヒシュタインならではのアレンジになっだんだなあと感じます。
12月のコンサートでも、このベヒシュタインを携えて演奏してくださいました。取り上げる曲も多彩なら、アレンジも自由自在、そして新しい楽器に出会うことで、演奏にも新しい可能性が広がった、ホントに素晴らしいミュージシャンの演奏を堪能できて幸せでした。
ますます新境地を開く矢野顕子さんに、今後もワクワク、期待が高まります!