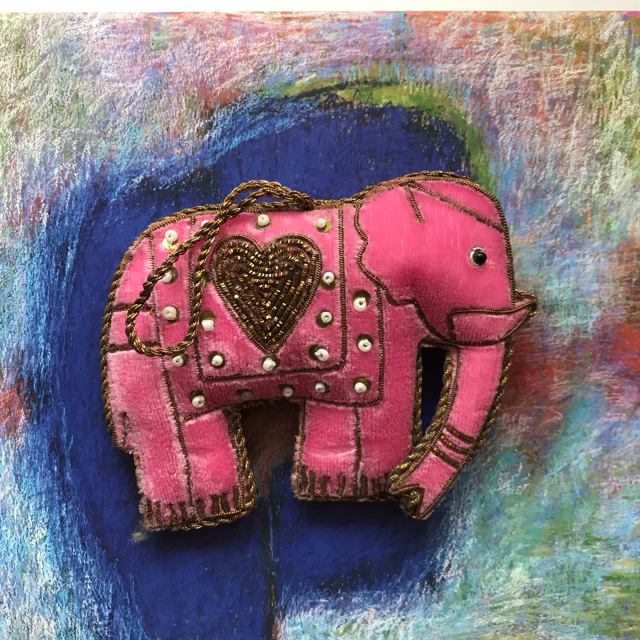ここ1年ほどで、京都のミニシアター系(アート系)映画館をめぐる状況が一変しました。3月末をもって、50年以上の歴史のあった「京都みなみ会館」が建物の老朽化により閉館。滋賀県に越してきてからは、ずいぶんお世話になりましたので、とっても淋しい…。移転後の再開が期待されますが、まだ未定のようです。
そして、ここ数年、非常に元気のあった「立誠シネマ」が、昨年7月に元・立誠小学校での活動を終了して後、出町桝形商店街に場所を移して、新しく「出町座」として、年末に移転オープン!この誕生にあたっては、私も映画館を応援したい!という気持ちからクラウドファンディングにも参加してみました。オープン以来、なかなか機会がなかったのですが、ついに先日、訪ねてまいりました。
京阪電車出町柳駅、地上に出ると、目に飛び込むのは涼やかな川の風景。ここは賀茂川と高野川が合流し三角州を形成している鴨川デルタと呼ばれるところ。飛び石渡りでも有名です。暑いくらいの5月の日差しの中、若者たちが憩っています。お~、なんて気持ちのいいところなんだ!
そこから歩いて10分もかからないところに、昭和の香りがぷんぷん漂う商店街の入口が見えてきます。その手前に、何やら行列が…、そう、有名な「出町ふたば」です。ここの「豆餅」は、風味豊かなあんこがたっぷり、大粒の赤えんどう豆が練り込まれた柔らかい口当たりのお餅が最高に美味しい!しかしながら、きょうはスルー。
そして商店街を進むと「出町座」がお目見えです。新しいのにすっかりなじんだ感のある素敵な外観。この映画館には、カフェとブックストアが併設されていて、映画だけではない文化の発信の場となっています。カフェでサンドウィッチとカフェオレをいただき、いろいろなジャンルに編集されている本たちを眺めます。私のお気に入りのフィルムアート社の本がたくさんあって、楽しかった!
それでも映画が始まるまでに時間があったので、商店街をぶらぶら。鯖寿司が美味しいと評判の「満寿形屋」は、もう夕方なので閉店してましたが、美味しい匂いが充満していた「ふじや鰹節店」で乾物など(これ持って映画館、行く?的な)を購入。古本屋もありました。絵本が前面に出ているのが珍しいな~。久しぶりに古本を眺める楽しさを満喫し、2冊ほどチョイス。何やら楽しいわ~。
ところで、今回、鑑賞した映画は、「ブンミおじさんの森」。タイの映画監督・美術家であるアピチャッポン・ウィーラセタクンが、2010年にカンヌ映画祭でパルムドールを獲得した作品です。Twitterでアート情報をフォローしていると、たびたび見かけるこの監督の名前、ぜひ一度作品を見てみたかったのです。
今、東京・森美術館でアピチャッポンの映像インスタレーションが紹介されているそうですが、今回、出町座で実現した特集上映。彼の名を知らしめた3つの長編作品に合わせ、自選短編集も上映されています。
「ブンミおじさんの森」は、何といえばよいのか、すごく不思議な映像体験でした。自分の中では、ブンミおじさんて沖縄のキムジナーみたいな人?と勝手に想像してたのだけど、そうではなく、家の中で(!)透析を行う重病の人だった。木々で埋め尽くされる森の映像も、思ったより緑が濃くなくて、これこそアジアの森なのかも、と思った。淡々と過ぎる日常の中に、亡き妻の幽霊や、行方不明となり毛むくじゃらの森の猿の精霊となって帰ってきた息子があらわれるのだが、それも当然のことのように受け入れられる。現実にはあり得ない…でも、その現実って何だろう?最後にはブンミおじさんも亡くなってしまうし、死の影がずっと漂ってはいるけど、すべてがナチュラルなのは、人と動物の垣根を越えた「転生」がこの作品のテーマだからなのでしょう。随所にタイ独特の文化や風習が見られるのも興味深いし、最後は、森と程遠い街の食堂のシーンで終わるのもシュール。
続けて、自選短編集も鑑賞。どれも20分以内の短いプログラムでしたが、アピチャッポンは映画監督というより映像アーティストだなと感じました。「音」にもすごくこだわっていたようで、水の音、風で木がざわめく音、が映像の主役でもありました。ブンミおじさんともつながる、死者を弔う行事を再現した作品は、感じ入るものがありました。
理解する、とかじゃなく感じる映像、ぜひ他の作品も見てみたいです。アピチャッポンの映画の上映は5月11日(金)まで。出町座、これからも通うぞ!