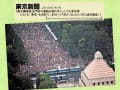[↑ ※「サルまで怒る 自民の腐敗」(週刊金曜日 1454号、2023年12月22日・2024年01月05月合併号)] /
/ /
/ (2024年05月06日[月])
(2024年05月06日[月])
連合のアノ体たらく。「労」の味方かと思っていたら、「使」やキシダメ独裁政権、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」「不明」党や下駄の雪党、お維やコミのミカタな連合・芳野友子会長。連合には、骨のある組合や組合員は居ないのかね? 日教組などは、こんな会長をさっさと蹴り出すべきでしょうに、何をやってるのでしょうか。救われない中小零細企業の労働者や非正規労働者ら。《賃上げに苦悩…余力がない中小企業経営者の板挟み 価格交渉で強く出られず「好景気の実感はない」けれど》(東京新聞)。
再度の引用。日刊スポーツのコラム【政界地獄耳/もはや連合は「第2経団連」 労働組合を名乗る資格はあるか】によると、《連合会長・芳野友子…首相、厚労相、経団連副会長らが列席する中、忖度(そんたく)したのか。最後には「正義を語り、未来を語り、人々に生きる希望を与えるのが政治家の仕事」と政治とカネが国民の一大関心事になっていても自民党という党名も出さずに妙な説明をした。去年「第2自民党でいい」という政党があったが、連合は「非自民・非共産」を返上、「自民党に寄り添い、第2経団連を目指す」と言うべきだろう。春闘も労働者が勝ち取るのではなく、政府に寄り添い成就か。労働組合を名乗る資格あるか。》
『●「死の商人」経団連会長人事…《安倍首相は「儲からない」
原発輸出に国民の血税を投入してバックアップ》』
『●軍事費倍増・消費税増税(法人税減税)…《政策をカネで買う》財界総理
《自民党への政治献金について「企業がそれを負担するのは社会貢献だ」》』
『●「労」も〝労〟なら、「使」も〝使〟、労使共々腐っている…十倉雅和経団連
会長と芳野友子連合会長が「利権」「裏金」「脱税」党に媚を売る醜悪な図』
呆れた、《裏金》《ヤミ金》やりたい放題の「利権」「裏金」「脱税」党から《政策をカネで買う》財界総理。自身の会社・住友化学の経営はどうなっているのですか? デタラメの限りを尽くすキシダメ政権の評価が…「ひとつひとつの施策はいいことをやっている。防衛、GX(脱炭素化)、原子力、デフレからの完全脱却など、きちっとした政策だと私たちは思っている」。正気なのかね。消費税増税をせがむ…(法人税減税してね! 「輸出戻し税」分の還付・丸儲けもお願い!)。
鈴木太郎・砂本紅年両記者による、東京新聞の記事【賃上げに苦悩…余力がない中小企業経営者の板挟み 価格交渉で強く出られず「好景気の実感はない」けれど】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/316899)によると、《今月13〜15日、城南信用金庫(品川区)と東京新聞が実施したアンケートによると、同信金と取引のある東京都と神奈川県の中小零細企業811社のうち30.9%が「賃上げの予定なし」と回答した。「賃上げをする予定」と答えた36.0%の企業の多くも、「従業員の意欲向上と人材定着」が理由で、人材のつなぎ留めに必死だ》。
【中小企業の賃上げはどうなる 賃上げを阻む構造【The Burning Issues】20240321】
(https://www.youtube.com/watch?v=dXwwoFB_CAw)
《デモクラシータイム》
《春闘は「5%超えの賃上げ」で沸いています。「賃金の上がらない国」に変化が出てきました。でも、物価も上がっています。果たして「賃金は物価を上回るか?」 焦点は、マイナスが続いている実質賃金がプラスに転ずるか。中小企業の賃上げが、どこまで広がるか、にかかっています。城南信用金庫の川本恭治理事長に登場いただき、取引先の中小零細企業の実態を伺いました。そこには、大企業の高額回答とは、全く別の世界がありました。賃上げしたくてもできない企業が3割もあります。どうしてこんなことになるのか。労働問題に詳しい和光大学名誉教授の竹信三恵子さんを交え、日本社会を支える中小企業で賃金が上がらない構造や格差が広がる産業の現実、政治の貧困などを語り合います。 2024年3月21日 収録》
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/316899】
賃上げに苦悩…余力がない中小企業経営者の板挟み 価格交渉で強く出られず「好景気の実感はない」けれど
2024年3月24日 06時00分
大手企業の大幅な賃上げが相次ぐ今春闘では、中小企業も個々の経営状況にかかわらず賃上げを迫られている。人手不足にあえぐほか、原材料費や人件費の上昇分を販売価格に十分転嫁できない課題も抱え、賃上げの余力に乏しい企業は少なくない。(鈴木太郎、砂本紅年)
◆今年も賃上げせざるを得ない状況、ではある
(商品の値上げや賃上げに関する悩みを語る
大崎商会の吉田進太朗社長)
「中小企業は価格交渉で大手ほど強く出られない。同業の中でも値上げはできている方だが、仕入れ値と人件費の全ては吸収できていない」。東京都品川区のねじ商社「大崎商会」の吉田進太朗社長(35)は悩ましげに語る。
役員含め15人が働く同社は、メーカーから仕入れた1000種類以上のねじを、自動車部品や電子部品の製造会社に販売する。吉田社長によると、ねじの原材料価格は4年ほどで3割ほど上昇。燃料代の高騰や人手不足にも悩むメーカーの要望をなるべく受け入れ、販売価格を順次引き上げてきた。
大手の賃上げムードにも押され、昨年は基本給の底上げに初めて踏み切った。最近の物価上昇から、今年も賃上げせざるを得ない状況と認識している。ただ、ねじ業界の売り上げは低調で、「好景気の実感はない」。得意先が離れる不安から交渉で思い切った値上げはできず、「利益率を下げて何とか対応している」。
◆「大手とは別次元」の中小 格差拡大への懸念
今月13〜15日、城南信用金庫(品川区)と東京新聞が実施したアンケートによると、同信金と取引のある東京都と神奈川県の中小零細企業811社のうち30.9%が「賃上げの予定なし」と回答した。「賃上げをする予定」と答えた36.0%の企業の多くも、「従業員の意欲向上と人材定着」が理由で、人材のつなぎ留めに必死だ。
個別企業から聞き取った声も「大手とは別次元」(目黒区・婦人服卸売業)、「ニュース番組などで大手の賃上げを見て、従業員がどう感じているか不安」(世田谷区・酒販売業)など格差拡大への懸念が寄せられた。大手への人材流出や、慢性的な人手不足に悩む企業も目立ち、賃上げの原資や人材確保のための補助金や制度拡充を国に求める声が相次いだ。
【関連記事】城南信金と東京新聞アンケート 中小企業の30.9%が「賃上げ予定なし」 大手は待遇改善が進むのに…
【関連記事】中小の賃上げは「原資がどれだけあるかに尽きる」 小林健・東商会頭「価格転嫁をしっかりやろう」
=====================================================
[※ 『この国の「公共」はどこへゆく』(花伝社)(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51XYxs4shnL._SX338_BO1,204,203,200_.jpg)] (2022年12月06日[火])
(2022年12月06日[火])
日刊ゲンダイの記事【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に薦めたい企業3社】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/315317)にて、《■城南信用金庫》《■久遠チョコレート》《■大川原化工機》の三つの「いい会社」が紹介されている。「久遠チョコレート」については存じ上げず、初めて知った。
城南信用金庫については:
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●脱原発は可能: ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●城南信金の吉原毅理事長が退任・・・
脱原発という、「理事長交代後も考え方は引き継がれ」て欲しい』
『●警察や消費者庁の沈黙…「商取引の原則」を無視して、
なぜ核発電料金を支払わなければならないのか?』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の救い様の無さと、
アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
『●東電核発電人災から7年: 「村の生活は百年余りにわたり、
人生そのもの」…「やっぱりここにいたいべ」』
『●中西宏明経団連会長《再稼働が進まない要因を、
原発と原爆を同一視する地域住民の理解不足と決めつけ》?』
『●核発電「麻薬」中毒患者・中西宏明経団連会長自ら、
ニッポンは《民主国家ではない》ことを立証して見せた』
『●「しなやかな反骨」をテーマに東京新聞のシリーズ対談:
城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さん』
『●《継承》《前例踏襲ばかり》の大惨事アベ様政権・スガ様…《故
吉岡斉さん…「原発はリスクを伴う。過大な投資のつけは国民に回る」》』
『●城南信金元理事長・吉原毅さん「原発推進というのは明らかに国民全体の
幸福に反すると確信したので、それはいけないと主張すべき…」』
大川原化工機については:
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
未来工業はいまどうなのだろう?
『●「報われない国」の労働環境の「質」の劣化』
「人を大事にする経営で知られる岐阜県の未来工業(電気・ガス設備
資材)は、全員が正社員で定年も七十歳。昭和四十年の創業以来、
赤字はなく、社員約八百人の平均年収は六百二十万円(四十三歳)。
好業績は社員の提案に基づく商品開発力にあるという。かつてと違い、
大手企業からヒット商品が生まれないのも人件費削減に躍起な経営と
無縁ではあるまい。/ところが安倍政権は「世界一企業が活動しやすい国」を
掲げ、解雇しやすい正社員といわれる「限定正社員」など雇用流動化に
力を入れる。派遣労働についても規制緩和を一段と進める方針である」
『●「報われない国」のこんな労働環境質の悪い中での希望の光』
『●「政策をカネで買う」経団連の企業行動憲章には
「従業員のゆとりと豊かさを実現する」と謳っている』
【【私説・論説室から】儲かる秘訣を尋ねたら…】《「人材確保、
人材雇用という時の、人材の『材』の字が気に入らない。人間は
材料じゃない。財産の『財』、人財と書くべきだ」
型破りな経営で半世紀近く、目を見張る好業績を続けてきた
名物経営者が七月末に逝った。岐阜県に本社がある電気設備資材
メーカー「未来工業」の創業者、山田昭男さん。
社員をとことん大事にした。残業なし。パートや派遣社員なし。
八百人の社員は全員正社員だ。年間休日はおそらく日本一の百四十日。
有給休暇四十日を合わせれば一年の半分は休日になる。六十代社員の
平均年収は約七百万円、それが定年の七十歳まで続く。
「豊かな人生が、やる気を生む」という信念からだ。唯一社員に
求めたのは常に考えること。アイデア、提案、何でも一件五百円で
買い取り、それが国内有数のシェアにつながった。》
『●「優しくすれば、社員もここを守りたいと働いてくれる」:
未来工業の創業者のお一人が亡くなる』
=====================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/315317】
辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に薦めたい企業3社
公開日:2022/12/05 06:00 更新日:2022/12/05 06:00
(佐高信氏(C)日刊ゲンダイ)
辛口の経済評論家として知られる佐高信氏の新著、「この国の会社のDNA」(発行/日刊現代)には帯に「裏・就職読本」とある。長年、日本の企業の身勝手、閉鎖性を取材し、警鐘を鳴らし続けてきた筆者が有名企業の「体質=DNA」を痛快に活写した本だが、その内容たるや表の就職読本はもちろん、ネットでもなかなか読めないものばかり、就活生に大いに参考になるからだ。
例えば、東京電力を紹介するページでは2011年の株主総会の描写がある。入口に「撮影、録音、配信につきましてはご遠慮願います」と書いてあって、佐高氏は仰天したという。過去にも不祥事を起こした企業の株主総会は見てきたが、こんな無反省な会社は初めてだと佐高氏は驚く。同時に、記者が抗議すらしなかったことにがっくりする。そして、<居丈高な掲示に象徴されるように東電は株主に対してだけでなく社会に開かれていない。利用者、株主、労働組合、そしてマスコミ、いずれのチェックもきかず、裸の王様になって迷走している>と佐高氏は書くのだ。
まさに一刀両断、痛快だが、だとすると、そんな佐高氏が「いい会社」として、就活生に薦める企業はどこなのか。これが大いに気になってくる。そこで佐高氏に「これは」という3社をあげてもらった。佐高氏がこの3社についてどう書いたか。全文を紹介しよう。
■城南信用金庫
(城南信用金庫の吉原毅顧問(C)日刊ゲンダイ)
城南信金だけでなく、信金界のドンだった小原鐵五郎の遺したセリフがいい。
「信用金庫は銀行に成り下がるな」
みんな成り上がりたがるが、「銀行に成り下がるな」は言い得て妙だろう。
元理事長の吉原毅が元文部官僚の寺脇研や前川喜平と語った『この国の「公共」はどこへゆく』(花伝社)によれば、吉原が大学を出て就職試験を受けた時、役員面接とかで、「銀行とは公共的な存在ですよね。私は公共的な仕事がしたいので銀行に勤めたいと思います」と言ったら、きょとんとされたという。
また、愛読書を聞かれて太宰治の『人間失格』と答えて落とされた。
信金も銀行と同じように利益だけを求めているのだろうと思ったら、前記の小原の言葉を知らされたのである。
信金は公共的使命をもった協同組織金融機関であり、「世のため人のために尽くすことがわれわれの使命だ」と小原はためらいもなく言った。
吉原の祖父は城南信金の常務理事だったが、吉原が4歳の時に強盗に襲われて亡くなっている。小原はその祖父の知人でもあり、信じられる人だと思って城南信金に入った。小原の言葉で有名なのに「貸すも親切、貸さぬも親切」というのもある。
吉原は2010年に理事長となったが、翌年、あの東日本大震災が起こった。東京電力福島第1原発の大事故で大変なことになる。
それを機に吉原は脱原発に踏み切った。組織の方針をそのようにはっきりと決めたのである。多分、さまざまな圧力があっただろう。いまでもあるに違いない。しかし、城南信金はそれを貫いてきている。
「原発推進というのは明らかに国民全体の幸福に反すると確信したので、それはいけないと主張すべきだと思いました」と語る吉原は「原発推進で動くカネに目がくらむ企業は、企業としての誇りがなくなるはずです」とも言っている。
■久遠チョコレート
(QUON(久遠)チョコレート代表の夏目浩次氏の
インスタグラムから)
『死刑弁護人』や『ヤクザと憲法』などのユニークなドキュメントをプロデュースしている東海テレビの阿武野勝彦と『俳句界』の2021年11月号で対談した時、彼が「チョコレートな人々」を映画にしようとしていると発言した。テレビで「久遠チョコレート」という50事業所ほど展開している会社を放送したのだが、「その後」を加えて映画化するというのである。阿武野の発言を引く。
「社長の夏目さんはいま40代なんですが、どんどん事業を展開しています。この人は、20代で、障害を持った人たちが最低賃金すらもらえていないという姿を見て、豊橋の商店街にパン屋を出して雇用したんです。その17年後、チョコレートに出会って転換。パンは、焼き損じたり、日が経ったりすると捨てないといけないですが、失敗してもチョコレートは温め直したらもう1回やり直せる。テンパリングなど作業にこだわりのある人に向ているかもということで。付加価値もパンより大きいので利益を貧困地域の子供食堂に充てたりと展開していく」
放送後に、「使える障害者しか雇っていないんでしょう」という批判が出たので、社長の夏目浩次は「それならば、寝たきりの人もできる仕事を」とチョコレートを破砕する工房をつくった。「使える障害者」というコトバに私はひっかっかる。会社にとって「使える」ということだろうが、会社を人間に合わせてもいいのではないか。会社本位主義をひっくり返す会社としても私はこの会社に注目したが、「社会をたのしくする障害者メディア」が謳い文句の『コトノネ』の42号に、夏目浩次が始めた久遠チョコレートが取り上げられている。
夏目は都市設計の会社に勤めて「仕方がないを覚えろ」と教えられ、違和感を抱く。
そして障害者施設と関わりができ、クロネコヤマトの宅急便の創業者、小倉昌男の『福祉を変える経営ー障害者の月給一万円からの脱出』を読んで、施設の人に問うた。
「そもそも1万円なんて月給じゃないよね」
福祉はおカネじゃないと思っていた彼らはポカンとしたり、嫌な顔をした。
そして夏目は障害者と共にパン屋を始めたが、見事に失敗する。パン屋は重労働の弱い事業だった。いろいろ考えて次にチョコレートをスタートさせる。
「人はみな凸凹あるわけなので、そのままでいいだろうって、それを無理に標準化させてはいけない。ありのままで、それをどういうふうに、凸凹組み合わせていくかっていうことを、チョコレートが実現させてくれた」
夏目はこう語っているが、仕事に合った人を選ぶより、人に合った仕事をつくり出す方がおもしろかったのである。既製服に合った人を探したり、無理矢理、レディメードの服を着せるより、ひとりひとりに合った服を見つけるか、つくる方に引かれるという夏目の発想は、とりわけ窮屈な日本の企業社会を超える道を示唆している。
■大川原化工機
(起訴取り消しについて思いを語る大川原化工機の
大川原正明社長(C)共同通信社)
偏狭な政治によって優秀な中小企業が破綻の淵に追い込まれた大川原化工機の事件を語る前に、やはり現在のような中国排除(それに経済安保の名をかぶせる)に抵抗した倉敷絹織(現クラレ)の社長、大原総一郎について触れよう。
大原社会問題研究所を設立した大原孫三郎の息子だった総一郎は企業の社会的責任を強調し、公害の発生者責任を高唱した。
その総一郎が1960年代に中国向けにビニロン・プラントを輸出しようとして、いわゆる台湾派の政治家や右翼のいやがらせを受ける。しかし、彼は自分の考えを曲げず、1年半にわたる粘り強い説得によって、時の首相、池田勇人や、ワンマン吉田茂、それに池田の次に首相になる佐藤栄作らを説き伏せ、このプラント輸出を認可させた。もちろん、中国との国交回復前で、アメリカや台湾の反対も激しかった。現在とよく似ているだろう。この時の思い出を、のちに総一郎はこう書いている。これは、対中プラント輸出を思いとどまれば、アメリカや台湾から商談が来る。その方がずっといいではないかと、彼を翻意させようとする財界人たちに対する答えでもあった。中国に対する戦争責任も総一郎の思想の根底にはあったのである。
『世界』3月号に載った青木理のルポ「町工場vs公安警察」という大川原化工機事件についてのドキュメントを読むと、大企業だから大原総一郎は意思を貫くことができたのであって、中小企業は目をつけられたら逃れられないと、改めて経済安保なるものの危険性を痛感せざるをえない。
2020年3月11日、横浜に本社のある化学機械メーカーの大川原化工機の社長ら3人が警視庁公安部に逮捕され、330日以上にもわたって勾留された。生物兵器の製造にも転用可能な化学機械を無許可で中国に不正輸出したという容疑をかけられてだった。
同社は経営理念に「平和で健康的な社会作りに貢献する」と謳うほど「平和への貢献」にこだわってきた。
しかし、警視庁公安部外事1課の「強引で偏見に満ちた見込み捜査」によって、クロと認定される。そして東京地検が3人を起訴したが、初公判の4日前に検察が起訴を取り消すという異例中の異例の結果になった。それほどムチャな捜査だったということである。
経済安保なるものが進められていけば、こうした例は増えていくだろう。政治という名の歪んだ思想が生活に基づいた経済をつぶしていくのである。
同社は逮捕直後から銀行に融資をストップされ、部品の納入元や取引先との関係も大幅に制約されたという。それらは容易に元に戻らない。
◇ ◇ ◇
どうだろうか。どれも個性的で魅力あふれる社風である。佐高氏にどんな基準でこの3社を選んだのかも聞いてみた。
「寄らば大樹で会社に入ろうとする者にすすめる会社はありません。働く意味を求めて入社しようとする者にすすめられる会社を選びました」
就活生はぜひ、参考にしてほしい。(文中敬称略)
=====================================================
[※ 『この国の「公共」はどこへゆく』(花伝社)(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51XYxs4shnL._SX338_BO1,204,203,200_.jpg)] (2021年02月11日[木])
(2021年02月11日[木])
日刊ゲンダイのコラム【佐高信「この国の会社」/「銀行に成り下がるな」を地で行く誇り高き城南信用金庫】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/284834)。
《元理事長の吉原毅が元文部官僚の寺脇研や前川喜平と語った『この国の「公共」はどこへゆく』(花伝社)によれば、吉原が大学を出て就職試験を受けた時、役員面接とかで、「銀行とは公共的な存在ですよね。私は公共的な仕事がしたいので銀行に勤めたいと思います」と言ったら、きょとんとされたという》。
まもなく、東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。
さて、城南信用金庫、そして、吉原毅さん。東京電力核発電人災の直後から注目していました。
《「原発推進というのは明らかに国民全体の幸福に反すると確信したので、それはいけないと主張すべきだと思いました」と語る吉原は「原発推進で動くカネに目がくらむ企業は、企業としての誇りがなくなるはずです」とも言っている》。
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●脱原発は可能: ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●城南信金の吉原毅理事長が退任・・・
脱原発という、「理事長交代後も考え方は引き継がれ」て欲しい』
『●警察や消費者庁の沈黙…「商取引の原則」を無視して、
なぜ核発電料金を支払わなければならないのか?』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の救い様の無さと、
アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
『●東電核発電人災から7年: 「村の生活は百年余りにわたり、
人生そのもの」…「やっぱりここにいたいべ」』
『●中西宏明経団連会長《再稼働が進まない要因を、
原発と原爆を同一視する地域住民の理解不足と決めつけ》?』
《原発を推進する経団連の中西宏明会長が原発について一般公開の
討論を提唱していることを受け、原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟
(原自連)は十四日、経団連に公開討論会の開催を要請した…
中西氏は年初に際した報道各社とのインタビューで、原発について
「国民が反対するものはつくれない」と述べ、「真剣に一般公開の討論を
するべきだ」と発言。この発言について、原自連会長の吉原毅・
城南信用金庫顧問は…「非常にまっとうなご判断。
公開討論で議論を深めたい」と話した》
『●核発電「麻薬」中毒患者・中西宏明経団連会長自ら、
ニッポンは《民主国家ではない》ことを立証して見せた』
『●「しなやかな反骨」をテーマに東京新聞のシリーズ対談:
城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さん』
『●《継承》《前例踏襲ばかり》の大惨事アベ様政権・スガ様…《故
吉岡斉さん…「原発はリスクを伴う。過大な投資のつけは国民に回る」》』
=====================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/284834】
佐高信 評論家
1945年山形県酒田市生まれ。「官房長官 菅義偉の陰謀」、「池田大作と宮本顕治 『創共協定』誕生の舞台裏」など著書多数。有料メルマガ「佐高信の筆刀両断」を配信中。
佐高信「この国の会社」
「銀行に成り下がるな」を地で行く誇り高き城南信用金庫
公開日:2021/02/08 06:00 更新日:2021/02/08 06:00
(城南信用金庫の吉原毅顧問(C)日刊ゲンダイ)
城南信金だけでなく、信金界のドンだった小原鐵五郎の遺したセリフがいい。
「信用金庫は銀行に成り下がるな」
みんな成り上がりたがるが、「銀行に成り下がるな」は言い得て妙だろう。
元理事長の吉原毅が元文部官僚の寺脇研や前川喜平と語った『この国の「公共」はどこへゆく』(花伝社)によれば、吉原が大学を出て就職試験を受けた時、役員面接とかで、「銀行とは公共的な存在ですよね。私は公共的な仕事がしたいので銀行に勤めたいと思います」と言ったら、きょとんとされたという。
また、愛読書を聞かれて太宰治の『人間失格』と答えて落とされた。
信金も銀行と同じように利益だけを求めているのだろうと思ったら、前記の小原の言葉を知らされたのである。
信金は公共的使命をもった協同組織金融機関であり、「世のため人のために尽くすことがわれわれの使命だ」と小原はためらいもなく言った。
吉原の祖父は城南信金の常務理事だったが、吉原が4歳の時に強盗に襲われて亡くなっている。小原はその祖父の知人でもあり、信じられる人だと思って城南信金に入った。
小原の言葉で有名なのに「貸すも親切、貸さぬも親切」というのもある。
吉原は2010年に理事長となったが、翌年、あの東日本大震災が起こった。東京電力福島第1原発の大事故で大変なことになる。
それを機に吉原は脱原発に踏み切った。組織の方針をそのようにはっきりと決めたのである。多分、さまざまな圧力があっただろう。いまでもあるに違いない。しかし、城南信金はそれを貫いてきている。
「原発推進というのは明らかに国民全体の幸福に反すると確信したので、それはいけないと主張すべきだと思いました」と語る吉原は「原発推進で動くカネに目がくらむ企業は、企業としての誇りがなくなるはずです」とも言っている。=文中敬称略
=====================================================
[※ ↑【夕食会5年間900万円分の領収書破棄か 安倍前首相の政治団体宛てに発行<桜を見る会問題>】(東京新聞 2020年11月26日)] (2021年01月03日[日])
(2021年01月03日[日])
マガジン9のインタビュー記事【伊藤塾 明日の法律家講座レポート/憲法と教育〜1947年教育基本法から安倍・菅政権まで〜講師:前川喜平氏】(https://maga9.jp/201223-5/)。
《7年8ヶ月続いた安倍政権から菅政権へと続く官邸一強体制は、本来自由であるべきメディア、文化、学問、そして教育の分野にも影響を及ぼしています。憲法と教育をめぐる問題について、また、これからの日本の政治教育がどうあるべきかについて、元文部科学事務次官の前川喜平氏にお話しいただきました》
『●小田嶋隆さん《行政の担当者としてのあたりまえの習慣を、
安倍晋三氏とその追随者たちは…この8年の間に完膚なきまでに破壊》』
『●息吐く様にウソをつく《稀代の“嘘つき総理”》による7年8カ月に
及ぶ《憲政史上最悪と名高い安倍政権》…漸く「前夜祭」の真相が』
『●息吐く様にウソをつくアベ様の政の下、この7年8カ月で社会は
どんどんと壊れていった。さらにスカスカオジサンにも《ビジョンはない》…』
『●《No1 募っているが募集しているという認識ではなかった …
No39 私が言っている方がおかしいと思う方、手を挙げてください》』
『●【中村敦夫/…嘘もひどいが答弁拒否は度が過ぎている】《Go Toの
正体は、オトモダチで税金をむさぼり、衆院選挙の準備へGo!》?』
息吐く様にウソをつくアベ様の政の下、この7年8カ月で社会はどんどんと壊れていった。スカスカオジサンにも《この国の未来を見据えたビジョンはない》。
教育においても、「教育再生」「教育改革」という名の教育破壊。「子育て支援など社会保障の充実を据える「1億総活躍社会」の推進」・「子育ての党」を詐称する与党・自公。癒着党・お維もハタやウタの推進が大好きだ。「教育再生」という名の下で、教育破壊してきた皆さんに投票し、支持している「1/4」の皆さんや、投票に行かないことで間接的に自公お維を支持しておられる「2/4」の皆さんの気が知れません。
この教育破壊までも、無《責任政党》総裁・スカスカオジサンも《継承》するつもりでしょうかね?
『●「日本教育再生機構大阪」という「教育破壊」つながり…
「安倍首相を中心とする異様な翼賛と癒着の構造」』
『●ハタやウタを強制し内心をかき乱す…「良心か職か」、
そんな冷たき「強制の発想」を支持する最「低」裁』
『●「教育再生」という名の教育破壊…「子どもから変えていこう
という動きは実に悪賢い」(小澤俊夫さん)』
「教科書検定や「ト」な歴史教科書の採択強要 ハタやウタの強制、
道徳の教科化(文科省道徳教育教材『わたしたちの道徳』)、
教育勅語の復活、古くは忠魂碑訴訟…現代の教育破壊は着実に
進む…。大変に憂慮すべき現状なニッポンの教育環境」
「《戦争屋》のアベ様らには、侵略戦争への反省も無く、壊憲して再び
「戦争のできる国」へ…、《自分たちの加害をはっきり残し
『もう絶対にやらない』と世界に約束している》ドイツと彼我の差。
そして今、「教育再生」という名の教育破壊が進む。札束で頬を
打つように、最高学府の研究・教育にまで侵食」
『●「教育再生」という名の教育破壊…《二つの流れには共通する
底流があるように思う。要は「安上がり」なのではないか。》』
『●【NNNドキュメント カネのない宇宙人 信州 閉鎖危機に揺れる
天文台】…《「経済的利益」を重視する国の政策によって…資金》大幅減』
「2005年から運営費交付金を年1%削減し続ける文科省。人件費が
どんどんと削られ、研究者が減らされていく。文系どころか、理系に
対しても未来に投資しない国。一方、巨額の軍事研究費で研究者の
良心を釣る。おカネ儲けのことしか考えていない独裁者・アベ様ら。
この国ニッポンの科学の未来はトンデモなく暗い…。」
アベ様やカースーオジサンによって、如何にニッポンは壊されていったかのか? 《本来は自由で自律的でなければならない分野にまで政治支配が及ぼうとしている》(前川喜平さん)。
『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」』
『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差』
『●前川喜平前文科次官、「本来、できてはいけないものが
完成した。見たくないものを見たという感じだ」』
『●前川喜平さん授業…検閲と恫喝、《意に沿わない人物は潰す――。
…安倍政権のやり口は、まさに恐怖政治》』
『●隗より始めよ: 「この国をガタガタにし、
支持率3割は取れる」高プロとして、「自分らができてから…」』
『●霞が関: 「佐川になるな前川になれ」…
《佐川のような官僚ばかりだったら絶望するしかないだろう》』
「日刊ゲンダイの佐高信さんによる書評【週末オススメ本ミシュラン/
「面従腹背」前川喜平著/毎日新聞出版】…。《落語家の立川談四楼が
ツイッターで、いま霞が関では<佐川(宣寿前国税庁長官)になるな
前川になれ>が合言葉になっているとつぶやいたらしい。
もちろん皮肉である。/…佐川のような官僚ばかりだったら
絶望するしかないだろう》」
『●〝前川喜平になるな佐川宣寿になれ〟!?
「官邸べったり」藤原誠官房長の文科事務次官への昇格人事』
『●「しなやかな反骨」をテーマに東京新聞のシリーズ対談:
城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さん』
『●前川喜平さん《社会全体が子どもたちを支えられるように、子どもたちに
税金を使う仕組みを作らなければいけない》…逆行するアベ様政権』
=====================================================
【https://maga9.jp/201223-5/】
伊藤塾 明日の法律家講座レポート
憲法と教育〜1947年教育基本法から安倍・菅政権まで〜講師:前川喜平氏
By マガジン9編集部 2020年12月23日
7年8ヶ月続いた安倍政権から菅政権へと続く官邸一強体制は、本来自由であるべきメディア、文化、学問、そして教育の分野にも影響を及ぼしています。憲法と教育をめぐる問題について、また、これからの日本の政治教育がどうあるべきかについて、元文部科学事務次官の前川喜平氏にお話しいただきました。[2020年11月28日@渋谷本校]
――――――――――――――――――――――――――――――――――
官邸一強体制による政治支配の広がり
安倍政権が7年8ヶ月続いて退陣し、いま菅政権になって3ヶ月です。この安倍・菅政権の大きな特徴は、官邸が非常に強い政治権力を握っていることです。「官邸一強」体制という状況です。強い権力は続けば必ず腐敗すると言われますが、そういう状況が現に起こっていると私は思っております。
たとえば安倍政権時代には、憲法9条のもとでは集団的自衛権は認められないという見解を持っていた内閣法制局長官をクビにして、その代わりに集団的自衛権は認められると解釈する人を据え、解釈改憲を断行しました。また、菅政権になってからは、極めて高い独立性と自律性を持った国家機関である日本学術会議にまで政治支配を及ぼそうとしています。
この官邸一強体制が国家機構の中での三権分立の仕組みまで壊してきています。それだけではなく、国家権力の外にあって、本来は自由で自律的でなければならない分野にまで政治支配が及ぼうとしているのです。その一つはメディア、新聞やテレビですね。それから教育、文化や学問といったところにまで政治の支配が及ぼうとしていて、非常に危ない状況があると思います。
本日の講演は「憲法と教育」というタイトルですけれども、教育との関係でも危ないことが起きているというお話をさせていただこうと思っております。
教育基本法と日本国憲法
今から73年前の1947年、教育基本法は戦前の日本の教育に対する深い反省のもとに作られました。戦前の日本教育は、国の言うことをなんでも信じ込んでしまう子どもたちを育ててしまった。そうではなく、一人ひとりがちゃんと自分で考えて行動できる、そんな健全な市民を育てよう――こういう考え方で教育基本法ができたわけです。現在ではこの教育基本法は「改正」されていますが、ここでは改正前の法のことを単に「教育基本法」と呼んでお話ししていきます。
この教育基本法はGHQが日本に押し付けたものだと言う人がいるのですが、当時、戦後の教育の在り方を考える学者たちを集めた教育刷新委員会と文部省との間で、非常に緻密な協議を行った上で作られた法律なんです。当時の文部省では、文部大臣、次官や局長もみんな学者でした。そして教育刷新委員会も学者や教育者で作られていた委員会でした。少なくとも、この教育基本法を作ったメンバーの中に、いわゆる「政治家」はいないんです。
そして、内容を議論する上で、日本国憲法との関係が非常に強く意識されていました。このことは、教育基本法の前文に非常にはっきりと記されております。
〈われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである〉
憲法の理想にある民主主義や平和、こういうものを実現するためには教育の力が必要だということを言っていたわけです。逆に言うと、戦前のような全体主義、軍国主義のような教育に戻ってはいかんという、戦前の教育に対する痛切な反省がここにはあります。日本国憲法の一番大切な価値は「個を尊重する」ということです。一人ひとりの人間をかけがえのない存在として尊重する。教育基本法は、この根本に立ってつくられたのです。
自分で考えて行動できる独立した精神を育てる
教育基本法は、その第一条で「教育の目的」を打ち出しています。教育の目的には2つあり、第一は「人格の完成」です。人間にとって一番大事なものは何かといえば、私は自由だと思います。つまり自由で独立した人格を持った人間、その人格の完成というのが第一の目的です。そして第二の目的は「平和的な国家及び社会の形成者として」の国民の育成です。これら2つの目的が相まって、民主主義の担い手を育てるということになるわけです。
つまり自分で考えて行動できる独立した人格と精神を持った自由な人間が、まず存在しなければいけない。この教育基本法の中に出てくる「形成者」という言葉が非常に大切で、最初から国家や社会が存在しているのではなく、国家や社会は我々が作り上げていくものなのです。こういう思想がこの「形成者」という言葉の中に含まれているのです。
一方、あらかじめ国が存在しているというのが戦前の考え方でした。神武天皇から始まる国体というのがあって、日本人は世界に冠たる国体を持つ日本という国に生まれた宿命を持つという考え方です。教育勅語もそういう考え方に基づいていたのですが、教育基本法では、まず人間がいて、その人間が社会や国家を作る。「市民社会の担い手である自由な市民を育てる」ことが目的だといえます。
天皇制と家制度による戦前の教育方針
ところが、この教育基本法を制定当初から快く思わない人たちがいました。それは主に教育勅語との関係からです。1890年に作られた教育勅語は、その後五十数年の間、日本の教育を支配したわけです。特に最後の1930年代以降は、教育勅語がファナティック(狂信的)なカルト教団の教義みたいになってしまいました。
実は、教育勅語そのものは、戦後に教育基本法ができた後もしばらく残っていました。教育基本法が制定されたのは1947年3月ですが、翌年1948年6月になってから、教育勅語をこのままにしてはいけないと衆院参院それぞれで決議を行っています。衆議院の決議では、これは憲法に違反する文書であるから排除すると宣言しました。参議院では、教育基本法ができたので教育勅語は失効したという確認をしました。これで教育勅語の命は絶たれたと思われていたのですが、復活させたいと思う人、教育勅語に代わる国民道徳が必要だと考える人が結構いたわけです。
たとえば、1950年代に文部大臣だった天野貞祐さんという人は、「国民実践要領」という教育勅語に代わる国定道徳というものを作ろうとしました。あるいは1966年に中央教育審議会から「期待される人間像」という答申が出されました。これもある意味、「国が国民の道徳を作る」という試みでした。国民実践要領にしても、「期待される人間像」にしても、最終的には「天皇に対する敬愛の念を持て」というものだったんです。最後に天皇が出てくるあたりが戦前とつながっているわけですね。
天皇については、日本国憲法第1条に〈日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く〉とあります。国民の道徳として「天皇を敬いなさい」と設定することは、私はこの憲法の規定を逸脱すると思います。しかし、それが戦後も言われてきたわけです。
もともと教育勅語では、「忠」と「孝」が道徳の柱です。「忠」というのは天皇に対して忠誠心を持てというもの。「孝」というのは家の中でお父様に対して忠誠心を持てというものです。つまり大日本帝国における天皇への忠誠心と、家制度のもとでの家長である父親への忠誠心というのは、一本でつながっている。国は大きな家であり、大きな家のお父様に当たるのが天皇である。そして、国は個人ではなく家を単位とし、家の集合体として作られている。その家長が父親であり、家というものは男系で継がれていくという考え方です。これは天皇が縦の男系家系で相続していくのと相似を成すものです。
忠と孝というのは一本でつながっていて、「天皇に対する敬愛の念を持て」ということを国民の道徳として定義しようとする動きがずっとあったのです。
「主体的に学ぶ」という視点と学問の自由
この教育勅語を復活させようとする時に、壁となるのが教育基本法でした。それで、教育基本法の改正をすべきだという議論がありました。教育基本法改正を最初に本気で目論んだ内閣総理大臣が中曽根康弘さんです。教育基本法の改正というのは、最終的には憲法改正につながり、その前段階といった位置付けで考えられていました。
中曽根さんが書いた回顧録を読むと、日本国憲法について非常に悪し様に言っています。特に個人を大事にするというところに反対だったわけです。国家あってこその個人だと。彼は、こういう非常に強い国家主義の方向で教育基本法の改正を目指しました。
ところが、中曽根さん主導のもとで1984年に設置された臨時教育審議会自体は、その方向に行きませんでした。臨時教育審議会には幅広い方たちが参加していました。必ずしも中曽根さんと同じような考え方の人ばかりではなかった。そこが今と違うんですね。安倍さんが閣議決定で設置した教育再生実行会議の委員は、全部「お友達」なんですよ。自分と同じようなことを考えてる人しか集めていない。中曽根さんの偉いところは、ちゃんと法律で審議機関を作って、自分と意見の違う人も入れたところです。そこで侃侃諤諤と議論をして、結局は中曽根さんの意に反して個人を重視する方向の改革を打ち出したわけです。
臨時教育審議会が打ち出した3つの視点のうち、第一が個性重視の原則でした。これは個人の尊厳を基礎にする考え方で、日本国憲法の立場と一緒です。さらに第二の視点が、生涯学習です。それまでの学校中心教育ではなく、生涯を前提とした教育システムに変えていこうというものでした。「生涯教育」と言わずに「生涯学習」としたところに非常に大事な意味があります。教育という言葉は学ぶ人が客体になるわけですが、学習というのは学習者が主体、学ぶ人が主語になります。しかも、その学習というのは、時も場所も選びません。いつでもどこでも、学校の中でも外でも、幸福追求のためには生涯を通じて学び続けることが大事だという考え方です。学習者が主体的に学ぶことが大事なのです。
この視点は、「学問の自由」と一体を成すものだと私は思っています。憲法第23条に〈学問の自由は、これを保障する〉とありますが、学問の自由というのは基本的人権であるから、学者だけではなくすべての人が学問の自由を持っている。臨時教育審議会が打ち出した個性重視や生涯学習という理念は、学問の自由に含まれるものだとも言えるでしょう。
この臨時教育審議会に基づくと、学校教育も知識を詰め込むのが目的ではなく、自分で学ぶ力をつけることが大切だということになります。自ら学び、自ら考える力こそが本当の学力だという風に、学力の定義が変わっていくわけです。日本の学校教育の問題点は、学校にいる間に知識をたくさん詰め込むのだけれども、学校を出たらそれが不要になってしまうところにある。「自ら学ぶ力」を見つけることができれば、学校の外でも自ら学んでいけます。主体的な学びこそが本当の学びだということなんです。
2006年の教育基本法改正で何が変わったか
教育基本法改正を、正式に政治課題にあげようとしたのは森喜朗内閣です。2000年12月に教育改革国民会議の報告の中で、教育基本法の改正や道徳の教科化を打ち出しました。これまで正式の教科ではなかった道徳を、教科にして成績をつけるという提言を出したわけです。
その森さんの後を継いだ小泉純一郎内閣で、教育基本法改正のための中央教育審議会の答申がまとめられました。その結果として、2006年の第一次安倍内閣のときに教育基本法の改正が行われたわけです。この改正教育基本法には、「道徳心を培う」とか「公共の精神」、「学校生活を営む上で必要な規律を重んじる」など、教育勅語を復活させたい、戦前に戻りたいという傾向を持った人たちが好むような言葉が、かなりちりばめられたことは確かです。なんと言っても「我が国と郷土を愛する」態度を養う、といった愛国心教育が教育の目標に掲げられました。
一方で、1947年の教育基本法が持っていた大事な部分は「かろうじて残った」と言っていいと思います。たとえば「日本国憲法の精神に則り」というのはそのまま残っています。また「個人の尊厳」や「学問の自由を尊重」するという言葉も残っています。それからもう一つ非常に大事な言葉として「教育は、不当な支配に服することなく」というのも残っています。「不当な支配」というのは、政治によって教育の自律性・主体性を歪められるということです。
1947年に最初の教育基本法が制定された時は、まだ国会がありませんでした。帝国議会でできたのです。帝国議会の審議の中で「不当な支配」の主体は何かと問われ、当時の文部省は政治家や官僚だと答えています。要するに権力を握っているものが一番危ないと言っているわけです。
ただ、もともとの教育基本法では、〈(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである〉という文言でした。この「直接」というのが非常に大事だったわけです。間接民主制ではなく、教える者、学ぶ者の直接性を大事にするということです。
しかし、改正法では「国民全体に対し直接に責任を負つて」という部分は削除されて、代わりに〈この法律及び他の法律の定めるところにより〉という言葉が加えられました。つまり、法律の根拠さえあれば、いくらでも政治が教育に介入できるかのような条文になってしまっています。
学習指導要領も教科書検定も「学問の自由」に則るべき
文部科学省の教育現場に対する関与というのは、教育内容に関しては大きく2つあります。その1つは「学習指導要領」という法的拘束力がある規範を作り、これに従って指導・授業をしなさいというものです。もう1つは教科書使用義務です。文科省の検定を受けた教科書の使用義務を学校に課しています。この2つには、それぞれ法律の根拠もありますが、だからといって文部科学大臣が自分に都合のいいように関与していいわけではありません。
今の政権にいる人たちの中には、明らかな歴史修正主義者がたくさんいます。たとえば南京虐殺事件はなかったと言ったり、従軍慰安婦の問題をあれはただの商売だったと言ったり、沖縄戦におけるいわゆる集団自決は軍の強制ではなかったと言ったり……。こういう考えを持った人がたくさんいるわけです。これは歴史学という学問からすると否定される考え方です。学問という世界に立脚するかぎり、このような歴史教育をするわけにはいきません。
学校で教える教科の背景には、何千年にもわたって蓄積してきた学問や文化の体系があります。学問や文化というものは、人間の自由な精神が生み出してきた遺産です。学問の自由、思想の自由、表現の自由といったものの積み重ねの上に、学問や文化があって、その上に学校の教科があるのです。そのことを無視して捻じ曲げて教えることは許されないわけです。それは「不当な支配」であって、いかに法律上、学習指導要項を定める権限が文部科学大臣にあるからと言って、学問の世界で検証された事実と異なることを教えることはできないはずです。つまり学習指導要領に関しても、教科書検定に関しても、全て学問の自由に則っていなくてはいけないのです。
自由権、社会権、参政権の側面をもつ「学習権」
憲法には、第26条に「教育を受ける権利」は出てきますが、「学習権」という言葉は出てきません。教育を受ける権利というのは社会権です。自由権として「学びたいことを学ぶ権利」というのは、むしろ第23条の「学問の自由」に根拠を求めた方がいいと私は思います。第13条の幸福追求権(包括的基本権)に根拠を求めることも可能だと思います。もともと学習権という人権は、複合的な権利だと私は考えていて、自由権としての側面と社会権としての側面、そして参政権という側面も持っていると思っています。
社会権としての学習権は、第26条にはっきりと明示されています。〈ひとしく教育を受ける権利〉と「ひとしく」という言葉が入ってきます。これを「教育の機会均等」と言いますが、この「ひとしく」という言葉の意味するところは、憲法14条の「法の下の平等」というだけではないんですね。憲法14条は、〈人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、〉差別されないと言っているんですが、「教育を受ける権利」における平等性というものは、それに留まらず経済的地位による差別も禁じています。
現在の教育基本法の第4条〈すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない〉を憲法第14条と照らし合わせると分かるのですが、教育基本法の第4条にだけ「経済的地位」という言葉が入っています。経済的な地位により教育を受ける機会を差別されることは許さないという思想が「ひとしく」という中に入っているんです。しかし、これは実現されておりません。経済的な理由で進学を諦めるという人たちは今でもたくさんいます。それをなくしていくのが国の責任であり義務ですが、まだ果たしていないというわけですね。奨学金制度などが少しずつ進んできてはいますが、全く不十分です。
そして、憲法第26条の第2項には〈すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする〉とありますが、私は立憲主義の考え方からすれば、憲法に国民の義務の規定はいらないと思っています。この「普通教育を受けさせる義務」というのは、国民ではなく、むしろ国が義務を負うという形で書き直した方がいい。私なりにこの憲法第26条2項の改正草案を考えるなら、〈国はすべての人に無償の普通教育の機会を与える義務を負う〉としたらいいと思います。
「義務教育」という言葉をやめて「無償普通教育」とし、その権利を保障するのが国の義務だという風に書き換えると、その無償普通教育の権利を保障されていない人たちが実は世の中にたくさんいるということが分かります。それは、国が十分な責任を果たしていないということです。
そして学習権は参政権でもあります。学ぶことは政治に参加することに不可欠の営みです。知る権利というものが、主権者が主権者たるために必要なのは間違いありませんが、知るだけでは賢明な主権者にはなれません。学ぶことが参政権を実質化するのです。
日本の政治教育の問題点
最後に、主権者として政治に参加するために必要な政治教育について話します。2015年10月に、選挙権年齢や国民投票権年齢が18歳以上に引き下げられることに対応して、文部科学省が「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」という通知を出しています。この通知で、「現実の具体的な政治的事象」を授業として取り上げなさいとあります。これは文部科学省としては良いことを言っているなと思いました。
しかし、一方で「教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること」「学校の内外を問わず……不用意に地位を利用した結果とならないようにすること」とも言っているんですね。これは教師を過度に萎縮させるものです。
たとえばドイツの政治教育における考え方は、教師は自分の考えを述べてもいいけれど、その反対の考え方もちゃんと生徒に伝えて、生徒自身に考えさせなさいというものです。日本の考え方は、教師が右と言ったら生徒が右を向いてしまう、左と言ったら左を向いてしまうような影響力を教師は持っているから、そういうことを言うなと言うものです。
この文科省の通知の決定的な問題点は、生徒が批判的精神を持っていないとしている点です。生徒というのは、教師の言うことを鵜呑みにしてしまうような存在だという前提に立っているんです。そこが根本的に間違っています。
生徒自身が自分自身で考えることが大事なのですから、そういう生徒を育てるために「先生はこう思っているが、君たちは君たちで考えなさい。先生を批判するのは自由だ」と教えるべきなんですね。日本の学校での政治教育が不十分なのは、過度な政治的中立性を求めているからではないかと思います。
学校という「部分社会」において、教師は権力側にいるんだという考え方をする人がいますが、生徒には教育を受ける権利や学習権があります。小学生であっても学問の自由は保障されている。そういう認識をもつことが、主体的な教育の場をつくるために、とても大事なことだと思います。
*
奈良県出身。1973年、東京大学文科一類入学。法学部へ進学し、故芦部信喜氏に憲法を学ぶ 。1979年、文部省(現・文部科学省)に入省。初等中等教育局教職員課長、大臣官房総括審議官、官房長などを経て、2016年に文部科学事務次官。2017年に退官。現在は、日本大学文理学部教育学科講師 (非常勤)。現代教育行政研究会代表。自主夜間中学のスタッフとしても活動する。著書に『面従腹背』、『官僚の本分』(柳澤協二氏との共著)など多数。
=====================================================

城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さんによる、東京新聞のシリーズ対談4回。
【<親友対談 しなやかな反骨>(1) 城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さん】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019073002000118.html)、
【<親友対談 しなやかな反骨>(2) 元文科次官・前川喜平さん×城南信金顧問・吉原毅さん】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019073102000144.html)、
【<親友対談 しなやかな反骨>(3) 元文科次官・前川喜平さん×城南信金顧問・吉原毅さん】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019080102000124.html)、
【<親友対談 しなやかな反骨>(4) 元文科次官・前川喜平さん×城南信金顧問・吉原毅さん】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019080202000128.html)。
《二人は麻布中・高校(東京)の同級生で、ともにラグビー部で汗を流した親友だ。強い者に負けない志の根っこはどこにあるのか。「しなやかな反骨」をテーマに存分に語り合ってもらった》。
《どんな組織が好ましいのか。元文部科学次官の前川喜平さんと城南信金顧問の吉原毅(よしわらつよし)さんの対談は「理想の組織」論に入った》。
《個人と対立しがちな組織の論理。その中で人はどう生きたらいいのか。対談は佳境に入っていく》。
《二人は、麻布中学・高校の同級生で、ともにラグビー部で過ごした仲間。「しなやかな反骨」の根っこは「麻布のDNA」だ》。
小泉純一郎氏を持ち上げすぎな点が気に入りませんが、城南信金顧問・吉原毅さんと元文科次官・前川喜平さんの楽しい対談。
反核発電、反アベ様等々、ぶれないお二人の《面従腹背》な《反骨》。
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●脱原発は可能: ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●城南信金の吉原毅理事長が退任・・・
脱原発という、「理事長交代後も考え方は引き継がれ」て欲しい』
『●警察や消費者庁の沈黙…「商取引の原則」を無視して、
なぜ核発電料金を支払わなければならないのか?』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の救い様の無さと、
アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
『●東電核発電人災から7年: 「村の生活は百年余りにわたり、
人生そのもの」…「やっぱりここにいたいべ」』
『●中西宏明経団連会長《再稼働が進まない要因を、
原発と原爆を同一視する地域住民の理解不足と決めつけ》?』
『●核発電「麻薬」中毒患者・中西宏明経団連会長自ら、
ニッポンは《民主国家ではない》ことを立証して見せた』
『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」』
『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差』
『●前川喜平前文科次官、「本来、できてはいけないものが
完成した。見たくないものを見たという感じだ」』
『●前川喜平さん授業…検閲と恫喝、《意に沿わない人物は潰す――。
…安倍政権のやり口は、まさに恐怖政治》』
『●隗より始めよ: 「この国をガタガタにし、
支持率3割は取れる」高プロとして、「自分らができてから…」』
『●霞が関: 「佐川になるな前川になれ」…
《佐川のような官僚ばかりだったら絶望するしかないだろう》』
「日刊ゲンダイの佐高信さんによる書評【週末オススメ本ミシュラン/
「面従腹背」前川喜平著/毎日新聞出版】…。《落語家の立川談四楼が
ツイッターで、いま霞が関では<佐川(宣寿前国税庁長官)になるな
前川になれ>が合言葉になっているとつぶやいたらしい。
もちろん皮肉である。/…佐川のような官僚ばかりだったら
絶望するしかないだろう》」
『●〝前川喜平になるな佐川宣寿になれ〟!?
「官邸べったり」藤原誠官房長の文科事務次官への昇格人事』
==================================================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019073002000118.html】
<親友対談 しなやかな反骨>(1) 城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さん
2019年7月30日 朝刊
加計学園の大学獣医学部設立認可をめぐり「行政がゆがめられた」と証言した元文部科学次官の前川喜平さん(64)と、経営トップでありながら脱原発の旗を掲げた城南信用金庫顧問の吉原毅(よしわらつよし)さん(64)。二人は麻布中・高校(東京)の同級生で、ともにラグビー部で汗を流した親友だ。強い者に負けない志の根っこはどこにあるのか。「しなやかな反骨」をテーマに存分に語り合ってもらった。 (四回シリーズでお伝えします)
吉原 文科省の課長当時、「奇兵隊、前へ!」というブログがあったよね。官僚なのにこんなこと書いていいのって思いました。
前川 確かに突出した行動ではあった。二〇〇五~〇六年ごろかな、小泉純一郎内閣の看板政策の三位一体の改革で、国から地方に税源移譲し、地方の財政の自主性を高めるという話になった。そのために国から地方への補助・負担金を減らす。そこで三兆円ある義務教育費国庫負担金がなくなりそうになった。それでは子供たちが困ると思って、反対だと言って回ったんです。地方の財政力にかかわらず、教育の機会均等を保障するためのお金です。
吉原 ブログは一般の方も見られるものですし、勇気がいりますよね。
前川 月刊誌に名前を出して書いたりしましたしね。はっきり言ってクビが飛んでもいいと思いました。
吉原 組織の上の方が白旗揚げて、ほかの人は静観する中で孤軍奮闘して…。
前川 いや、孤軍でもないのよ。課長仲間や下の連中は、すごく応援していた。素晴らしい改革のように見せようとしていたけど、小泉純一郎内閣の目玉として総務省が作り上げた話。地方公共団体はだまされたと言ってもいい。だから文科省と総務省とでドンパチやってたんです。
吉原 文科省の当時の上司の了解は?
前川 上司の初等中等教育局長は、青年将校みたいなのが暴れるのを黙認していたって感じ。次官や官房長は、ほとんど白旗を揚げてました。次官のところに行ったら「この制度は廃止でしょうがないだろう」って。負け戦と思っている人もいるし、ぎりぎりまで頑張ろうという人もいた。最後の最後、助けてくれたのは与謝野馨さん(当時、自民党政調会長)。文科省の土俵で議論させてやるって、仕切ってくれた。
その代わり中央教育審議会に、総務官僚が握っている知事・市長・町村会推薦の首長が三人入った。われわれも三人の首長に一本釣りで来てもらった。その一人が当時の鳥取県知事の片山善博さん。三位一体改革の本質を見抜いてるから、良い意見を言ってくださった。
そのときにカウンターパートで、当時の総務省の自治財政局調整課長だったのが務台(むたい)俊介さん(現衆院議員)。中教審の会議の後、道端である女性の委員をつかまえて、いかに文科省が間違っているかと言ってるわけですよ。僕も入っていって、そうじゃないんですよと言ったら「前川さん、そんなこと言ってたらクビが飛ぶよ」と。それでブログに「クビが飛んでも構わない」と書いた。そのくらいの気持ちでした。結局、制度は守るが、負担率を二分の一から三分の一に下げることで決着をみた。
吉原 なんで文科省(旧文部省)に入ったの? 使命感を持って入ったと思うけど、誰の影響なんですか。
前川 人間の精神的な活動を広げていくっていうか、人の心の豊かさを大きくしていくっていうか。
吉原 人間教育とか、人間の魂とか、子供たちを育てたいっていう気持ちの人は文科省に入る。
前川 そういう人が多い。僕の場合はやりたい仕事のところに配置してもらえたけど、そんなに幸せでもないのよ。初等中等教育の仕事は確かにさせてもらえてよかったんだけど、それ以外の仕事も多くて。
吉原 もちろんそうでしょうね。
前川 多かったのは、政治家相手の仕事。秘書官で与謝野(馨)さんみたいな大臣と一緒に仕事をするのは楽しかったけど、理不尽なことで怒り狂っている政治家のところに行ってなだめるとか、何で怒っているか分からないけどとにかく謝るとか、そんなことばっかりやってました。国会の委員会で野党から追及されるよりも自民党の部会で攻撃されるほうがしんどいですよ。本当に言いたい放題言われますからね。
吉原 組織の中で仕事をする中で、自分が情熱をかけている初等教育、中等教育の話とは別のものがいっぱいある。それでもう嫌だという人もいるけど、本当にやりたいことがあるから頑張って、初志を貫くと。
前川 それはあるよね。義務教育費の時は、案外楽しかった。だけど防衛戦ですからね、仕掛けられた闘いをやってる感じ。その中で思ったのは、この機会に制度を見直して良い制度にすること。三位一体の改革は、義務教育費国庫負担制度(*)を良い方向に、地方の自由度を高める方向に変えるきっかけになった。外圧が改革のきっかけになることはありますよね。
吉原 厳しい状況の中で、上は支持しない、あるいは上はもう闘いを放棄してるところで、上がどうであろうとみんなの思いを結集して情熱と信念を持って、組織をまとめて。言われて動く組織じゃなくて自分が組織を組織化し、みんなのチームをつくり理想を実現していく。それをやった人だったってことです。なかなか組織人として難しいことだと思うんです。言われたことやってないと干されるし、クビにされるぞと脅かされるわけだし、その中で頑張る人って、なかなかいないと思います。
前川 安倍政権では(官僚は)なかなか言えない。小泉政権は思いっきり議論ができる政権だった。最後は小泉さんの鶴の一声で決まるけれども、そこに至るまでの間に思いっきり言いたい放題言える。僕も一見、三位一体改革という看板政策にたてついてるとんでもないヤツなんだけど。
吉原 当時は、組織が生きていた。今は全然違って、政府の上から言われたことを全部やらないとダメっていう絶対服従みたいなことをやる。小泉さんは、僕も付き合いあるから言うけども、決めたらドーンとやるけども、その前に必ず意見を言わせるんですよ。
僕がびっくりしたのは、今原発反対をやってるんだけども、小泉先生は違う意見を聞くんですよ。僕らなんかが「あんなの頭きちゃいますよね」って言うと、そんなことない、民主主義なんだからいろんな意見があっていい、違う意見があってはじめて民主主義ってのは成り立つんだと。懐がでかいなと思ったんです。たぶん小泉政権は「万機公論に決す」で、最後は政治決着だというところがあった。今はいきなり結論ありきで、とにかく黙って従えと。この度量の狭さは、政府だけじゃなくて、現代社会に、いろんな企業も含めて組織体の共通の社会病理みたいになっている。これについてはどうですか。
前川 安倍政権的な組織体質が、日本中に広がっちゃってるんじゃないかっていう気はしてるよね。
吉原 力で勝負とか、問答無用とかね。言論しない、言論に重きを置かないでいきなり結論がある。別に安倍さんの悪口を言ってるわけじゃなくて、世の中全体がそうなってるのはどうしてだろう。不思議です。
前川 僕は安倍さんの悪口言ってるんだけど。
吉原 この場ではあんまり言わないほうがいいんじゃないか(笑)。
前川 やっぱり、そういう忖度(そんたく)が蔓延(まんえん)してますよ。
* 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、小・中学校など義務教育の学校の教職員給与の3分の1を国が負担する制度。以前は2分の1負担だった。
<まえかわ・きへい> 1955年、奈良県生まれ。東京大卒。79年、旧文部省(現文部科学省)に入り大臣秘書官、官房長、初等中等教育局長などを経て、2016年、文部科学次官。天下りあっせん問題の責任を取って退官後、夜間中学スタッフ、大学講師などとして活動。著書に「面従腹背」、共著に「これからの日本、これからの教育」など。
<よしわら・つよし> 1955年、東京都生まれ。慶応大卒。77年、城南信金に入り、企画部、副理事長などを経て2010年、理事長。15年、顧問。17年から麻布学園理事長。東日本大震災後、同信金の脱原発宣言を主導。小泉純一郎元首相らと活動を続ける。著書に「幸せになる金融」「原発ゼロで日本経済は再生する」など。
(対談は六月二十六日、東京都千代田区の東京新聞で行われた)
==================================================================================
==================================================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019073102000144.html】
<親友対談 しなやかな反骨>(2) 元文科次官・前川喜平さん×城南信金顧問・吉原毅さん
2019年7月31日 朝刊
(理想的な組織のあり方などについて意見を交わす吉原毅さん(左)と
前川喜平さん=東京都千代田区の東京新聞で)
どんな組織が好ましいのか。元文部科学次官の前川喜平さんと城南信金顧問の吉原毅(よしわらつよし)さんの対談は「理想の組織」論に入った。
吉原 今の政府の人たちが心配です。安倍(晋三)さんが絶対的な権限を持っていて、総理が言えば何でも通っちゃう。でも安倍さんが逆の立場になると、自分が徹底的にやられるわけです。そういう組織は、非常に不安定です。「正しい」「間違っている」よりも力を取ったら勝ち。それで本当にいいのかと。
前川 多様性が失われている。いろんな意見があっていいんだ、存念を述べよ、みたいなところがなくなってきて。
吉原 それに対して前川さんは警鐘を鳴らしている。正しいことは正しい、あるものをなかったとは言えないと言う。素朴な言い方だけど、勇気がある人だと思って喝采しました。
前川 意を決して告発したなんていうことじゃなかったんだけどね。この文書を見たことありますかって言うから、ありますよって。加計学園問題(*1)に関しては、内部文書を表に出した職員が、今も文科省に複数人いるわけです。彼らの方がずっと僕より勇気がありますよ。
吉原 世界中が上意下達の方向に行っている気がします。時代なんですかね。
前川 国際政治も一国主義がはびこっている、リーダーが強い力を持って。プーチン(*2)だ習近平(しゅうきんぺい)(*3)だ、トランプ(*4)だ、エルドアン(*5)だと。城南信金の「クーデター」の話をしてよ。
吉原 会社も政府も一つの政治システムだと思うんです。目的は定款に書かれている。憲法みたいなものです。人々を幸せにしたいなどと書いてあり、金もうけが目的ではない。それが外国資本が増えて、成果主義とトップダウンの傾向が強まった。新自由主義です。でも、成果主義で人を人と思わずに多様性を否定すると、組織は生きない。(よい企業は)相互コミュニケーションが利いている。自由な言論があって、英知を集めて最善の道を探る。
フラットな分権型にするのは、経営学の世界では主流になった。ところが、いまだに威張り散らして、間違った考え方を押しつける人たちが上にいる。
これでは力を結集できないし、お客さまにちゃんとサービスを提供できない。だったらトップに代わってもらうしかないよねと。給料は保証するから権力からは外れて、という極めて穏当な「クーデター」でした。
前川 城南信金の新理事長となった吉原さんは、自らの給料を支店長平均より低い千二百万円に下げた。
吉原 千二百万円でも随分いただいていますけど。世の中がおかしくなったのは、大会社の社長がめちゃくちゃな報酬を取るようになってから。国会議員もお金をいっぱいもらうようになってから劣化した。
小原鐡五郎(てつごろう)(*6)という、信用金庫法を作って業界を率いてきたリーダーに数年間お仕えした。その方が「吉原くん、お金は麻薬だ。持っていると人間は身を持ち崩す。適正なお金を使うことが大事。それをお勧めして、指導するのが信用金庫の仕事だ。貸すも親切、貸さぬも親切」と言った。身を持ち崩さないようにお金を使うのが大事。
前川 すごいよね。お金を扱う仕事の中にいて、お金に溺れないという哲学を持つのが。そういう話、小泉さん(純一郎元首相)とはするの?
吉原 小泉さんもお金にこだわらない清廉潔白で純粋な人ですよ。自民党って自由に民主的に話ができた政党で、けんかしたり仲良くしたりして、個性あふれる先生方が自由闊達(かったつ)に議論していた。今や一枚岩でどうしちゃったのと。
前川 首相問責決議案への三原じゅん子さん(参院議員)の反対討論を聞くと、ひと言彼女が話すたび、与党席から「そうだ!」と。
吉原 もはや自民党は、全体主義政党になってしまった。悲しい。自民党ファンとしては(かつての自民党が)復活してほしい。
前川 国民政党と言えたのは多様性があったから。宇都宮徳馬(*7)、野中広務(*8)のような人もいた。派閥は政策集団でもあったからカラーが違った。その多様性が消え、本当の保守主義でなくなった。
吉原 小泉先生は一生懸命に原発反対運動をしているけど、私は自民党です、と必ず言うんです。党の多様性を復活させようと努力している。いろんな意見を取り入れる幅広さがないと、政治も経営も社会も閉塞(へいそく)する。最大の懸念です。
前川 霞が関も全体主義になった。もともと「司(つかさ)」という言葉があって、それぞれの分野については自信と誇りと責任感を持ってやっていた。その司の責任感や独立性がほとんど失われ、官邸が肥大化して、官邸官僚といわれる人たちが総理や官房長官をガチッと固めてしまった。どの分野の政策も官邸が決めている。
吉原 現場には五感を通じて情報が集まってくるが、中央には数字のみ。数字じゃ骨しか入らない。血や肉や魂になる情報は入ってこない。でも上はアメとムチで脅かす。「良い暮らしをしたいだろう。良い地位につきたいだろう。従わないヤツは全部クビだ」と。これでは、うまくいくわけがない。危機感を覚えます。
<親友対談 しなやかな反骨>(1)
*1 安倍晋三首相の長年の友人が経営する学校法人「加計学園」が、獣医学部を新設する国家戦略特区の事業者に唯一選ばれた際、「首相案件」として官邸側が特別の便宜を図ったのではないかとされた疑惑。
*2 ロシア大統領。
*3 中国国家主席。
*4 米大統領。
*5 トルコ大統領。
*6 城南信金元理事長。元全国信用金庫協会長。1899~1989年。
*7 元衆院・参院議員。月刊誌「軍縮問題資料」創刊者。1906~2000年。
*8 元衆院議員。官房長官、自民党幹事長などを歴任。戦争反対を訴えた。1925~2018年。
==================================================================================
==================================================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019080102000124.html】
<親友対談 しなやかな反骨>(3) 元文科次官・前川喜平さん×城南信金顧問・吉原毅さん
2019年8月1日 朝刊
(「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」創設の記者会見をする
吉原毅さん(左)と元首相の小泉純一郎さん=東京都品川区で)
個人と対立しがちな組織の論理。その中で人はどう生きたらいいのか。対談は佳境に入っていく。
吉原 しょうがないから歯車になるという選択肢もあるかもしれないが、それでは面白くない。前川さんも歯車のふりをしながら、変えなきゃという思いも持っていたわけでしょ。
前川 ヨットは逆風でも前に進む。役人の立場から言うと、風に相当するのが政治の力。政治の力が正面から吹いている時、かいくぐりながら前に進む。
沖縄・八重山の教科書採択問題がそうでした。中学の公民の教科書の採択で石垣市、与那国町、竹富町の三自治体の教育委員会が、同じ教科書を共同採択しないといけない縛りがあったが、意見が割れた。石垣市と与那国町が育鵬社、竹富町は東京書籍。東京書籍は基地問題の記述が充実し、育鵬社は領土問題をちゃんと書いていた。その時、担当の初等中等局長だった僕は無理やりは良くないと思うが、やれと言われて、竹富町に育鵬社の教科書を採択するよう地方自治法に基づく是正要求をした。面従腹背の腹背の部分では無理筋と思っていました。
ちょうどそのころ教科書無償措置法改正案を作り、そこに共同採択地区を分けることができる仕組みを忍ばせたんです。沖縄県と竹富町の教育長とは裏で話して、法案が通ったら独立の採択地区にできるから踏ん張ってくださいと。県の教育長は半年粘った。二〇一四年に法律が通って、円満に採択地区から分離して採択できるようになった。
吉原 素晴らしいですね。そういう話聞くと、ちゃんとした考えの人が組織のあちこちにいることで、組織が正しい方向でできると思う。トップダウン組織は、トップが狂うと暴走する。自立分散型ネットワーク型組織がいい。それぞれが考えて連携しながらやっていけば、穏当で最適で正しい解決方法につながる。考えてくれる人を大事にするのが良い組織です。
前川 それぞれの組織の中のポジションに、一定の自由度や裁量はある。それぞれの頭で考えれば、組織もうまく回っていく。
(加計学園問題をめぐり記者会見する前川喜平さん。
「あったものをなかったことにできない」と証言した=東京・霞が関で)
吉原 みんなが考えていく組織、そういう組織人にならないと。面白くないから辞表を突きつけて辞めちゃうというのは、一見かっこいいようだけど負け。なんとか踏みとどまって、正しい組織運営のために努力しなきゃ。前川さんの言っている面従腹背が正しい組織人としてのあり方だ。
前川 そうだけど、かなり面従ばっかりしていた気もしますよ。今はメディアがねえ。東京新聞は何でも言える社風があるようだけれど、メディアが歯切れ悪くなり、権力に忖度(そんたく)する状況が出てくれば、国全体がおかしくなってしまう。
吉原 うちの会社は五権分立でやっている。台湾は五権分立。司法・立法・行政の三権分立だけでは、バランスを保てない。行政に当たる執行、国会に当たる取締役会あるいは株主総会、それらを統合する内部管理がある。さらに人事権を独立させ、外部監査を付けて監査役が監視する。この五権をしっかりやれば、均衡ある組織運営ができる。
前川 日本国憲法の中にも会計検査院という独立の組織がある。憲法上の組織ではないが、人事院もある。この会計検査院と人事院の地位が低下している。
吉原 国会が組織を作ればいい。例えば原発事故の時の事故調査委員会。政府から独立した指揮命令系統で動かすことで、議論の余地を作ることが大切です。
前川 六年半かけて、中央省庁の幹部を官邸の言うことを聞く人間ばっかりにしたから、下のレベルまで忖度感情の分厚い層ができちゃっている。それをちゃんと自分で考える人間に入れ替えていくのは、かなり時間がかかると思います。
吉原 ところで道徳の復権が叫ばれていますけど、道徳教育を押しつけちゃダメだと前川さんは言う。じゃあどうしたらいいのか。
前川 基本は自分の命を大切にすること、自分らしい生き方を大切にする自主性を持つこと。自分が大切だと思わなければ、人を大切に思わない。今の道徳教育が目指すのは滅私奉公で、自分を犠牲にしなさい、自分を抑えて全体の役に立つ人間になれという方向性を持っているが、危ない。全体のために抑圧された人間は、今度はより弱い人間を抑圧する連鎖が起こる。昔の軍隊みたいに。
今の道徳教育をやっていくと、若い人はむしろ逃避する方向に行くと思う。ここ数年、実は不登校が増えている。どうやら学校が息苦しい場所に戻ってしまっている。いったん校則が緩まったけど、また厳しくなった。改正教育基本法第六条に「規律を重んじる」って条項が入って、後押しになった。規律を守れ、自分を抑えて全体に奉仕せよという、上からの道徳です。
吉原 権力を握っている人の了見が狭いって言うか。なんとかしなくちゃって思い、品川区(東京)と一緒にこども食堂を開いた。
前川 こども食堂とか夜間中学に出入りしていると、地域の力って捨てたもんじゃないと思います。お金にならないけど、それを喜んでやっている。労力で協力する人もいれば、お金で協力する人もいる。品川区のこども食堂は、ふるさと納税を使って支援している。返礼品じゃなくて、子供たちの喜びがお返しです。
連載<親友対談 しなやかな反骨>(1)前川さん「三位一体改革に反対 クビ飛んでもいい」 吉原さん「官僚なのにこんなブログ書いていいの」
連載<親友対談 しなやかな反骨>(2)吉原さん「多様性が組織生かす」 前川さん「いろんな意見大切」
==================================================================================
==================================================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019080202000128.html】
<親友対談 しなやかな反骨>(4) 元文科次官・前川喜平さん×城南信金顧問・吉原毅さん
2019年8月2日 朝刊
(若き前川喜平さん(右)と吉原毅さん(左)。英国駐在中の前川さんを
吉原さんがビジネススクールの卒業旅行で訪ねた=吉原さん提供)
二人は、麻布中学・高校の同級生で、ともにラグビー部で過ごした仲間。「しなやかな反骨」の根っこは「麻布のDNA」だ。
前川 僕は奈良の田舎の出身。小三で東京に引っ越したけど、東京の子供のリズムについていけず、不登校になった。六年になったころ急に親が麻布中学を受験してみたらと言うので、バタバタと勉強した。
吉原 僕は、もともと大田区の蒲田の梅農家です。蒲田は梅の名所で、梅を集めて作ったのが梅屋敷。麻布学園は、城南地区出身が多い。近所の兄ちゃんとかがいて親しみがある。
前川 弁当は休み時間に食べちゃう。売店で毎日、あんパンを買って食べた。中一か中二のころついたあだ名が、あんパンだぬき。
吉原 育ち盛りだからね。購買所のパンで足りなくて外で焼きそばを食べたり、一日五食ぐらい。中三でラグビー部に入った。青春と言えばラグビーという時代。あこがれますよね。
前川 僕は中二から。しばらく部活をせずにボーッとしてましたけど、授業で麻布ボールっていう麻布独自の球技をやって、その発展上にラグビーがあった。
吉原 前川さんとは体格が同じぐらいだったから「君たちはフォワードのロックね」と言われて…。
前川 スクラムの二列目です。プロップというでっかいのが二人、真ん中に足でボールをとるフッカー。その三人のお尻の間から頭を入れて押すのがロック。
吉原 展開するバックスがヒーローで、フォワードは裏方。裏方でも前の三人がかっこいいけど、後ろになると全然目立たない。
前川 勝った記憶がほとんどない。ラグビー部をつくって最初の練習試合に選んでくれた学校には勝った。
吉原 前川さんは寡黙なイメージ。テレビで見て、こんなにしゃべるのかと思った。当時は深い言葉をぼそっと言うような感じで。
前川 少しずつ外交的になってきた。中学、高校はおとなしい少年だった。
吉原 前川さんはいつも体操服。男子校って、バンカラでオッケー。共学校だと女性を意識するけど、みんなバンカラで気楽だった。
前川 吉原さんは紅顔の美少年。もう一人吉原がいてきれいな吉原と、そうでない吉原と言われていた。
吉原 「ラグビーは男のスポーツ」、この一言でなかなかやめられなくて。試合では、体格のいい選手が突っ込んでくる。左右を見ると、おまえが守るしかないと目でサインしてくる。しょうがないから、真っ正面で膝から太ももあたりを目がけてタックルする。目をつぶって。止めることはできた。勇気というほどではないけど、自己犠牲。
前川 ラグビーで身に付けたものは、何だろう。負け続けても続ける粘り強さが面従腹背につながっているのかも。麻布中高で過ごした六年は、貴重な時間だったのは間違いない。僕らの時代は紛争の真っ最中。その中で人間形成をしたのは得難い経験だった。
吉原 校長室を友達が占拠したことも。早熟な先輩たちが建国記念日制定の年、反対のデモをしたいという話から紛争になった。建国記念日は戦前回帰の動きだろうとあおって。われわれは遠巻きに見ていた。
前川 僕はノンポリ。今だったらデモに参加しているかもしれないけど。
高校生のとき、音楽の先生が、きょうは君たちと話し合いたいと言って朗読したのが、宮沢賢治(*1)の「生徒諸君に寄せる」という詩。「本気になって取り組めば、未来が開けてくる」というメッセージをくださった。読むと、未来に向かって生きていこうという気になる。あれは、僕のその後の人生をけっこう決めている。人間には何げない一瞬がものすごく大事なことがある。僕の場合は、音楽の先生の賢治の詩。
吉原 高二の文化祭の時、機動隊が学内に入り、仲間が蹴飛ばされた。次に放水が来る。ここで逃げるわけにはいかない。ラグビー精神ですよ。ワン・フォー・オール。迷ったときは傍観者はだめ。そういうことはラグビーから学んだ。
前川 「いちご白書」(*2)の世界みたい。僕は校庭の端っこでフォークダンスをしていた。女の子と手をつなぐチャンスで。傍観者にもなっていない。
ぼんやりした夢は、小説家か物理学者。宮沢賢治を読んでいると、宇宙がたくさん作品に出てくる。宇宙を知りたい気持ちと、人間の世界に入っていきたいという気持ち。仏教の本を読んでいたから、仏教を通じて真理に迫りたいとも。国家公務員になりたいなんて全然考えてなかった。
吉原 ラグビー部でもプラトンとか仏教の本を読む友達がいて、いろいろ個性を持っていた。旧制高校ほどデカンショ(*3)してたか分からないけれども。いろんな人たちがいるのが麻布の面白さ。目先の損得を考えるんじゃなくて、理想とか理念とか、そういったものに関心を持ってる人が多かった。最近ラグビー部の友達に会ったら、言うんだ。「麻布は結局、倫理の学校だよな」って。 =おわり
<親友対談 しなやかな反骨>(1)前川さん「三位一体改革に反対 クビ飛んでもいい」 吉原さん「官僚なのにこんなブログ書いていいの」
<親友対談 しなやかな反骨>(2)吉原さん「多様性が組織生かす」 前川さん「いろんな意見大切」
<親友対談 しなやかな反骨>(3)吉原さん「辞めてしまうのは負け」 前川さん「ヨットは逆風でも進む」
*1 詩人、童話作家。1896~1933年。
*2 米コロンビア大の学生運動を描いた米作家ジェームズ・クネンのノンフィクション。1970年に映画化された。
*3 デカルト、カント、ショーペンハウアーの三人の哲学者の名前を合わせた呼び名。
【https://youtu.be/JAzRZSvdWoo】
==================================================================================


東京新聞の社説【102歳の自殺 原発事故のもつ罪深さ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018022402000168.html)。
日刊ゲンダイの城南信用金庫の顧問・吉原毅さんへのインタビュー記事【注目の人 直撃インタビュー/吉原毅氏突く原発推進の矛盾 “自然エネは儲かる”が新常識】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/223325)。
『●言葉が見つかりません・・・』
「須賀川市の野菜農家の男性(64)は、福島産野菜の一部に国の
出荷停止指示が出された翌日の二〇一一年三月二十四日に自殺した。
遺族によると、男性は原発事故後「福島の百姓は終わりだ」と話していたという」。
『●哀しい遺書: 「原子力さえなければ」』
『●ドキュメンタリー映画『わすれない ふくしま』:
「震災さえ」ではなく 「原発さえなければ・・・」』
『●「「3.11」から2年② 原発という犯罪」
『週刊金曜日』(2013年3月8日、934号)』
『●「原発さえなければ」「福島の百姓は終わりだ」:
東京電力原発人災と自殺には因果関係あり』
『●「原発さえなければ…」: それでも川内原発や伊方原発を再稼働したいの?』
《福島第一原発事故による強制避難を前に百二歳の男性が自殺した。福島地裁が東京電力に対し遺族への賠償を命じたのは、事故との因果関係を認めたからだ。原発事故の罪深さをあらためて思う》。
《福島第1原発事故を受け「脱原発」を宣言した異色の金融マンは、絶対に「原発ゼロ」をあきらめない。…産経新聞…素晴らしい批判をいただき、感謝申し上げる次第です。おかげで原発推進派の典型的な考え方がよく分かりました。産経新聞でさえ、世界のエネルギー情勢を誤認している。真実を教えて差し上げ、認識を改めていただこうと反論書を送りましたが、いまだ回答はいただけていません》。
『●お見舞い申し上げます・・・』
『●あの3・11原発人災から1年: 松下竜一さん「暗闇の思想」を想う』
『●3.11東京原発人災から2年が過ぎて』
『●「福島原発事故の今」
『週刊金曜日』(2014年3月7日号、982号)について』
『●3.11東京電力原発人災から4年:
虚しき「地球にやさしいエネルギー原子力 人にやさしい大熊町」』
『●東電核発電人災から5年: 「今や世界の笑い者…
政権批判をいとわないキャスターの首を差し出した」』
『●東電核発電人災から6年: 4つの「生」+「命」「活」「業」「態」…
どれか一つでも原状回復できたか?』
《政府は原発再稼働の政策を進める。だが、原発事故という取り返しのつかない罪をこの判決は、われわれに思い出させる》…強い憤りを感じる。《戦前の日本軍も、「航空主兵論」が世界の趨勢だったのに、時代遅れの「大艦巨砲主義」に固執し、戦艦大和に莫大な資金と労力を費やし、無用の長物と化した。その結果、この国は一度、滅びたのです。現政権は同じ轍を踏んでいるように見えます》…核発電「麻薬」中毒患者がこの国を滅ぼす。
東京新聞の記事【仮設打ち切り 怒りの春 「何もできねえうちから戻れって。早いんでねえか」】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018022790070520.html)によると、《東京電力福島第一原発事故で全域避難した七町村のうち、避難指示が最初に解除された福島県楢葉町(ならはまち)。二〇一五年九月の解除から二年半たっても、住民は32%しか帰還していない。三月末には町外にある仮設住宅の提供が打ち切られ、全員が退去を迫られる。町に帰るか、町外に移り住むかの選択を強いられる住民からは、怒りや不安の声が上がっている》。
東電や原子力「寄生」委員会、アベ様ら核発電「麻薬」中毒患者は福島県楢葉町を《原状回復》して見せよ。話はそれからだ。
マガジン9の記事【雨宮処凛がゆく!/第43回:3・11から7年〜遺族が見る「大切な人の夢」〜の巻】(http://maga9.jp/180221-3/)/《だけど、「忘れない」ということ以外に、できることは多くない。…心の復興。おそらく、今、一番置き去りにされていることだ。どうしたら、それに少しでも役立つことができるのか。わからないまま「あの日」が近づくたびに、こうしてあの日にかかわる言葉に触れ、書くことしかできない》。
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●脱原発は可能: ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●城南信金の吉原毅理事長が退任・・・
脱原発という、「理事長交代後も考え方は引き継がれ」て欲しい』
『●警察や消費者庁の沈黙…「商取引の原則」を無視して、
なぜ核発電料金を支払わなければならないのか?』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の救い様の無さと、
アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
吉原毅さんへのインタビュー記事に出てくるアベ様広報紙といったマスコミも核発電「麻薬」中毒そのもの。
日刊ゲンダイのコラム【金子勝の「天下の逆襲」/日本は原発輸出も 世界で普及が進む再生可能エネルギー】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/221757)によると、《総額3兆円という日立のイギリスへの原発輸出プロジェクトについて、安倍政権は政府系金融機関が出資し、メガバンクの融資についても政府保証をする方針だという。原発の再稼働も進めるつもりだ。しかし、こうした動きは国際社会とあまりにも隔絶している》
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018022402000168.html】
【社説】
102歳の自殺 原発事故のもつ罪深さ
2018年2月24日
福島第一原発事故による強制避難を前に百二歳の男性が自殺した。福島地裁が東京電力に対し遺族への賠償を命じたのは、事故との因果関係を認めたからだ。原発事故の罪深さをあらためて思う。
福島県飯舘村。農家で生まれた男性は長男で、尋常小学校を出たあと、父母とともに農地を開拓した。牛馬を飼い、田畑を耕した。葉タバコや養蚕も…。
次男の妻は共同通信に対し、「年を重ねてからは老人会で温泉に出掛け、地域の祭りでは太鼓をたたいて楽しんでいた」と答えている。九十九歳の白寿を祝う宴には、村中から百人近くも集まったともいう。そのとき、「大好きだった相撲甚句を力強く披露した」とも次男の妻は語り、忘れられない姿となったという。
二〇一一年。原発事故が起こり、飯舘村が避難区域となると知ったのは四月十一日である。
「やっぱりここにいたいべ」
男性はこうつぶやいたという。両手で頭を抱えるようなそぶりで下を向いた姿を見ている。二時間もテレビの前で座り込んでいた。
次男の妻は「避難指示はじいちゃんにとって、『死ね』と言われるのと同じだった」と受け止めている。確かにそうだろう。
福島地裁の判決も、男性の百年余に及ぶ人生を語っている。
<結婚や八人の子の誕生と育児、孫の誕生を経験し、次男の妻、孫と生活した。村の生活は百年余りにわたり、人生そのもので家族や地域住民との交流の場だった>
だから、避難は男性にとり、過酷なストレスとなる。科学的に言えば、降った放射性物質セシウム137の半減期は約三十年。避難は長期にわたるのは必至で、これも耐えがたい苦痛である。
「ちいと俺は長生きしすぎたな」と避難前にこぼした。判決は「不自由な避難生活の中で家族に介護という負担をかけるのを遠慮したと認めるのが相当」と述べた。原発事故と避難が男性を押しつぶすストレスを与えた。そして、首を吊(つ)って自殺したのだ。
原発事故での自殺をめぐる訴訟で東電への賠償命令はこれで三件目になる。一方、東日本大震災や原発事故の関連自殺者は厚生労働省調べで一七年までに、福島県は九十九人。岩手県や宮城県のほぼ倍だ。
政府は原発再稼働の政策を進める。だが、原発事故という取り返しのつかない罪をこの判決は、われわれに思い出させる。
==================================================================================
==================================================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/223325】
注目の人 直撃インタビュー
吉原毅氏突く原発推進の矛盾 “自然エネは儲かる”が新常識
2018年2月19日
(「自然エネ価格は世界規模で急速に低下し、石炭や天然ガスよりも
安くなっている」/(C)日刊ゲンダイ)
福島第1原発事故を受け「脱原発」を宣言した異色の金融マンは、絶対に「原発ゼロ」をあきらめない。
先月には小泉純一郎元首相らと「原発ゼロ・自然エネルギー基本法案」を発表。全ての原発の即時廃止と自然エネへの全面転換を目指す内容に、「原子力ムラ」に毒されたメディアがかみついたが、原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長の吉原毅氏は「批判はすべて事実誤認」とあきれ顔だ。多くの国民が知らされていない世界のエネルギーの新常識とは――。
■原子力ムラが殺す日本の技術
――基本法案について、産経新聞が1月14日付の社説で〈亡国基本法案〉〈夢想の虚論〉〈これでは国が立ちゆかぬ〉と痛烈に論評していました。これに反論したそうですね。
素晴らしい批判をいただき、感謝申し上げる次第です。おかげで原発推進派の典型的な考え方がよく分かりました。産経新聞でさえ、世界のエネルギー情勢を誤認している。真実を教えて差し上げ、認識を改めていただこうと反論書を送りましたが、いまだ回答はいただけていません。
――産経の社説は〈太陽光や風力発電の電気代が年々、家計に重くのしかかっている〉と高コストを指摘していました。
海外で言ったら、笑われますよ。世界の常識を全くご存じない。自然エネ価格は世界規模で急速に低下し、比較的低コストの石炭や天然ガスよりも安くなっています。太陽光の最安値は1キロワット当たり1・77セント。円換算で2円を切る。風力も肉薄しています。
――ところが、政府は「原発のコストは安い」と喧伝し、ベースロード電源の20~22%に組み込もうとしています。
コスト計算はわれわれ金融機関が専門です。経済人なら、誰もが原発は採算割れだと知っています。さすがに政府もウソをつけないのか、資源エネルギー庁の発電コストの検証資料には、原発だけ「1キロワット当たり10・1円~」と余計な「~」が付いています。「~」とは無限大の可能性もあるということ。苦肉の策の真意を読み取ってあげなければいけません。
――発電コスト低下の裏で何が起きているのですか。
目覚ましい技術革新です。太陽光や風力の発電設備はシンプルで、生産するほど習熟曲線効果で技術は進歩する。大量生産によって製造コストは下がり、設備投資の額も安くなる。特に中国は愚直なまでに品質を年々向上させ、世界中で飛ぶように売れています。ソーラーパネルと風力装置はともに中国企業が世界シェア首位。今や世界一の自然エネ大国です。
――日本のメーカーはどうなのですか。
技術面で後れを取っています。私も各地の自然エネ推進プロジェクトに関わっていますが、太陽光も風力もバイオマスも、まず日本製が採用されない。現場に聞くと、実績がないし、故障が多いと言うのです。「世界に誇る日本の技術」も経験を積まなければ、国際競争に勝てない。原子力ムラの妨害によって、自然エネ開発が遅々として進まないままだと、日本の技術はますます世界から取り残されます。
――先日も電力各社が「満杯」としてきた送電線の容量が、実際は平均8割も空いていたとの京大の研究グループの調査結果が報じられました。
原発再稼働のために確保しているのです。風力発電の供給を検討していた福島の「飯舘電力」は、送電線に空きがないとして、東北電力から20億円もの送電増強費を要求され、事業断念に追い込まれた。こんなバカげた妨害を政府が容認するから、自然エネは拡大しない。政府が原発即時ゼロを決断し、送電線が空けば瞬く間に普及します。
日本の全原発の廃炉費用は多く見積もっても10兆円でしょう。バブル崩壊後に国内金融機関は110兆円もの不良債権を処理し、旧国鉄の分割・民営化で国は37兆円の債務を処理しています。それらと比べれば、どうってことない金額です。
国際金融界からツマハジキ
――産経は社説で〈日本が資源に乏しい島国であることを完全に無視している〉と書きました。
米エネルギー学者のエイモリー・ロビンス博士は「太陽光、風力、地熱に恵まれた日本は、ドイツの9倍の豊かな資源がある」と語っています。例えば日本の農地460万ヘクタールを使い、農作業しながら空中で発電を行う「ソーラーシェアリング」の技術を用いれば、日本の電力需要の10倍に当たる1840ギガワットの発電が可能です。
農家にもお金が回り、耕作放棄地もなくなる。地方に新たな産業が興れば、さまざまな関連ビジネスや雇用が生まれる。若者も希望を持って帰ってくる。こうして自然エネに転換したドイツやデンマークは、地域経済の活性化に成功しました。自然エネは、安倍政権が掲げる「地方創生」の切り札なのです。
――ワクワクします。
産経が大好きな国防面も盤石です。原油に頼らなくなれば、ホルムズ海峡の封鎖は心配無用。逆に危険な原発が54基もあれば、「さあ、ミサイルを撃ってくれ」と国を差し出すようなもの。産経的には北朝鮮の脅威が高まる中、それでいいのでしょうか。
――皮肉ですね。
何より海外に支払う年間25兆円もの化石燃料費が丸々国内に返ってくる。それだけの富が国民に幅広く行き渡るのに、原発温存による「政策障害」が、日本の経済発展を阻害しています。
――中国の方がよっぽど進んでいますね。
昨年10月の共産党大会で、習近平国家主席は「エネルギー革命を起こす」と宣言。2050年までに自然エネを全電力の8割に拡大させる国家目標を掲げました。中国が自然エネに力を入れるのは単純に儲かるから。利にさとい国ですから、儲からないことはやりません。太陽光も風力も燃料費ゼロ。設備の寿命も40年はもつ。設備投資の減価償却を終えれば、近い将来、コストゼロの電力で経済を賄えるのです。
――なるほど、儲かるに決まっています。
“自然エネは儲かる”が、世界の常識。新たな産業革命ともいわれています。低コストで効率良く、安全性が高い。今や電力の主役です。太陽光の総発電量は毎年純増し、380ギガワットを超えた。風力も500ギガワットを超え、両者で1000ギガワット目前。原発1000基分に匹敵します。
加速度的に市場は拡大しているのに、日本だけが立ち遅れている。自然エネに舵を切らなければ、それこそ「亡国」につながりかねません。
――自然エネには世界の金融機関が、かなり投資しているそうですね。
ゴールドマン・サックスが27兆円、シティ・グループは16兆円など景気のいい話が飛び交っています。また、事業運営の自然エネ100%調達を目指す「RE100」には、アップルやNIKE、BMWなど日本でも有名な世界企業122社が加盟していますが、日本企業はリコー、積水ハウス、アスクルの3社のみ。
もはや環境意識の高い企業でなければ、国際金融界から相手にされません。追い込まれた日本の財界や大企業は悲鳴を上げ始めています。原子力ムラのせいで、国際金融界から日本企業が排除されかかっているとは、由々しき問題です。
■戦艦大和の過ちを繰り返すのか
――自然エネはいいことずくめなのに、政府はなぜ、かたくなにデメリットだらけの原発に固執するのでしょうか。
簡単に言えば、原子力ムラのエゴイズムです。従来の方針を続ければ、とりあえず目先の利益や自分たちの利権は守られる。「今だけ、金だけ、自分だけ」の発想です。
そして政官財ともリーダー不在で、誰もが政策転換の責任を負うのを恐れている。戦前の日本軍も、「航空主兵論」が世界の趨勢だったのに、時代遅れの「大艦巨砲主義」に固執し、戦艦大和に莫大な資金と労力を費やし、無用の長物と化した。その結果、この国は一度、滅びたのです。現政権は同じ轍を踏んでいるように見えます。
――目先の利益といえば、アベノミクスの異次元緩和策にも相通じるものを感じます。
株価上昇が目的なら、問題です。株式投資は一種のバクチ。資産を持つ人が、その資産によって、また儲かる仕組みです。カネがカネを生むような風潮を政府が助長すれば、人々の勤労意欲や社会貢献の気持ちを逆なでします。
拝金主義の蔓延でモラルが崩壊し、国家の衰退を招きかねません。原発の背後でうごめいているのは「原子力ムラ」の住人だけではない。拝金主義の蔓延で増殖した利己主義、自己中心的となった日本の世相が深く根を張っています。
(聞き手=本紙・今泉恵孝)
▽よしわら・つよし 1955年東京生まれ。77年慶大経済学部卒業後、城南信用金庫入職。2010年11月理事長就任。15年6月に退任し、相談役に。17年6月から顧問。東日本大震災以降、被災地支援を精力的に行うと同時に、原発に頼らない安心できる社会を目指して「脱原発」を宣言。17年4月に全国組織「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」を創設、会長に就いた。
==================================================================================
[※ 報道特集(2017年7月8日)↑]

東京新聞の記事【経団連、自民への政治献金 4年連続呼びかけへ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201709/CK2017092702000129.html)。
《経済再生を最優先に掲げる安倍晋三政権を支える方針を会員の約千三百社に伝える。献金の是非を判断するための基礎資料となる政党の政策評価に関しては、自民・公明の与党について「国内外の政策で成果を上げており評価できる」とし、昨年の内容をほぼ踏襲する見込み》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」…
「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
2017年10月衆院選で自民党を支え、「トンズラ総理」の「大政翼賛体制・独裁社会」の完成を後押しした経団連。
消費税増税大好き、「死の商人」志向で、核発電「麻薬」中毒な経団連…そんなに企業献金が貰えるのならば、二重取り・詐取した政党助成金を返して下さいナ。自分たちの財布ばかりが潤うような、アベ様らの「政策をカネで買う」ために、企業献金という名の賄賂を自民党に二重取りさせる愚行、立派な詐欺じゃないのか?
《共産党の小池晃書記局長は、衆院選前に民放番組で「4年間で、従業員1人当たりにすると825万円も増えた。その1~2割でも(労働者に)回せば、月2万円の賃上げができる」と訴えていた》(『●「国民に「痛み」を与えてでも消費税を上げよ」!? 自民党・核発電・戦争大好きな経団連なんて要らない』)。一方、《榊原氏はこれまで政治献金に関し「民主主義に必要なコストで企業による社会貢献の一環。何か見返りを求めて呼びかけるわけではない」と説明している》そうだが、白々しいにもほどがある。
『●FUKUSIMAでも変わらないNIPPON』
(このブログは2011年3月27日)
「3月21日の東京新聞特報面に日本経団連米倉弘昌会長の
驚くべきコメントが掲載されていた。
経済界からは早くも原発の危険性を忘れたかのような
発言が飛び出した。
日本経団連の米倉弘昌会長は記者から「日本の
原子力政策は曲がり角か」と問われ
「そうは思いません。今回は千年に一度の津波だ。
(地震に)あれほど耐えているのは
素晴らしい」と強調。見直しの必要について「ないと思う。
自信を持つべきだと思う」と述べた。」
『●議論などする気もなく、原発推進に邁進』
『●今に始まったことではないが、財界も腐ってる』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●消極的にしろ、積極的にしろ、「原発0%」しかない』
『●視察パフォーマンスと経団連詣で』
『●東京電力人災以降も、原発推進の姿勢を変えず』
『●東京電力原発人災が続くさ中に
「会費」なるものを払うというその無神経さ』
『●「原発推進」という結論ありきのパフォーマンス』
『●そりゃ、「老残」でしょ ~石原慎太郎・森喜朗・
米倉弘昌・渡辺恒雄の各氏のことです~』
『●原子力「推進」委員会であり、
「規制」委でもなく、「寄生」委員会(1/2)』
『●脱原発は可能:
ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●ノーベル平和賞「国民対話カルテット」は
「武器は何も解決せず」……ニッポンの経団連は武器輸出推進』
「《「武器では何も解決しない。対話が民主主義への唯一の道だ」
と訴えた》そうです。かたや我がニッポン国の経団連は……
「武器輸出推進」。《政党間の仲介や政治家と市民の対話》どころか、
政党助成金という税金をもらっておきながら、「社会貢献」と嘯きつつ、
「政策をカネで買う」ための企業献金という名の賄賂を、自民党に
二重取りさせる愚行。挙句に、自公政権は壊憲法・戦争法をごり押し。
「対話」どころか、クーデター。」
「国家戦略としての「武器輸出」を推進する「死の商人」と彼我の差を
感じる…平和憲法を持つ虚しいニッポン」
『●「政策をカネで買う」経団連の企業行動憲章には
「従業員のゆとりと豊かさを実現する」と謳っている』
「随分と酷かった前経団連会長の米倉弘昌氏の流れをくむ
現会長榊原定征氏は、自民党と癒着し、「政策をカネで買う」
そうです。そして、ノコノコとアベ様に御伴する経営者たちの
なんという浅ましさよ。「死の商人」と呼ばずして、
なんと呼べばいいのか?」
「「僕についてくれば原発や武器でがっぽりだ」か。
ノコノコとお供する経営者たちも「同じ穴の狢(むじな)」である」
『●政治献金という名の「賄賂」:
アベ様達は原発産業と「ズブズブ」の関係』
『●経団連は、「プルトニウムをつくる装置」再稼働を後押し。
そして、国家戦略としての「武器輸出」を推進!』
『●「国民に「痛み」を与えてでも消費税を上げよ」!?
自民党・核発電・戦争大好きな経団連なんて要らない』
「《国民に「痛み」を与えてでも消費税を上げよ》!?
「随分と酷かった前経団連会長の米倉弘昌氏の流れをくむ
現会長榊原定征氏は、自民党と癒着し、「政策をカネで買う」…
2017年10月衆院選の結果に大満足なんでしょう、
浮かれた経団連。自民党大好き、核発電・核輸出大好き、
戦争大好きな経団連なんて要らない!」
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201709/CK2017092702000129.html】
経団連、自民への政治献金 4年連続呼びかけへ
2017年9月27日 朝刊
経団連は会員企業に対し政治献金をするよう、四年連続で呼びかける方針を固めた。経済再生を最優先に掲げる安倍晋三政権を支える方針を会員の約千三百社に伝える。献金の是非を判断するための基礎資料となる政党の政策評価に関しては、自民・公明の与党について「国内外の政策で成果を上げており評価できる」とし、昨年の内容をほぼ踏襲する見込みだ。
十月上旬に開く会長・副会長会議で政策評価を了承し、幹事会で榊原定征(さだゆき)会長が自民党への政治献金を呼び掛ける。政策評価は政治献金の参考資料との位置づけで、榊原会長がこれまでと同様、会員企業の自主判断に基づいた政治献金を呼びかけるが、実質的には自民党への献金を続けることになる。
榊原氏は会長に就任した二〇一四年九月、中断していた政治献金を「社会的貢献」として呼び掛ける形で五年ぶりに再開。四年目となる今回も「経済最優先」を唱える安倍政権との連携の必要性を強調する。
経団連は一九九三年まで業界に必要金額を割り当てる「あっせん方式」を採用し、年百億円以上を集めていた。自民党向けの企業献金は一二年が約十四億円。政権復帰後の一三年には約二十億円に増え、その後は年二十数億円で推移している。
榊原氏はこれまで政治献金に関し「民主主義に必要なコストで企業による社会貢献の一環。何か見返りを求めて呼びかけるわけではない」と説明している。
==================================================================================
[※ 報道特集(2017年7月8日)↑]

日刊ゲンダイの記事【冷血の経団連 国民に痛みを強いてでも消費増税実現を提言】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/216327)。
《企業の内部留保は過去最高の406兆円…庶民の生活は苦しくなるばかりだ。経団連の榊原定征会長は、安倍自民が大勝した衆院選の結果を受け、「安定的な政権基盤が維持、強化された」と評価。「国民の痛みを伴う思い切った改革は、安定的な政権基盤がないとできない」とし、「消費税は増税しないと財政を再建できないので、勇気を持ってやってもらいたい」と言い放った》。
《国民に「痛み」を与えてでも消費税を上げよ》!? 「随分と酷かった前経団連会長の米倉弘昌氏の流れをくむ現会長榊原定征氏は、自民党と癒着し、「政策をカネで買う」…2017年10月衆院選の結果に大満足なんでしょう、浮かれた経団連。自民党大好き、消費増税大好き、核発電・核輸出大好き、戦争大好きな経団連なんて要らない!
『●FUKUSIMAでも変わらないNIPPON』
(このブログは2011年3月27日)
「3月21日の東京新聞特報面に日本経団連米倉弘昌会長の
驚くべきコメントが掲載されていた。
経済界からは早くも原発の危険性を忘れたかのような
発言が飛び出した。
日本経団連の米倉弘昌会長は記者から「日本の
原子力政策は曲がり角か」と問われ
「そうは思いません。今回は千年に一度の津波だ。
(地震に)あれほど耐えているのは
素晴らしい」と強調。見直しの必要について「ないと思う。
自信を持つべきだと思う」と述べた。」
『●議論などする気もなく、原発推進に邁進』
『●今に始まったことではないが、財界も腐ってる』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●消極的にしろ、積極的にしろ、「原発0%」しかない』
『●視察パフォーマンスと経団連詣で』
『●東京電力人災以降も、原発推進の姿勢を変えず』
『●東京電力原発人災が続くさ中に
「会費」なるものを払うというその無神経さ』
『●「原発推進」という結論ありきのパフォーマンス』
『●そりゃ、「老残」でしょ ~石原慎太郎・森喜朗・
米倉弘昌・渡辺恒雄の各氏のことです~』
『●原子力「推進」委員会であり、
「規制」委でもなく、「寄生」委員会(1/2)』
『●脱原発は可能:
ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●ノーベル平和賞「国民対話カルテット」は
「武器は何も解決せず」……ニッポンの経団連は武器輸出推進』
「《「武器では何も解決しない。対話が民主主義への唯一の道だ」
と訴えた》そうです。かたや我がニッポン国の経団連は……
「武器輸出推進」。《政党間の仲介や政治家と市民の対話》どころか、
政党助成金という税金をもらっておきながら、「社会貢献」と嘯きつつ、
「政策をカネで買う」ための企業献金という名の賄賂を、自民党に
二重取りさせる愚行。挙句に、自公政権は壊憲法・戦争法をごり押し。
「対話」どころか、クーデター。」
「国家戦略としての「武器輸出」を推進する「死の商人」と彼我の差を
感じる…平和憲法を持つ虚しいニッポン」
『●「政策をカネで買う」経団連の企業行動憲章には
「従業員のゆとりと豊かさを実現する」と謳っている』
「随分と酷かった前経団連会長の米倉弘昌氏の流れをくむ
現会長榊原定征氏は、自民党と癒着し、「政策をカネで買う」
そうです。そして、ノコノコとアベ様に御伴する経営者たちの
なんという浅ましさよ。「死の商人」と呼ばずして、
なんと呼べばいいのか?」
「「僕についてくれば原発や武器でがっぽりだ」か。
ノコノコとお供する経営者たちも「同じ穴の狢(むじな)」である」
『●政治献金という名の「賄賂」:
アベ様達は原発産業と「ズブズブ」の関係』
『●経団連は、「プルトニウムをつくる装置」再稼働を後押し。
そして、国家戦略としての「武器輸出」を推進!』
==================================================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/216327】
冷血の経団連 国民に痛みを強いてでも消費増税実現を提言
2017年10月27日
(ベッタリの榊原会長(左)/(C)共同通信社)
企業の内部留保は過去最高の406兆円
庶民の生活は苦しくなるばかりだ。経団連の榊原定征会長は、安倍自民が大勝した衆院選の結果を受け、「安定的な政権基盤が維持、強化された」と評価。「国民の痛みを伴う思い切った改革は、安定的な政権基盤がないとできない」とし、「消費税は増税しないと財政を再建できないので、勇気を持ってやってもらいたい」と言い放った。
国民に「痛み」を与えてでも消費税を上げよ、とはフザケた言い分だ。何しろ、財務省の「法人企業統計」(2016年度)によると、企業の内部留保は前年度を28兆円上回る406兆円。過去最高額を更新したばかりだ。
自民党の試算では、消費税を現状の8%から10%に上げると、税収が約5兆6000億円増加するという。企業の内部留保と比べ、消費税増税による税収増は雀の涙のようなもの。共産党の小池晃書記局長は、衆院選前に民放番組で「4年間で、従業員1人当たりにすると825万円も増えた。その1~2割でも(労働者に)回せば、月2万円の賃上げができる」と訴えていた。
生活苦にあえぐ庶民に消費税の「痛み」を、大金持ちの大企業が強いる――こんなことが許されていいのか。立正大名誉教授の金子勝氏(憲法)はこう言う。
「日本の消費税は収入の低い人にとって負担が重く、高い人には
軽い不平等なものです。経団連は将来的に消費税を約20%にまで
上げるべきと主張する一方、企業にかかる法人税を軽くせよと、
政府に働きかけている。『でないと海外の大企業と渡り合えない』
というのが彼らの言い分ですが、負担増で苦しむのは低所得層です。
経団連は安倍自民と距離が近いですから、今回の選挙結果には
大喜びしていることでしょう。本来は、日用品や食品には消費税を
かけず、高級品に高い税率を適用するといった対策が必要なのですが、
経団連は安倍自民に働きかけ、真逆のことをやろうとしているのです」
大企業こそ、真っ先に「痛み」を受け入れるべきではないのか。
==================================================================================


東京新聞の吉田通夫記者の記事【<いま原発へもの申す> 過去分の国民負担は政府の不当請求】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201702/CK2017020902000134.html)。
《◆城南信金・吉原相談役に聞く …「責任の所在など現代の経済社会のルールを根本から逸脱した考え方で、政府による国民への不当請求だ」と厳しく批判》。
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●脱原発は可能: ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●城南信金の吉原毅理事長が退任・・・
脱原発という、「理事長交代後も考え方は引き継がれ」て欲しい』
城南信金の相談役・吉原毅さんは、《脱原発を掲げるのは、地域を守る金融機関として当たり前の行動だ》と仰います。事実、城南信金は、そういう《行動》を実践してきました。数少ない、心ある金融機関。
そして、今回は、《経済産業省が「過去の原発事故の賠償費用が積み立て不足だった」として「過去分」と称する費用を国民に負担させる方針》に対して、重要な指摘です。《現代の経済社会のルールを根本から逸脱》《政府による国民への不当請求》《商取引の原則に反している》《東電の契約書(約款)のどこにも原発のための料金を支払わなければならないという記述はなかった》というもの。さらに、《一般の企業がやったら警察や消費者庁が黙っていない》とも仰っています。警察や消費者庁は、なぜ、沈黙を守るのでしょう?
『●原状回復が損害賠償の基本: 東京電力原発人災で
「ふるさとをなくした痛み」は全く癒えていない』
『●「核発電は安い」と言っておきながら、
「原発の電力を使っていない消費者にまで負担を強いる方針」』
『●まずは、広域に撒き散らした
「無主物」の主・東京電力が「移染」費用を支払うのがスジ』
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201702/CK2017020902000134.html】
<いま原発へもの申す> 過去分の国民負担は政府の不当請求
2017年2月9日 朝刊
◆城南信金・吉原相談役に聞く
金融機関の立場から脱原発を訴える城南信用金庫(東京都品川区)の吉原毅(よしわらつよし)相談役が本紙のインタビューで、経済産業省が「過去の原発事故の賠償費用が積み立て不足だった」として「過去分」と称する費用を国民に負担させる方針を固めたことについて「責任の所在など現代の経済社会のルールを根本から逸脱した考え方で、政府による国民への不当請求だ」と厳しく批判した。
城南信金は福島第一原発の事故後に脱原発を宣言。二〇一二年一月から電力の購入先を東京電力から原発を持たないエネットに切り替えた。にもかかわらず、費用を請求される。吉原氏は「契約が終わった後に請求するなんて商取引の原則に反している。金融機関にとって、受け入れがたい」と憤りをあらわにした。
吉原氏は「電力会社と契約者の間には電力の供給と料金の支払いという約束しかなく、東電の契約書(約款)のどこにも原発のための料金を支払わなければならないという記述はなかった」と指摘。「国家がやるから許される風潮になっているが、一般の企業がやったら警察や消費者庁が黙っていない」と述べた。 (吉田通夫)
==================================================================================


asahi.comの記事【武器輸出「国家戦略として推進すべき」 経団連が提言】(http://www.asahi.com/articles/ASH9B5S9HH9BUTFK01C.html?iref=comtop_pickup_06)。
経団連は、「10月に発足する防衛装備庁に対し、戦闘機などの生産拡大に向けた協力を求めている」。
ブログ主の頭に浮かんだのは、「死の商人」、「赤紙」。
これまで数十回にわたって、CMLの記事について、以下を「つぶや」いてきました。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
■「赤紙」が来る時代(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/c5aecf5f3f80e3bdca64d1b8b6603ed0) 『[CML 035569] 武器輸出に資金援助』(http://list.jca.apc.org/public/cml/2014-December/035684.html)/「武器を売って手にした金で、娘はピアノを買ってもらい平和の曲を奏でる」
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
改めて、東京新聞のリンクは既に切れていますが、そのまま、このCMLの記事を以下に引用させていただきます。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
【http://list.jca.apc.org/public/cml/2014-December/035684.html】
[CML 035569] 武器輸出に資金援助
・・・・・・ ・・・ at ・・・・・・.jp
2014年 12月 21日 (日) 20:15:57 JST
<http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014121702000121.html>
武器輸出に資金援助を検討とあるが、おそらく安倍はやる気だろう。
税金を投入して武器輸出を援助し雇用創出で経済も上向きになる企てなのかも知れない。
武器で生計を立てる人々が増えれば、戦争を望む人々が増えるだろう。
日本以外の国で戦争が起これば「武器セールスマン」の出番だ。
娘:「お父さん、今度の誕生日にはピアノを買って」
父:「いいとも、今景気がいいから大丈夫だ」
武器を売って手にした金で、娘はピアノを買ってもらい平和の曲を奏でる。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
東京新聞の元記事は、ある方のブログ(http://blog.livedoor.jp/gataroclone/archives/41861798.html)に貼ってありましたので、以下に孫引きさせて頂きます。望月衣塑子記者は原発関連の記事も手掛けておられます。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
【http://blog.livedoor.jp/gataroclone/archives/41861798.html】
どこへ行く、日本。
政治に無関心な国民は愚かな政治家に支配される。
2014年12月17日
国が企業向け促進策検討 武器輸出に資金援助【東京新聞】
(本ブログ主注: 東京新聞の当該記事の写真)
国が企業向け促進策検討 武器輸出に資金援助
東京新聞 2014年12月17日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014121702000121.html
防衛省が、武器を輸出する日本企業向けの資金援助制度の創設を検討していることが分かった。国の資金で設立した特殊法人などを通して、低利で融資 できるようにする。また輸出した武器を相手国が使いこなせるよう訓練や修繕・管理を支援する制度なども整える。武器輸出を原則容認する防衛装備移転三原則の決定を受け、国としての輸出促進策を整備する。 (望月衣塑子)
防衛省は、武器輸出支援策を具体化するため、有識者による検討会を十八日にも立ち上げる。検討会には、防衛産業の関係者や金融、法律の専門家などのほか、森本敏元防衛相らも参加する予定。来夏をめどに議論をまとめ、二〇一六年度の予算要求などに反映させていく。
検討会では、日本企業による武器輸出を後押しするため、財政投融資制度などを活用した企業向けの資金援助制度の創設などを話し合う。国が出資して 特殊法人や官民ファンドを設立。この特殊法人などが債券を発行して調達した資金や、国が保有する株式などの配当金や売却益を財源として、武器輸出を行う企業に長期で低利融資できる制度などを議論する。さらに経済産業省と連携し、防衛産業振興のための補助金制度の創設なども検討する。
また武器輸出を進めるには、武器だけの販売ではなく、定期的な整備や補修、訓練支援なども含めた「パッケージ」として販売していくことが必要とさ れる。実際、海上自衛隊が使う救難飛行艇(US2)にインドが関心を示しているが、日本に補修や訓練などを含めた販売ノウハウがないことが障害となっている。
このため相手国の要望に応じて、退職した自衛官などを派遣し、訓練や修繕・管理などを行う制度などを整備することについても検討している。
検討会について防衛省幹部は「武器輸出を進めるためのあらゆる課題を議論する」としている。
<財政投融資> 国が財政政策の一環として行う投資や融資で、「第2の予算」ともいわれる。国債の一種である財投債を国が発行して特殊法人など財 投機関に資金配分したり、財投機関が自ら財投機関債を発行し資金を調達、政策を実行する。かつては郵便貯金などの資金を旧大蔵省が運用、配分していたが、 2001年の財投改革で廃止された。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
『●ブレーキは無く、二つの「アクセル」な自公政権』
「防衛産業でつくる経団連の防衛生産委員会が、
事実上の禁輸政策だった武器輸出三原則を大幅に
緩和すべきだとする提言をまとめた。安倍政権が
進める三原則見直し作業に呼応した内容で、
官民一体を演出し、武器輸出解禁に道を開く狙いが
あるとみられる」
『●経団連の本音、「市民を戦場に連れてって」:
「米国の商売としての戦争」という地獄へ突き落す行為』
『●悪徳企業型徴兵制……「(自衛隊の)派兵はもちろんのこと、
派遣も反対」の中山素平さんは泣いている』
財界・経済界・産業界は、まさに「死の商人」……「財界の鞍馬天狗」中山素平氏は泣いていないか?
『●1000000年間「死の灰」を管理、
「国が科学的に有望な候補地を絞り込」むと云う「科学的」とは?』
「原子力発電環境整備機構(NUMO)が見つけることの
出来なかった「死の灰」の処分地。そして、国がコソコソと
候補地を非公開で探すそうだ。災害大国ニッポンに処分地など
あるはずもないというのに、原発推進とはね。原発を動かせば、
もれなく「死の灰」が付いてくるわけで、「核のゴミを出さない国」
って、矛盾もいいところ。「死の灰」を回避し得ない上に、
「たかが電力のため」の単なる「発電機能付き湯沸し装置」に
群がるヒトたち。そして「内橋克人さんは
「原発は『プルトニウムをつくる装置』」だと喝破している」。
自公議員をはじめ、電力会社、原子力「ムラ寄生」委員会、
財界、・・・本当にアサマシイ人たちだ。
「原発を使い続ければ、必ず核のごみは出る。
発生抑制こそ、最善のごみ対策だ」」
「たかが電力のための単なる「発電機能付き湯沸し装置」「プルトニウムをつくる装置(内橋克人さん)」である核発電所を再稼働したいと熱望したのも経団連その他の財界でした。特に、2011年3月の3・11東京電力原発人災直後から蠢き始めた、経団連の米倉弘昌元会長の言動や行動は目に余りました。
『●FUKUSIMAでも変わらないNIPPON』
(このブログは2011年3月27日)
「3月21日の東京新聞特報面に日本経団連米倉弘昌会長の
驚くべきコメントが掲載されていた。
経済界からは早くも原発の危険性を忘れたかのような
発言が飛び出した。
日本経団連の米倉弘昌会長は記者から「日本の
原子力政策は曲がり角か」と問われ
「そうは思いません。今回は千年に一度の津波だ。
(地震に)あれほど耐えているのは
素晴らしい」と強調。見直しの必要について「ないと思う。
自信を持つべきだと思う」と述べた。」
『●議論などする気もなく、原発推進に邁進』
『●今に始まったことではないが、財界も腐ってる』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●消極的にしろ、積極的にしろ、「原発0%」しかない』
『●視察パフォーマンスと経団連詣で』
『●東京電力人災以降も、原発推進の姿勢を変えず』
『●東京電力原発人災が続くさ中に
「会費」なるものを払うというその無神経さ』
『●「原発推進」という結論ありきのパフォーマンス』
『●そりゃ、「老残」でしょ ~石原慎太郎・森喜朗・
米倉弘昌・渡辺恒雄の各氏のことです~』
『●原子力「推進」委員会であり、
「規制」委でもなく、「寄生」委員会(1/2)』
『●脱原発は可能:
ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●「政策をカネで買う」経団連の企業行動憲章には
「従業員のゆとりと豊かさを実現する」と謳っている』
「随分と酷かった前経団連会長の米倉弘昌氏の流れをくむ
現会長榊原定征氏は、自民党と癒着し、「政策をカネで買う」
そうです。そして、ノコノコとアベ様に御伴する経営者たちの
なんという浅ましさよ。「死の商人」と呼ばずして、
なんと呼べばいいのか?」
「「僕についてくれば原発や武器でがっぽりだ」か。
ノコノコとお供する経営者たちも「同じ穴の狢(むじな)」である」
『●政治献金という名の「賄賂」:
アベ様達は原発産業と「ズブズブ」の関係』
一方、アベ様のお膝元での「戦争できる国」、壊憲法案・戦争法案へのハタ振りの動き。東京新聞の記事【安保法案成立先取りの決議案 首相地元の下関市議会】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015091001001635.html)によると、「議案は「平和安全法制の速やかな確立に関する決議案」と題し、「平和安全法制整備法ならびに国際平和支援法が成立した今こそ、国民の生命と財産を守る安全保障体制を確立することを強く要望する」としている」。
呆れます。「平和安全法制」「国際平和支援」……「私は総理なのだから」のアベ様のお膝元では壊憲法案に「平和」「安全」というラベルが上貼り。
『●「平和」「安全」ラベル付き「戦争法案」:
「非戦闘地域」で「後方支援したい。リスクとは関わりない」』
「アベ様の妄想に付き合っていては、アベ様の暴走を許せば、
ニッポンは御終いだ。挙句に、「我々が提出する法案についての
説明は全く正しい。私は総理なのだから」・・・・・・恐ろしい人が
首相になったものである、それも二度もネ」
「死の灰」製造再開、そして、「死の商人」……ニッポンは大丈夫なんですか? 正気でしょうか??
ブログの末尾になってしまいましたが、いま、茨城や栃木で、鬼怒川氾濫水害で被災されている全ての方々にお見舞いを申し上げたい。「死の灰」製造、「死の商人」、五輪等々にドブガネするお金があるのならば、東京電力原発人災も含めて、一人でも多くの被災者の皆様に有効に使われるべきだ、と強く思う。
3・11東京電力原発人災から4年半が経過した。この水害の解決と同時に、3.11原発人災の被災者救済も、国会での壊憲法案の廃案も引き続きとても重要。アベ様達自公議員に任せていてはいけない。
=====================================================
【http://www.asahi.com/articles/ASH9B5S9HH9BUTFK01C.html?iref=comtop_pickup_06】
武器輸出「国家戦略として推進すべき」 経団連が提言
小林豪2015年9月10日19時50分
経団連は10日、武器など防衛装備品の輸出を「国家戦略として推進すべきだ」とする提言を公表した。10月に発足する防衛装備庁に対し、戦闘機などの生産拡大に向けた協力を求めている。
提言では、審議中の安全保障関連法案が成立すれば、自衛隊の国際的な役割が拡大するとし、「防衛産業の役割は一層高まり、その基盤の維持・強化には中長期的な展望が必要」と指摘。防衛装備庁に対し、「適正な予算確保」や人員充実のほか、装備品の調達や生産、輸出の促進を求めた。具体的には、自衛隊向けに製造する戦闘機F35について「他国向けの製造への参画を目指すべきだ」とし、豪州が発注する潜水艦も、受注に向けて「官民の連携」を求めた。産業界としても、国際競争力を強め、各社が連携して装備品の販売戦略を展開していくという。(小林豪)
=====================================================

東京新聞の記事【「脱原発経営 引き継ぐ」 城南信金 吉原理事長退任へ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2015041702000126.html)。
「吉原氏は十六日、「脱原発を掲げるのは、地域を守る金融機関として当たり前の行動だ」と語り、理事長交代後も考え方は引き継がれると述べた」。
城南信金の吉原毅理事長が退任するそうだ。脱原発は可能と信じる、数少ない、ビジョンある金融機関のトップ。「エネルギー問題のシンクタンク「城南総合研究所」を設立・・・・・・名誉所長に小泉純一郎元首相を迎えた」というのは気に入らないけれど、「理事長交代後も考え方は引き継がれ」て欲しい。
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
『●脱原発は可能: ビジョンある金融機関(城南信金)のトップもいる』
======================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2015041702000126.html】
「脱原発経営 引き継ぐ」 城南信金 吉原理事長退任へ
2015年4月17日 朝刊
(原発を使わないエネルギーへの切り替えを発表する
吉原毅理事長=2011年12月)
脱原発を掲げた経営者として知られた城南信用金庫(本店・東京都品川区)の吉原毅(よしわらつよし)理事長(60)が六月の任期満了で退任し、相談役に就くことが決まった。吉原氏は十六日、「脱原発を掲げるのは、地域を守る金融機関として当たり前の行動だ」と語り、理事長交代後も考え方は引き継がれると述べた。 (須藤恵里)
後任には、常勤理事の守田正夫(もりたまさお)氏(58)が就く。
吉原氏は相談役として「利益優先ではなく地域の幸せを守るという信金の原点を新しい世代に伝えていく」という。脱原発についても発信を続けていく考えだ。
吉原氏は二〇一一年、理事長に就任した直後に起きた東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故を受け、「脱原発」を標榜(ひょうぼう)した。「信金は地域に寄与するための金融機関。原発事故が起これば存在基盤の地域そのものが失われてしまう」(同氏)との使命感からだった。震災翌年には、エネルギー問題のシンクタンク「城南総合研究所」を設立。一四年七月には名誉所長に小泉純一郎元首相を迎えた。
情報発信だけでなく、信金自らの取り組みも行ってきた。東電から店舗で使う電気を購入することをやめ、原発に頼らない自然エネルギーなどを使う電力会社に切り替えた。「日本で使われる電力の三割を占める原発に頼らないためには自ら節電をする必要がある」とし、職員の協力で震災翌年には使用電力の三割削減を実現。
震災や原発事故の影響で東北の信金から内定が取り消された学生十人の採用も行った。
=======================================================

東京新聞の社説【年のはじめに考える 真の強者は弱者に優しい】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015010402000123.html)。
「◆方向違いの三本の矢 翻ってアベノミクスです。なぜ行き詰まり、格差拡大などの問題が生じているのでしょうか・・・・・・大切なのは、社員とその家族ら企業に関わるすべての人の幸せづくり・・・・・・アベノミクスは一番大切なものをないがしろにしているのです」
『●所得再分配機能が破壊: 「眠り猫」はアベ様を「支持」することで自分の首を絞めている』
「病名は「再分配機能の不全」」なり。「弱者に厳しく強者に優しい」ドアホノミクス(©浜矩子さん)は「一番大切なものをないがしろにしている」。
『●「資本主義に絶望せよ!? ピケティ」
『週刊金曜日』(1021号)についてのつぶやき』
「大切なのは、社員とその家族ら企業に関わるすべての人の幸せづくり」・・・・・・それを見失っては「未来」は無いでしょう。
『●働くとは何か? 生業とは?』
『●「報われない国」の労働環境の「質」の劣化』
「人を大事にする経営で知られる岐阜県の未来工業(電気・ガス設備
資材)は、全員が正社員で定年も七十歳。昭和四十年の創業以来、
赤字はなく、社員約八百人の平均年収は六百二十万円(四十三歳)。
好業績は社員の提案に基づく商品開発力にあるという。かつてと違い、
大手企業からヒット商品が生まれないのも人件費削減に躍起な経営と
無縁ではあるまい。/ところが安倍政権は「世界一企業が活動しやすい国」を
掲げ、解雇しやすい正社員といわれる「限定正社員」など雇用流動化に
力を入れる。派遣労働についても規制緩和を一段と進める方針である」
『●「資本主義の狂気」 『週刊金曜日』
(12月13日、972号)についてのつぶやき』
『●「報われない国」のこんな労働環境質の悪い中での希望の光』
『●「優しくすれば、社員もここを守りたいと働いてくれる」:
未来工業の創業者のお一人が亡くなる』
『●「政策をカネで買う」経団連の企業行動憲章には
「従業員のゆとりと豊かさを実現する」と謳っている』
『●「非正規労働者2000万人時代」
『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号)について』
「■⑦『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 東海林智氏
【「正社員ゼロ」「残業代ゼロ」 労働の商品化が加速する 「派遣村」から
6年、「人間の尊厳」を奪う安倍政権】、「短期化、流動化する雇用・・
安倍政権・・働く者の尊厳を大事にするという発想が決定的に
欠けている」。未来工業や城南信金と経団連
(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/793d40802e3c432fc29f0b21c17b62db)」
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015010402000123.html】
【社説】
年のはじめに考える 真の強者は弱者に優しい
2015年1月4日
アベノミクス「再起動」の年となります。デフレからインフレへの転換を目指すも行き詰まり、むしろ弊害が目立ちます。根底から軌道修正すべきです。
昨年末、日本のあるビジネス書が日本と中国で同時出版という珍しいケースがありました。もっとも翻訳作業の関係で中国での出版は少し遅れていますが。
タイトルは「逆風を追い風に変えた企業」。副題に「元気印中小企業のターニングポイント」とあります。円高や構造不況などさまざまな逆境を乗り越えた中小企業十七社の成功例を示していて、そのポイントも分析しています。
◆読まれる徳の経営書
「中国側からの執筆依頼がきっかけです。それだけ中国企業の多くがターニングポイント(曲がり角)にあるということです」
著者を代表する法政大学大学院の坂本光司教授が語ります。すでに中国でも二冊の著書が出版され、その「人を大切にする経営哲学」は経済成長にまい進する隣国でもよく知られているのです。
以前にも坂本教授のもとには、北京からこんな話がありました。
中国のシンクタンクに勤める女性からの訴えです。「日本に追いつき追い越せと中国の企業は、この数十年がむしゃらに頑張ってきました。確かに国内総生産(GDP)は増えましたが、企業や地域社会からはぬくもりが消え、まるで砂漠のようになってしまいました。幸せになりたいから頑張ってきたのに、やたらギスギスしているのです」。そして中国の経営者組織向けの講演を依頼したのです。
米国をもしのぎ世界一の経済大国になるであろう中国ですが、経済発展とは裏腹に貧富の格差や都市と農村の落差は同じ国とは思えないほど。行き過ぎた成長至上主義、拝金主義ゆえのひずみが国を蝕(むしば)んでいる。反動から日本の徳を勧める経営書が読まれ、代表例は京セラ創業者で日本航空の再建を率いた稲盛和夫氏の著書です。
◆方向違いの三本の矢
翻ってアベノミクスです。なぜ行き詰まり、格差拡大などの問題が生じているのでしょうか。
まず日銀が国債を買いまくって金利を下げる異次元緩和です。金利が異常な低水準になっても企業の投資や生産は伸びません。消費が冷え込んだまま、需要が盛り上がらないのだから当然です。
よってデフレ脱却も怪しい。想定したシナリオはこうでした。日銀が「二年で2%の物価上昇を実現する」と約束して緩和すれば、物価が上がるとの予想が広がり、そうなる前にと消費や投資が誘発され、物価が上昇する、と。
しかし、その通りに進みません。日銀の物価上昇目標は消費税増税による分(約2%)を除きます。すると上昇率は1%にも達しない。一方、賃金上昇は物価上昇より低く、消費は誘発されません。
四月で「約束の二年」です。急激な原油安が物価を押し下げた面もあり、物価上昇率や時期の目標を柔軟に修正すべきでしょう。
次に機動的な財政出動。公共事業を急増させるも建設現場の人手不足や資材高騰で消化不良に陥りました。公共事業が民間から仕事を奪う弊害も指摘されます。そもそも財政は危機的状況だから大盤振る舞いは続けるべきでない。
最後に成長戦略。この哲学にこそ問題があります。「企業が世界で一番活動しやすい国」といって経営者寄りの、目先の利益しか考えないような政策ばかりです。一時的に株価が上昇しても長続きはしない。
日本経済にとって必要なのは消費を支え経済社会に安定をもたらす中間層の存在です。勝ち組と負け組をつくり、二極化する分断社会ではありません。
アベノミクスに最も欠けている視座は、弱者への配慮であり、再分配政策など格差を縮める努力です。真の強者は弱者に優しい。弱者に冷たいのは、ただの弱い者いじめでしかないのです。
世界のトップクラスになった韓国サムスン電子。その幹部はわざわざソウルから坂本教授の自宅を訪ねてきたそうです。「かつて世界の羨望(せんぼう)の的であり、我々の目標でもあった日本の著名企業はなぜつまずいたのか、そうならないためにどうすればいいでしょうか」と危機感いっぱいに尋ねました。
◆一番大切なものとは
対する答えは、こうでした。
「大切にすべきことをないがしろにすると組織は必ずおかしくなる。一番大切なのは業績でもシェアでもない。それらは経営の結果としての現象です。大切なのは、社員とその家族ら企業に関わるすべての人の幸せづくり。ご指摘の企業は、残念ながらその視点がいつの間にか欠落してしまったのではないでしょうか」
アベノミクスは一番大切なものをないがしろにしているのです。
==============================================================================

『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号)について、最近のつぶやきから、AS@ActSludge。
今週のブログ主のお薦めは、鎌田慧さん【保革乗り超え新基地を拒否した「オール沖縄」のこころ 10万票の大差で辺野古移設反対の翁長氏が圧勝】と高嶋伸欣さん【「韓国紙記事を誤読」の事実を伏せている『産経』前支局長問題】。
******************************************************************************
■①『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 「非正規労働者2000万人時代」。【元「31歳、フリーター」はなぜ、「希望は戦争」を諦めたか 赤木智弘×雨宮処凛】。安田純平さん『ルポ戦場出稼ぎ労働者』、一読の価値大あり、「この流れが加速し、定着すれば、「愛国心」と「空気」は戦場へ「行くな」から「行け」へと変わっていくだろう。そのときのために用意されてきたのが格差である。仕事がないなら戦場へ行け、ということだ」」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/25aeb85839f7e9274655adf7a976c909)
■②『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 明石昇二郎さん【福島第一原発事故で故郷を喪失の飯舘村民、身体に影響も 裁判外紛争解決手続き申し立て】、「謝れ! 償え! かえせふるさと・・・・・・「もう、あの飯舘村は戻ってこない」・・・・・・「・・・・・原発さえなければ、孫と一緒に暮らせたのに」」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/06eaf88a6d6b6f7d2f7d116b9f39a96e)
■③『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 永野厚男氏【都立大島高校が自衛隊と訓練 「防災教育」を逸脱か】、「災害時、生徒は自分の命を守るのが第一。避難民救済の役割まで求めるのはボランティアの範囲を超える・・・・・・学校現場に〝異変〟が生じている」。「いろんな意味で疲れます・・・住民基本台帳活用とアイドルによる「番宣」で「果てしない夢」へGO!」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/c5aecf5f3f80e3bdca64d1b8b6603ed0)
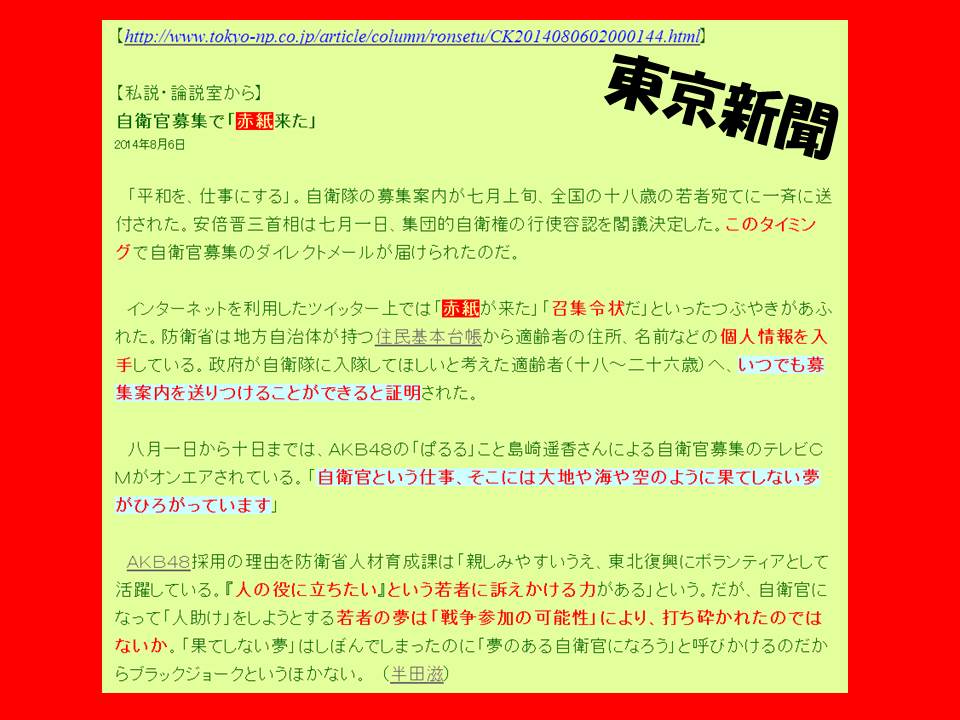
■④『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 【村岡和博の政治時評/大義なき衆院解散を安倍サヨナラ選挙に】、「デタラメなアベノミクスも、民意も立憲主義も無視する安倍首相のやり口も、まとめてさよならする選挙にしなければなるまい」。「●選挙を何度やっても、「騙されることの責任」「考えないことの罪」を自覚し得るかどうか?」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/15305f7db74dbd06410433167abaf585)
■⑤『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 鎌田慧さん【保革乗り超え新基地を拒否した「オール沖縄」のこころ 10万票の大差で辺野古移設反対の翁長氏が圧勝】、「新たな基地は造らせないとい沖縄の民意は揺るがないことが明確に」。「さあ、ここから。高江・辺野古破壊問題等々・・・「過去のもの」や「終わり」にしてはいけない」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/b989d3a41d428a9731edceaf156ba86c)
■⑥『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 【佐高信の新・政経外科第20回/疑惑隠しの自己都合解散】、「「脱税」の疑い指摘され激昂した安倍首相・・相続税3億円を脱税したという疑惑」。そして、「暴力団人脈」による「ダーティな政治手法」!? またしても、アベ様、ダークすぎます(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/beae9170eb3ab970e4aa27aaf77124cc)
■⑦『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 東海林智氏【「正社員ゼロ」「残業代ゼロ」 労働の商品化が加速する 「派遣村」から6年、「人間の尊厳」を奪う安倍政権】、「短期化、流動化する雇用・・安倍政権・・働く者の尊厳を大事にするという発想が決定的に欠けている」。未来工業や城南信金と経団連(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/793d40802e3c432fc29f0b21c17b62db)
■⑧『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 平舘英明氏【臨時教員は潜在的失業者だ 「安上がり」教育が生む労働破壊】、「官製ワーキング・プア・・子どもの学習環境に直結・・「安上がり」教育のツケは大きい」。未来に投資しないアベ様(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/7907fe4edcb5c8f185faeedc8513702d)
■⑨『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 山口正紀さん【〈大政翼賛新聞〉への回帰 『読売』憲法改正試案20周年】、「〈・・・・・・タブー打破 先駆的意義/論議活性化 きっかけに〉・・・・・・『読売新聞』・・・・・・特集の見出しだ。1ページ全部を使った自画自賛」。恥ずかしい新聞、社主だけの問題か?(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/ab709a5ec0b6dfdfee9e4b814272fb58)
■⑩『週刊金曜日』(2014年11月21日、1017号) / 高嶋伸欣さん【「韓国紙記事を誤読」の事実を伏せている『産経』前支局長問題】、「もともと『産経』に『朝日新聞』の不手際の連鎖を責める資格はないし、他のメディアも五十歩百歩の類だ」。全く同感! 『産経』新聞韓国大統領名誉棄損事件の記事は声高に「言論の自由の侵害」を叫べるようなモノ?』、まさか、ご冗談を(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/cb7468d1eb62dcb08262fc7656d96ad2)
******************************************************************************

東京新聞の社説【政治献金 経団連の再開に反対だ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014090102000173.html)と、
コラム【【私説・論説室から】儲かる秘訣を尋ねたら…】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2014090102000175.html)。
「過去二十年、経団連自身が悩み考え、二転三転しながらも中止している政治献金を、榊原経団連が再開するという。「政策をカネで買う」という根本的な批判に応えられるのか」・・・・・・経団連の企業行動憲章は「従業員のゆとりと豊かさを実現する」「企業は雇用の維持・拡大を実現し、国民生活を豊かにする役割を果たしている」と謳っている。
『●企業の貯金250兆と「働くとは何か?」』
「人材確保、人材雇用という時の、人材の『材』の字が気に入らない。人間は材料じゃない。財産の『財』、人財と書くべきだ」・・・・・・未来工業や城南信金に対して、経団連という組織は本当に「従業員のゆとりと豊かさを実現する」「企業は雇用の維持・拡大を実現し、国民生活を豊かにする役割を果たしている」と言えるでしょうか? 随分と酷かった前経団連会長の米倉弘昌氏の流れをくむ現会長榊原定征氏は、自民党と癒着し、「政策をカネで買う」そうです。そして、ノコノコとアベ様に御伴する経営者たちのなんという浅ましさよ。「死の商人」と呼ばずして、なんと呼べばいいのか?
『●「優しくすれば、社員もここを守りたいと働いてくれる」:
未来工業の創業者のお一人が亡くなる』
『●アベ様が「原発再稼働、進める方針を明言」
・・・・・・世界に向けて「恥」を発信』
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014090102000173.html】
【社説】
政治献金 経団連の再開に反対だ
2014年9月1日
過去二十年、経団連自身が悩み考え、二転三転しながらも中止している政治献金を、榊原経団連が再開するという。「政策をカネで買う」という根本的な批判に応えられるのか。再開には反対だ。
今年六月に就任した榊原定征経団連会長は「政治と経済は車の両輪」と語り、ぎくしゃくしていた安倍政権との関係修復を加速している。二〇〇九年十月以降、中止している政治献金の再開はその象徴といえる。
民主主義の下で企業と政治、カネはどうあるべきか-。考え抜いたあげく、企業の政治献金は廃止すべきだとの結論を出したのは一九九三年、当時の平岩外四会長だった。
保守合同の五五年以来、経団連は、会員企業に割り当てる「あっせん方式」で年間百億円程度を自民党に献金していた。これが金権腐敗の温床になり、リクルート事件、佐川急便事件、金丸信自民党副総裁をめぐる巨額脱税事件などを引き起こす。
世論の批判で自民党一党支配が終わり、細川連立政権誕生後の九三年九月、平岩経団連が公表したのが「企業献金に関する考え方」だった。冒頭を引用する。
「民主政治は、国民全ての参加によって成り立つものである。それにかかる必要最小限の費用は、民主主義維持のコストとして、広く国民が負担すべきである。従って、政治資金は、公的助成と個人献金で賄うことが最も望ましい」
平岩会長は企業献金の廃止を考えていたとされるものの、慎重論もあり、まずはあっせんを廃止。企業献金については「一定期間後、廃止も含めて見直すべきだ」とした。
〇四年になると奥田碩会長が、各政党の政策を評価して金額を決定する方式で、献金への関与を復活させた。小選挙区制が導入されたのを受け、「二大政党制」定着を目指して民主党への献金も表明したが、この方式は民主党政権発足後、民主党が献金を断り、〇九年十月から中止されている。
企業と政治、カネの問題は「政策を買う」との批判と政治改革の中で揺れ動き、経団連の献金は中止に至っている。にもかかわらず再開するのは何のためか。
見えてくるのは政権との関係修復とアベノミクス推進の算術だけで、民主主義や政党政治への見識はうかがえない。再開の決定は九月以降となる。その前に榊原会長には「企業献金に関する考え方」をもう一度読んでほしい。選ぶべきは再開ではなく廃止ではないか。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2014090102000175.html】
【私説・論説室から】
儲かる秘訣を尋ねたら…
2014年9月1日
「人材確保、人材雇用という時の、人材の『材』の字が気に入らない。人間は材料じゃない。財産の『財』、人財と書くべきだ」
型破りな経営で半世紀近く、目を見張る好業績を続けてきた名物経営者が七月末に逝った。岐阜県に本社がある電気設備資材メーカー「未来工業」の創業者、山田昭男さん。
社員をとことん大事にした。残業なし。パートや派遣社員なし。八百人の社員は全員正社員だ。年間休日はおそらく日本一の百四十日。有給休暇四十日を合わせれば一年の半分は休日になる。六十代社員の平均年収は約七百万円、それが定年の七十歳まで続く。「豊かな人生が、やる気を生む」という信念からだ。唯一社員に求めたのは常に考えること。アイデア、提案、何でも一件五百円で買い取り、それが国内有数のシェアにつながった。
儲(もう)かる秘訣(ひけつ)を聞かれ、「儲からない会社の反対のことをやる」。時流に流されずに年功序列を貫き、成果主義に背を向け続けた。
では、「あの人」に儲かる秘訣を尋ねたら…。「労働時間でなく成果で評価する残業代ゼロで働かせる」「派遣や解雇しやすい限定正社員を増やして労働コストを抑える」とでも答えるか。それこそ、働く人を「儲けるための材料」としかみていないのである。
あるいは「僕についてくれば原発や武器でがっぽりだ」か。ノコノコとお供する経営者たちも「同じ穴の狢(むじな)」である。 (久原穏)
==============================================================================

東京新聞の記事【原発再稼働、進める方針を明言 安倍首相、ロンドンの講演で】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014050201001077.html)。
CMLの記事【[CML 031105] Fw:30日の政府交渉/火山評価・汚染水問題・防災避難計画について】(http://list.jca.apc.org/public/cml/2014-May/031126.html)。
最後に、asahi.comの社説【電力経営―逆境を「変革元年」に】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)。
『●世界に向けて「汚染水漏えい問題はない」と言い切ってしまったょ・・・・・・』
ドイツ訪問後、イギリスにて「経済成長の実現に向けて原発再稼働を進める方針を明言・・・・・・経済成長のためには安定的で安いエネルギー供給の実現が不可欠とし「世界のどこにも劣らないレベルの厳しい安全基準を満たした原発を、慎重な手順を踏んで再稼働させる」と表明。英国と原子力技術の開発に取り組む考え」・・・・・・恥ずかしいー! 「安定的で安いエネルギー」なんてまだ言ってるし!! ドイツに行って何見てきたんだ? おまけに、「世界のどこにも劣らないレベルの厳しい安全基準を満たした原発」って、よく言えたものだ。逆に、3.11以前はそのレベルではなく、「想定不適当事故」などを許してきた自民党の責任を一体どうするつもりなのか。
CMLに「参議院議員会館で行われた「川内原発の再稼働審査・汚染水問題に関する政府交渉」について、阪上武さん(福島老朽原発を考える会)の報告」が出ています。川内原発をはじめ、こんな状況で再稼働する心算でしょうか? 電力会社によるヤラセ自己評価を、この先に、原子力「推進」委員会(原子力「寄生」委員会)が認めたからといって、何なんでしょうか?
『●無責任の極み:
「政府、東電の再建計画を認定 柏崎刈羽「7月再稼働」」』
『●「エレファント・イン・ザ・ルーム」:
原発再稼働・輸出という、「危険なゾウ」の暴走』
『●東電原発人災対策がお粗末すぎる・・・・・・、
そして「推進」しか出来ない原子力「規制」委員会』
『●トリチウム、使用済み吸着剤の処理・処分、
・・・再稼働や輸出なんてやっている場合か?』
『●原子力「寄生」委員会の審査に通ったからといって何だというのでしょう?』
最後に、「福島第一原発の事故が起きた後も、東京電力以外の各社は基本的に、震災以前の路線を踏襲してきた。だが、自民党が政権に戻っても、事態は電力会社の都合のいいようには動いていない。原発維持を打ち出した安倍政権も、安易な再稼働や電気料金の値上げは国民の反発を招くことを承知しているからだ」。言っちゃぁ悪いが、電力会社の経営者は能無し、センス無し。すぐさま、脱原発に転換すれば、こんな体たらくにならずに済んだはずなのに、経営センスが悪すぎる。特に、東京電力と九州電力、関西電力。そして、なんと言っても経団連。城南信金に学べないダメ経営者。
『●マガイ物ではないモノもある ~城南信金~』
『●財界の総理大臣はもはや大企業の単なる代弁者』
『●経団連は原発推進・復活の第4案を希望?』
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014050201001077.html】
原発再稼働、進める方針を明言 安倍首相、ロンドンの講演で
2014年5月2日 08時35分
(ロンドンの金融街シティーで講演する安倍首相=1日(共同))
【ロンドン共同】 安倍晋三首相は1日夜(日本時間2日早朝)、ロンドンの金融街シティーで講演し、経済成長の実現に向けて原発再稼働を進める方針を明言した。日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)に関し、2015年中の交渉妥結に意欲を示した。
経済成長のためには安定的で安いエネルギー供給の実現が不可欠とし「世界のどこにも劣らないレベルの厳しい安全基準を満たした原発を、慎重な手順を踏んで再稼働させる」と表明。英国と原子力技術の開発に取り組む考えを明らかにした。
==============================================================================
==============================================================================
【http://list.jca.apc.org/public/cml/2014-May/031126.html】
[CML 031105] Fw:30日の政府交渉/火山評価・汚染水問題・防災避難計画について
杉原浩司(Koji Sugihara) kojis at agate.plala.or.jp
2014年 5月 2日 (金) 00:29:36 JST
東京の杉原浩司(福島原発事故緊急会議/緑の党・脱原発担当)です。
[転送・転載歓迎/重複失礼]
4月30日に参議院議員会館で行われた「川内原発の再稼働審査・汚染水問
題に関する政府交渉」について、阪上武さん(福島老朽原発を考える会)の
報告を転送します。火山影響評価、避難計画、汚染水問題と重要テーマの
三本立てでした。
重要な内容ですので、ぜひご一読ください。
---------------------------------------
みなさまへ
昨日(注:30日)は政府交渉お疲れさまでした。
◆火山影響評価について
参議院議員会館で参加者は70名ほど。鹿児島、佐賀、福岡、関西、首都圏他か
ら参加がありました。テーマは、川内原発の火山影響評価、汚染水問題、原子力
防災・避難計画の3つですが、そのうち、火山影響評価について簡単にご報告い
たします。
川内原発の火山影響評価については、審査の過程で火山学者が全く関与しておら
ず、火山学者から懸念の声が上がっている中、こちらからは、有識者会合の開催
しその間は審査を止めるべきではないかという旨の事前質問を出していました。
折しも、交渉の前日の毎日新聞に、規制庁は、再稼働後に有識者会合を開催する
方針だとの記事が流れました。交渉は、再稼働後ではおかしいではないかという
点に集中しました。
規制庁は、地震・津波担当の牧野氏が対応しました。牧野氏の回答は、「外部有
識者に意見を聴くというのは、今後行われるモニタリングの結果に関しまして、
事業者の評価が適切かどうかを判断するの際の規制側の考え方を整理するためで
ございまして、許認可時に求めるものではございません。」というものでした。
しかしこれは、前回4月23日の規制委適合性審査会合で、島崎委員長代理の発
言とは異なります。島崎氏は、「火山学者の、専門家の方を集めていただいて、
議論をする。それを九州電力さんが、設定してやるというのは非常にいいことだ
と思いますが、私どもとしましても、ある段階で、しかるべき検討が必要である
ことは自覚しております。判断基準はあらかじめもっておくということは非常に
重要で、それは大切だと思いますけれど、やはり決める場合にはもう少し慎重な
検討が必要だと思います。」と述べていました。ここで判断基準と言っているの
は、火山活動の兆候を把握した場合の対処を講じるための判断条件のことです。
交渉はまず、破局的噴火について、兆候を把握した場合の対処のための判断基準
が現時点でないことを確認し、新規制基準火山審査ガイドに、兆候を確認した場
合の対処方針を定めることが要求されていることを確認した上で、この判断基準
が定められないうちに再稼働を許すのは、火山審査ガイドに違反しているのでは
ないかと問い質しました。牧野氏は、詳細な判断基準は必要ない、有識者会合は
適合性審査とは別だ、などと繰り返すだけでした。
破局的噴火の兆候の把握については、そもそも核燃料の避難が間に合うようなタ
イミングで把握することそのものが可能かどうかも不明確であり、島崎氏の適合
性審査会合でもまさにそこが問題になっています。
大飯原発の断層問題では、有識者会合を開き、その間は再稼働の申請を受け付け
ませんでした。これに比べても明らかに対応が異なります。法的にも問題がある
対応です。有識者会合の開催とその間の審査の中断については、今後も直接の抗
議、要請、議員へのはたらきかけ、署名などで要求していきましょう。
◆汚染水問題について
こちらが問題にしたのは、各地の原発の再稼働審査における重大事故対策の中
に、福島第一原発でいま問題になっているような汚染水事故を防止するような対
策が含まれていない問題と、現在福島第一原発で問題となっている地下水バイパ
スの問題でした。
重大事故対策については、規制庁PWR担当の布田氏が、汚染水対策として九電が
対策を示しているのは、ガス状の放射能を放水砲で叩き落とした際に出てくる汚
染水をシルトフェンスで防ぐというものだけであること、九電は、格納容器の健
全性は保たれると主張していること、そして、福島第一原発事故で発生している
ような汚染水事故の対策については、審査で検討もしておらず、新規制基準でも
要求していないと回答しました。
福島事故を踏まえて新規制基準が定められ、審査が行われているはずですが、そ
れが守られていないことが明確になりました。
地下水バイパスについては、汚染が昨年8月のタンク漏れに起因する可能性につ
いて問題提起をし、計画を中止するよう求めました。対応したエネ庁の柴田氏
は、関係は不明、今後も注視すると回答しました。
◆原子力防災・避難計画
規制庁の防災担当者は、交渉ははじめてとのことでしたが、それにしても答えら
れずに窮する場面が多すぎでした。
交渉で特に問題になったのが、避難途中で放射線計測と除染を行うスクリーニン
グでした。
規制庁の担当者は、スクリーニングの対処方針については、4月に行われた道府
県との連絡会で、自治体側の意向を受けて改定されたとの説明から入りました。
よく聞くとその資料は非公開だとのこと。即座に公開するように求めました。
スクリーニングの場所については、改定により、30キロ圏の近傍1~2キロの地
点とされたことが明らかになりました。しかし現実には、何百台もの車が押し寄
せる場所の確保が問題です。
川内原発で鹿児島県が昨年実施した避難訓練では、40キロ先の姶良市の高校が避
難先で、その避難先でスクリーニングが行われました。このやりかたではスク
リーニングの対処方針に反することになります。
また、スクリーニングでは、時間を短くするとの理由で、車を測って人を測った
ことにしたり、人を測る場合も代表者だけで済ませてしまおうとしています。こ
れは、避難者の安全確保という点でも、避難先への汚染拡大防止という点でも問
題があります。
代表者をどうやって選ぶのかも問題ですが、4月の道府県連絡会で、自治体側か
ら反発があったようで、地域の実情に合わせて行うことをさまたげないという文
言が入ったとのことでした。事実上代表を任命するやり方はやめにした反面地域
の実情にという形で、責任を自治体に押しつける問題も出てきました。
交渉には、佐賀から、そして玄海原発の避難元となる伊万里市の市議さん、そし
て一部が避難元、一部が避難先になる福岡市の市議さんが参加され、避難先にほ
ぼ同じ人口が避難してくることになっている過密避難の問題(しかもそれが避難
先に伝えられていない!)や風下へ避難することになっている件など、具体的な
問題が示されました。
規制庁は、国は援助をするだけで、所掌ではない、計画を立てるのは自治体だと
逃げ回っていました。では一体避難計画の実行性を誰が検証するのか。問い質し
ましたが回答はありませんでした。
引き続き情報を整理し、連絡をとりあいながら、避難の非現実性をリアルに明ら
かにしていきましょう。
阪上 武
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p】
電力経営―逆境を「変革元年」に
2014年5月4日(日)付
電力各社にとっては、旧来の思考法から脱し、先を読んで攻めていく力が問われる1年になりそうだ。
電力会社の今年3月期決算は6社が赤字だった。うち5社は3期連続だ。北海道電力と九州電力は日本政策投資銀行から資本支援を受けることにした。
福島第一原発の事故が起きた後も、東京電力以外の各社は基本的に、震災以前の路線を踏襲してきた。
だが、自民党が政権に戻っても、事態は電力会社の都合のいいようには動いていない。原発維持を打ち出した安倍政権も、安易な再稼働や電気料金の値上げは国民の反発を招くことを承知しているからだ。
ここにきて、新しい規制基準に見合うよう資金を投じても回収の見込みが立たない老朽化原発について、ようやく「廃炉」の選択肢を口にする会社が出始めた。
日本では今後、小さなトラブルでも原子炉を止めての原因究明と対策とが求められるだろう。もはや原発は「安くて安定的」な電源とは言えない。
社内でも原子力部門以外からは「限られた資源を最新鋭火力や送電網の増強に」との声があがり出している。原発にこだわりすぎると深い傷を負うとの危機感は、厳しい状況を考えれば自然の成り行きだ。
電力改革が与えるインパクトも大きい。経費をすべて電気料金から回収できる総括原価方式や地域独占が撤廃されれば、いま以上に多くの「変数」を見極めながら戦略を立てる力が不可欠になる。
兆しはすでに東電管内での動きに表れている。
自力で新たな発電所をつくれない東電は、他社との提携を進める。国内最大の電力消費地である首都圏が今後は草刈り場になる。
電力業界だけでなく、国内外のガス会社や鉄鋼メーカー、商社といった異業種も関心を寄せる。電力大手が従来の横並びに甘んじていると、致命的な出遅れになりかねない。
中部電力や中国電力は、それぞれ関係の深いガス会社や鉄鋼メーカーと組んで名乗りをあげる構えだ。原発依存率が高く、経営が苦しい関西電力がどう出るのか。注目が集まる中、悩ましさは人一倍だろう。
とはいえ、それらは他の産業が自由化やグローバル化の中で失敗や淘汰(とうた)を繰り返しながら経験してきた道である。
そんな当たり前の経営へ。逆境の14年度を、ぜひ「変革元年」にしてもらいたい。
==============================================================================