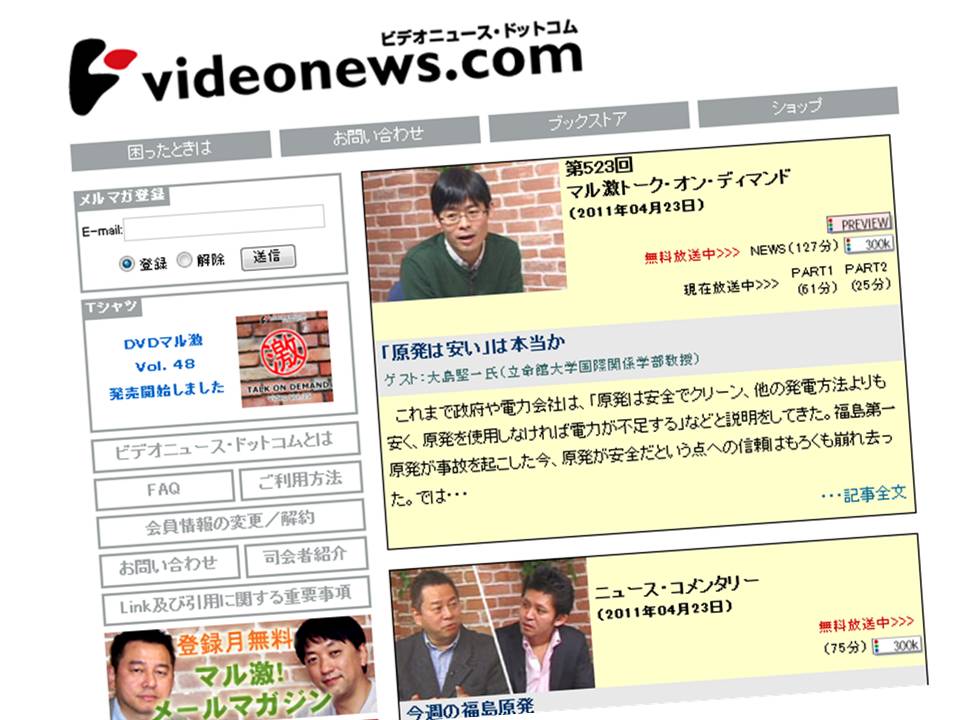

東京新聞の記事から(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011120201001767.html)。
財界と呼んでよいのかどうか分かりませんが、腐っていない金融機関もあります。
前から書こうと思っていた城南信金。THE JOURNALの記事(http://www.the-journal.jp/contents/jimbo/2011/07/post_120.html)とUSTREAMの映像資料(http://www.ustream.tv/recorded/17446156)もどうぞ。
「脱原発宣言」につづいて、東京電力との契約解除だそうです。素晴らしい! 筋の通った、骨のある金融機関だ。日本の救い。
================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011120201001767.html】
城南信金、東電の電気買いません 「脱原発」取り組み
2011年12月2日 19時03分
城南信用金庫(東京)は2日、本支店などで使用する電力について東京電力との契約を解除し、ガスや自然エネルギーの電力を販売する「エネット」(東京)から購入する、と発表した。来年1月から始める。城南信金は福島第1原発事故後、「脱原発」を宣言しており、今回の取り組みもその一環。
城南信金は、年間約900万キロワットの電力を使う全85店のうち77店でエネットに契約を変更する。契約の切り替えに伴い、年間の電気料金は従来の約2億円から1千万円減らせるという。8店舗はビルに入居しているなどの理由で、引き続き東電から供給を受ける。
(共同)
================================================================================
================================================================================
【http://www.the-journal.jp/contents/jimbo/2011/07/post_120.html】
信用金庫が脱原発宣言をすることの意味
マル激トーク・オン・ディマンド
第536回(2011年07月23日)
信用金庫が脱原発宣言をすることの意味
ゲスト:吉原毅氏(城南信用金庫理事長)
プレビュー
菅直人首相は震災発生から「脱原発宣言」までに4ヶ月あまりを要したが、震災の衝撃も覚めやらない4月1日に、堂々と脱原発宣言をやってのけた金融機関がある。日本初の脱原発金融機関として今や全国的に有名になった東京の城南信用金庫だ。同庫のホームページに掲載された宣言「原発に頼らない安心できる社会へ」は瞬く間にツイッターなどで広がり、同時期にウェブサイトに公開された吉原毅理事長のインタビューは8万回以上も再生された。
経済界では異例の脱原発宣言はなぜ行われたのだろうか。また、脱原発で城南信用金庫に続く金融機関はなぜ現れないのだろうか。
城南信用金庫は世田谷区や品川区など東京の城南地区を中心に地域金融を展開する信用金庫で、都内に50店舗、神奈川県に35店舗を持ち、店舗数、預貯金額ともに信金としては日本でトップクラスの規模を誇る。数々のユニークな取組みで金融界の異端児と評されることが多いが、3代目理事長の故・小原鐡五郎氏の教えである「裾野金融」「貸すも親切、貸さぬも親切」「カードは麻薬」など「小原鐡学」を社是に、目先の利益を追求せず、人と人とのつながりや地域貢献に主眼を置く、地道な経営でも知られる地域密着型の信用金庫だ。
なぜそのような地域の金融機関が、脱原発宣言などを行ったのかについて、吉原氏は原発事故の発生以後、誰も責任を取とろうとしない政府や企業の姿勢に強い違和感を持ったことをあげる。どんな企業でも事故が発生したら、謝り、責任をとるはずだが、原発については誰も責任をとらない。政府もマスコミの報道にも違和感を覚え、誰かが発言しなければならないと考えた結果が、この宣言だったという。
しかし、脱原発を宣言した以上、自らもそれを行動で表さなければなければならない。自分たちに何ができるかを考えた結果、原子力の占める発電量が3割なので、まずは自社の電力消費量を3割節電することを決めた。全店舗でLED照明を導入や冷暖房の設定温度の見直しなどを実施した結果、3割削減は十分可能だったと吉原氏は言う。
また、ボランティア休暇の導入や社員の被災地ボランティアのサポート、被災した地域の信金の内定取り消し者の採用なども積極的に行っている。
城南信金では同時に、消費者がソーラーパネルやLED照明、蓄電池など節電のための商品を購入する際の、低金利のローンなど、本業でも脱原発・節電を推進している。
しかし、城南信金のこのような動きをよそ目に、経団連に代表される日本の経済界は依然として原発推進の立場から抜け出ることができないのはなぜか。
吉原氏は、表では勇ましく原発推進を謳っている企業や企業人も、個人レベルでは原発が危険であることは十分にわかっているし、おそらく、できることなら原発はやめたいと思っているにちがいないと言う。しかし、大企業ほど地域独占の電力会社との関係は深く、株式や電力債などを通じた実利面でも、多くの企業が電力とは強い利害関係で結びついている。個人的な思いはあっても、経済的、心理的にそう簡単には原発から抜け出せない構造になっているというのだ。
とは言え、城南信用金庫も、事業として金融業を行っている業界トップクラスのれっきとした金融機関だ。損得勘定抜きで事業は成り立たないはずだ。目先の利益に目が眩みそうになった時、吉原氏は城南信用金庫の中興の祖、故小原鐵五郎氏の教えを改めて肝に銘じるという。小原哲学とは、目先の利益を追い求めるものは、最後には大きな損をするという教えだと、吉原氏は言う。小原氏の「貸すも親切、貸さぬも親切」の教えを守り、バブル期にゴルフ場開発や株式、投資信託など投機性の高いプロジェクトへの融資をあえて行わなかったことが、城南信金がバブル崩壊の痛手を大きく受けずに、今日の地位を気づけている要因になっていると吉原氏は胸を張る。
実際のところ、今後コミュニティバンクとしての信用金庫が担うべき役割は多い。あの悲惨な原発事故を受け、これからの電力供給は、これまでのような大手の電力会社に全面的に依存する中央依存型から、再生可能エネルギーなどを中心に、地域の比較的小規模な事業者や各家庭が担っていく地域分散型へのシフトが避けられない。この中央から地方分散へのシフトを支えていけるかどうかに、信用金庫の真価が問われることになるだろう。
吉原氏に、脱原発宣言の経緯やその影響、そしてその背後にある小原哲学などの理念と金融機関が追うべき社会的責任について聞いた。
<ゲスト プロフィール>
吉原毅(よしわらつよし)城南信用金庫理事長
1955年東京生まれ。77年慶応大学経済学部卒業。同年城南信用金庫入庫。企画課長、企画部長、副理事長などを経て2010年11月から現職。
投稿者: 神保哲生 日時: 2011年7月23日 23:23
================================================================================
================================================================================
【http://www.ustream.tv/recorded/17446156、2:45あたり吉原氏】
録画日時 : 2011/09/23 12:58 JST
2011年9月23日シンポジウム「脱原発社会は可能
2011年9月23日シンポジウム「脱原発社会は可能だ!」
シンポジウム「脱原発社会は可能だ!」
================================================================================











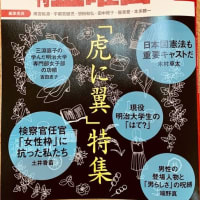











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます