

ムダ首相が反原発連合と面談した件についてのasahi.comの社説(http://www.asahi.com/paper/editorial20120823.html)と東京新聞の社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012082302000121.html)。国民が示した民意についてのasahi.comと東京新聞の記事(http://www.asahi.com/business/update/0822/TKY201208220162.html?ref=reca、http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012082390070419.html)、さらに、東京新聞の社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012082402000119.html)。
東京新聞の記事『再稼働平行線 脱原発団体と首相面会』、(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012082302000114.html)によると、
「首相と反原発連合との面会を受け、藤村修官房長官は
記者会見で「一つの連合体との話はこれで終わっている」と、
今後の面会予定はないとの考えを示した」
・・・そうなので、要は形だけ実施して、脱原発なんてお題目だけで、やる気など全くないことを表明し、ご意見拝聴の場を設けたという既成事実だけを作りたかったわけ。
「首相は反原発連合との面会後、日本商工会議所の岡村正会頭とも
官邸で会談。原発再稼働の必要性などについて意見交換した」
・・・そうなので、要は、財界や大企業の方しか向いていない。
「反原発連合側は「承服しかねる。福島の事故も収束していない。
安全を保てない政府を国民は信用していない」と反発。
首相に官邸前での抗議活動の参加者に直接、説明をすることを求めた」
・・・そうだが、抗議の声も耳に入らず、官邸でお食事会でも開いているようなムダ首相ですから、しょせん無理なお話でしょう。
消極派にしろ、即時廃炉の積極派にしろ多くの人々の「原発0%」の決意は既に見えているのではないか。私自身は、即座に廃炉にすべきだと思う。また、核燃サイクルの幻想もすぐさま捨て去るべきだ。原発関連の事業は、福島第一原発4号炉の使用済み燃料プールに集中すべきだし、今後、10,0000年とも、100,0000年ともいわれる核廃棄物・死の灰の管理に集中すべきだと思う。
『●核燃サイクル: 核燃料再生率に根拠無し、15%どころか1%?』
『●核燃サイクルという幻想、推進ありき』
『●核燃サイクルという幻想に、まさに金をドブに湯水の如く』
『●玄海原発プルサーマル賛成派質問者8人中7人が仕込みだった!』
『●プルサーマルの無意味さ再び: 核燃サイクルという幻想の破綻』
『●原子力ムラは土台から腐ってる』
================================================================================
【http://www.asahi.com/paper/editorial20120823.html】
2012年8月23日(木)付
首相との対話―開かれた政治の一歩に
両者の溝は埋まらなかった。それでも意義は小さくない。
首相官邸前で「脱原発」を求める抗議行動の主催者らが、きのう官邸内に招かれ、野田首相に会って抗議した。
経済団体や労働組合に属さぬ「組織されない市民」が首相に直接訴えるのは異例だ。これまでの政治の意思決定の仕方や、政治文化を変える可能性をはらんでいる。評価したい。
20分の予定は30分に延びた。だが、中身は平行線だった。
主催者の市民らの要求は(1)大飯原発の再稼働中止(2)全原発を再稼働させない(3)全原発廃炉への政策転換(4)原子力規制委員会の人事案の白紙撤回、だ。
主催者らは口々に訴えた。原発がとまっても電力は足りている。大飯には活断層の存在が疑われ、危険だ……。
首相は、中長期的に原発依存を改めるとの政府方針を説明したが、それ以上の歩み寄りはなかった。「ほとんど承服しかねる」が、主催者らの返答だ。
溝は深かった。
それにしても、もっと時間をとり、首相の口から説明を尽くすべきだった。そうすれば、意義はより大きくなった。
むろん、主催者たちは民意を広く代表するわけではない。抗議行動の場を提供しているが、参加者の代表とも言いがたい。
しかし、面会の模様はネットで生中継され、数多くの市民がみた。それは、首相と市民とをつなぐ新たな回路の役割を果たしただろう。
市民の抗議は、再稼働だけに向けられているわけではない。
それを決めた意思決定の仕組みと、民意を代表すると想定されている間接民主主義の機能不全への異議申し立てだ。
ものごとを政治家と既得権を持つ組織の代表や一部の専門家で決め、ふつうの市民はかかわりにくいのが、従来の「ムラ社会」型の意思決定の仕組みだ。
典型が電力であり、「原子力ムラ」による政策決定だ。
電力会社の利益が優先され、自分たちの安全が軽んじられるのではないか……。
不信はそこに根ざしている。
組織されない市民の声を、どう政策決定に組み込むか。エネルギー政策の意見を聞く討論型世論調査は試みのひとつだが、ほかにも様々な回路を開かなければならない。
今回のような面会も、一回で終わらせず、次の機会を持つべきだ。今度は抗議だけに終わらせず、胸襟を開いた対話と呼べるものにしよう。
これを、開かれた政治への一歩とすべきである。
================================================================================
================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012082302000121.html】
【社説】
市民団体と面会 反原発の声受け止めよ
2012年8月23日
野田佳彦首相が、毎金曜日夕方に官邸前での反原発デモを呼び掛けている「首都圏反原発連合」代表らと面会した。首相は反原発を訴える国民の「声」を受け止め、原発稼働の停止を決断すべきだ。
首相が官邸で市民団体代表らと会うのは異例だという。約三十分で打ち切られ、主張は平行線に終わったが、首相が市民団体の意見を直接聴く場を持とうとしたことは率直に評価したい。その上で双方に注文がある。
原発依存からの速やかな脱却はもはや国民の「声」である。
共同通信社による直近の全国電話世論調査によると、二〇三〇年の原発比率「0%」を求める意見は最も多い42%と半数に迫る。
政府の「討論型世論調査」でも三〇年の原発比率で「0%」を評価する人が46%と最も多く、この数字は討論を経て増えていったことが重要だ。「原発ゼロ」は原発事故後の一時の感情や、短慮や浅慮では決してないことを意味する。
しかし、首相は明確な安全基準を欠いたまま、関西電力大飯原発3、4号機を再稼働させた。「国民の生活を守るため」という詭弁(きべん)が、国民を逆に不安にさせている矛盾になぜ気付かないのか。
毎週末、多くの人が官邸前の抗議行動に足を運ぶのも、国民との約束や思いが政治に反映されず、代議制民主主義が機能不全に陥っているという危機感からだろう。
原発なしでも節電など国民の努力で暑い夏を乗り切れそうなことは、今夏が証明している。
首相は国民の声を真摯(しんし)に受け止め、再稼働させた大飯原発を停止させ、今後予定するほかの原発の再稼働も取りやめる。持続可能なエネルギー源の開発に力を注ぐ。消費税増税に費やすような政治的情熱はむしろ、エネルギー構造の改革にこそ振り向けるべきだ。
市民団体の側にとっては、首相との面会はゴールではなく、通過点の一つにすぎない。
原子力規制委員会の委員長と委員の人事案の撤回を求められた首相は「最終的には国会に判断いただく」と述べた。同意人事の可否を判断するのはもちろん、首相を選ぶのも、原発政策に関する法律をつくるのも国会だ。
脱原発を揺るぎないものにするには官邸前のエネルギーを実際の投票行動につなげる必要がある。
脱原発に無理解だったり、原発維持を画策しようとする経済界や官僚になびくような政党や議員が選ばれては、せっかくの民意の広がりも報われない。
================================================================================
================================================================================
【http://www.asahi.com/business/update/0822/TKY201208220162.html?ref=reca】
2012年8月22日14時50分
「原発0%」支持、伸びる 討論型世論調査
政府がエネルギー政策の意見を聞いた討論型世論調査の結果が22日、まとまった。2030年の電力に占める原発割合を「0%」「15%」「20~25%」とする三つの選択肢のうち、0%支持が討論や学習を経て32.6%から46.7%に増え、最も多かった。エネルギーには「安全の確保」を重視する人が増えたためだ。
15%支持は16.8%から15.4%に減り、20~25%は13.0%のまま横ばいだった。政府は「国民的議論」を経てエネルギー政策を決めるとして討論型世論調査をとり入れており、0%支持の増加は政策決定に大きな影響を与える。
調査は、三つの選択肢について「強く反対(0)」~「強く賛成(10)」の11段階で支持の度合いを聞き、最初の電話調査(1回目)、討論会前(2回目)、討論会後(3回目)の調査でどのように意識が変わったかを調べた。
・・・・・・。
================================================================================
================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012082390070419.html】
原発ゼロ 民意鮮明 意見公募経過89% 意見聴取会81%
2012年8月23日 07時04分
二〇三〇年時点の原発依存度をめぐる国民的議論の結果を検証する政府の第一回専門家会合が二十二日開かれ、パブリックコメント(意見公募)の集計経過や、意見聴取会のアンケート結果が報告された。それぞれ89・6%、81%が原発ゼロ案に賛成。国民同士で議論して意識の変化を調査する討論型世論調査(DP)は事前に32・6%だった原発ゼロ案が最終的には46・7%に拡大した。いずれも原発15%案や20~25%案を圧倒しており、「原発ゼロ」の声を無視できない状況に政府を追い込んでいる。 (山口哲人)
政府が今後のエネルギー・環境戦略に反映すると位置付けるのは、意見公募や全国十一都市で開かれた意見聴取会のほか、DP、報道機関による世論調査など。原発ゼロを願う民意の大きなうねりは明確なデータの裏付けを土台にして、揺るぎないものとなった格好だ。
意見公募では、約八万九千件の意見が寄せられ、うち約七千件の分析が終了。81%が即時の原発ゼロを求めたほか、8・6%も段階的な原発ゼロを訴えた。
意見聴取会で来場者約千二百人を対象に行ったアンケートでは、「その他」意見を除くと原発ゼロ案支持が81%。会場での発言を希望した人への調査でも68%が原発ゼロ案を選択した。
DPでも、電話調査時には32・6%だった原発ゼロ案が、議論などを経て最終的には46・7%に伸びた。15%案を最も評価したのは15・4%、20~25%案は13%にとどまった。
この日の会合では、各種調査による意見や情報をどう解釈するかを議論した。田中愛治・早稲田大教授が、意見公募について「強い意見を持つ人が出すので、(比率は)偏る可能性が高い。世論調査が(本当の)国民の縮図なのでは」と指摘する場面があった。
だが、小幡純子・上智大法科大学院教授は「意見公募は世論調査とは違って誰でも意見を出せ、国民参加が保証されている」と反論。
今後、二十七日の専門家会合を経て、九月ごろに開くエネルギー・環境会議で政策を決定する見通しだ。鮮明になった民意を政府がエネルギー政策にどう反映させるのか。国民は厳しい目で見つめている。
(東京新聞)
================================================================================
================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012082402000119.html】
【社説】
原発ゼロ 熟慮の民意が表れた
2012年8月24日
二〇三〇年の原発比率をめぐる「国民的議論」の結果が出た。負担増を受け入れても安全を優先させたい「原発ゼロ」の民意が読み取れる。国民の覚悟の選択を、政府はただちに尊重すべきだ。
これで「原発ゼロ」の声は無視できなくなったろう。野田政権が今後のエネルギー・環境戦略に反映させるとした国民的議論の結果が出そろった。意見公募(パブリックコメント)と、全国十一都市で開いた意見聴取会、さらに討論型世論調査である。
これらの「国民的議論」は、三〇年の原発比率について「0%」「15%」「20~25%」の三つを選択肢とした。意見公募と意見聴取会の会場アンケートは、ともに八割以上が「0%」を支持した。
とりわけ注目すべきは、国民同士の議論や専門家の話を聞き、その前後で意見が変化したかを調べる「討論型世論調査」の結果である。最多は「0%」支持で、討論前の32%から討論後は46%に大きく増えたのが特徴だ。
事前の予想では、専門家の話を聞けば「原発ゼロ」支持は減るとの見方があったが、結果は逆だった。このことは「原発ゼロ」の選択が一時の感情などではなく、賛否多様な意見を踏まえ熟慮した末の決定を意味するものだろう。
しかも、選択する上で何を最も重視するかとの問いには、「安全の確保」が80%強を占めた。原発維持派の大きな論拠である「電力の安定供給」(15%)や「発電費用」(2%)を圧倒したのは、電気料金が高くなったり省エネなど不便な生活をも引き受ける国民の覚悟の表れである。
経済界は、脱原発では電力不足やそれに伴う企業の海外移転、失業増など経済が停滞すると主張している。これは、原発で稼いできた東芝、日立製作所や東京電力が中枢を占めてきた経団連の言い分である。枝野幸男経済産業相が「(原子力)依存度低下は経済のマイナスにつながらない」と反論したように、考慮すべき材料だが鵜呑(うの)みにすることはできない。
低成長が定着し、大量生産・大量消費の時代はとうに過ぎ去り、国民の多くは省資源・省エネの暮らしを志向している。討論型世論調査でも、懸念される電力不足に対し、参加者の七割が「国民、産業とも省エネ余地がある」と、エネルギーを減らすライフスタイルへの転換を提案した。
国民の重い選択を考えれば、政府が九月までに下す選択は「原発ゼロ」しかない。
================================================================================













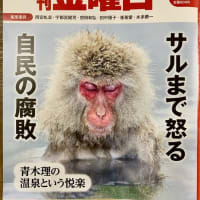

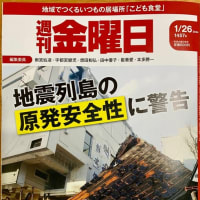






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます