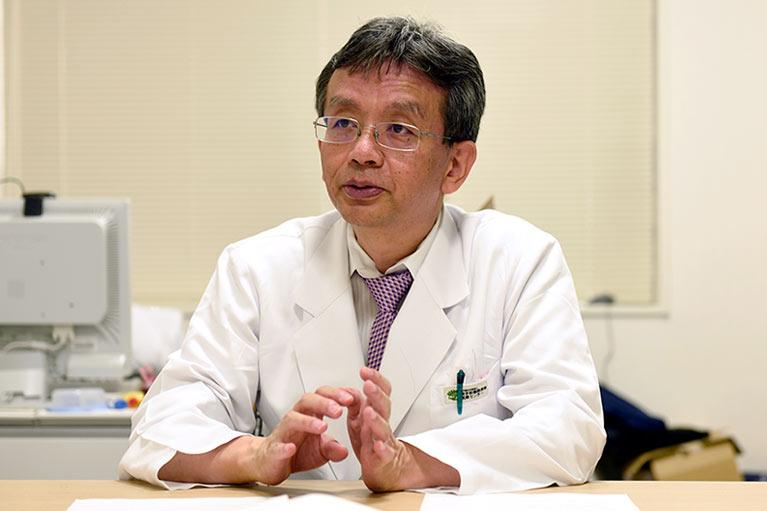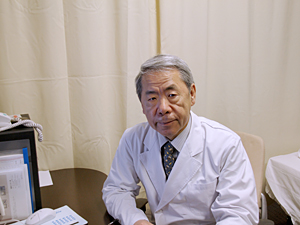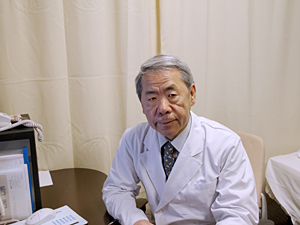8/8(水) 16:56 夕刊フジ
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
荒木厚内科統括部長
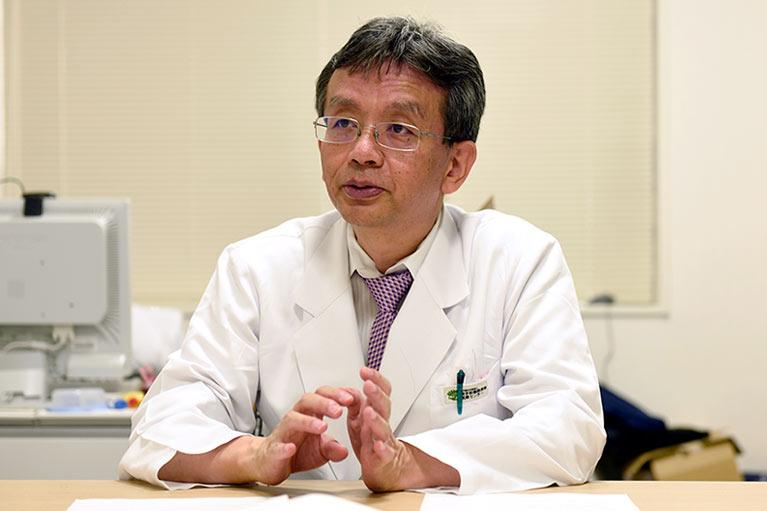
【健康寿命UP術】
国内で予備群も含めて約2000万人と推計される糖尿病。高血糖状態が続くことで血管などに悪影響を及ぼし、腎不全や心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる合併症であることはよく知られている。近年、高齢者の「フレイル」に関係が深いことも明らかになってきた。フレイルとは、加齢によって運動機能や認知機能などの予備能力が低下し、要介護状態や死亡に至りやすい状態のことだ。
「血糖値検査のヘモグロビンA1c(HbA1c/正常値は6%未満)の値が8%を超えると、フレイルになりやすく転倒や骨折による入院患者が増加することは、米国の疫学調査で報告されています。高血糖状態を放置することが、健康寿命を縮めるのです」
こう話すのは、東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科の荒木厚内科統括部長。長年、高齢者の糖尿病の診療と研究を行い、2015年には同センター受診者向けにフレイル外来も開設した。
糖尿病とフレイルの関係については、世界的に研究が進んでいる。英国の疫学研究報告によれば、糖尿病の人はそうでない人と比べて死亡リスクは1・4倍、フレイルを合併していると2・7倍にも跳ね上がった。
「フレイルは、中年期でも起こります。内臓に脂肪が溜まった肥満の人は、内臓脂肪によって糖尿病になりやすく、筋肉量が低下することでさらに糖尿病の後押しをします。筋肉量が低下したサルコペニアと呼ばれる状態を招き、身体活動量が減ることでフレイルにつながるのです」
内臓脂肪が多く筋肉量が少ないと、血糖値をコントロールするインスリン(ホルモンの一種)の効きが悪くなり、分泌量も減ることで高血糖につながる。インスリンの効きが悪いと、筋肉の細胞は必要なタンパク質を合成できないので、筋肉量は落ちていく。肥満→糖尿病→サルコペニア→フレイル→糖尿病の悪化。この悪循環は断ち切らなければならない。
「生活習慣病による糖尿病は、医療機関でご自身の状態を把握した上で、食生活の改善と運動療法が不可欠です。また、ご高齢の方は、フレイルチェック(別項)も行い、要介護状態に至らないように医療機関などに相談していただきたいと思います」
国内の疫学調査では、糖尿病の人は認知症の発症率が、そうでない人と比べて高いと報告されている。高血糖を改善することは、心筋梗塞や脳卒中の死亡リスクを下げると同時に、フレイルや認知症予防にもつながる。
「フレイルは、単に身体的な機能の低下にとどまりません。認知機能の低下や鬱など、精神的な機能も低下させます。心身機能が低下することで社会活動も損なわれ、総合的な機能低下につながるのです。それを防ぎ、改善することを心掛けていただきたい」
健康寿命を縮める高血糖予防では、食べ過ぎない、食事を偏らせない、適度な運動習慣も忘れずに。(安達純子)
■「フレイル」をチェックしよう
□ダイエットをしていないのに体重が減った
□疲れやすい
□握力が低下した
□体力がなく動くのがおっくうと感じる
□歩行速度が遅くなった
※3つ以上当てはまると「フレイル」の可能性が大。老年病科を扱う医療機関へ相談を