新司法試験の初期の頃は、権利の性質の多様性を意識した問題が主流でしたが、徐々に次の段階とも言うべき、「制約の程度」にも配慮が必要となってきています。特に、「直接的か間接的か」というファクターは受験生泣かせでしょう。
直接・間接の違いは、簡単に言えば、何らかの規制の目的・手段がその権利の制約そのものに向けられているか、そうではなく、他の目的で規制したところ、たまたまその権利が制約されるに過ぎないような場合なのか、という違いです。
例えば、駅前等で立看板を禁止した場合、その規制の目的は「歩く人の安全への配慮」だとします。この場合、立看板的なものがすべて規制対象になります。何の表現媒体性のないものから、政治集会のビラが貼られたものまで全部です。規制を実行すると、「場合によっては」、ビラが貼られた立看板も禁止ということになります(この限りでは表現の制約になります)。
しかしそれは「たまたま」であり、すべてのケースで「一般的に」表現が制限されるわけではありません。これが、間接的・付随的制約に過ぎない、という典型パターンです。確かに、立て看板的なものは千差万別なので、表現行為をなんらかの規制目的で一般的に制約する場面ではないと言えますね。しかし、これは事実上「直接的な制約だ」という人もいます。どちらが正解かというのはありませんが(この点も重要です)、直接的制約と言うためには、ちょっと説明がいります。例えば、駅前の立看板は事実上、ほとんどすべてが表現媒体性があるものである、などの説明がいるということです。当然に表現への制約が目的となっている、というのはやや厳しいからです。
立川自衛隊官舎立ち入り事件も同様で、住居侵入罪は、たまたま「あのケースでは」表現行為を制約することになるだけ、と言わざるを得ません。(そもそも住居侵入罪は一般的には表現行為とは無関係に発動されるものなので(表現への違憲的制約を理由とした法令違憲は無理筋です)、制約がどうこう言う前に、やはり適用違憲で勝負するのがいい事例ですね(違法性阻却パターンがいいかな)。)
君が代伴奏事件は「思想良心への制約はない」とされ、起立斉唱事件では「直接的な制約はないが、間接的な制約はある」とされた理由を、もう一度よく考えながら判例を読むと勉強になります。何度も言いますが、正解はありません。判例がそれぞれの事件で「そう判断したロジックの違い」を理解することが大切です。












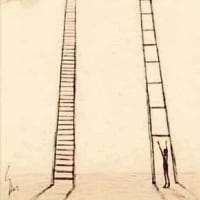

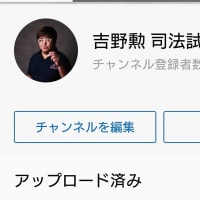
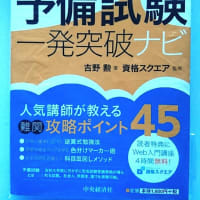

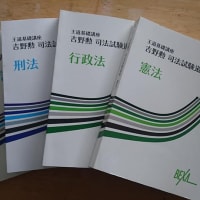







きちんと読めるようになりました。