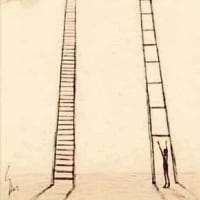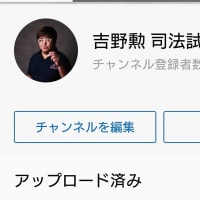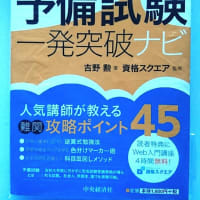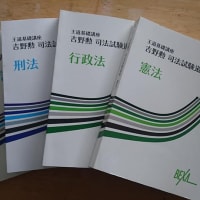0.今から始めよう司法試験!
①25年6月開始
②26年7月短答合格目標
➂27年7月短答合格
④27年9月論文合格目標
*今から始めればこのタイムラインをベースに受験計画を立てられる。
・第1目標:「26年短答合格」
・第2目標:「26年論文合格」or「26年論文上位不合格」
・第3目標:「27年論文合格」
*1年目は手を広げない
*「暗記の時間」を意識的に取る
・「暗記の時間」には、「覚える時間」と「思い出す時間」がある
1.演習ベース主義の罠
最大のリスク
→「何ができない原因なのか」が分かりにくくなる。
→「復習の仕方」の個人差が大きく出てしまう
2.シン・王道基礎講座で「不安」を無くす
(1)網羅的な知識
・知識の穴を無くせる
→ 論文段階で、知識不足が原因なのか、論文対策固有のスキルに原因があるのかの区別がつかない人が沢山出て来る。間違いなく「受験期間が長期化」する。
・「判例だけ知ってる受験生」からの脱却
→ 令和時代の司法試験委員の揺さぶりに耐えられる。
*CBT時代による「大きな変化」に「対応できる講座」を受講すべき
(2)「論文突破に必要な思考力」を身につけることができる
・論文思考力は「論文段階」で身につけるものではない!「基礎段階」から身につけるべきもの。普通の入門講座では「論文の壁」にぶち当たる。
<司法試験で求められる「法令解釈能力」とは?>
水道法第十五条一項「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない」。
Q「正当な理由」とは何か?
(この法律の目的)
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
(責務)
第二条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。
第二条の二
4 水道事業者等は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければならない
第六条 水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 水道事業は、原則として市町村が経営する
その他、「水道の基盤の強化」に関する規定が多数ある。
答え「水道法15条1項にいう『正当の理由』とは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水契約の締結を拒まざるを得ない理由を指す」(最判平成11年1月21日(福岡県志免町給水拒否事件)
最決平成元年11月8日(武蔵野市給水拒否刑事事件)
事案:「東京都武蔵野市では、マンション建設に当たり指導要綱を制定して、マンション事業者がこれに従わない場合には市の水道を供給しない旨を定めていた。建設業者Xは反対住民との話合いを進めてきたが、全員の同意を得ることは困難と判断し、同意を得る努力を打ち切り、寄付願も取下げることをYに通知した。Xは、Yに給水契約の申込をしたが、指導要綱に従っていないとしてYはこれを拒否した。そこで、市長は水道法15条1項違反の罪に問われた」。
→ 「正当な理由」なし
最判平成11年1月21日(福岡県志免町給水拒否事件)
事案:「志免町(Y)においてマンションを建設している不動産会社Xは、Yに対し、水道法15条に基づき給水の申込みをした。しかしYは、本件マンションが志免町水道事業給水規則に規定されている「開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるもの」又は「共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合は全戸」に該当するとして、給水契約の締結を拒否した」。
→ 「正当な理由」あり
(3)重要判例を徹底的に学べる
・事実関係・法令解釈の仕方・規範・当てはめ・裏話
(4)「事実の評価」の仕方を学べる
・普通の入門講座では扱わないことが多い
(5)「具体例」が豊富
・学んだことを具体例を通じて自分で追思考ができる
(6)ベテラン講師から学べる安心感
3.CBT新時代が幕を開ける
・キーボード入力に慣れる
・デジタル六法に慣れる