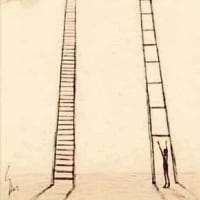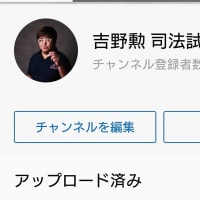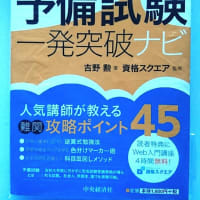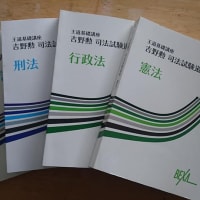0.大前提
「不合格者」の属性は多様であること。
→ 「自分の立ち位置」を冷静に見極める必要性。
論文500位も「不合格者」
論文2500位も「不合格者」
短答落ち(160点)も「不合格者」
短答落ち(100点)も「不合格者」
∴「自分はいま何合目あたりにいるのか」を認知する。
1.「不合格答案」とは?
=「説明不足の答案」である。
「説明不足」とは?
(1)問題提起部分
何故その点につき論じるのかの「説明」がいる。
= 今から取ろうとする立場が、「形式論的には当然ではない」ときに問題になる。
→「条文がなく問題となる」と言うのも、条文がない以上、「当然にそのような立場」をと れないので類推適用の可否の話になっていく。
(2)規範定立部分
内容的に不正確 → 読み手に対し「法的な説得力」を失う
例:著名な判例があるのに違う規範を使う
→ 何故?となる。
→ なお、違う立場を取ること自体は構わないが、違う立場を取る理由の説明がいる(判例批判+自説の理由付け)
*特に民訴のような理論系科目では致命的
*本当は刑法も同様。
例:未遂の教唆の可罰性は、行為無価値か結果無価値か、共犯の処罰根拠論(惹起説3種の うちどれを取るか)で変わりうる。
(2)’ 理由を何処まで書くか問題
「理由(=主旨)」から例外を認めたい場合などにはその対応する理由の記載は不可欠。
例:民法540条
解除の意思表示には条件を付けられない → 相手方の地位を不安定にするから(理由)
不安定にしなければよい(理由からの論証) → 停止条件付解除は認められる(判例)
(2)’第二次規範何処まで書くか問題
書くのが理想だが、実際には難しい場合も(=原則書かなくても良い)
但し、「書かなくて良い」という事と「覚えなくて良い」という事は同義ではない。
(3)当てはめ部分(=評価)
「事実の評価」とは何か?
=「理由を説明する部分」
=規範と事実との「橋渡し」部分
例1:Xへの所有権・登記の移転は、所有者でなければできない処分であり、不法領
得の意思の実現といえ実質的に権限を逸脱する行為であるから、Aには横領行為が
あるといえる。
「Xへの所有権・登記の移転」=生の事実
「横領した」=結論
「所有権登記の移転の事実」から何故「不法領得の意思を実現した(=横領行為)」と言えるのかの「説明」がいる。
「所有者でなければできない処分行為を勝手にやったと言えるから」=説明=評価
例2:「被告人には同種前科があるので、本件行為が「欺罔行為」に当たることの認識はあったと言える」。
→ 説明が抜けている。
「被告人には同種前科がある」 →「生の事実」
「欺罔行為」に当たることの認識はあったと言える」 →「結論」
両者には隔たりがある。同種の前科があれば、何故今回も欺罔行為との認識があると言えるのかの「説明」が抜けているからである。
*「被告人は同種類似行為が詐欺として処罰対象となることは前回の裁判結果で分かって いた」→「起訴された事実についても詐欺として違法な行為であることを認識していたであろう」という推認がなされている
「生の事実」→「評価(=説明部分)」→「結論」
*余談だが、「事実の評価」が苦手な人は、おそらく、刑訴における証拠の使い方も苦手だと思われる。ある証拠からどのようにすれば犯罪事実を立証できるかは、正に「使い方の説明」そのものだからである。
2.・スピーディーに問題文を読みきり、事案を把握する能力
→ 「文字情報のビジュアル化能力」
= 自分で図を描く作業をする。
・「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を整理する(生の事実)
「要求」→「法的な効力」→「法律構成を考える」
ex「この話はなかった事にする」=「契約をなしにしたい」=「解除、取消し、無効」
・「問題文の生の事実」から「行為」を切り出す→法的な評価を加える。
→ 「論点抽出」は、前提として「主要論点が頭に入っていないと駄目」。
→ 論点は条文の文言との関係性が強いので、何条の問題かも意識する。
→ 「こういう制度の問題かな」→「条文見てもない」→「結論の座りが悪い」→「論点 化(類推適用、規範を立てる」、と言うパターンもある。
→ 結論を出すうえで「判断基準」を示さないといけない=「判例の規範の問題」
3.まとめ
インプットレベルの問題
→ 論点抽出能力に難
アウトプットレベルの問題
→ 規範部分の論証力に難
重要な事実の抽出と割り振りに難
事実の評価部分に難
*シン・王道 総合100