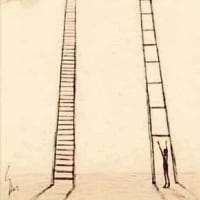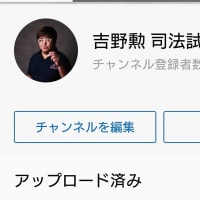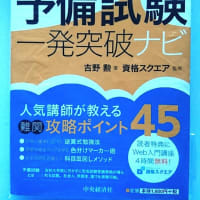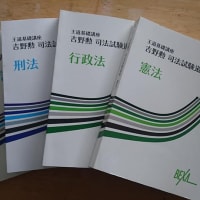X,Y1から拳銃強取を企てる。Y1殺害の可能性を認識しつつ,手製装薬銃発射。Y1胸部貫通銃創を負う。Y1を貫通した鋲が,偶然30メートル前方を歩行中のY2に命中し,Y2死亡。検察官,XをY1Y2両名に対する強盗殺人未遂罪で起訴。
Y2に何罪が成立するか。
この判例は,いわゆる方法の錯誤における法定的符合説(数故意説)を取ったことで有名な判例である。知らない人はいないと思われる。しかし,何罪が成立するのか,という観点から見ると意外に答案上処理しにくいケースである事がよく分かる。
<判例のY2に関する罪の処理の仕方>
|
Y2に強盗殺人未遂を如何にして成立させるか。 まずは,Y2に対する殺人未遂罪の成否を検討する。 → Y2に対しては「強取」行為を行っているわけではないので,Y2との関係でいきなり「強盗殺 人未遂が成立するか問題となる」という問題提起の仕方はかなり違和感がある。 → 殺人未遂罪が成立するかどうか,というところで,例の判断(法定的符合説,数故意説)をしている。この部分だけが独立して有名になっている。 殺人未遂を成立させた後,どう強盗殺人未遂罪に切り替えるか。 → 本件殺人未遂行為は,Y1に対する強盗の手段としての鋲発射行為でもあるから,殺人未遂罪と強盗の結合犯として,強盗殺人未遂罪が成立する,というロジックを採った。 |
注意しよう!
刑法の問題は,最終的には「何罪が成立するか」に尽きる。しかし,結合犯等の場合,答案上は非常に書きにくいケースが出てくることがあるので注意したい。結果的加重犯の共犯事例など事前に処理手順を身につけていないと非常に書きにくいのが良い例である。行為をばらして見る,という視点は知っておいて良いだろう(結果的加重犯なら基本犯部分と加重部分,結合犯なら2つに分けてみる等)。
<応用ケース>
|
Aを殺害する意図で発砲したところ,弾丸がAに命中しないで,傍らにいたBに命中し,Bが死亡した場合,Bに対する殺人罪を認めるが,結果の発生しなかったAに対して殺人未遂罪を認めるのかどうかにつき,実は判例はハッキリしていない(判例の事案では,何れの場合も,結果の発生していないAに対する関係では起訴されていないため,判断の対象となっていないのである) |
法定的符合説は,行為者の意図が同一構成要件内で現実に発生した事実の上に故意の実現があったとするものとする論理であるから,Aに結果が発生しなかった場合には,Bに対する故意犯の一罪の成立を認めることで評価が尽くされ,Aに対する故意犯の既遂を認めないからといって,論理の一貫性を欠くという事にはならないであろう。(実務上、検察官がAに対する殺人未遂罪で起訴しない処理が一般)