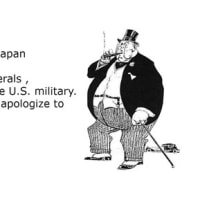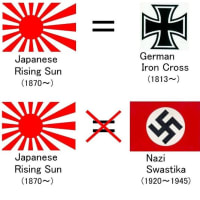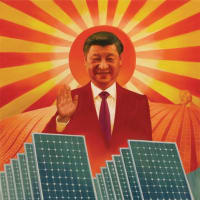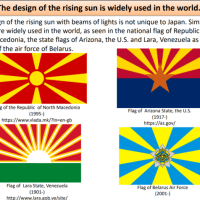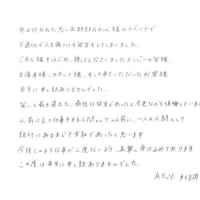おやおや、いまさら基礎付けかよ、最近にしちゃあ、珍しいなあ、と思って読んだ本道徳を基礎づける―孟子vs.カント、ルソー、ニーチェ (講談社現代新書) (新書)
フランソワ ジュリアン
著者によると、道徳の基礎ってのは、他人の権利を侵害するな、といった道徳の原理原則ではなく、「徳を勧める理由や、それが義務である根拠」である。(29ページ)
で、昔は、神様や、人間性の本質がそれとして受け入れられてきたが近代になってそうもいかなくなった。神様が言ったからと言って、それを受け入れる必然性はないし、人間性の本質といっても仮にそうしたものがあったとして、だからと言ってそうべき理由はない。
で、カントもそうしたことを試みたが、目的の王国と感覚の世界との二元論になって、要するに神の代わりに超越的世界を置き換えたにすぎない。
で、著者は何がしたいかというと、道徳の基礎付けをしたいというようり、孟子などの中国の思想と西洋の思想を比較することによって、そうした知的枠組み自体を揺るがしたい、というわけだ。まあ、ここいら、現代の、特にフランスの思想家っぽいね。
で、興味のあるところを拾っていくと、孟子やルソーなど、道徳の端緒として「憐れみ」というか、人の不憫な姿をみて忍びがたく思う気持ちを取り上げているが、ルソーなどは、それを個人主義に還元してしまって、憐れみに基づく行動というのも、結局は自分の為にやっているだけなんだ、という風に解釈したのに対して、孟子のほうっていうと、実体としての個人ではなく、人と人との関係を基底においた。
ここいらは面白くて、西洋流だとどうしても個人を基体におくが、東洋流では、主客未分の「それ」を見る傾向がある。
で、次にいくと、西洋流は道徳的責任として「違うようにも行為することができた」というところ、その意志に責任を求めていく。要するに神様の命令に、「いやだよおお」と言っちゃった、その罪を背負うというのが原型になってくる。
ところが、孟子などの東洋流は、植物の成長がモデルになる。つまり、ある傾向の可能性を持った種が、環境の違いによってよくも悪くも成長する。だから、そうした素質をはぐくみ、環境を整えると言うほうに力点が置かれる。で、その概念装置の中に西洋流の意志の自由という概念が、幸か不幸か欠如していたから、それにまつわる難題に直面することを逃れた。
じゃあ、道徳の端緒である、憐れみや忍びがたい気持ちに誠実であれば幸福になれるかっていうと、それが天ーーと言っても超越的ではなく、内在的なーー通じており、それこそが道徳の基礎なのだ、ということらしい。
もちろん、基礎づけに成功しているわけはない。著者の意図がむしろ、現代の西洋人の固定観念や概念枠組みを揺さぶろう、ということなのだから、これはこれでいい。
全般として、西洋人にありがちな西洋の枠組みから東洋をとらえるといった陥穽におちいることなく、まじめに中国思想ととりくんだおもしろい作品だと思う。翻訳もこなれて読みやすい。
フランソワ ジュリアン
著者によると、道徳の基礎ってのは、他人の権利を侵害するな、といった道徳の原理原則ではなく、「徳を勧める理由や、それが義務である根拠」である。(29ページ)
で、昔は、神様や、人間性の本質がそれとして受け入れられてきたが近代になってそうもいかなくなった。神様が言ったからと言って、それを受け入れる必然性はないし、人間性の本質といっても仮にそうしたものがあったとして、だからと言ってそうべき理由はない。
で、カントもそうしたことを試みたが、目的の王国と感覚の世界との二元論になって、要するに神の代わりに超越的世界を置き換えたにすぎない。
で、著者は何がしたいかというと、道徳の基礎付けをしたいというようり、孟子などの中国の思想と西洋の思想を比較することによって、そうした知的枠組み自体を揺るがしたい、というわけだ。まあ、ここいら、現代の、特にフランスの思想家っぽいね。
で、興味のあるところを拾っていくと、孟子やルソーなど、道徳の端緒として「憐れみ」というか、人の不憫な姿をみて忍びがたく思う気持ちを取り上げているが、ルソーなどは、それを個人主義に還元してしまって、憐れみに基づく行動というのも、結局は自分の為にやっているだけなんだ、という風に解釈したのに対して、孟子のほうっていうと、実体としての個人ではなく、人と人との関係を基底においた。
ここいらは面白くて、西洋流だとどうしても個人を基体におくが、東洋流では、主客未分の「それ」を見る傾向がある。
で、次にいくと、西洋流は道徳的責任として「違うようにも行為することができた」というところ、その意志に責任を求めていく。要するに神様の命令に、「いやだよおお」と言っちゃった、その罪を背負うというのが原型になってくる。
ところが、孟子などの東洋流は、植物の成長がモデルになる。つまり、ある傾向の可能性を持った種が、環境の違いによってよくも悪くも成長する。だから、そうした素質をはぐくみ、環境を整えると言うほうに力点が置かれる。で、その概念装置の中に西洋流の意志の自由という概念が、幸か不幸か欠如していたから、それにまつわる難題に直面することを逃れた。
じゃあ、道徳の端緒である、憐れみや忍びがたい気持ちに誠実であれば幸福になれるかっていうと、それが天ーーと言っても超越的ではなく、内在的なーー通じており、それこそが道徳の基礎なのだ、ということらしい。
もちろん、基礎づけに成功しているわけはない。著者の意図がむしろ、現代の西洋人の固定観念や概念枠組みを揺さぶろう、ということなのだから、これはこれでいい。
全般として、西洋人にありがちな西洋の枠組みから東洋をとらえるといった陥穽におちいることなく、まじめに中国思想ととりくんだおもしろい作品だと思う。翻訳もこなれて読みやすい。