◎尾崎光弘氏評『曼陀羅国神不敬事件の真相』
尾崎光弘さんから、小笠原日堂著『曼陀羅国神不敬事件の真相』の書評が送られてきた。この本は、本年二月、批評社によって復刻されたもので、僭越ながら、礫川が注記・解題を担当した(同書の初版は一九四九年、無上道出版部)。
ご本人のお許しを得て、転載させていただく。なお、尾崎さんによれば、本格的な書評は、このあと、ご自身のブログに掲載される予定だという。
『曼陀羅国神不敬事件の真相』の感想 尾崎 光弘
本文より先に「解題」を一読しました。現在「平成法難」といった情況にいたる可能性がある時代の中で、「まさにいま読まなくてはならない一冊」であると記されたその根拠とは何だろうか、この疑問を自分なりに確かめてみたい、というのが最初の感想でした。わたしなりに、時代の妙な雲行きを感じているからだと思います。
さて三月に入り本文を読んでみたところ、難解な仏教用語がたくさん散りばめられた文章にもかかわらず、一気に読了させたのは何と言っても著者小笠原日堂氏自身の獄中記の箇所でした。辛い体験なのにどこか痛快に感じさせるその思想と行動は、どこかしら、かつて親しんだ大映映画『兵隊やくざ』を彷彿させるものでしたが、いわゆる娯楽作品と同一視するのは、いかにも故人や関係者に気の毒です。そこで、きちんと理解するにはいささか遠回りが必要でした。
また、「解題」に紹介されてあった関連文献に目を通しながら思い至ったことの一つは、戦後、世俗化が進み伝統宗教離れが当たり前になっていく中で、仏教関係の用語が固苦しく並ぶ講話や文章が一般に受け入れられることの難しさでした。もしかすると、ご指摘のように、旧本門法華宗への弾圧事件の真相を扱った本書が、これまでよく知られて来なかったのは、戦後の世俗化に原因の一端があったのかもしれません。実際、仏教用語に疎いわたしのような者にとって本書を読み解くのは容易ではありませんでした。
とすれば、できることは本書と、わたしのように信仰もなく仏教用語にも疎い者との間の接点を求めることではないかと考えました。とはいえ、この歴史的な国家権力による宗教弾圧事件と似た体験などわたしにあるはずもなく、そこで構造が近似した体験がなかったかを探ってみることにしたのです。その構造をもとにこの事件の性格を読み解きながら最初の疑問に迫ってみたいと思ったのです。それを長々と綴っては失礼ですから、ここではその概要をごく簡単に綴ってみます。詳細は後日ブログで紹介するつもりでいます。
その構造とは、わたしたちは「世俗倫理で解決できない事態になると、自分との対話を始める」ことです。そして「自分との対話において倫理を超越した議論が行われ、そこで得られた何かをもってまたその事態に対処する」という、往き還りの論理です。「自己対話」は徹底的に<私>の営みですが、そのやり方によって、<私>にとどまるかあるいは<個>の確立に向うか、が決まって来るように思います。ただ実際はその中間が多いのではと想像します。
つぎに「自分との対話」の内容についてです。少年時代のわたしは、思わず悪事を実行してしまう自分という人間の不思議さにとまどったり、何かにつけてこづいてくる同級生に対する反撃のへの覚悟をきめることであったり、これらをもって世俗倫理では解決できない困難に立ち向かったという気がします。
「曼陀羅国神不敬事件」の主人公の一人であり、本書の著者である小笠原日堂氏の場合はどうだったかといえば、(並べて書くのは怖れ多いのですが)それは自分の位置に日蓮を置く主客を交換した「自分との対話」でしたが、この営みによって再びその弟子として生きる覚悟、これに加えて検察側の「不敬の根拠」の破砕、さらに「日蓮曼荼羅」の本尊を題目とする構成原理への解脱によって、国家権力の弾圧という世俗倫理の困難を乗り越えたということができます。ここには一つの普遍性の獲得があります。敷衍すると、世俗倫理の不可能性をもたらした国家権力に対する、普遍性による根底的な枠組みの相対化です。
これを<私と個>の問題として見直してみると、<私>への徹底的なこだわりが社会的な性格をもつ<個>の確立を可能にした、ということができるかもしれません。とすると、<個>の問題に注目することで、この事件の歴史的意義が、ほの見えてきます。
わたしに、日本人の「ある国民性」について重要な知見をもたらせてくれた得難い文献をふり返ってみます。まず、柳田国男『明治大正史 世相編』における「公民として病みかつ貧しい」日本人、吉本隆明『敗北の構造』における征服される部族国家の「敗北の構造」、増田義郎『純粋文化の条件』における日本人の「ケロリ主義」、山本武利『日本兵捕虜は何をしゃべったか』における日本兵捕虜の敵国への追従、そして最近では、孫崎亨『戦後史の正体』における戦後政治家・官僚・マスコミ一体となったアメリカへの追従、礫川全次『攘夷と憂国』における近代化のネジレと捏造された維新史などです。
これらの文献に共通するテーマは何かと問われれば、わたしは西洋流の「個」の確立とは異なる、曰く言い難い卑屈な「個」の歴史ということができます。こういう日本人の歴史に小笠原日堂氏の「獄中記」をおいてみれば、本書の意義は明瞭です。戦時下、旧本門法華宗を除く伝統仏教団体の多くが、天皇制国家神道体制に追従し、のみ込まれていった事実に鑑みるならば、戦時下、非宗教としての国家神道を含めた世俗倫理との接点を失わず、かつその不可能性に抗した旧本門法華宗の闘いぶりは、永く記憶に留められべきだと思います。これが、本書をなぜ「まさにいま読まなくてはならない一冊」なのか、わたしなりの解です。(2015.6.4)


















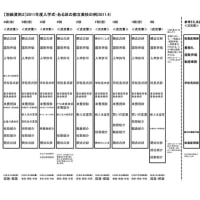
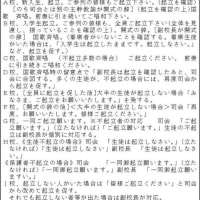









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます