◎青木茂雄氏の映画評『アラビアのロレンス』は未完
昨日の続きである。映画評論家・青木茂雄氏の映画評『アラビアのロレンス』。これは、三回分に区切られていたが、昨日、その第一回を紹介した。本日は、第二回と第三回をまとめて紹介したい。最後まで読むとわかるが、これでも「話」は、完結していない。
記憶の中の映画(8) 青木茂雄
観るたびに発見のあった映画 『アラビアのロレンス』 2
私は『アラビアのロレンス』を過去10回観ている。劇場で8回、ビデオで1回、テレビ放送で1回。劇場で数十回、メモを取りながら観たという、かのスティーブン・スピルバーグにはかなわないにしても(私もスピルバーグにならったというわけではないが、暗闇でメモを取ったことも数回ある)、劇場8回(今度で9回)は、かなり多い方ではないのかと自負している。このうち何回かは、座りっぱなしで立て続けに2回(つごう8時間弱)観続けたことも数回あるから、実際には、劇場でもうすでに10回以上は観ている。
なぜ、回数を重ねたのか?
『アラビアのロレンス』には、観るたびに必ず何か新しい発見があった。その発見が、新たな感動と必ず結びついていた。“この映画から、また何か発見がある”、その期待が、再三にわたって、私の足を劇場に運ばせたのである。しかし、9回目の今回は、新しい発見は何もなかった、そのことが今回の「感動は中程度」なのだが、逆にそのことによって私は、また新しい謎をかけられていることに気づいた。それについては、おいおい述べて行くことにして、私の『アラビアのロレンス』観賞歴をひとまず披露しよう。
第1回目は、水戸市内の新設したばかりの70ミリ映画上映館「京王グランド」(これも今はもうない)で、1964年、私が高校2年の時に観た。シネマスコープサイズの湾曲した画面が更に上部に広がっていくと、そこにはこれまでに観たことのない70ミリ用の大画面が出現した。上映開始して、その大画面と色彩と画面のキメの細かさには驚いた。それと完璧な立体音響である。とくにロレンスがファイサルの陣地に到着した際、ワジの谷間を低空飛行するトルコ軍機から攻撃を受けるシーンでは、劇場の背面からバリバリという機銃の音を聴いたときの驚き(今ではこんなものは珍しくも何ともないのであるが)。また、列車爆破シーンには思わず身をのけぞった。それと、独特の幾何学模様をなすセメントの床面を、真上から俯角でとらえた斬新なタイトルの画面。シンプルであるがゆえにかえって斬新である。画面の左上部の斜めにオートバイが置かれ、ロレンス(ピーター・オトゥール)がいそいそと、バイクとの間を往復し、出発の準備に励む。
音楽は、上映前の序曲。空気をつんざくような激しい打楽器の連打から始まり、砂漠を連想させるゆったりしたメロディーと、その後のアラビア風のテーマから一変して、上映開始とともに、リズミカルなタイトルバックへと変わっている。やがて疾走するバイク。バイクを運転するロレンスの目は、観客の目と同致する。ここでもう完全に映画の世界に入り込んでしまう……。感興の3時間半であった。
しかし、1回目では、必ずしも内容がよく分からず、特に後編にはいささか退屈した。「サイクス・ピコ協定」など知る由もなかったし、登場人物も識別できていなかった。ただ、モーリス・ジャールのあの音楽だけは耳に残り、何度も何度も繰り返した。
当時の新聞でもラジオでも、『アラビアのロレンス』がしばしばとりあげられ、ラジオで誰だったか、ロレンスがトルコの将軍に捕縛され性的な虐待を受けるところなどをとらえ、これがホモ・セクシャルをテーマとする映画だと解説する評論家に、“そんな観方もあるのか”と感心したりした。たしかに、この映画のどのカットにも、女性の影はなかった。
2回目は、東京の新宿の武蔵野館でのリパイパル上映(この時は全編の上映時間が187分、初公開時は202分)で観た。この時は文句なく感動した。とくに前半、ロレンスとアリ(オマー・シャリフ)との対抗を軸に、ドラマが進行する。砂漠の井戸での劇的な出会いから始まって、ファイサル王子のテントの中での再度の出会い。テントの中では、イギリス軍のブライトン大佐(アンソニー・クウェイル)とファイサル(アレック・ギネス)とのやりとりも興味深かった。ファイサルが「我々には大砲がないのが敗因だ」と言うのに対して、大佐は「訓練がないからなのだ」と応じる。「イギリスは小さい国だ、あなたの国より小さい。しかし、小さいけれども良く訓練されているので強い(Britain is small, but strong, because it is well disciplined)」。これに対して、ファイサルが即座に反応する。 「それは武器があるからだ“because it has guns"」。たしかにアラブ側から見れば、帝国主義イギリスの存在とは強力な武力であったに違いない…。
私には、大佐が会話の中で繰り返すこの“disciplined"という言葉が印象に残った。そう、この映画のテーマの一つが、合理性と組織性の“英国主義”なのだ(『戦場にかける橋』でもテーマの一つは“英国主義”の“合理性と組織性”であり、アレック・ギネスがそれを体現していた)。
そして、ネフド砂漠横断の決死行。行進中に落駝したカシムを取り戻しに出ようとするロレンス。それを必死で止めるアリ。アリは「カシムは昼頃までには死ぬだろう。それが彼の運命だ(In the midday he will be dead , it is written.)」。これに対するロレンスの応えは、“Nothing is written(字幕は「運命なんてない」)”。そう言い残して、2人の若い従者を連れて、一目散に砂漠の中へ……。やがてカシムを連れて帰ってきたロレンスは、アリに“Nothing is written.”と吐き捨てるように言って、倒れるように眠りこける。
“Nothing is written.”これがこの映画の前半部のキーワードとなっている。運命に逆らい、自ら切り拓いていったロレンスは、ベドウィンの民の英雄となる。真白の族長服を身にまとって、短剣に身を写し、恍惚とするロレンス……。
私には、前半部の英雄となるロレンスがこの時観た『アラビアのロレンス』の全てだったが、ラスト近くの、ファイサルのロレンスに対する言葉、「戦いの徳は若者の徳であり、平和の徳は老人の徳だ(The virtue of war is the virtue of young men. The virtue of peace is the virtue of oldmen)」も印象に残り、そしてイギリス軍のアレンビー将軍(ジャック・ホーキンス)に対する、「あなたはただの将軍だが、私は王にならねばならぬ(You are a mere general, but I must be a king)」にはうなった。さすが、デイウッド・リーン、さすがアレック・ギネス……。
20代の私にとって、『アラビアのロレンス』は人生の教科書であった。
当時私は、日記に次のような感想を書いた。
「この映画に文字通りabsorbされてしまった。自分は今ヘナヘナしていて書くことを持た
ない。英雄がいて、栄光があり、孤独があり、悲惨があり、権謀があり……。これはextremeなdramaだ。」
さて、この“written”という語だが、『聖書』にそう書かれているという意味なのだろうが、ロレンスとアリとでは「本」が違う。アリの場合はもちろん『コーラン』だろう。映画のシナリオの上だけの話ではあるが、これで通じさせてしまうところが強引だが面白い(そもそも、こんなに流暢に英語を話すベドウィンが当時いたわけないし、歴史上のロレンスはひどい訛りはあったらしいが、一応全部アラビア語で話していた、当然だが。映画のロレンスもアラビア語は読めるし、書ける、という設定。アラビア語の現地新聞は読んでいるし、ベドゥウィンの族長への“証書”は、ちゃんと右から横書きした。当然話せたはずだが……。ま、これは映画の上での話)。
ところで、“written”という語は、キリスト教世界ではキーワードであるらしい。『十戒』(1956年、セシル・B・デミル監督)では、話の展開点ごとに、“So it was written, so it was done.(聖書の預言の通りに成就した)" というタイトルが挿入されていた。
キリスト教世界では“Nothing is written.”という言葉はどのような意味を持つのだろうか。
記憶の中の映画(9) 青木茂雄
観るたびに発見のあった映画 『アラビアのロレンス』 3
1976年に観た3回目を最後に、しばらく『アラビアのロレンス』からは遠ざかった。この映画から観るべきものは観た、と思っていた。1988年に完全版が作成され、翌年に日本で公開されたことにも、私はまったく気が付かなかった。たしか1993年だったと思うが、NHK教育テレビで完全版が放映され、それをビデオに録っておいたのを、たまたま観た。16インチの小さなモニター画面で、トリミングなしの、上下に黒い部分が残るままの、画面としては本当に貧弱なものだったが、その面白さにしばし時間の経つのを忘れた。10年以上経つと、どんなにその内容を詳細に覚えていようとも、始めて観た時のような印象を受ける(だから時間を置いて観ることも大切だ)。
まず、セリフが面白い。言葉のやりとりが丁々発止と(それこそ「弁証法」、即ちディアレクティークだ)。
砂漠の井戸で、ロレンスの供のベドウィンを射殺した後、アリがロレンスに「あなたの名前は何か?」と訊くと、ロレンスはこれに対し“My name is for my friend.”(字幕・名前は教えない)。そして、 アリは、“The well is everything. He is nothig. ”(井戸が全てだ。 かれはとるに足らない奴だ)。
ファイサルのテントの中で、ファイサルがロレンスに。“Are you another desert-loving Englishman?”。そして、 アラブがトルコに勝つためには“We need miracle.”と、 ロレンスに告げる。
miracleという語がキーワードになって、 ロレンスは一昼夜考え抜いて、「アカバ急襲」作戦を思い立つ。“I'll go to Acaba, that is written.”(アカバへ行こう、それが運命だ)。そして、アカバ急襲作戦成功ののち、アリがロレンスに“Miracle is accomplished.”(奇跡は起こった)。
優れた作劇は、優れたせりふを伴う(フランス映画などでは、シナリオライターの外に、せりふの専門のライターを用意したものもあった)。その意味では、『アラビアのロレンス』は、シナリオだけでも独立した価値を持つと思う、シェークスピア劇がそうであるように。その意味では、付された日本語字幕が、私には不満足であった。原文の意味合いを生かしきれていない。原文の全文シナリオを、ぜひどこかで入手したいのだが、まだ果たせずにいる。
タイトルにクレジットされた脚本家はロバート・ボルトだが、実際はマイケル・ウィルソンとの共作である。ウィルソンは“赤狩り”でハリウッドを追われ、公開当時(1963年)には、まだ表に名前を出せなかったらしい。完全版のエンド・タイトルには、クレジットされているとのことである。
完全版を念願のスクリーンで観たのは、しばらく後の1999年、今はなき新宿のコマ劇場にある“シネアップル”(たしかそういう劇場名だったかと思う)での「コロンビア映画特集」というシリーズでだった。私は、メモ帳を携えて、朝から丸一日、コマ劇場に詰めた。一度目はそのまま通して観て、二度目にはメモをとりながら観た。そして私は、この作品の構成の見事さに舌を巻いた。私は、これまでこの作品から実は何も観てこなかったのだということを痛感した。コマ劇場ですごした8時間は、『アラビアのロレンス』という映画の観方を根底から変えた。それについては、次回以降に述べることにしよう。
*このブログの人気記事 2015・4・15
- 青木茂雄氏の映画評『アラビアのロレンス』(1963)
- 石原莞爾がマーク・ゲインに語った日本の敗因
- 草野大悟さんと柏木法隆さん
- 病む犬に煮たアズキ、病む猫に削った銅
- 憲兵はなぜ渡辺錠太郎教育総監を守らなかったのか
- スズリの水が凍るのを防ぐ方法
- 岩波文庫に先行したアカギ叢書
- 伊藤博文、ベルリンの酒場で、塙次郎暗殺を懺悔
- 古畑種基と冤罪事件
- 乳カバーは授乳中の女性が使う


















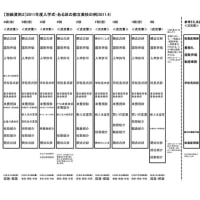
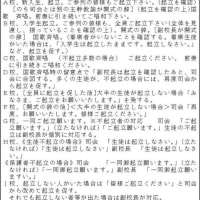








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます