読売新聞の「父の戦争 母の終戦」には、
阿川佐和子さんの回もありました。
亡くなったお父様に関して、
「あなたのお父様は 戦争がお好きでしたね」
と言われた事があるそうです。
戦争が好きだなんて、
そんな人がいるものでしょうか?
たとえ 昭和天皇を崇拝していようと
(昭和天皇の話をすると、いつも涙ぐんだそうですが)、
たとえ海軍に誇りを持っていようと
(海軍は、どうも、確かに、お好きだったみたい)、
「お父様は戦争がお好き」だなんて、
口に出して言うべき言葉でしょうか?
悪意を感じます!



お父様は、こんな本も書いていらっしゃいますけど。
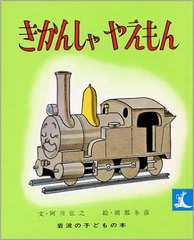
新聞をきちんと保存していなかったので、
阿川佐和子さんの回のものは、
(『蝿の帝国』の帚木 蓬生氏の回などを含めて、)
残念ながら、手元にありません。
手元にありませんが、
記憶に残っているのは、
最近 時々目にする言葉です。
「君が代」を歌ったり 日の丸を掲げただけで
「右翼」と呼ばれるのは、ちょっと、どうなんだろう?
といった意味の言葉です。
他国の国旗、国歌を尊重するのは当然の事で、
それはもちろん、自国のものに対しても、同様なはずです。
日本人が 日本の国旗や国歌を大事にすると口撃されるのは、
どうしてでしょう?
お風呂で「君が代」を歌ったら、家族に笑われるのは、
何故でしょう?(笑)
阿川佐和子さんの最近の著作『恐父論』、お貸し出来ます。
(文藝春秋、2016.7.30、1300円)
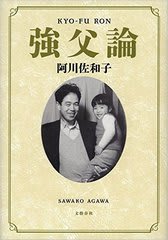
帯には ビートたけし氏の
「阿川さんには言わなかったけど、
はっきり言って
あなたのお父さんは 私の理想です」
という言葉が載っています。
読売新聞の特別編集委員、橋本五郎氏は、
「『恐父論』は一見父親批判に見えますが、
本当は「父を恋る詩」ではないのか。
全く揺らぐことなく関白であり続けた父を
本当は愛していたのではないかと思うのです。」
と書いています。(9月10日朝刊、13面)
ともかく、すごいお父様だったようです(笑)。
お父様の阿川弘之氏は。
大正9年のお生まれでした。
阿川佐和子さんの回もありました。
亡くなったお父様に関して、
「あなたのお父様は 戦争がお好きでしたね」
と言われた事があるそうです。
戦争が好きだなんて、
そんな人がいるものでしょうか?
たとえ 昭和天皇を崇拝していようと
(昭和天皇の話をすると、いつも涙ぐんだそうですが)、
たとえ海軍に誇りを持っていようと
(海軍は、どうも、確かに、お好きだったみたい)、
「お父様は戦争がお好き」だなんて、
口に出して言うべき言葉でしょうか?
悪意を感じます!



お父様は、こんな本も書いていらっしゃいますけど。
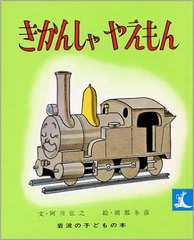
新聞をきちんと保存していなかったので、
阿川佐和子さんの回のものは、
(『蝿の帝国』の帚木 蓬生氏の回などを含めて、)
残念ながら、手元にありません。
手元にありませんが、
記憶に残っているのは、
最近 時々目にする言葉です。
「君が代」を歌ったり 日の丸を掲げただけで
「右翼」と呼ばれるのは、ちょっと、どうなんだろう?
といった意味の言葉です。
他国の国旗、国歌を尊重するのは当然の事で、
それはもちろん、自国のものに対しても、同様なはずです。
日本人が 日本の国旗や国歌を大事にすると口撃されるのは、
どうしてでしょう?
お風呂で「君が代」を歌ったら、家族に笑われるのは、
何故でしょう?(笑)
阿川佐和子さんの最近の著作『恐父論』、お貸し出来ます。
(文藝春秋、2016.7.30、1300円)
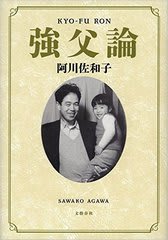
帯には ビートたけし氏の
「阿川さんには言わなかったけど、
はっきり言って
あなたのお父さんは 私の理想です」
という言葉が載っています。
読売新聞の特別編集委員、橋本五郎氏は、
「『恐父論』は一見父親批判に見えますが、
本当は「父を恋る詩」ではないのか。
全く揺らぐことなく関白であり続けた父を
本当は愛していたのではないかと思うのです。」
と書いています。(9月10日朝刊、13面)
ともかく、すごいお父様だったようです(笑)。
お父様の阿川弘之氏は。
大正9年のお生まれでした。
















 574-6631とあります。)
574-6631とあります。)

