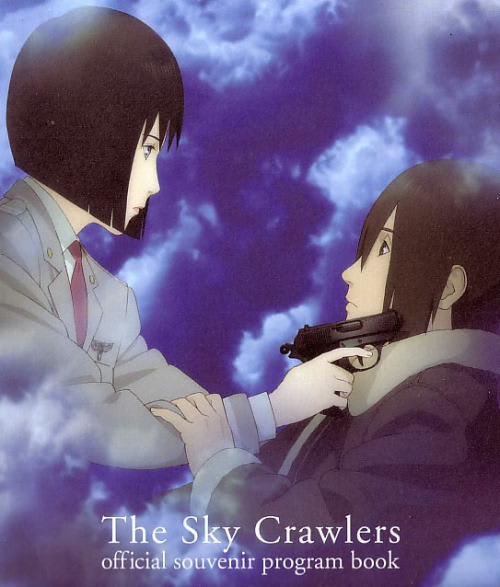しかしぼくとしても、“なんなの、コレ?”と溜息をついていても、仕方がないのである。
ぼくは、“正義”が欲しいのだろうか。
“真理”が欲しいのだろうか。
“女”が欲しいのだろうか。
つまり、“そういうこと自体が”わからない。
ぼくは、ほんとうは、メクラめっぽうに生きてきた-生きているだけである。
ぼくが、本を読むのも(ほんとうは)、めくらめっぽうに、である。
たとえば、今日、Amazonマーケット・プレイスから本が届いた。
それは、高橋哲哉『国家と犠牲』(NHKブックス2005)という本である。
ぼくは高橋哲哉氏の本は、『現代思想の冒険者たち-デリダ』しか読んだことがない。
有名な『靖国問題』も買ってない。
つまり実は(このブログの良き読者なら明察の通り)ぼくは、“靖国問題”とか“護憲”とか“政党政治”とか“選挙”とか“安全な社会”とかに、“関心がもてない”のである。
ぼくの最近のブログは、むかしより、そのことに正直になってきている、と思う。
じゃあ、ぼくは何に関心があるんだろうか。
たぶん“暴力”には関心がある。
ぼくが“連続レイプ魔”的人間に関心があることは、わりと最近書いたはずである。
だから、そういう“異常者”とか“狂人”と呼ばれうる人々に関心がある。
それから、近代-現代の言説を読めば読むほど“性的倒錯者”と呼ばれうる人々に関心がある;プルースト、ジュネ、バルト、フーコー、パゾリーニ……まだまだいくらでもいる。
ぼくは、ときどき、自分が“倒錯者でない”ことを、残念にさえ思う(笑)
自分には、“情熱がない”ような気がする。
さて、高橋哲哉氏のこの本をパラパラと見ると、この本には“まともなこと”が書かれている。
ぼくは“まともなこと”にも、敬意を払っている。
あまり良い読み方ではないが、いきなり最後の章を読んでみた。
この章は、デリダの『死を与える』という本をモチーフとしている。
デリダのこの本をぼくは読んでいないが、それは、聖書の“アブラハムのイサク奉献”をモチーフにしている。
“アブラハムのイサク奉献”の話を、ぼくは聖書自体で読んだことがないのだが、この“話”は、いろんな所で引用されているので知っていた。
つまりアブラハムは、神の命令で息子のイサクを殺さなくてはならなくなるのである。
この聖書の記述の“読み”を通じて、デリダも高橋哲哉も(デリダの読みを通じて)、“「絶対的犠牲」の意味を問う”のである。
ぼくは、こういう“読みの連鎖”が無駄であるなどとは、思わない。
もしそう思うなら、ぼくは書を捨てて町にでる、だけである。
というか、“町に出ても”ナンモ面白いことがないし、テレビをつけてもナンモ面白いことはないのである。
この最後の章の最後に高橋哲哉氏は書いている;
★ 私の認識はこうです。あらゆる犠牲の廃棄は不可能であるが、この不可能なものへの欲望なしに責任ある決定はありえない、と。
なにを言っているかは、“わかる”。
それどころか、この言葉は、“ただしい”と思う。
次ぎの行も読んでみる;
★ 「あらゆる犠牲の廃棄」とは、特異な他者たちの呼びかけに普遍的に応えることにほかなりません。わたしたちは「絶対的犠牲」の構造のなかで、しかし、あらゆる犠牲の廃棄を欲望しつつ決定しなければならないのではないでしょうか。
うーむ(笑)
ぼくはこの文章の以下の部分に、傍線をボールペン(青)で引きました;
★ 特異な他者たち
★ 普遍的に応える
ぼくは、高橋氏の言説を“揶揄”したいのではない。
ほんとうに(たんに)“特異な他者たち”とは誰のことか?と思った。
“普遍的に応える”とは、どういうふうに“応える”のだろう?と思った。
“この不可能なものへの欲望”
というのは、よい言葉だと思った。
そのあと(最後の最後)に、高橋氏は魯迅の『狂人日記』を取り上げて(引用をふくむ)いる;
★ 魯迅はしかし、「人間が人間を食う」社会に絶望しつつ、しかし希な(まれな)望み=希望への問いを最後に発したのでした。
なるほど(実はぼくは『狂人日記』を読んでない)、魯迅も“希望”を語ったのだ。
もちろんぼくはベンヤミンの言葉を思い出す;“希望なきもののためにのみ、希望はぼくらに与えられている”(ぼくが暗証できる数少ない言葉である;笑)
しかし、“希望”を語るものは、“狂人”であるのだろうか。
ぼくの次ぎの読書予定は、猿谷要『検証 アメリカ500年の物語』(平凡社ライブラリー2004)である。
その前に、髭を剃って、爪を切る。
これはなんの“儀式”でもなく、昨夜風呂から出てパンツ一丁で髭を剃っていたとき、妻が転んで、家具の角に額をぶつけて出血したためである。
今日夕食のあとには、“生ゴミ”も捨てよう。
<追記>
ぼくが読み続けている『ブリキの太鼓』だって、いっしゅの“狂人日記”である。
その書き出しは以下のようであったではないか;
《そのとおり、ぼくは精神病院の住人である。ぼくの看護人はぼくを見張っていて、ほとんど眼をはなすことがない。ドアに覗き窓がついているのだ。それなのに、看護人の眼は例の茶色なので、青い眼のぼくを看破することができない。》
つまりヒットラーのような狂人に対抗し、そうでない世界をもたらすためには、“別の狂気”が必要なのかもしれない。
なぜなら“ヒットラーのような狂人”とは、この世界の凡庸なものの極端化でしかないからだ。
かつて大江健三郎氏も以下の言葉を自著のタイトルとしたではないか;
”われらの狂気を生き延びる道を教えよ”
<再追記>
“狂気に汚染されていないもの”のぼくがモデルと考える(感じる)のは、バッハです。
とくにグレン・グールドのバッハ。
だから、ぼくは感覚の調整のために、グールドのバッハを聴いています。
モーツアルトには(ぼくはさほど聴いていませんが)、すでに狂気があります。
けれどもぼくは、“狂気”が悪いものであるだけだと、いっていないわけです。
もちろんぼくの好きなロックやPOPSに、どんな狂気があるかは、そういう音楽を無視しない方々には明瞭だと思います。
ぼくは、“正義”が欲しいのだろうか。
“真理”が欲しいのだろうか。
“女”が欲しいのだろうか。
つまり、“そういうこと自体が”わからない。
ぼくは、ほんとうは、メクラめっぽうに生きてきた-生きているだけである。
ぼくが、本を読むのも(ほんとうは)、めくらめっぽうに、である。
たとえば、今日、Amazonマーケット・プレイスから本が届いた。
それは、高橋哲哉『国家と犠牲』(NHKブックス2005)という本である。
ぼくは高橋哲哉氏の本は、『現代思想の冒険者たち-デリダ』しか読んだことがない。
有名な『靖国問題』も買ってない。
つまり実は(このブログの良き読者なら明察の通り)ぼくは、“靖国問題”とか“護憲”とか“政党政治”とか“選挙”とか“安全な社会”とかに、“関心がもてない”のである。
ぼくの最近のブログは、むかしより、そのことに正直になってきている、と思う。
じゃあ、ぼくは何に関心があるんだろうか。
たぶん“暴力”には関心がある。
ぼくが“連続レイプ魔”的人間に関心があることは、わりと最近書いたはずである。
だから、そういう“異常者”とか“狂人”と呼ばれうる人々に関心がある。
それから、近代-現代の言説を読めば読むほど“性的倒錯者”と呼ばれうる人々に関心がある;プルースト、ジュネ、バルト、フーコー、パゾリーニ……まだまだいくらでもいる。
ぼくは、ときどき、自分が“倒錯者でない”ことを、残念にさえ思う(笑)
自分には、“情熱がない”ような気がする。
さて、高橋哲哉氏のこの本をパラパラと見ると、この本には“まともなこと”が書かれている。
ぼくは“まともなこと”にも、敬意を払っている。
あまり良い読み方ではないが、いきなり最後の章を読んでみた。
この章は、デリダの『死を与える』という本をモチーフとしている。
デリダのこの本をぼくは読んでいないが、それは、聖書の“アブラハムのイサク奉献”をモチーフにしている。
“アブラハムのイサク奉献”の話を、ぼくは聖書自体で読んだことがないのだが、この“話”は、いろんな所で引用されているので知っていた。
つまりアブラハムは、神の命令で息子のイサクを殺さなくてはならなくなるのである。
この聖書の記述の“読み”を通じて、デリダも高橋哲哉も(デリダの読みを通じて)、“「絶対的犠牲」の意味を問う”のである。
ぼくは、こういう“読みの連鎖”が無駄であるなどとは、思わない。
もしそう思うなら、ぼくは書を捨てて町にでる、だけである。
というか、“町に出ても”ナンモ面白いことがないし、テレビをつけてもナンモ面白いことはないのである。
この最後の章の最後に高橋哲哉氏は書いている;
★ 私の認識はこうです。あらゆる犠牲の廃棄は不可能であるが、この不可能なものへの欲望なしに責任ある決定はありえない、と。
なにを言っているかは、“わかる”。
それどころか、この言葉は、“ただしい”と思う。
次ぎの行も読んでみる;
★ 「あらゆる犠牲の廃棄」とは、特異な他者たちの呼びかけに普遍的に応えることにほかなりません。わたしたちは「絶対的犠牲」の構造のなかで、しかし、あらゆる犠牲の廃棄を欲望しつつ決定しなければならないのではないでしょうか。
うーむ(笑)
ぼくはこの文章の以下の部分に、傍線をボールペン(青)で引きました;
★ 特異な他者たち
★ 普遍的に応える
ぼくは、高橋氏の言説を“揶揄”したいのではない。
ほんとうに(たんに)“特異な他者たち”とは誰のことか?と思った。
“普遍的に応える”とは、どういうふうに“応える”のだろう?と思った。
“この不可能なものへの欲望”
というのは、よい言葉だと思った。
そのあと(最後の最後)に、高橋氏は魯迅の『狂人日記』を取り上げて(引用をふくむ)いる;
★ 魯迅はしかし、「人間が人間を食う」社会に絶望しつつ、しかし希な(まれな)望み=希望への問いを最後に発したのでした。
なるほど(実はぼくは『狂人日記』を読んでない)、魯迅も“希望”を語ったのだ。
もちろんぼくはベンヤミンの言葉を思い出す;“希望なきもののためにのみ、希望はぼくらに与えられている”(ぼくが暗証できる数少ない言葉である;笑)
しかし、“希望”を語るものは、“狂人”であるのだろうか。
ぼくの次ぎの読書予定は、猿谷要『検証 アメリカ500年の物語』(平凡社ライブラリー2004)である。
その前に、髭を剃って、爪を切る。
これはなんの“儀式”でもなく、昨夜風呂から出てパンツ一丁で髭を剃っていたとき、妻が転んで、家具の角に額をぶつけて出血したためである。
今日夕食のあとには、“生ゴミ”も捨てよう。
<追記>
ぼくが読み続けている『ブリキの太鼓』だって、いっしゅの“狂人日記”である。
その書き出しは以下のようであったではないか;
《そのとおり、ぼくは精神病院の住人である。ぼくの看護人はぼくを見張っていて、ほとんど眼をはなすことがない。ドアに覗き窓がついているのだ。それなのに、看護人の眼は例の茶色なので、青い眼のぼくを看破することができない。》
つまりヒットラーのような狂人に対抗し、そうでない世界をもたらすためには、“別の狂気”が必要なのかもしれない。
なぜなら“ヒットラーのような狂人”とは、この世界の凡庸なものの極端化でしかないからだ。
かつて大江健三郎氏も以下の言葉を自著のタイトルとしたではないか;
”われらの狂気を生き延びる道を教えよ”
<再追記>
“狂気に汚染されていないもの”のぼくがモデルと考える(感じる)のは、バッハです。
とくにグレン・グールドのバッハ。
だから、ぼくは感覚の調整のために、グールドのバッハを聴いています。
モーツアルトには(ぼくはさほど聴いていませんが)、すでに狂気があります。
けれどもぼくは、“狂気”が悪いものであるだけだと、いっていないわけです。
もちろんぼくの好きなロックやPOPSに、どんな狂気があるかは、そういう音楽を無視しない方々には明瞭だと思います。