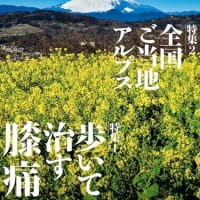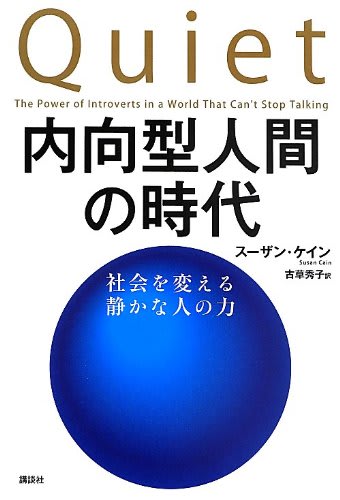
この外向型人間中心の世界で、内向型の人間はどうやって生きていけばいいのか?内向型は外向型に比べて劣っているのか?どうして内向型人間はそうなったのか?この本ではそんな疑問に対して、多くの研究報告や取材を通して丁寧に説明していく。
私は根っからの内向型人間だ。本書には内向型か外向型かを判断する質問が設定されており、20問中〇の数が多いほど内向型である確率が高く、〇の数がほぼ10であれば両向型かもしれないという。問いてみたら〇が15個あったので、私は間違いなく内向型だ。だからこんな本が出るのを待っていた。心理学的には内向型・外向型という分け方はそんなにオーソライズされたものではないらしい。著者は、心理学者でも精神神経医でもない。元弁護士で、著述業に転身した人である。だからこそ、学問的にとらわれずにこのような本が書けたのだろう。
話題が多方面にわたっていて、論理展開の仕方がやや冗長な感じもしたが、多くの示唆に富んでいる本である。
例えば次のようなことがポイントとして挙げられるかもしれない。
・この社会は外向型が理想とされている。とくにアメリカはそうであるが、実際には1/3から1/2のアメリカ人は内向型である。内向的だと過小評価されるし、劣等感を感じやすい。
・しかし、ニュートン、アインシュタイン、ショパン、スピルバーグ、ガンジーといった内向型の人々は内向性ゆえに偉業を成し遂げてきた。
・ジェローム・ケーガンの研究によると、生後4か月の乳児期に刺激に対して高反応の子は将来内向的になり、低反応の子は将来外向的になる確率が高いという。ということは、内向性・外向性は生後ずいぶん早い時期に決まってしまうということになる。そして、刺激への反応性というのが重要なポイントである。
・大脳辺縁系の奥に位置する偏桃体は感情脳とも呼ばれ、食欲・性欲・恐怖といった根源的な本能の多くを司っている。外界からの刺激を受けて脳の他の部分に指令を出すスイッチになる。ケーガンの仮説では、この偏桃体が興奮しやすいと、外界の刺激に大きく反応し、人に対して用心深く接して内向型になる。
・内向型と外向型はそれぞれ特定のレベルの刺激を好む。自分にとっての「スイートスポット」を知って仕事も趣味も社交もそれに合うように設定すれば、より生き生きとした人生が送れる。
・内向型は、人とうちとけにくかったり、否定的な感情に圧倒されると他人のことを二の次にする場合もあるが、感受性の鋭さは良心を形づくる。
・外向型はドーパミン、脳の報酬系の活性が強く、ギャンブルや冒険に駆り立てられる。アメリカの金融危機をもたらしたのは、押しの強い外向型である。
・内向型でも外向型のようにふるまうこともできる。自分にとって非常に重要な事柄、すなわち「コア・パーソナル・プロジェクト」に従事するとき、内向性の枠を超えてふるまえるのである。それはブライアン・リトルという心理学者が提唱した「自由特性理論」という。彼自身内向型であるにもかかわらす、大学での講義は非常に魅力的で受賞もしているが、講演などの後は疲れてしまうので、一人になる時間が必要だという。つまり「回復のための場所」が必要になる。
・著者のスーザン・ケインは弁護士であったが、自己のコア・パーソナル・プロジェクトとして見つけたのは、作家や心理学の仕事だった。そうしたことを見つけるのに3つの重要なステップがあった。第一に子供のころに大好きだったことを思い返すこと、第二に、どんな仕事に興味を持っているか考えること、最後に、自分が何をうらやましいと感じるか注意してみることであった。
・内向型と外向型が付き合っていくのには、それなりの工夫がいる。夫婦がそうだった場合、それぞれの違いを認識すること、相手の考えかたを理解することが重要である。相手が外向型で激しい感情を込めて不明不満を訴えてきても、内向型の自分は相手の口調を除外していったい何が言いたいのかを知るように心がける。相手は私を大切にして、私を愛してほしいと思っているのだと考えるようにすることを、長年の結婚生活で学んだ内向型の夫もいる。
・自分の子供が内向型であったら、それを受け入れて、才能や興味を育み、社会的なつきあいについても子供ができることを手助けしてやればよくて、無理なことを強制はしない、ということをしていくことで、子供は伸び伸びと成長することができる。
これまでの人生で、自分の性格が内向的であることはどうにも変えられないことであり、つねに悩みの種であった(とくに中学・高校時代)が、そのことをもっとポジティブにとらえるべきであるし、自分の特性を活かした生き方を追及していくことが大事なのだと思った。