こんばんは、ヨン様です。
昨日行われるはずだった5月最後の練習は主要参加者の一人に急遽仕事がはいってしまったため中止となりました。
シュビが仕事の話をするなんて…。
みんな大きくなったものです(目を細めながら)。
さて、22日に書いた記事の続きがまだでしたね。
今日はその続きを書いてしまいたいと思います。
前回触れられなかったのは、翻訳と編曲には似ているところと全然似ていないところがあるという話の内、似ていないところについてのお話でした。
翻訳と編曲の似ていない側面というのは、実用性の違いという視点から考えることができます。
この間の記事は「目的は共通している」という趣旨で話を進めましたが、実は、それはほとんど芸術的な側面にのみ言えることなのです。
たとえば言語は文学などに典型的に見られるような美的(詩的)価値ばかりでなく、伝達や記述という、極めて即物的な役割も持っています。一方で「運命」という象徴的な名を持ちながら、「交響曲第5番」という単なる機械的なナンバリングにすぎない名前も持つ曲があるということ、これらの言語(命名)のあり方は、前者は象徴的であるという点で文学的、後者は機械的であるという点で記述的であるということができます。つまり、言語は単に物語(虚構)を生みだすだけでなく、事実を描写、記述することができるわけです。
そして、美的価値ではなく確実な伝達に目的をおいてある言語を翻訳する場合(たとえば公文書や学術書の翻訳など)、それは明らかに組み換えでも再解釈でもなく、A言語によるB言語の記述でしかないのです。
編曲においてはどうでしょうか。はたして同じようなことがいえるのでしょうか。
そもそも音楽という表現手段は、言語のように記述という目的(機能)を持っていません。それはいわゆる真理命題的な意味を音楽という表現がもちえないということから明らかであります。真理命題的というのは、真偽を確かめることができる性質を持っているということです。たとえば、「シュビドゥヴァーズが歌を歌った」という文があるとすると、「シュビドゥヴァーズが歌を歌った」のは真か偽かと確かめられるということはこの文が真理命題的であり、真か偽かを確かめられる範囲がこの文の真理命題的な意味ということになります。仮に真理命題的な意味を伴わない表現があるとすれば、それは少なくとも概念的な何かを指すことができないということですから、その表現を用いての記述は不可能であるか極めて困難なものになるでしょう。
いくら音楽が種々の複雑な要素から構成され、あたかも文法的にふるまっていたとしても、そこに真か偽かという問いを立てることはほとんど無意味です。つまり、音楽には記述的な機能はなく、当然編曲も「意味」を正確に伝えいようという意図はないのです。もちろん、なにか素晴らしい音楽体験をして頭の中でさまざまな想いが渦巻き、それを誘発してのは間違いなく音楽であると感じることもあるでしょう。しかし、そいうった感動体験から得られる伝達内容は、推論的で極めて確定性の薄い伝達の結果にすぎません。言語を分析する際の術語としての真理命題的意味という概念はいろいろと見直されてはいますが、言語と音楽の比較のような場合は推論的な伝達レベルの問題でなく、それとは別の次元の問題であるととらえるほうが妥当でしょう。
さきほど述べた翻訳と編曲の実用性の違いというのは、つまり以上のような対照から考えられることで、翻訳は伝達を目的として記述的に用いられることがあるのに対し、音楽(もちろん歌詞のような言語的な要素は含みません)にはそのような役割はほとんどないといっていい、ということです。そもそも記述している対象も意味もないわけですから、意味伝達の目的で編曲することはないのは当たり前でしょう。
と、いうわけで、翻訳と編曲の違いについて、言語と音楽の「意味」という観点から考えてみました。
まだまだつきつめるべき点があるかとは思いますが、このままいくとなんだかきりがないのでやめておきます。
しばらく書けなくなるだろうし、2~3週間分を前倒しってことで。
それでは、また。
昨日行われるはずだった5月最後の練習は主要参加者の一人に急遽仕事がはいってしまったため中止となりました。
シュビが仕事の話をするなんて…。
みんな大きくなったものです(目を細めながら)。
さて、22日に書いた記事の続きがまだでしたね。
今日はその続きを書いてしまいたいと思います。
前回触れられなかったのは、翻訳と編曲には似ているところと全然似ていないところがあるという話の内、似ていないところについてのお話でした。
翻訳と編曲の似ていない側面というのは、実用性の違いという視点から考えることができます。
この間の記事は「目的は共通している」という趣旨で話を進めましたが、実は、それはほとんど芸術的な側面にのみ言えることなのです。
たとえば言語は文学などに典型的に見られるような美的(詩的)価値ばかりでなく、伝達や記述という、極めて即物的な役割も持っています。一方で「運命」という象徴的な名を持ちながら、「交響曲第5番」という単なる機械的なナンバリングにすぎない名前も持つ曲があるということ、これらの言語(命名)のあり方は、前者は象徴的であるという点で文学的、後者は機械的であるという点で記述的であるということができます。つまり、言語は単に物語(虚構)を生みだすだけでなく、事実を描写、記述することができるわけです。
そして、美的価値ではなく確実な伝達に目的をおいてある言語を翻訳する場合(たとえば公文書や学術書の翻訳など)、それは明らかに組み換えでも再解釈でもなく、A言語によるB言語の記述でしかないのです。
編曲においてはどうでしょうか。はたして同じようなことがいえるのでしょうか。
そもそも音楽という表現手段は、言語のように記述という目的(機能)を持っていません。それはいわゆる真理命題的な意味を音楽という表現がもちえないということから明らかであります。真理命題的というのは、真偽を確かめることができる性質を持っているということです。たとえば、「シュビドゥヴァーズが歌を歌った」という文があるとすると、「シュビドゥヴァーズが歌を歌った」のは真か偽かと確かめられるということはこの文が真理命題的であり、真か偽かを確かめられる範囲がこの文の真理命題的な意味ということになります。仮に真理命題的な意味を伴わない表現があるとすれば、それは少なくとも概念的な何かを指すことができないということですから、その表現を用いての記述は不可能であるか極めて困難なものになるでしょう。
いくら音楽が種々の複雑な要素から構成され、あたかも文法的にふるまっていたとしても、そこに真か偽かという問いを立てることはほとんど無意味です。つまり、音楽には記述的な機能はなく、当然編曲も「意味」を正確に伝えいようという意図はないのです。もちろん、なにか素晴らしい音楽体験をして頭の中でさまざまな想いが渦巻き、それを誘発してのは間違いなく音楽であると感じることもあるでしょう。しかし、そいうった感動体験から得られる伝達内容は、推論的で極めて確定性の薄い伝達の結果にすぎません。言語を分析する際の術語としての真理命題的意味という概念はいろいろと見直されてはいますが、言語と音楽の比較のような場合は推論的な伝達レベルの問題でなく、それとは別の次元の問題であるととらえるほうが妥当でしょう。
さきほど述べた翻訳と編曲の実用性の違いというのは、つまり以上のような対照から考えられることで、翻訳は伝達を目的として記述的に用いられることがあるのに対し、音楽(もちろん歌詞のような言語的な要素は含みません)にはそのような役割はほとんどないといっていい、ということです。そもそも記述している対象も意味もないわけですから、意味伝達の目的で編曲することはないのは当たり前でしょう。
と、いうわけで、翻訳と編曲の違いについて、言語と音楽の「意味」という観点から考えてみました。
まだまだつきつめるべき点があるかとは思いますが、このままいくとなんだかきりがないのでやめておきます。
しばらく書けなくなるだろうし、2~3週間分を前倒しってことで。
それでは、また。














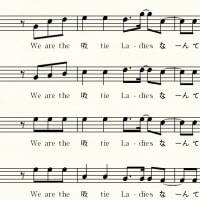
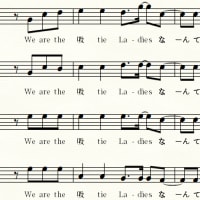
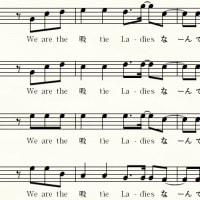

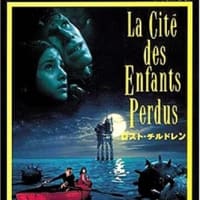

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます