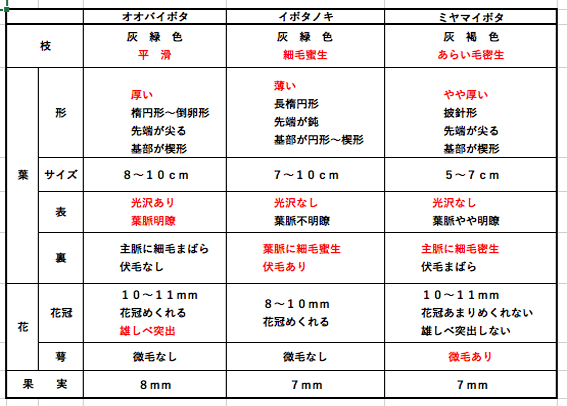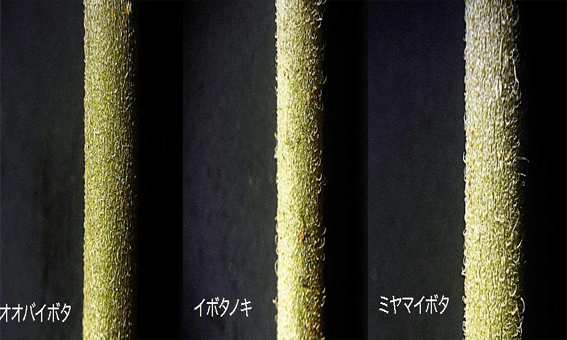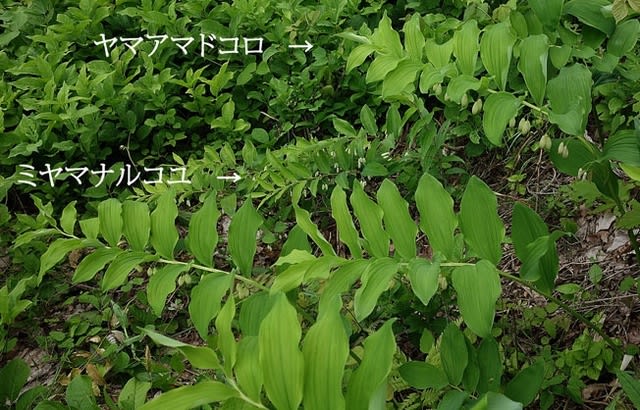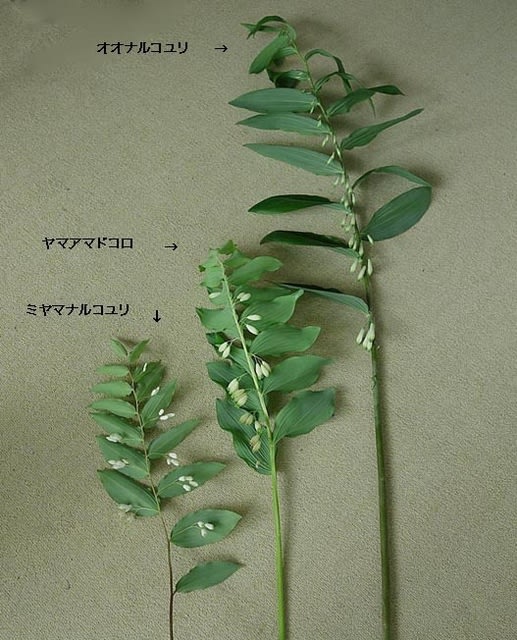8月11日秋田空港まで客を送って行った折、駐車場の隅の舗装の切れ目の所から出て枝分かれして舗装された歩道の上にまで広がって繁殖しているのはクルマバザクロソウだと知りました。


在来種ザクロソウはこれまでに何度か見ていますが、帰化種クルマバザクロソウは初めてなのでその違いを知るために撮影して比較してみました。
湿った荒れ地に一面に繁茂しているのはクルマバザクロソウと同じですが、根部から枝分かれし株となって増えているためやや違った外観を示します。


ザクロソウの葉は披針形〜倒卵形でクルマバザクロソウの線状披針形の葉に比べて幅広く、節に輪生する葉の数もクルマバザクロソウが多いという違いがあります。
花は花被片が5、内面に3脈があり、雄蕊3、花柱(子房)1と兩種に違いはないのですが、クルマバザクロソウでは雄蕊が花柱に接触するように湾曲しています。






















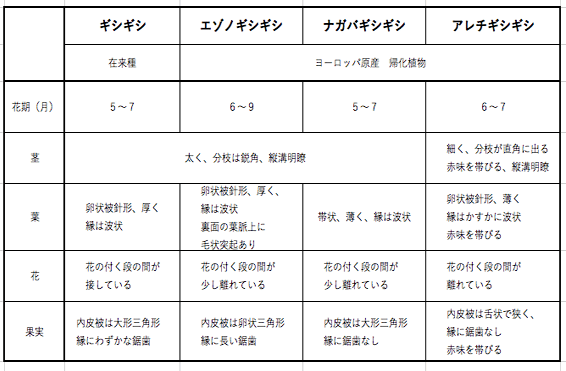















 マリリン・モンロー
マリリン・モンロー