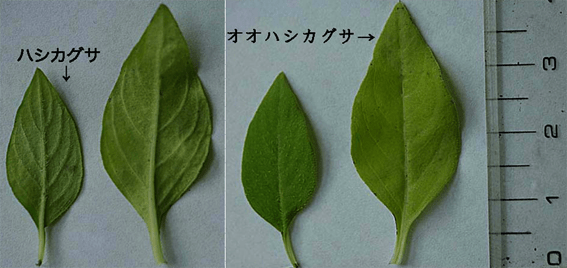・・・ 今日の話題は山野草とは無縁な事柄です ・・・
今朝、通勤の車の中で聴いたNHK秋田のローカルニュースでは、昨年の秋田県内での
熊の目撃情報は1298件で、人が被害に遭ったのが20件と伝えておりました。
この目撃数というのは警察に届けられた数であって、過疎地などではクマの目撃など
は極めて日常的なことなので人が被害に遭わない限り届け出などはしないため実際の目
撃数というのはこの数よりも格段に多いと考えられます。
事実、私たちの施設でもクマによる器物損壊の被害を蒙っていますが警察への届け出
はしていません。
秋田市より北に約53Km離れた山間部にある私の勤務する施設周辺には日常的にクマ
が出没しているらしく、晩秋になると連日町役場からクマ目撃の防災放送が流されます。
平成29年9月29日朝、 職員が出勤してきて施設敷地内にある旧宿舎を改造して使用し
ている更衣室に入ったところ、壁が大きく抉られているのに気付き管理課に連絡してきま
した。
連絡を受けた管理課の職員が建物の裏に回って調べたのが次の画像です。

外壁が乱暴に破られ床にまで穴があけられたているのはどう見ても人間の仕業とは考え
られません。
3日後に修理に入った職員が破られた壁のすぐ近くの2ヶ所に巨大な糞塊を発見し、犯人
はクマに間違いないと確信しました。
糞塊を拡大しました 。
破られた壁と床の周辺には蜂の巣の破片が散乱していましたから、クマは建物の床下に
営巣したススメバチの巣を狙ってかかる乱暴狼藉をはたらいたものと思われます。


























 道端
道端