監督 マルコ・ベロッキオ 出演 ジョヴァンナ・メッツォジョルノ、フィリッポ・ティーミ
ジョヴァンナ・メッツォジョルノとフィリッポ・ティーミのセックスシーンにびっくりする。特別に過激なこと(?)をしているわけではないのだが、目が離せない。ジョヴァンナ・メッツォジョルノがムッソリーニに夢中になっているのが伝わってくる。セックスの官能の悦び、というのではない。セックスの官能を超えている。それはセックスをするというより、ムッソリーニを発見していくという感じ。ムッソリーニの可能性を子宮で感じとる興奮がスクリーンからあふれてくる。
フィリッポ・ティーミのムッソリーニはうさんくさくて、ペテン師のにおいがつきまとっているが、その負の部分をセックスで洗い流し、隠れている可能性のすべてを引き出して見せる、誰も知らないムッソリーニを子宮で育てていくのだ、という悦びにあふれている。
ものすごいですなあ。これだけで、この映画を見た価値がある。
このあとは、ジョヴァンナ・メッツォジョルノはムッソリーニに裏切られ(ムッソリーニは家庭を選んでしまう)、捨てられるだけではなく、精神病院へ追いやられ、愛の痕跡を消されてしまう。それでもジョヴァンナ・メッツォジョルノはムッソリーニを愛しつづける。ムッソリーニを発見し、育てたのは自分だという自負を生き抜く。ジョヴァンナ・メッツォジョルノにとって愛とは人の可能性を発見し、それを育てることなのだけれど、これはムッソリーニにとってはうれしいことではない。女に育てられ、最高権力者になったということを認めることは、自分の価値を低めることだと思ってしまったんだろうなあ。で、彼女の存在を抹殺しようとする。
この、一種理不尽な戦いが、延々とつづく。
映画の力は、その理不尽な戦いを、ジョヴァンナ・メッツォジョルノの肉体に封じ込めているところにある。ジョヴァンナ・メッツォジョルノを捨てて、家庭を選んだあと、ムッソリーニはほとんど登場しない。いや、登場するのだが、ジョヴァンナ・メッツォジョルノとはきちんと向き合わない。セックスしたときのように、真っ裸では向き合わない。だから、ジョヴァンナ・メッツォジョルノは、目の前にいないムッソリーニを相手に、ひとりで戦う。ジョヴァンナ・メッツォジョルノの肉体が、たったひとりで、戦いつづける。愛も、怒りも、絶望も、ただ肉体だけで具体化する。
このジョヴァンナ・メッツォジョルノの演技力はすごい。演技力というか、存在感、生のジョヴァンナ・メッツォジョルノと言えるかもしれない。実際、彼女の肉体を見ていると、相手がムッソリーニであることを忘れてしまう。ヒットラーでも、スターリンでも、毛沢東でもいい。いや、そういう巨大な人間ではなく、普通の、となりのおじさんでもいい。相手が誰であるかは、どうでもよくなる。愛したのだ、男を育てたのだ、その男の子供を産んだのだという子宮の存在そのものだ。だから、彼女の悲しみや絶望は、「ムッソリーニを愛した女」を超え、女そのものの感情になる。女そのものの肉体になる。
特別な女の悲劇を見ているのではなく、いま・ここに生きている女という性そのものの絶望と怒り、愛と悲しみ、そして悦びにさえ見える。個人であるけれど、個人を超越して女という普遍に到達している。
ジョヴァンナ・メッツォジョルノはムッソリーニを愛し、ムッソリーニを発見し、ムッソリーニを育てると同時に、彼女自身を発見し、彼女自身を普遍にまで育てたのである。これを、ジョヴァンナ・メッツォジョルノはほんとうに彼女ひとりの肉体で具現化するのである。
すごい、すごい、すごい。
映画は、このジョヴァンナ・メッツォジョルノの壮絶な戦いを、古いフィルム(ムッソリーニの実写を含む)やチャプリンの映画(キッド)、さらには当時の映画の手法(大きな文字をスクリーンに登場させる)などを巧みに融合させながら「ドキュメンタリー」に、あるいは「史実」にしようとしている。とても巧い、とても技巧的に完成された映画である。(あたりまえか……。)完璧な映画になっている。
しかし。
それが私にはちょっと不満。ムッソリーニとその時代にこだわったために、ジョヴァンナ・メッツォジョルノの具現化した女が、その時代の女に封じこめられてしまったような感じがしないでもない。相手がムッソリーニだったから、こういう悲劇があったというのは「事実」なのだが、相手がムッソリーニでなくても、女は同じ悲劇を生きる--その普遍的な事実が、なんだか「物語」のなかにとじこめられてしまったような感じがするのである。ジョヴァンナ・メッツォジョルノの演技は「物語」を突き破っているのに、マルコ・ベロッキオがそれをもう一度「物語」に封印してしまっている感じがするのである。
だからね、というのは少し論理的におかしいかもしれないけれど、映画を見終わるとムッソリーニがとってもつまらない人間に見えるでしょ? 実際につまらない人間なのかもしれない。けれど、ムッソリーニがつまらない人間にみえてしまえば、マルコ・ベロッキオは何のためにそんなつまらない人間を愛したのか--という変な疑問が残ってしまい、彼女の具現化した絶望や怒りが、なんとなく虚しくなる。弱くなる。それが残念。
(KBCシネマ1)
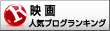
ジョヴァンナ・メッツォジョルノとフィリッポ・ティーミのセックスシーンにびっくりする。特別に過激なこと(?)をしているわけではないのだが、目が離せない。ジョヴァンナ・メッツォジョルノがムッソリーニに夢中になっているのが伝わってくる。セックスの官能の悦び、というのではない。セックスの官能を超えている。それはセックスをするというより、ムッソリーニを発見していくという感じ。ムッソリーニの可能性を子宮で感じとる興奮がスクリーンからあふれてくる。
フィリッポ・ティーミのムッソリーニはうさんくさくて、ペテン師のにおいがつきまとっているが、その負の部分をセックスで洗い流し、隠れている可能性のすべてを引き出して見せる、誰も知らないムッソリーニを子宮で育てていくのだ、という悦びにあふれている。
ものすごいですなあ。これだけで、この映画を見た価値がある。
このあとは、ジョヴァンナ・メッツォジョルノはムッソリーニに裏切られ(ムッソリーニは家庭を選んでしまう)、捨てられるだけではなく、精神病院へ追いやられ、愛の痕跡を消されてしまう。それでもジョヴァンナ・メッツォジョルノはムッソリーニを愛しつづける。ムッソリーニを発見し、育てたのは自分だという自負を生き抜く。ジョヴァンナ・メッツォジョルノにとって愛とは人の可能性を発見し、それを育てることなのだけれど、これはムッソリーニにとってはうれしいことではない。女に育てられ、最高権力者になったということを認めることは、自分の価値を低めることだと思ってしまったんだろうなあ。で、彼女の存在を抹殺しようとする。
この、一種理不尽な戦いが、延々とつづく。
映画の力は、その理不尽な戦いを、ジョヴァンナ・メッツォジョルノの肉体に封じ込めているところにある。ジョヴァンナ・メッツォジョルノを捨てて、家庭を選んだあと、ムッソリーニはほとんど登場しない。いや、登場するのだが、ジョヴァンナ・メッツォジョルノとはきちんと向き合わない。セックスしたときのように、真っ裸では向き合わない。だから、ジョヴァンナ・メッツォジョルノは、目の前にいないムッソリーニを相手に、ひとりで戦う。ジョヴァンナ・メッツォジョルノの肉体が、たったひとりで、戦いつづける。愛も、怒りも、絶望も、ただ肉体だけで具体化する。
このジョヴァンナ・メッツォジョルノの演技力はすごい。演技力というか、存在感、生のジョヴァンナ・メッツォジョルノと言えるかもしれない。実際、彼女の肉体を見ていると、相手がムッソリーニであることを忘れてしまう。ヒットラーでも、スターリンでも、毛沢東でもいい。いや、そういう巨大な人間ではなく、普通の、となりのおじさんでもいい。相手が誰であるかは、どうでもよくなる。愛したのだ、男を育てたのだ、その男の子供を産んだのだという子宮の存在そのものだ。だから、彼女の悲しみや絶望は、「ムッソリーニを愛した女」を超え、女そのものの感情になる。女そのものの肉体になる。
特別な女の悲劇を見ているのではなく、いま・ここに生きている女という性そのものの絶望と怒り、愛と悲しみ、そして悦びにさえ見える。個人であるけれど、個人を超越して女という普遍に到達している。
ジョヴァンナ・メッツォジョルノはムッソリーニを愛し、ムッソリーニを発見し、ムッソリーニを育てると同時に、彼女自身を発見し、彼女自身を普遍にまで育てたのである。これを、ジョヴァンナ・メッツォジョルノはほんとうに彼女ひとりの肉体で具現化するのである。
すごい、すごい、すごい。
映画は、このジョヴァンナ・メッツォジョルノの壮絶な戦いを、古いフィルム(ムッソリーニの実写を含む)やチャプリンの映画(キッド)、さらには当時の映画の手法(大きな文字をスクリーンに登場させる)などを巧みに融合させながら「ドキュメンタリー」に、あるいは「史実」にしようとしている。とても巧い、とても技巧的に完成された映画である。(あたりまえか……。)完璧な映画になっている。
しかし。
それが私にはちょっと不満。ムッソリーニとその時代にこだわったために、ジョヴァンナ・メッツォジョルノの具現化した女が、その時代の女に封じこめられてしまったような感じがしないでもない。相手がムッソリーニだったから、こういう悲劇があったというのは「事実」なのだが、相手がムッソリーニでなくても、女は同じ悲劇を生きる--その普遍的な事実が、なんだか「物語」のなかにとじこめられてしまったような感じがするのである。ジョヴァンナ・メッツォジョルノの演技は「物語」を突き破っているのに、マルコ・ベロッキオがそれをもう一度「物語」に封印してしまっている感じがするのである。
だからね、というのは少し論理的におかしいかもしれないけれど、映画を見終わるとムッソリーニがとってもつまらない人間に見えるでしょ? 実際につまらない人間なのかもしれない。けれど、ムッソリーニがつまらない人間にみえてしまえば、マルコ・ベロッキオは何のためにそんなつまらない人間を愛したのか--という変な疑問が残ってしまい、彼女の具現化した絶望や怒りが、なんとなく虚しくなる。弱くなる。それが残念。
(KBCシネマ1)
 | 肉体の悪魔 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 紀伊國屋書店 |

























